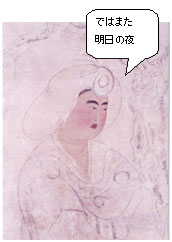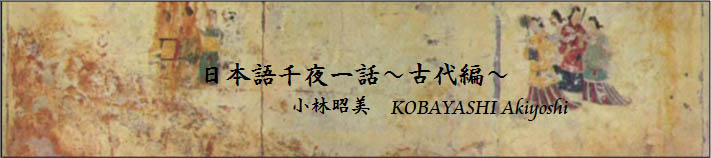
第242話 和語と漢語のあいだ
5世紀の日本語を写す資料としては稲荷山鉄剣な どがあるが、これも文字数は表に57字、裏面に58字が書かれているだけであり、5世紀の日本語の全体像を復元するにはまったく不十分である。
古代の日本語の姿を体系的にしることができるよ うになるのには8世紀まで待たなければならない。記紀万葉は古代の日本語の姿を伝えている。なかでも古事記と日本書紀にそれぞれ120首あまり記録されて い る、いわゆる記紀歌謡は漢字の音だけを使ってかかれており、8世紀の日本語の音声を復元するためには欠かせない資料である。
やまとは 国のまほろば たたなづく 青垣
山こもれる やまとしうるはし
ここで注目されるのは「やまと」というやまとことばが「夜摩苔」と表記されていることである。日本書紀歌謡には「やまと」ということばが9回使われてい
る。それらをすべて列記してみるとつぎのようにな
る。
し)、揶莽等能倶珥珥(やまとのくにに)、野麼等能(やまとの)、婀岐豆斯麻野麻登(あ
きづしまやまと)、蘇羅瀰豆野麻等能矩儞嗚(そらみつやまとのくにを)、野麻登陛儞(や
まとへに)、野麻騰能(やまとの)、
これらの漢字の古代中国語音は等[təng]、苔[də]、登[təng]、騰[dəng] であると推定されている。発音記号の[ə]
はあいまい母音と呼ばれるのもで、英語の冠詞の a
に近い音である。中国語の音韻体系は日本語の音韻体系と違うから、中国語の韻尾[-ng]
の漢字も使われている。これも日本語にはない発音
である。現代の日本漢字音では等(トウ)、登(トウ・ト)、騰(トウ)となるが、日本書紀歌謡では「と乙」に使われている。
また、古代日本語では濁音が語頭にたつことはな
かった。そのため、中国語の濁音は語頭では清音になり語中では濁音になることも多い。
このことから、「やまとことば」の「やまと」は[jya-mai-də]
に近い音価をもっていたものと考えることができる。また、魏志倭人伝に出てくる「邪馬台国」も[jya-mai-də]
に近い音価をもっていたものと考えられる。つまり
「邪馬台国」は現代の日本漢字音では「やまたいこく」だが、3世紀の日本列島にあったのは「やまと国」を写したものであると考えることができる。
「莽」の字はこの歌謡では許莽例屢(こもれる)
と莽(も)の音にあてられているが、ほかの歌謡では揶莽等能倶珥珥(やまとのくにに)、と莽(ま)の音にあてられている。
中国語と日本語では音韻体系が違うから、中国語の一字に日本語の一音をあてることはできなかったのである。
「やまとことば」のなかには、弥生時代以降8世紀
にいたる間に中国語から取り入れられた語彙がかなり含まれていると考えざるをえない。
「国」には「區珥」があてられている。現代の日本
漢字音では「くじ」と読めてしまう。日本書紀歌謡では「區珥」のほかに「倶珥」「矩儞」「倶儞」「屨儞」が使われている。「珥」「儞」はいずれも中国語音
韻学で日母[nj-]と呼ばれる声母で、「珥」の古代中国語音は珥[njiə]であり、「儞」の古代中国語音は儞[njiai]である。
「珥」は日本語の珥(ニ)にあてられることが多いが、珥(ジ)にも使われることもある。
つぎに日本書紀歌謡に使われている人称名詞についてみてみることにする。
やすみしし 我が大君は うべなうべな 我を問はすな あきづ島
やまとの国に 雁子生むと 我は聞かず
大君の 八重の組垣 かかめども 汝をあましじみ かかぬ組垣
このなかで一人称には和我(我)、和例(我)、 二人称には儺(汝)が使われている。日本書紀歌謡のなかで汝(な)は5回使われているが、いずれも「儺」と表記されている。「汝」は「なれ」ともいわれ、 文 語では「なむぢ」「なむち」あるいは「なんじ」となってあらわれる。「君」は「大君」のように使われることもあるが君(きみ)として二人称に使われること もある。日本書紀歌謡全部について表記のしかたを調べてみると次のようになる。
汝(儺)、
君(企弭・企瀰・枳美・枳彌・枳瀰・耆瀰)、
古代日本語の「我」は我(わが・あが)、我(わ
れ・あれ)、二人称は「汝」は汝(な)、「君」は君(きみ)であったことがわかる。三人称については代名詞としての用例は日本書紀歌謡にはない。
「我」の古代中国語音は我[ngai] であり、「和」「倭」「涴」「阿」は和[huai]、倭[iuai]、涴[uan]、阿[ai] である。我(わが・われ)は我[ngai]
の頭子音の前に脣音の「わ」と添加したものであり、我(あが・あれ)は我[ngai]
の頭子音が脱落したものである。古代中国語の疑母[ng-]は古代日本語や朝鮮語では語頭にはあらわれない音
であり、「やまとことば」に取り入れられるときに転移した。我(わが・あが)は現代日本語では「我は」という場合に使われ、我(われ・あれ)は「我・を」
「我・に」などの場合に使われている。
古代中国語の「和」の音価は和[huai] であり、「倭」は倭[iuai] であると考えられている。[h]も日本語にはない喉音であり、あとに[-iu-]介音を伴うものは唐代の中国語音では[h] が失われていた。「和」と同じ声符をもつ「禾」の日本漢字音は禾(か)(旧仮名使いでは禾(くわ))であるが、「和」では頭音が失われて和(わ)になって いる。
日本漢字音では拗音になっている「許」「伽」「玖」「虚」「擧」「流」などの漢字も日本書紀歌謡では直音で使われている。
伽餓奈倍氐(かがなべて)、用珥波虚虚能用(夜には九夜)、擧曾(こそ)、
漢和辞典などによれば州・洲[tjiu] は音が州・洲(シュウ)、訓が州・洲(す)とされ ているが、州・洲(シュウ)は唐代の中国語音に準拠した音であり、州・洲(す)は古代日本語に拗音がなかった時代の古音である可能性が高い。巣[dzheô](す・ソウ)なども中国語と同源である可能性が高 い。
日本書紀歌謡の歌に使われている漢字はナ行とタ行
濁音にまたがって使われているものもみられる。例えば「泥」である。「泥」の古代中国語音は泥[nyei]であると考えられているが、泥(寝)、泥(根)赴
泥(船)、麻泥(まで)、阿泥素企多伽避顧禰(あぢすきたかひこね)、菟藝泥赴(つぎねふ)などに使われている。
また、日本語の野(の)には奴[na]、怒[na]、努[na]などの文字が用いられている。ナ行とダ行にわたっ
て使われている文字を一覧表にしてみるとつぎのようになる。(数字は使用回数)
|
|
奴[na] |
怒[na] |
弩[na] |
努[na] |
尼[niei] |
泥[nyei] |
埿[nyei] |
旎[nyei] |
|
ナ行 |
ナ (3) |
ヌ(3) |
ノ甲(2) |
ノ甲(1) |
ニ (4) |
ネ(18) |
ネ (2) |
|
|
ダ行 |
ド甲(2) |
ド甲(2) |
ヅ (1) |
|
デ (1) |
デ (7) |
|
ヂ (3) |
|
|
那[nai] |
娜[nai] |
涅[nyet] |
廼[nə] |
|
ナ行 |
ナ(70) |
ナ (1) |
ネ (1) |
ノ乙(12) |
|
ダ行 |
|
ダ(13) |
デ (8) |
ド乙 (6) |
現代の日本語でも、内(ない)はお内裏様では内 裏 (だいり)である。タ行、ダ行、ダ行は調音の位置が同じであり、同じ日本語のなかでも転移することがある。東北の仙台(せんだい)と鹿児島県の川内(せん だい)とは同義である。さらに大阪の河内(かわち)も同系のことばであろう。
日本書紀歌謡では同じ文字がマ行とバ行に用いられ
ている例が多くみられる。例えば、次の歌には同じ声符をもつ「麻」と「磨」、「摩」が使われているが、「麻」「摩」は「マ」に読み、「磨」は「バ」と読
む。
烏波利珥 多陁珥霧伽弊流 比苔菟麻菟 阿波例 比等菟麻菟 比苔珥阿利勢磨
岐農岐勢摩之塢 多知波開摩之塢
尾張に ただに向へる 一つ麻菟(松) あはれ 一つ麻菟(松) 人にありせ磨(ば)
衣着せ摩(ま)しを 太刀佩け摩(ま)しを
日本書紀歌謡に使われている文字のうち日本語の
マ
行、バ行に使われている漢字のうち主なものを調べてみると次のようになる。
|
|
麻[mea] |
魔[mua] |
磨[muai] |
摩[muai] |
麽[mo] |
謎[myei] |
寐[miuəi] |
|
マ行 |
マ(39) |
マ(10) |
マ(35) |
マ(72) |
マ(12) |
メ甲(11) |
ミ甲 (1) |
|
バ行 |
|
バ (5) |
バ (8) |
|
バ(36) |
ベ甲 (1) |
ビ甲(11) |
|
|
清 音 |
半濁音(鼻音) |
濁 音 |
|
前口蓋音 |
タ 行 |
ナ 行 |
ダ 行 |
|
脣 音 |
ハ 行 |
マ 行 |
バ 行 |
ナ行とマ行にわたって使われている漢字もある。日
母[nj-] の漢字はナ行にあらわれやすく、明母[m-]の漢字はマ行であらわれることが多いが、日母[nj-] と明母[m-]
はイ段ではナ行とマ行にわたってつかわれる例がみ
られる。
例:區珥(くに=国)、那羅珥(ならび=並 び)、企珥(きみ=君)、
なお、「珥」は「伊茂播和素等邏珥=妹は忘ら
じ」
のように珥(ジ)にも使われている。日母[nj-]の音価の不安定さは、その歴史にあるようである。
日母の原型はおそらく[m-] であり、それが口蓋化して[nj-] になったものと思われる。しかし、その後[dj-] あるいは[zj-]
へと変化していった。日本漢字音でも「一日」は一
日(イチニチ)であるが、「元日」は元日(ガンジツ)である。
|
|
耳[njiə] |
餌[njiə] |
珥[njiə] |
|
ニ |
|
|
ニ (81) |
|
ジ |
ジ (1) |
ジ (1) |
ジ (5) |
|
|
爾[njiai] |
邇[njiei] |
儞[njiei] |
禰 [myei] |
彌 [miai] |
瀰[miai] |
弭[mie] |
|
ナ行 |
ニ (29) |
ニ (4) |
ニ (50) |
ネ (15) |
|
|
|
|
マ行 |
|
|
|
|
ミ甲(42) |
ミ甲(109) |
ミ (1) |
|
バ行 |
|
|
|
|
ビ (1) |
|
ビ (8) |
、 異玖用伽禰菟流(いく夜か寝つる)、伊麻柂藤柯禰波(いまだ解かねば)、
日本漢字音でも壬生(みぶ)、任那(みまな)な ど 日母[nj-]がマ行であらわれる例はみられる。巻貝の「蜷」は 蜷(にな)とも蜷(みな)ともいう。「韮」も韮(にら)ともいい、韮(みら)ともいう。日本語の乙女(おとめ)、たわや女(め)、やまし ろ女(め)などの女(め)も、古代中国語で「女」が女[njia] となる前の、女[mia] であった時代の痕跡をとどめたものでなないだろう か。また、日本語の耳(みみ)も古代中国語の耳[miə] と関係のあることばであろう。
「君」の古代中国語音は君[giuən]
である。日本書紀歌謡では「君」に次のような文字
があてられている。
君(企珥、企瀰、枳美、枳彌、枳瀰、耆瀰)
「企」「耆」「枳」はいずれも「君」の頭子音の 音 に使われているが、その中国語古代音と確定することは必ずしも簡単ではない。「企」の声符「止」には止(し)の音があり、枳(き)と同じ声符をもつ漢字に 只(し)がある。また、「耆」は「伯耆」などでも「き」に使われているが、同じ声符をもつ「旨」は旨(し)である。漢和辞典を調べてみると耆(き・ぎ・ し)、枳(き・し)とある。音韻学者や韻書もその音価を確定しかねているようである。緒説を一覧にしてみると次のようになる。(該当する文字の音価が示さ れていない文字については[--] あるいは○○で表示した)
|
|
1.王力 |
2.董同龢 |
3.森博達 |
4.韻鏡 |
5.反切 |
|
企・止 |
[khiə]・[tjiə] |
[khieg]・[tjiəg] |
渓寘・○○ |
渓寘・清止 |
乞義・止矣 |
|
岐・支 |
[--]・[tjiə] |
[gieg]・[kjieg] |
群支・○○ |
群紙・精支 |
勤移・職奇 |
|
枳・只 |
[--]・[tjie] |
[kjieg/tieg]・[kjieg] |
見紙・○○ |
精紙・○○ |
軫倚・軫倚 |
|
耆・旨 |
[--]・[tjiei] |
[giei/dhiei]・[kjed] |
群脂・旨開 |
群脂・清旨 |
勤夷・支倚 |
韻鏡は唐代の発音を示しており、反切は七世紀初頭、隋の時代の発音に依拠している。それ以前の発音については『詩経』の韻などを参考にしながら、唐代の発音から遡って復元されているので、学者によって 見方が異なる場合がある。
董同龢は「枳」「耆」については二つの読み方をしめしている。森博達は「企」には渓母[kh-]、「岐」「耆」には群母[g-]、「枳」には見母[k-]をあてている。唐代の漢字音をあらわすために作られた『韻鏡』では「枳」の声母には精[tz-] をあてているから、日本語ではサ行に近いということになるだろう。
漢字音を声母と韻母に分けて示す反切では「枳」 には「軫倚」があてられている。反切は循環論にだから「軫」を診(シン)と読むか珍(チン)と読むかによって、「枳」の音価も変わってしまう。いずれにして も、日本語音としてはサ行かタ行に近く、カ行音とみるのはむずかしそうである。
「支」は稲荷山鉄剣では「獲加多支鹵」と書いて「ワカタケル」とカ行で読ませている。古代中国語には「支」に支[gie] に近い音があったのではないかと思われる。支[gie] は後口蓋音であるが介音[-i-] の発達によって口蓋化して支[tjiə] に近い音になり、支[tjiə] はさらに摩擦音化して支[zhi] になったと考えることができる。
日本書紀歌謡では「岐」「企」「耆」は日本語の「き甲」に使われており、「旨」「指」「斯」は日本語の「し」にあてらている。日本書紀歌謡の漢字音はおおむね唐代の漢字音に依拠しているといえるのでは なかろうか。
多山耆*摩
知烏能流(當麻道を告る)、旨我那稽皤(其が無けば)、
倭須羅廋麻旨珥(忘らゆましじ)、瀰我保指母能婆(見が欲し物は)、
與慮斯企野麼(よろしき山)、
|
|
耆[giei] |
山耆*[giei] |
指[tjiei] |
旨[tjiei] |
基[kiə] |
斯[sie] |
|
カ行 |
キ甲 (15) |
キ甲 (1) |
|
|
キ乙 (4) |
|
|
サ行 |
|
|
シ (1) |
シ (3) |
|
し (25) |
○ カ行とサ行のあいだ
用例は多くはないがカ行とサ行にわたって使われる声符もある。「氏」の声符をもつ漢字に
祇[giei] と氐[tyei]
がある。「祇」は日本書紀歌謡では祇(キ甲)に、
「氐」は氐(て)に使われている。
枳彌波夜那祇(君はや無き)、菟玖波塢須擬氐(筑波を過ぎて)、
多遇譬氐序豫枳(偶ひてぞ良き)、
声符「氐」は祇[gei] であったものが、介音[-i-]の発達により氐[tyei] になり、さらに氏[sjie] になったものと思われる。群母[g-] は後口蓋で調音される音であるが、介音[-i-]は前口蓋で調音される音であるので、声母も後口蓋音[g-] から前口蓋音氐[tyei] へと転移し、さらに摩擦音化して氏[zjie] に転移したものと思われる。
同じ声符をもった漢字がサ行とタ行に読み分けられている例が日本書紀歌謡にも、いくつかみられる。陁(ダ)・施(シ)、都(ツ)・諸(ソ乙)、などである。その主なものを一覧表にしてみると次のようになる。(
)は使用回数をあらわす。
|
|
陁dai |
柂dai |
池die |
施sjiai |
絁sjiai |
都ta |
覩ta |
屠da |
諸sjia |
|
サ行 |
|
|
|
シ(1) |
シ(8) |
|
|
|
ソ乙(2) |
|
タ行 |
タ(38) |
タ(29) |
チ(2) |
|
|
ツ(50) |
ツ(1) |
ツ(1) |
|
|
ダ行 |
ダ(3) |
ダ(2) |
|
|
|
ヅ(1) |
|
|
|
声符「也」の古代中国語音は也[dai] であったものが、介音[-i-] の発達によって池[die] になり、さらに口蓋化によって施[sjiai] に変化したものと考えることができる。
|
|
等[təng] |
詩[sjiə] |
時[ziə] |
苔[də] |
笞[thiei] |
始[sjiə] |
|
タ 行 |
ト乙(72) |
|
|
ト乙(35) |
チ(1) |
|
|
サ 行 |
|
シ(1) |
シ(1) |
|
|
シ(18) |
等[təng] と同じ声符をもつ漢字では詩[sjiə] と時[ziə] があり、「し」に使われている。
例:愛瀰詩烏瀰亻嚢*利(蝦夷を一人)、阿阿時夜塢(ああしやを)、
また、苔[də]と同じ声符をもつ漢字では笞[thiei] が笞(ち)に、始[sjiə] が始(し)に使われている。
日本書紀歌謡では「やまと」は「夜摩苔」と表記されている。「夜摩苔」は現代の日本漢字音で読めば「やまたい」である。魏志倭人伝の「邪馬台国」は日本書紀歌謡にある「夜摩苔」を指すものと考えて間違い ないのではなかろうか。
中国語には日本語にはない喉音[h-][x-]がある。中国語の喉音[h-]・[x-]
は日本書紀歌謡ではア行、カ行、ワ行にあらわれる。
【ア行】于[hiua] ウ(42)、宇[hiua] ウ(18)、禹[hiua] ウ(3)、
【カ行】河[hai] カ(1)、訶[xai] カ(13)、許[xa] コ乙(16)、
【ワ行】和[huai] ワ(51)、衛[hiuai] ヱ(5)、恵[hyuei] ヱ(5)、慧[hyuəi] ヱ(1)、廻[huəi] ヱ(1)、
隈[huəi] ヱ(1)、弘[huəng] ヲ(5)、謂[hiuəi] ヲ(3)、偉[hiuəi] ヲ(2)、韋[hiuəi] ヲ(1)、
為[hiuai] ヲ(1)、位[hiuəi] ヲ(1)、乎[ha] ヲ(1)、
「于」「宇」「禹」はいずれも介音[-iu-]を伴っており、頭音[h-]
は脱落している。「和」「廻」「隈」「弘」は介音[-u-] を伴っており、いずれも頭音[h-] は脱落し、ワ行であらわれている。
「衛」「恵」「慧」「謂」「偉」「韋」「為」
「位」はいずれも介音[-iu-]・[-yu-] を伴っており、頭音[h-]
は脱落し、日本書紀歌謡ではワ行に使われている。
このことから、次のようなことがいえると思われる。
例:于[hiua](ウ)、宇[hiua](ウ)、禹[hiua](ウ)、
2.古代中国語の声母[h-]・[x-] は介音[-u-] の前では脱落し、ワ行であらわれる。
例:和[huai](ワ)、廻[huəi](ヱ)、隈[huəi](ヱ)、弘[huəng](ヲ)、乎[ha](ヲ)、
3.古代中国語の声母[h-]・[x-] は介音[-iu-]・[-yu-] の前では脱落し、ワ行であらわれることがある。
例:衛[hiuai](ヱ)、恵[hyuei](ヱ)、慧[hyuəi](ヱ)、謂[hiuəi](ヲ)、偉[hiuəi](ヲ)、
韋[hiuəi](ヲ)、為[hiuai](ヲ)、位[hiuəi](ヲ1)、
日本書紀歌謡が編纂された時代の中国語音では介音[-i-]が十分発達していなかったため、于[hiua]、宇[hiua]、禹[hiua] は「ウ」となり、衛[hiuai]、恵[hyuei]、慧[hyuəi]、謂[hiuəi]、偉[hiuəi]、韋[hiuəi]、為[hiuai]、位[hiuəi] はワ行であらわれたものと考えられる。
日本書紀歌謡では日本語のワ行には次のような漢字があてられている。[--]は古代中国語音であり、数字は日本書紀歌謡で使われた回数を示す。
「和」「倭」「涴」はいずれも「われ」「わが」などに使われる。
例:和例(われ)、倭例(われ)、和我(わが)、倭我(わが)、涴餓(わが)
日本書紀や古事記では「われ」とともに「あれ」も使われている。
例:阿例(あれ)、阿我(あが)、阿餓(あが)、婀我(あが)
「われ」と「あれ」はともに1人称をあらわす名詞である。古代日本語の「あ」は中国語の我[ngai]あるいは吾[nga] と同源である。朝鮮漢字音では疑母[ng-]は規則的に脱落して我(a)、吾(o) となる。古代日本語も濁音が語頭にくることはなかったので中国語の声母[ng-] が脱落して「あ」となった。
それでは「わ」とは何かということが問題になる。 中国語の疑母[ng-] の朝鮮漢字音(--) について詳細に調べてみると次のようなことがわかる。
元[ngiuan]
(won)、
月[ngiuat]( wol)、
疑[ngia]( wi)、
芸[ngiei]( ye)、
迎[ngyang]( yeong)、
現代の日本語では助詞の「~は」も発音は「わ」であるが、古代日本語では助詞の「~は」に「和」が用いられることはない
【ヰ】偉[hiuəi] (2)、爲[hiuai] (1)、威[iuaəi] (3)、謂[hiuəi] (3)、韋[hiuəi] (1)、位[hiuəi] (1)、委[iuai] (1)、
古代日本語の「ゐ」は中国語の声母[h-] が脱落したものに対応して、介音[-iu-] をあらわしている。
古代日本語の「ゑ」は中国語の声母[h-]が脱落したものに対応して、介音[-u-]あるいは[-iu]をあらわ している。
古代日本語の「を」は中国語の声母[h-]の脱落したものに対応するものが多い。いずれも助詞の「を」に多く使われている。
阿烏(青)、佐烏(棹)、烏箇(岡)、烏志(鴛鴦).弘(緒)、苔塢伽(十日)、
惋等賣(乙女)、
日本書紀歌謡で日本語のヤ行音に使われている漢字のなかには喉音[h-]・[x-]
の脱落では説明のつかない例がいくつかみられる。
【ユ】 喩[jio] (23)、由[jiu] (13)、廋[oa] (4)、瑜[jio] (1)、愈[jio] (1)、
【ヨ甲】用[jiong] (6)、庸[jiong] (2)、遥[jiô] (1)、
【ヨ乙】豫[jia] (29)、余[jia] (9)、與[jia] (7)、譽[jia] (5)、預[jia] (3)、
「夜」と同じ声符をもった漢字に夕(セキ)、汐
(セキ)、液(エキ)がある。「夜」は液[jyak] のように韻尾[-k]
をもった文字であったことがわかる。また、「夜」はさらにさかのぼると夕[zyak]
のように頭子音をもっていたものと考えられる。さらに、汐[zyak]は潮[diô]と同義であることから、「夜」という文字は次のような音韻史をたどったものと推測できる。
夜[diok]→夜[zyak]→夜[jyak]→夜[jya]
夜[diok] は介音[-i-] の影響で頭音が摩擦音になり夜[zyak]となった。夜[zyak] は頭音が脱落して夜[jyak] となり、さらに韻尾の[-k] が脱落して夜[jya] となった。
日本語の夜(よる)は夜[jyak] の転移したものであり、夜(ヤ・ヨ)は夜[jya] に依拠したものである。日本語の汐(しほ)は汐[zjyak] の韻尾[-k] が[-p] に転移したものであり、夕(ゆふ)もやはり夕[jyak]の韻尾[-k] が[-p] に転移したものであろう。
「野」と同じ声符をもった漢字に「預」「豫」「序」などがある。「序」は日本書紀歌謡のなかでも使われている。
例:多遇譬氐序豫枳(偶ひてぞ良き)、
「序」は古代日本語の序(ぞ乙)にあてられてい る。「序」のの古代中国語音は序[zia] であり、野[jya] も野[zia] の頭音[z-] が介音[-i-] の影響で脱落したものである。古事記歌謡では「野」と同じ声符をもつ漢字「杼」が杼(ど乙)にあてられている。
例:知杼理(千鳥)、迩本杼理能(にほ鳥の)、袁登賣杼母(乙女ども)、
このことから「野」の音韻史は次のように再構することができる。
野[da]→野[dia]→野[zia]→野[jia]
漢字の「野」に野(ど)という音価があったということは、漢和字典などにも書いてないことだが、事実として古事記歌謡では、同じ声符をもつ「杼」を「ど乙」にあてている。日本語の野(の)は野[da] の転移したものであり、野(ヤ)は野[zia]の頭音が脱落したものである。[d-]と[n-]は調音の位置が同じであり、転移しやすい。
「喩」は日本書紀歌謡では日本語の「ゆ」をあらわす文字としてよく使われている。「喩」と同じ声符をもった漢字に「愈」「輸」がある。「輸」の日本漢字音は輸送(ゆそう)などのごとく輸(ゆ)であるが、
日本書紀歌謡では「輸」は輸(す)に使われている。
例:輸區埿(宿禰)、輸孺(鈴)、など
「輸」の古代中国語音は輸[sjio] である。喩[jio] は輸[sjio] の頭音が口蓋化によって脱落したものである。日本 語の愈・癒(いえる・いやす)、喩(さとす・さとる)などは古代中国語語音の痕跡をとどめたことばであろう。
「由」も日本書紀歌謡では「ゆ」によく使われる文字である。古代日本語の「~ゆ」は現代の日本語では「~から」の意味である。ほかにも次のような用例がある。
例:由瀰(弓)、由介那(行かな)、由羅能斗(由良の門)、由豆流(弓弦)、
「由」と同じ声符をもった漢字に軸[diuk]、宙[diu] などがある。「由」は次のような音韻変化をたどったものと考えられる。
軸[diuk]→宙[diu]→由[jiu]
「由」には軸[diuk] と同じ発音であった時代があり、頭子音と韻尾[-k]がともに脱落して由[jiu]になり、日本書紀歌謡では由(ゆ)に使われている。「由」の訓である由(よし・よる)も由[jiuk]などの痕跡を伝えるものであろう。
日本書紀歌謡では用[jiong]、庸[jiong]、遥[jiô] が「ヨ甲」に使われている。「用」と同じ声符をもつ漢字に通[thong]、桶[dong] などがある。用[jiong] の原型は[dong] であり、介音[-i-]の発達により[diong] になり、さらに頭音が脱落して用[jiong] になったものであろう。日本語の通(とほる)、桶(おけ)などは中国語と同源である。
余[jia]
は日本書紀歌謡では「ヨ乙」に用いられている。同じ声符をもつ叙[zia] は叙(ぞ乙)に用いられ、途[da]は途(つ)に用いられている。
例:泥辭區塢之叙(寝しくをしぞ)、之摩途等利(島つ鳥)、
声符「余」は次のような音韻変化をたどったものと考えられる。
途[da]→除[dia]→叙[zia]→余[jia]
與[jia] も日本書紀歌謡では「ヨ乙」に使われている。「與」と同じ声符をもつ漢字に嶼[zio] があり「島嶼」などに使われることがある。與[jia]は嶼[zio]
の頭音が脱落したものであろう。嶼(ショ)が古く、與(ヨ)の方が新しい。
日本漢字音(呉音・漢音)は唐代の古典を読むとき規範をしめしたものであり、現代の中国語とは違いが大きい。しかし、そこには一定の転移の法則を見出すことができる。上海(シャン・ハイ)の上(シャン) は上海(Shang-hai) の上(Shang) の韻尾(-ng) を「ン」であらわしたものであり、日本漢字音の上 (ジョウ)は上(Shang) を上(ジョウ)と表記したものである。香港(Hong Kong) についても同じであり、北京(ペキン)の京(キン)も北京(Peking)の韻尾(-ng)を「ン」で表記したものである。
これでは中国語の韻尾(-n) と(-ng) の区別がなくなってしまう。しかし、日本語には(-ng)
で終わる音節がないから、上(ジョウ)、香(コウ)、港(コウ)、京(キョウ)と表記するか、上(シャン)、香(ホン)、港(コン)、京(キン)に転移させるかしか表記の方法はないのである。また、朝
鮮漢字音では釜山港は釜山港(プサンハン)である。いずれにしても、中国漢字音は地域によって、その土地のことばに転移することになる。
海(ハイ)、香(ホン)の中国語音は海(hai)、香(xiang)
であり、日本語にはない喉音である。この場合も日
本漢字音ではカ行に転移し、現代の中国語ではハ行に転移している。古代中国語の喉音は古代日本語(弥生音)でもしばしばハ行であらわれる。