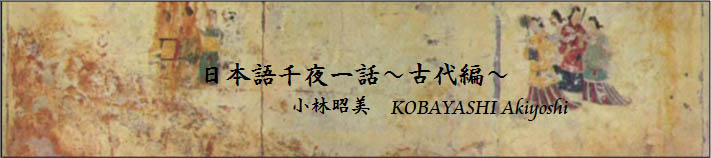
第232話
書きことばの変遷
わが国で文字が使われるようになったのは4世紀か
ら5世紀のことのようである。
○ 古墳時代
埼玉県行田市にある稲荷山古墳から発見された鉄剣
には、辛亥年(471または531)七月に乎獲居臣(おわけのおみ)が上祖オホヒコからヲワケ臣に至る八代の系譜が書かれており、彼の家は世々杖刀人首
(じょうとうじんのかしら)として仕えてきたこと、ヲワケ臣はワカタケル大王(雄略)のものとにあって、斯鬼宮(しきのみや)で天下を左治したことなどが
漢文で記されている。
(表)
辛亥年七月中記乎獲居臣上祖名意富比垝其児多加利足尼其児名弖已加利獲居其児名
多加披次獲居其児名多沙鬼獲居其児名半弖比
(裏)
其児加差披余其児名乎獲居臣世々爲杖刀人首奉事來至今獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮
時吾左治天下令作此百錬利刀記吾奉事根原也
この鉄剣の主人公は乎獲居(ヲワケ)で、和名は漢
字の音を使って書かれている。意富比垝(オホヒコ)、多加利足尼(タカリスクネ)、弖已加利獲居(テヨカリワケ)、多加披次獲居(タカハシワケ)、多沙鬼
獲居(タサキワケ)、半弖比(ハテヒ)、加差披余(カサハヨ)、獲加多支鹵(ワカタケル)、斯鬼(シキ)などを読みとることができる。
○ 文字とは何か
「ことば」は口で発した音波を耳でとらえて解読す
る技術である。「文字」はそのことばを映像にかえて描き、それを眼でとらえて解読する技術である。「文字」は音を眼で見る技術だからラジオとテレビほどの
違いがある。だから、「ことば」をもたない民族はないが、文字を発明しなかった民族はいくらでもある。
「ことば」の古さにくらべると「文字」の歴史はき
わめて新しい。しかも「文字」は歴史上限られた地域でしか発達しなかった。もっとも古い文字とされるエジプトのヒエログリフ、シュメールの楔形文字の原型
とされる象形文字が成立したのは、紀元前31世紀とされており、今からおよそ5千年前のことにすぎない。
漢字の成立はそれよりなお新しく大体紀元前14世
紀ごろのことであろうと白川静は『漢字』(岩波新書)で述べている。文字をもった中国の文化が日本列島に伝わってきたのは紀元5世紀頃のことで、日本語は
中国語を表記するために発明された漢字によってはじめて記録されることになる。
○ 飛鳥時代
日本には金石文は多くは残されていないが飛鳥時代
の仏像にも文字が刻まれている。その一例として法隆寺薬師仏像造像記をみてみる。
池邊大宮治天下天皇大御身勞賜時歳次丙午年召於大王天皇与太子而誓願賜我大御病太平
欲坐故将造寺藥師像作仕奉詔然當時崩賜造堪者小治田大宮治天下大王天皇及東宮聖王大
命受賜而歳次丁卯年仕奉
この文章は漢字で書かれているが、漢文の文法にし
たがって書かれているというよりは、漢字を使った日本文とでもいうべきものである。この文章は次のように読み下されている。
池辺(いけのへ)の大宮に天下(あめのした)治(しら)しめしし天皇(すめらみこと)、大御身 (おほみみ)労(や)み賜ひし時、歳(とし)丙午(ひのえ
うま)に次(やど)る年に大王(おほ きみの)天皇と太子(ひつぎのみこ)とを召して、誓ひ願ひ賜はく、我が大御病(おほみやま ひ)、太平(たひら
か)に坐(いま)さむと欲(おも)ほすが故(ゆゑ)に、寺を造り薬師の像を 作り仕(つか)へ奉(まつ)らむと詔(のりたま)ひ
き。然(しか)あれども、当時(そのか み)、崩(かく)り賜ひて造り堪(あ)へざりけれ者(ば)、小治田(をはりだ)の大宮に天下治 しめし大王天
皇と東宮(ひつぎのみやの)聖王(おほきみ)と大命(おほみこと)受け賜はりて歳 丁卯(ひのとう)に次る年に仕へ奉りつ。
法隆寺薬師仏造像記は、この薬師如来像の光背の部
分にこの像を作った事情を記したもので、光背銘ともいわれている。この文によれば、用明天皇が病気になったときに、推古天皇や聖徳太子を呼んで、自分の病
気をなおす祈願のために寺を作り薬師如来を安置するようにとおっしゃったが、まもなく崩御されたので作ることができなかったので、推古天皇と聖徳太子は用
明天皇の意志を継いで薬師如来を作った、というのである。
この文章では、「薬師像作仕奉」や「造不堪」は、
語の順序が日本語風になっており、漢文ならば「作薬師像」「不堪造」となるはずである。また、敬語が多く使われており、「我大御病太平欲坐」は天皇のこと
ばを引用したものであり、天皇が自身にたいして敬語を使っていることになる。
この時代には、聖徳太子が十七条憲法を発布したと
されている。その原文は残っていないが『日本書紀』推古天皇十二年四月の条にその記録が残されている。
夏四月丙寅朔戊辰、皇太子親肇作憲法十七条。一曰。以和為貴、無忤爲宗。人皆有黨。
亦少達者。是以、或不順君父。乍違于隣里。然上和爲下睦、諧於論事、則事理自通。何
事不成。
この文章は完全な漢文である。読み下すとつぎのよ
うになる。
夏(なつ)四月(うづき)の丙寅(ひのえとら)の戊戌(つちのえいぬ)の朔(ついたちのひ) に、皇太子、親(みづか)ら肇(はじ)めて憲法(いつくしきのり)十七条(とをあまりななを ち)作(つく)りたまふ。
一(にとつ)に曰(い)はく、和(やはら)ぐを以て貴(たふと)しとし、忤(さか)ふること無 (な)きを宗(むね)とせよ。人(ひと)皆(みな)党(た
むら)有(あ)り。亦(また)達(さ と)る者(もの)少(すく)なし。是(これ)を以て、或(ある)いは君父(きみかぞ)に順(し たが)はず。乍(ま
た)隣里(さととなり)に違(たが)ふ。然(しか)れども、上(かみ)和 (やはら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事(こと)を論(あげつら)ふに諧
(かな)ふときは、 事理(こと)自(おの)づからに通(かよ)ふ。何事(なにごと)か成(な)らざらむ。
『日本書紀』の文章が聖徳太子の書いたものをその まま伝えたものだとすれば、聖徳太子は正式な漢文を使って政治を行っていたことになる。
『日本書紀』はすでにみたように漢文で書かれてい
る。『古事記』は『日本書紀』より前に成立したものと考えられているが、和臭のある漢文で書かれている。
記紀にはそれぞれ約120首の歌謡が収録されてい
るが、それらはいずれも和語でつづられた歌を漢字の音を使って書き表したものである。
夜久毛多都 伊豆毛夜弊賀岐 都麻碁微爾 夜弊賀岐都久流 曾能夜弊賀岐袁(記1)
夜句茂多莵 伊都毛夜覇餓岐 莵磨語昧爾 夜覇餓枳莵倶盧 贈廼夜覇餓岐廻(紀1)
この歌は『古事記』と『日本書紀』で文字の選び方
に多少の違いはあるものの、当時のやまとことばを漢字の音を使って表記したものであるという点では一致している。
ところが万葉集になると、さまざまな表記法があら
われてくる。柿本人麻呂の歌についてみてみても、その表記法はさまざまである。
樂浪之 思賀乃辛﨑 雖幸有 大宮人之 船麻知兼津(万30)
左散難弥乃 志我能大和太 与杼六友 昔人二 亦母相目八毛(万31)
東 野炎 立所見而 反見爲者 月西渡(万48)
多麻藻可流 乎等女乎須疑弖 奈都久佐能 野嶋我左吉尒 伊保里須和礼波(万3606)
安麻射可流 比奈乃奈我道乎 孤悲久礼婆 安可思能門欲里 伊敝乃安多里見由
(万3608)
ささなみの志賀の辛﨑幸(さき)くあれど大宮人の船待ちかねつ(万30)
ささなみの志賀の大わだ淀むとも昔の人にまたも逢はめやも(万31)
東(ひむがし)の野に炎(かぎろひ)の立つ見えてかへり見すれば月傾(かたぶ)きぬ
(万48)
玉藻(も)刈る乙女を過ぎて夏草の野嶋の﨑に庵すわれは(万3606)
天離る鄙の長道を戀ひ來れば明石の門(と)より家のあたり見ゆ(万3608)
これらの歌には、さまざまな表記法が用いられてい
る。(万30)と(万31)の歌では日本語の助詞が表記されているが、(万48)の歌では助詞など日本語に特有の機能語はほとんど表記されていない。ま
た、(万3606)と(万3608)では漢字の音のみを使って日本語を表記している
もし、これらの歌が柿本人麻呂の書いた文字をその
まま伝えているとすれば、柿本人麻呂は三つの表記法を使っていたことになる。
○ 古今集
平安時代は日本が内向きになった時代であった。最
後の遣唐使が派遣されたのが838年である。そして、最初の勅撰和歌集である『古今和歌集』が編纂されたのが905年である。正式の文章が漢文であった時
代に紀貫之は『古今和歌集』の序文を仮名で書いた。古今集の仮名序は和文であって、漢字仮名交じり文ではあるものの、漢字は基本的に訓読みを基本とする。
和歌(やまとうた)は、人の心を種(たね)として、万(よろづ)の言(こと)の葉と
ぞなれりける。世の中にある人、事(こと)・業(わざ)しげきものなれば、心に思ふ事
を、見るもの聞くものにつけて、言ひいだせるなり。
古今集は万葉集とはちがい、歌も仮名を基本に書い
てあるので、解読がむずかしいということはない。
袖ひちて むすびし水の こほれるを 春立つけふの 風やとくらん(紀貫之)
夏の夜の 臥(ふ)すかとすれば 郭公鳴く 一こゑにあくるしののめ(きのつらゆき)
河風の すゞしくもあるか うちよする 浪とともにや 秋はたつらし(つらゆき)
雪ふれば 冬ごもりせる 草も木も 春に知られぬ 花ぞさきける(紀貫之)
紀貫之は歌ばかりでなく、『土佐日記』をも仮名で
書いている。
○ 漢学の系譜
しかし、漢文がすたれてしまったわけではない。日
本では内向きの時代と外向きの時代が交互にやってくるといわれている。江戸時代は鎖国の時代であり、内向きの時代であるが、朱子学が重んぜられ、漢籍がよ
く読まれた時代である。
「子曰。學而時習之不亦説乎。有朋自遠方來不亦樂乎。人不知而不愠。不亦君子乎。」
子曰く、学びて時にこれを習う。また説(よろ
こ)ばしからずや。朋(とも)遠方より
來たるあり。また楽しからずや。人知らずして愠
(いきどほ)らず。また君子ならずや。
「子曰。巧言令色鮮矣仁。」
子曰く。巧言令色には鮮(すくな)し仁。
「子曰。五十有五而志于學。三十而立。四十而不惑。五十而知天命。六十而耳順。七十
而従心所欲。不踰矩。」
子曰く。吾五十有五にして学に志す。三十にして
立つ。四十にして惑はず。五十にして
天命を知る。六十にして耳(みみ)順(したが)
ふ。七十にして心の欲する所に従(し
たご)うて、矩(のり)を踰(こえ)ず。
「子曰。温故而知新。可以爲師矣。」
子曰く。故(ふる)きを温(たず)ねて、而して
新しきを知る。以て師となるべしか。
「子曰。學而不思則罔。思而不學則殆。」
子曰く。学んで而して思はざれば則(すなは)ち
罔(くら)し。思ひて而して学ばざれ
ば則ち殆(あやふ)し。
漢文の読み下しは日本語として意味が通るようにす
ること、すなわち翻訳でもあった。ところが、漢字のもっている意味の範囲と日本語のことばの意味の範囲が必ずしも一致しない場合があるからかなりむりをし
た訓も生まれる。
愠(いきどほり)、鮮(すくなし)、踰(こえ
る)、故(ふるき)、温(たずね)、罔(くらし)、殆(あやふし)などは漢籍読み下しに現われる独特
な表現といえるだろう。漢文訓読では同じ漢字ないく通りにも読まれたり、おなじ日本語にさまざまな漢字があてらるということが起こる。次の例は『論語』に
みられる読み方である。
訓読みは漢字に字義の近い和語をあてはめたものだから、同じ文字にいく通りもの読み方がある場合
がある。
事(わざ、つかえる)、孰(いづれ、たれ)、能(あたう・よく)、斉(ひとし・ものいみ)、
与
(あづかる、ともに、あたふ、くみす・ゆるす)、復(また・ふたたび・かへる・ふむ)、
為(たすける・つく
る・をさめる・まなぶ)、悪(アク・にくむ・いずく)、富(さかん・とむ)、
疾(やまひ・やむ・にくむ)、病(やまひ・やむ、うれう)、拒(こばむ・ふ
せぐ)、
慢(あなどる・みだり)に、能(よく・あたふ)、事(つかへる・わざ)、舎(やめる・すてる)、為(たすく・つくる・をさむ)、孰(いづれ・たれ
か)、見(みる・まみへえる)、
識(しるす・しる)慢(あなどる・みだりに)、拒(こばむ・ふせぐ)、希(まれ・すくなし)、
長(たける・とこしへ)、
道(いふ・をさむる)、容(いれる・かたちづくる)、
○ 異字同音
意義の近い漢字に同じ「やまとことば」をあてる場合もしばしばみられる。
寡・鮮(すくなし)、誨・教(をしふ)、仕・事
(つかへる)、適・之・往(ゆく)、
賢・愈(まさる)、羞・恥(はじる)、謗・毀(そしる)、悪・疾(にくむ)、作・爲(なす)、
見・視・観(み)る、患(うれふ)・憂
(うれひ)、拠・依(より)・由(よる)、
蔵(かくす)・隠(かくれる)、撤・舎(すてる)、与・共(ともに)、賢・愈(まさる)、
患・
病(うれふ)、疾・病(やむ)、畏・懼(おそる)、泰・驕(おごる)、輔・扶(たすく)、
博(ひろく)・弘(ひろめる)、貪・求(むさぼる)、尊・尚
(たつとぶ)、赦・縦(ゆるす)、
また、現在ではあまり見られない読み方も行われて
いる。
文(かざ)る、衣(き)る、禱(いの)る、誉
(ほ)める、懐(おも)ふ、畜(やしな)ふ、
行(さる)、反(かへる)、困(くる)しむ、剛(つよ)し、少(わか)し、上(ほと)り、
攘(ぬす)む、賢
(まさ)る、昭(あきら)か、終日(ひねもす)、
これをもって、漢字の読み方の規範とするのであれ
ば、漢字の読み方は何でもありということになってしまう。
○ 国学の伝統
江戸時代には漢学が盛んになるのに対抗するかのよ
うに国学も興隆した。本居宣長は漢心(からごころ)を排することを主張したが、漢学の素養がなかったわけではない。漢字の世界につかりきっていたからこ
そ、そこから抜け出してわが国の独自性を見つめなおそうとしていたともいえる。本居宣長には『漢字三音考』という著作がある。
皇國の正音
皇大御國(スメラオホミクニ)ハ天地の間ニアラユル萬ノ國ヲ御照(ミテラ)シ坐(マ
シ)マス天照大御神(アマテラスオホミカミ)ノ御生(ミアレ)坐(マセ)ル本ツ御國
(ミクニ)ニシテ、卽其御後(ミスヱ)ノ皇統天地ト共ニ動キナク無窮(トコシヘ)ニ
傳ハリ坐(マシ)テ千萬(チヨロズ)御代(ミヨ)マデ天ノ下を統御(シロシメ)ス御
國(ミクニ)ナレバ懸(カケ)マクモ可畏(カシコキ)天皇ノ尊(タフト)ク坐(マシ)
マスコト天地ノ間ニ二ツナクシテ萬國ノ大君(オホキミ)に坐(マシ)マセバ異國々(ア
ダシクニグニ)ノ王等(ドモ)は悉ク臣ト稱シテ吾御國ニ服(ツカヘ)事(マツ)ルベ
キ理リ著明(イチジル)シ。
皇國言語ノ事
皇國ノ古言ハ五十ノ音ヲ出ズ。是レ天地ノ純粹正雅ノ音ノミヲ用ヒテ溷雜不正ノ音ヲ厠
(マジ)ヘザルガ故也。
漢意(からごころ)を排すべしと主張した本居宣長
も漢字を排したわけではなかった。本居宣長の漢字の読み方はほとんどが訓である。それは漢学者の漢文読み下しと同じ方法である。しかし、考え方は漢学者と
同じであったわけではない。日本には文字がなかったから『古事記』などは漢字を借りて書いてあるが、漢字は単なる仮の姿であって、日本古来の「やまとこと
ば」が漢字の陰にかくれているはずである。その「やまとことば」の姿を漢字のなかから読み解くのが本居宣長の生涯をかけた仕事であった。
「無窮」と書いて「トコシヘ」と読ませている。
「千萬(チヨロズ)御代(ミヨ)マデ天(アメ)ノ下(シタ)を統御(シロシメ)ス御國(ミクニ)ナレバ」と読む。国学者本居宣長は平安時代の歌人や日
記の作者よりもむしろ多くの漢字を使っている。しかし、漢語を使っているわけではない。
漢字の訓読みは「やまとことば」に漢字をあてはめ
たものであるから、読みにくい。そこで本居宣長の文章には、ひらがなに漢字でルビをふったものが多い。つぎの文章は『馭戎慨言』の冒頭の部分である。
天日大御神(アマツヒノオホミカミ)の御子(ミコ)の尊(ミコト)の所知食(シロシメス)、此 ≪ノ≫大御国(オホミクニ)に、外国(トツクニ)もろもろまつろひまゐる(朝貢)事の始≪メ≫ をたづぬれば、まづ師木瑞籬宮(シキノミヅガキノミヤ)御宇(アメノシタシロシメシシ)≪崇神≫ 天皇(スメラミコト)の大御代(オホミヨ)の七年に、天皇の大御夢(オホミユメ)に、大物主大神 (オホモノヌシノオホカミ)のみさとしごと有て、同き十一年に、あだし国人(クニビト)あまた 參りきつるよし見えたるは、いづれの国々ともしらねね共、今思ふに、よものほとりの ちひさき 国どものそのかみは、おのおのひとりだちたるをさ(君長)のありけむが、此御代より まつろひ まうき(帰化)きて、皇朝(スメラミカド)のみのりをばうけ(奉正朔)給はり始めけん。
『馭戎慨言』と表題は漢語で、西方の異民族(戎)を支配するにあたっての嘆きのことば(慨言)という意味である。漢字で書いてあることばも、訓で読むために振り仮名が付されている。なかには
ひらがなで書いても、逆に漢字でルビを振って、その意味を漢字で示したものさえみられる。「まつろひまゐる」は「朝貢」、「をさ」は「君長」、「まつろひまうき」は「帰化」、「みのりをはうけ給はり」は「奉正朔」の意味であるこ
とを漢字のルビによって表記している。本居宣長も、ひらがなだけでは意味が伝わらないと考えたからではなかろうか。
○ 福沢諭吉と日本語
明治の日本語は江戸時代の日本語とどのように変
わってきたのであろうか。『福翁自伝』には14、15歳のこととして次のように書かれている。
「塾に居て漢書は如何なるもの読んだかと申すと、経書を専らにして、論語、孟子は勿
論、すべて経義の研究を勉め、殊に先生が好きと見えて詩経に書経と云ふものは本当に
講義をして貰て善く読みました。ソレカラ蒙求、世説、左伝、戦国策、老子、荘子と云
ふやうなものも能く講義を聞き、其先きは私独りの勉強、歴史は史記を始め前後漢書、
晋書、五代史、元朝史略と云ふやうなものも読み、殊に私は左伝が得意で、大概の書生
は左伝十五巻の内三四巻で仕舞ふのを私は全部通読、凡そ十一度び読返して面白いとこ
ろは暗記した。」
明治初期は漢学の伝統のうえに洋学を取り入れた時
代であった。福沢諭吉は漢学から蘭学、蘭学から英学と、学習の重点の移動があった人である。しかし、福沢は明治六年『第一文字之教』の端書において次のよ
うに述べている。
日本ニ文字アリナガラ漢字ヲ交へ用ルハ甚ダ不都合ナレドモ、往古ヨリノ仕来リニテ全
国日用ノ書ニ皆漢字ヲ用ルノ風ト爲リタレバ、今俄ニコレヲ廃セントスルモ亦不都合ナ
リ。今日ノ処ニテハ不都合ト不都合ト持合ニテ、不都合ナガラ用ヲ便ズルノ有様ナルユ
ヘ、漢字ヲ全ク廃スルノ説ハ願フ可クシテ俄ニ行ハレ難キコトナリ。此説ヲ行ハントス
ルニハ時節ヲ待ツヨリ外ニ手段ナカル可シ。
時節ヲ待ツトテ唯手ヲ空フシテ待ツ可キニモ非ザレバ、今ヨリ次第ニ漢字を廃スルノ用
意専一ナル可シ。其用意トハ文章ヲ書クニ、ムツカシキ漢字ヲバ成ル丈ケ用ヒザルヤウ
心掛ルコトナリ。ムツカシキ字ヲサヘ用ヒザレバ、僅ニ千ニ足ラザレドモ、一ト通リノ
用便ニハ差支ナシ。(中略)故サラニ難文ヲ好ミ、其稽古ノタメニトテ、漢籍ノ素読ナド
ヲ以テ子供ヲ窘ルハ、無益ノ戯ト云テ可ナリ。
福沢は幼時に漢学を修めたにもかかわらす、漢字が
日本語を表記するには不便な文字であることに気がついている。「上ル、登ル、昇ル、攀ル」などの字を一々書き分けるのははなはだ面倒だとして、「猿ガ木ニ
攀ルモ、人ガ山ニ登ルモ、日本ノ言葉ニテハ、ノボルト云フユヘ、漢字ヲ用ルヨリモ仮名ヲ用ル方、便利ナリ」ともいっている。
明治維新は文明の規範が中国から西洋に変わるとい
う文明の衝突の時代であった。福沢諭吉より七年前、慶応二年(1866)に前島密は将軍徳川慶喜に「漢字御廃止之義」を建白している。前島密は国民の教育
を普及させるためには、簡易敏捷なる仮名字を専用にして「繁雑不便」で「難解多謬」の漢字を廃止する必要があると唱えた。
また、西周は「洋学ヲ以テ国語ヲ書スルノ論」(明
治7年(1874))を発表している。まさに「脱亜入欧」である。森有礼は明治政府初代の文部大臣であるが、日本語を廃止し英語を採用すべしと主張したこ
とで、その名が今なお知られている。一方、永井荷風のフランス語公用語論を展開している。
現代の眼からみると「馬鹿な」ということになる
が、はじめて西洋の文明に遭遇して、黒船や蒸気機関、エレキテルに圧倒され、漢字文化圏からの離脱を真剣に考えざるをいなかった時代であったのである。
○ 夏目漱石の日本語
明治のはじめ、日本の近代化は初期にはお雇い外国
人によって支えられていた。イギリスに留学して戻ってきた漱石が、ラフカディオ・ハーンの後任として、東京帝国大学文科で英文学講師という地位を得るまで
は大学の授業は英語であった。漱石は幼少時には漢籍中心の教育を受け、イギリスに留学して、英語の本を読むようになった。しかし、西洋の文学にはどこかな
じめなかったようである。漱石は英語で本を読み西欧の思考法を身につけたが、日本語で文学を書いた。
「私(わたし)は殉死(じゆんし)というふ言葉(ことば)を殆(ほとん)ど忘(わす)れてゐまし た。平生(へいぜい)使(つか)ふ必要(ひつやう)のない字(じ)だから、記憶(きおく)の底(そ こ)に沈(しづ)んだ儘(まま)、腐(くさ)れかけてゐたものと見(み)江ます。
妻(さい)の笑 談(ぜうだん)を聞(き)いて始(はじ)めてそれを思(おも)ひ出(だ)した時(と き)、私(わた し)は妻(さい)に向(むか)つてもし自分(じぶん)が殉死(じゆんし)するな らば、明治(めい ぢ)の精神(せいしん)に殉死(じゆんし)する積(つもり)だと答(こた)へま した。
私(わたし)の答(こたへ)も無論(むろん)笑談(ぜうだん)に過(す)ぎなかつたのですが、 私(わたし)は其(その)時(とき)何(なん)だか古(ふる)い不要(ふ江う)な言葉(ことば) に新(あたら)しい意義(いぎ)を盛(も)り得江たやうな心持(こゝろもち)がしたのです。
それから約(やく)一箇(か)月(げつ)程(ほど)經(た)ちました。御大葬(ごたいさう)の夜(よ る)私(わたし)は何時(いつ)もの通(とほ)り書齊(しよさい)に坐(すわ)つて、相圖(あひづ) の號砲(がうはう)を聞(き)きました。
私(わたし)にはそれが明治(めいぢ)が永久(江いきう)に去(さ)つた報知(はうち)の如(ご と)く聞(きこ)江ました。後(あと)で考(かんが)へると、それが乃木大將(のぎたいしやう)の 永久(江いきう)に去(さ)つた報知(はうち)にもなつてゐたのです。
私(わたし)は號(がう)外(がうぐわい)を手(て)にして、思(おも)はず妻(さい)に殉死(じゆ んし)だ殉死(じゆんし)だと云(い)ひました。
『心』は大正3年(1914)朝日新聞に連載され
た小説である。当時の新聞小説はふり仮名が施されていた。ここまで振り仮名をふるのならば、いっそうのこと全部ひらがなで書いてしまったらどうか、と思う
くらいである。しかし、「ひらがな」だけの文章はなおさら読みにくかったのであろう。『坊っちゃん』は最初「ホトトギス」に掲載されたので、振り仮名はな
い。夏目漱石の文章は現代の我々が使っている漢字仮名交じり文に近い。しかし、当時まだ識字率がそう高くなかったので、新聞小説では振り仮名をしたのであ
ろう。『心』は現在は文庫本でも出ているが、ふり仮名はない。
「こころ」先生の遺書56(角川文庫)
「私は殉死という言葉をほとんど忘れていました。平生使う必要のない字だから記憶の底に沈んだ まま、腐れかえていたものとみえます。
妻(さい)の冗談を聞いてはじめてそれを思い出した時、私は妻に向かってもし自分が殉死するな らば、明治の精神に殉死するつもりだと答えました。私の答もむろん冗談にすぎなかったのです が、私はその時なんだか古い不要な言葉に新しい意義を盛りえたような心持ちがしたのです。
それから約一か月ほどたちました。御大葬の夜私はいつものとおり書斎にすわって、あいずの号砲 を聞きました。私にはそれが明治が永久に去った報知のごとく聞こえました。
あとで考えると、それが乃木大将の永久に去った報知にもなっていたのです。
私は号外を手にして、思わず妻に殉死だ殉死だと言いました。
漱石は福沢諭吉と同様に漢籍の素養があったから、
もっと漢語も使いこなすことができたものと思われる。漱石は漢詩もいくつか残している。例えば「遊子吟」という漢詩がある。
樓頭秋雨到
楼頭に秋雨到り
樓下暮潮寒 楼下に暮潮寒し
澤國何蕭索 沢国何ぞ蕭索(さみしい)たる
愁人獨倚欄
紀行文なども漢文で書いている。「木屑錄(ぼくせ
つろく)」は、夏目漱石が、明治22年、23歳のときに友人とともに房総旅行にでかけた漢文紀行である。この頃、漱石はまだ第一高等中学校の生徒であっ
た。
八月復航海遊於房洲登鋸山經二總溯刀川面歸經日三十日行程九十餘里卽歸會秋雨連日閑
居一室懐旅中快樂辛酸之事
この八月にまたしても、船に打ち乗り房州に旅し、鋸山にのぼ
つて両総をあるき、利根
川をさかのぼつて東京にもどつた。旅は前後三十日、行程無慮九十餘里なり。
帰ってからは毎日雨だ。外にも出られずこもりきり。思ひ出すのは旅中のこと、愉快だ
つたもつらかったも、今となつてはなつかしい。(高島俊男『漱石の夏やすみ』)
漱石の時代の知識人は、自分の思うことを漢文でも
日本語文でもかなり自由に用言できるバイリンガルだった。森鴎外も明治17年(1884)にドイツへ留学したがその記録は『航西日記』として漢文で書かれ
ている。その書き出しは次のごとくである。
明治十七年八月二十三日。午後六時汽車発東京。抵横浜。投於林家。此行受命在六月十
七日。赴徳国修衛生学兼詢陸軍軍医也。七月二十八日詣闕拝天顔。辞別宗廟。
明治時代には大衆を対象とした文章には左右に振り
仮名をしたものもあるという。今野真一の『日本語のミッシング・リンク~江戸と明治の連続・不連続』(新潮選書)によると次のような例がみられるという。
左右に振り仮名がある場合は、右が語の発音をあらわし、左が語義の補助的説明をしていることが多い。
例:丹羽純一郎『龍動(ろんどん)新(しん)繁盛(はんじょう)●記』
漢字
右振り仮名
左振り仮名
星霜
セイソウ
トシツキ
落成
ラクセイ
デキアガリ
髣髴
ハウホツ
サモニタリ
遊泳
ユウエイ
オヨグ
彷徨
ハウクワウ
サマヨヒ
万葉の昔から日本人は漢字を手なづけて、日本語を
書く方法を模索し続けてきた。その模索は明治時代に入ってからも続いていたわけである。
古墳時代から明治時代までの日本語の表記法を駆け
足でみたが、日本語の表記法は現在でも完全に解決したわけではない。日本語をいかに表記するかとい問題は小学校の「こくご」の教科書にまで受け継がれてい
る。
