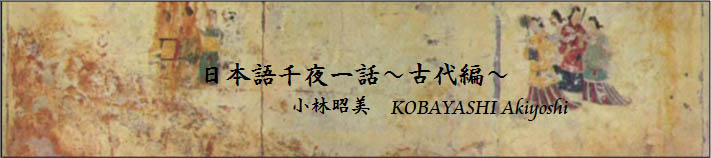
第
159話 『渋江抽斉』の日本語を解剖する
『渋江抽斉』は鴎外晩年の長編で、いわゆる史伝も
のに属する。石川淳はこれを鴎外の最高傑作だとしている。ここでは『渋江抽斉』の作品論ではなく、鴎外がどのような日本語を使ってこの晩年の傑作を書いた
か、を検証してみることにしたい。『渋江抽斉』は大正五年一月一三日『東京日日新聞』に森林太郎の名で第一回が掲載された。その冒頭の部分を当日の新聞で
見てみると、まず冒頭の部分は漢詩からはじまる。
三十七年如一瞬。學醫傳業薄才伸。榮枯窮達任天命。安樂換銭不患貧。これは澀江抽齊(ちうさい)の述志の詩で
ある。想ふに天保十
二年の暮に作つた
ものであらう。弘前の城主津軽順承(よりつぐ)の定府の醫官で、當時近習詰に
なつてゐた。
漢字に歯はルビが振ってあるが漢詩にはルビはない。漢詩は次のように読む。「三十七年一瞬の如し。医
を学び業を伝えては薄才伸ぶ。栄枯窮達は天命に任す。安楽貧に換え銭に患えず。」これは渋江抽斉の詩であるが、鴎外は人時代前の弘前藩の典医に自分自身を
見た。抽斉は医者であり、官吏であった。経書や諸子のような哲学の書を読み、歴史を読み、詩文集のような書も読んだ。抽斉は四十年足らずの月日を家業であ
る学医として過ごし、栄達は天命に任せてきた。貧を患えず安楽を得ている、と抽斉はいっている。しかし、鴎外はこの詩のことばのなかに抽斉の諦観をみだし
ているのである。鴎外は続けて書いている。
此詩を瞥見す
れば、抽齊は其貧に安(やす)ん
じて、自家の材能を父祖傳來の醫業の上に施し
て
ゐたかとも思はれ
よう。しかし私は抽の不平が
二十八字の底に隱さ
れてあるのを見(み)
ずにはゐられない。、、、老驥櫪に伏すれども、志千里に在りと云ふ意(い)が此中に蔵せられてゐる。
森鴎外は明治の時代を生き、ドイツで西洋医学を
学んだ第一世代の近代人だが、その教養の基礎は漢学にあった。鴎外の作品では漢詩が多く出てくるわけではないが、その日本語表現の底には漢学があり、その
文字使いは四書五経を読んだ人のそれである。
『渋江抽斉』には、当時使われていた外来語もで
てくる。煙草・烟草(タバコ)、煙管(キセル)、莫大小(メリヤス)、虎列拉(コレラ)、加答児(カタル)などである。キセルはカンボジア語に由来すると
いわれている。しかし、鴎外の日本語が現代の日本人にとって読みにくいのは外来語が多いからでも、漢語が多いからでもない。『渋江抽斉』の一部を読んでみ
ることにする。
わたくしは少い時から多読の癖があって、随分多く書を買う。わたくしの俸銭の大部分
は内地の書肆と、ベルリン、パリイの書估との手に入ってしまう。しかしわたくしはか
つて珍本を求めたことがない。或る時ドイツのバルテルスの『文学史』の序を読むと、
バルテルスが多くの書を読もうとして、廉価の本を渉猟し、『文学史』に引用した諸家の
書も、大抵レクラム版の書に過ぎないといってあった。わたくしはこれを読んで私かに
殊域同嗜の人を獲たと思った。(その二)
(ダイブブン)、内地(ナイチ)、書肆(ショ
シ)、書估(ショコ)、珍本(チンポン)、
学史(ブンガクシ)、序(ジョ)、廉価(レン
カ)、本(ホン)、渉猟(ショウリョウ)す
る、引用(インヨウ)する、諸家(ショカ)、大
抵(タイテイ)、版(ハン)、殊域(シュ
イキ)、同嗜(ドウシ)、
【訓読漢字】少(わか)い、時(とき)、癖(く
せ)、多(おお)く、買(か)う、手(て)
入(い)る、求(もと)める、或(あ)る、読
(よ)む、過(す)ぎない、私(ひそか
に、人(ひと)、獲(え)る、思(おも)う、
いて、勢(いきおい)集団教育の法に従(したが)わざるを得(え)ない。そしてその
弊を拯(すく)うには、ただ個人教授の法を参取する一途があるのみである。是(ここ)
において世(よ)には往々昔(むかし)の儒者の家塾を夢(ゆめ)みるものがある。然
(しか)るにいわゆる芸人ひ名取(なとり)の制があって、今(いま)なお牢守せら
ていることには想(おも)い及(およ)ぶものが鮮(すくな)い。(その百十八)
前の例文では「おもう」に「思う」があてられて
いたが、この文章では「想(おも)う」が当てられている。訓は漢字の意味に相当する日本語をあてるわけだから、同じ日本語にいくつかの漢字が当てられるこ
とが多い。
かす、鬆(ゆる)める、喪(うしな)う、纏(まと)う、翫(もてあそ)ぶ、儆(いま
しめ)る、遽(にわか)に、纔(わずか)に、聊(いささ)か、肆(ほしいまま)、輒(た
やすく)、闌(たけなわ)、
駐留、継続、教誨、看視、知識、過誤、譴責、困苦、依拠、捕捉、謀議、窮極、娯楽、
これらの漢字に対応する訓は同じである。
聴聞(きく)、怨恨(うらむ)、覚醒(さめる)、遭遇(あう)、墜落(おちる)、断絶(た
つ)、停止(とどめる)、駐留(とどめる)、継続(つぐ)、教誨(おしえる)、看視(みる)、
知識(しる)、過誤(あやまち)、譴責(せめる)、困苦(くるしむ)、依拠(よる)、捕捉
(とらえる)、謀議(はかる)、窮極(きわめる)、娯楽(たのしむ)、
漢字を使って表記しているからといって中国語を 表記しているのではなく、日本語を表記しているのだから「見る」あるいは「みる」と表記すればすむのではなかろうか。しかし、幼少のころから漢学を通じて 漢字の世界に親しんできた鴎外にとっては別の見方があったに違いない。漢字を使っている限り、その漢字の用法は漢字の本場である中国のそれに限りなく近い ものでなければならない。そこで、まず漢字で文章を構成する。そしてその漢字に日本語をあてはめていく、ということが行われていたのではないか。漢字の意 味が先にあって、それに日本語をあてはめていく。だから、日本語の読み方、訓は漢字の翻訳になる。
ことのり)、魁(さきがけ)、媒(なこうど・なかだち)、杯(さかずき)、諱(いみな)、
堆(うずたか) く、幼(いとけな)い、慮(おもんばか)る、顧(かえりみ)る、覆
(くつがえ)る、 抛(なげう)つ、指(ゆびさ)す、挟(さ
しはさ)む、
先(さ
きだ)つ、
媒人(なこうど)、草鞋(わらじ)、足袋(たび)、石灰(しっくい)、土器(かわらけ)、
記念(かたみ)、揶揄(からかう)、可笑(おか)しい、所以(ゆえん)、就中(な
かんずく)、
菜蔬は最も莱菔(だいこん)を好んだ。生で食うときは大根(だいこん)おろしにし、
烹て食うときはふろふきにした。(その六十二)
「魚」は魚(うお)に、「肴」は肴(さかな)に 用いられているらしい。「幼」は「幼(いとけな)い」に用いられ「穉」が「穉(おさない)」に用いられている。煙草を「のむ」ときは「喫(の)む」が使わ れている。しかし、同じ文脈のなかで同じ文字を使うのを避けている場合もしばしばみられる。
に掛かると、仙台藩の哨兵線に出合った。銃を擬した兵卒が左右二十人ずつ轎(かご)
を挟んで、一つ一つ戸を開けさせて誰何する。(その八十一)
常に弊衣を著(き)ている竹逕が、その頃から絹布を被(き)るようになった。(その九
十一)
あった。(その百十五)
の述志の詩である。想ふに天保十二年の暮に作つたものであらう。弘前の城主津軽順承
の定府の醫官で、當時近習詰になつてゐた。
ゐたかとも思はれよう。しかし私は抽齊の不平が二十八字の底に隱されてあるのを見
ずにはゐられない。、、、老驥櫪に伏すれども、志千里に在りと云ふ意が此中に蔵せられ
てゐる。
【音読字】年、一瞬、医、業、薄才、栄枯、窮達、天命、安楽、抽斉、述志、詩、天保
十二年、城主、定府、医官、当時、近習、瞥見、貧、自家、材能、父祖、伝来、医業、
不平、二十八字、老驥、櫪、千里、蔵、
【訓読字】如(ごと)し、学(まな)ぶ、伝(つた)える、伸(の)ばす、任(まか)
す、貧(まず)しい、銭(ぜに)、換(か)える、患(わずら)う、不・ず、生(い)か
す、渋江(しぶえ)、心(こころ)、述(の)べる、想(おも)う、暮(くれ)、作(つく)
る、弘前(ひろさき)、津軽(つがる)、順承(ゆきつぐ)、詰(つ)める、此(この)、
其(それ)、安(やす)んじる、上(うえ)、施(ほどこ)す、思(おも)う、私(わたく
し)、底(そこ)、隠(かく)れる、見(み)る、馬(うま)小屋(こや)、伏(ふ)す、
志(こころざし)、在(あ)り、云(い)う、中(なか)、
【その他】三十(サンジュウ)七(なな)年(ネン)、
てきた。栄枯窮達は天命に任せ。貧しさに患わされるのともなく安楽を得ている。これ
は渋江抽斉が心のうちを述べた詩である。思うに天保十二年の暮に作ったものであろう。
弘前の城主である津軽順承の定府の医者で、当時は近習詰めになっていた。
の上に施していたかと思われよう。しかし私は抽斉の不平が二十八字の底に隠されてあ
るのを見ずにはいられない。、、、老いた馬は馬小屋に伏すけれども、志は千里にあり、と
いう気持ちがこの中に込められている。
名詞や動詞など意味をになう単語をすべて漢字で
表記しようとしても、常用漢字だけでは足りない。しかし、明治時代の日本語である鴎外や漱石の文章を常用漢字で表記しようとすれば、それは不可能とはいえ
ない。むしろ問題は漢字の数よりも、訓読みの漢字をど
のように用いて日本語を表記するかにあるのではなかろうか。
つまり、「生える、
生やす」のときは「生(は)」、「生まれる、生む」
のときは「生(う)」、「生(ショウ)じる」のときは「生(ショウ)」と読む。送り仮名のない時は「生(なま)」
または「生(き)」となる。つまり現代の日本語の表記は「書いてある順番」では読めない。活用語尾をまず確認して、その後に漢字にもどって、その読み方を
決めるという、極めて変則的な表記法になっているということである。
中国語を表記するために発明された漢字を使っ て、日本語をどのように表記するかという万葉集の時代からの課題はまだ完全に解決されたわけではない。
