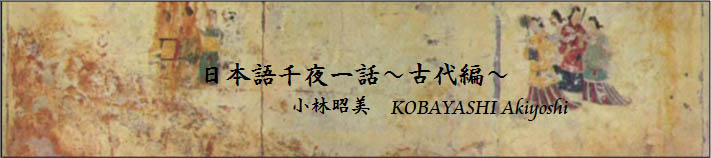
第156話
夏目漱石の言語生活
夏目漱石は慶応三年(1867)に生れた。明治改元の前年であり、良寛が示寂した
天保二年(1831)から三十六年後のことである。
漱石は明治七年(1874)浅草寿町の戸田小学校に入学している。このころの
小学校の教科書には洋学者による西洋の教科書の翻訳が多く、たいていは漢文直訳体であったという。その後、明治十二年(1879)に、その頃神田一ツ橋にあった府立一中(現在の日
比谷高校)に入学している。当時の中学校には正則中学校と変則中学校があり、府立一中は正則中学校であった。変則中学校では授業は英語で行われていたが、
正則中学校である府立一中では普通の授業は日本語ばかりで行われていた。漱石は一旦府立一中に入学したが、英語を習わなくては大学予備門へ進むことができ
ないと知ると、失望して退学した。
○漢学か英学か
ところが漱石は府立一中を退学したにもかかわらず、英語学校に転じようとはせず、漢学塾である二松学舎に移った。二松学舎では講義は朝の6時か、7時こ
ろから始まる。二松学舎では『日本外史』『十八史略』『小学』『蒙求』『文章規範』などを学び、さらには『唐詩選』『孟子』『史記』『論語』『唐宋八家
文』『前後漢書』へと進む。しかし、漱石が二松学舎に在学していたのは約一年間だけである。二松学舎を退いてから、明治十六年(1883)には大学予備門受験の目的で英語習得のために成立
学舎に入る。
儒学から洋学へ転換しつつある時代に、英語を学ぶためには、変則中学に転じなければならなかった。「考えて見ると漢籍許り読んでこの文明開化の世の中に
漢学者になった処仕方なし」と漱石は『落第』のなかで振り返っている。
漱石が生れた時代は、江戸時代の儒教的文化が作
るあげた世界像が崩れ落ちようとしている時代であった。漱石は近代的な学制によって教育された日本人の最初のジェネレーションに属していた。しかし、儒学
から洋学への転換は一朝にして行われたわけではない。当時の学校教育の根底にあったのはやはり依然として漢学であった。漱石も洋学よりは漢学により多くの
親近感を覚えていた。
漱石はとにかく大学に入って何かを学ぼうと決心
する。明治一七年(1884)神田一ツ橋の大学予備門予科に入学した。同級生に
南方熊楠などがいた。明治二一年(1888)には第一高等学校に進み、同級生に正岡子規がい
た。明治二三年(1890)には東京帝国大学文科大学英文科入学する。当時東
京大学の教官はほとんどがお雇い外国人であった。漱石は英文学が漢文学のようなものなら生涯を捧げて悔いはないと決心したのであった。『文学論』序で漱石
は次のように述べている。
余は少時好んで漢籍を学びたり。之を学ぶ事短かきにも関らず、文学は斯くの如き者な
りとの定義を漠然と冥々裏に左国史漢より得たり。ひそかに思ふに英文学も亦かくの如
きものなるべし、斯の如きものならば生涯を挙げて之を学ぶも、あながち悔ゆることな
かるべしと。余が単身流行せざる英文科に入りたるは、全く此幼稚にして単純なる理由
に支配せられたるなり。(『文学論』序)
起掌之下端稍坦平可坐數人其上巑岏開張如簦望之欲墜不墜如惴惴焉有不安者
湾の南端に巨岩があり、高さは五丈、上は豊かで、下は削られ巨人の拳(こぶし)のよ
うである。砉然(けきぜん)として地を裂いて起っている。掌(たなごころ)の下端は
やや平坦で数人が座ることができる。その上は巑岏(さんがん)として、開帳すること
簦(とう)のごとし。これを望めば墜(お)ちんとして墜ちず、惴惴(ずいずい)焉(え
ん)として安んぜざる者あるごとし。
・明治二八年愛媛県尋常中学校(松山中学)に赴任。子規の指導のもとに句作に打ち込む。
・明治二九年熊本の第五高等学校へ赴任。四年間を過ごす。教え子に寺田寅彦。
・明治三三年文部省から二年間の英国留学を命じられる。漱石三十四歳。
漢籍に親しみ、儒学、ことに朱子学の価値観を学んだ漱石にとって、英学は優越する西洋文明を学ぶためのものでなければならないはずであった。
大学在学中に漱石はJ.M.ディクソンの依頼で「方丈記」を英訳している。英
語名は”A Description of My Hut”である。明治二六年(1893)大学を卒業すると、「ジャパン・メール」の記者を
志願し、禅について英語の論文を提出したが不採用に終わった。入学当初からの夢であった、西洋人に伍して英語で文学上の著作をしようとした抱負が崩れはじ
めた。漱石は迷っている。
イギリスに留学中、漱石は英詩を作りはじめる。
漢学を学んだものにとって漢詩を作ることは必須の教養であった。漱石は英学を学んだ以上英詩を作ろうと決意したにちがいない。漱石は十二篇の英詩を残して
いる。そのうちのひとつに”I looked at
her”が
ある。
I
looked at her as she looked at me;
見
つめられ、その女(ひと)と目を合わす
We
looked and stood a moment, 二
人はしばし佇む
Between
Life and Dream
夢
か現か
We
never met since;
た
だそれだけの出会いだった
Yet
oft I stand
それなのに、しばしば私は佇む
In
the primrose path
サ
クラソウの小径に
Where
Life means Dream.
夢
は現
Oh
that Life could
おう、現は
Melt
into Dream,
夢
に忍びこむ
Instead
of Dream
夢
よ
Is
constantly
いつまでも消えないで、
Chased
away by Life!
現
にもどさないでくれ!
(November27,1903)
○英文学は男子一生の仕事か
その後の漱石は明治三六年(1903)小泉八雲の後任として東京帝国大学英文科講師にな
り、第一高等学校講師も兼任することになる。東京帝国大学では漱石は『マクベス』『リア王』『ハムレット』などを講じている。漱石は外国文学の批評的鑑賞
をするにも、日本人の標準をもってすることに意義があると考えた。しかし、漱石の考え方が英国人の見方と違う場合、自分の考え方を押し通すにはイギリス文
学は漱石からはあまりにも遠かった。漱石は漢学からきた文学観念をもって英文学を読んだ。しかし、漢学の価値観をもってイギリス文学をみることには限界が
あったともいえる。漱石はイギリス文学に打ち込みつつも迷い続けている。
能
もなき教師とならんあら涼し
薔薇ちるや天似孫(テニソン)の詩見厭(みあき)たり
明治三八年(1905)高浜虚子のすすめで『吾輩は猫である』を「ホトト
ギズ」に発表した。その評判はあまりにも高く、漱石は日本文学の作家として身を立てることを決意するにいたる。
明治四十年(1907)朝日新聞入社して『虞美人草』などを発表した。漱
石は『虞美人草』を書くために『文選』を読みなおしたという。漱石は自分の文学の思想をイギリス文学ではなく、漢学に求めていたともいえる。もっとも
「猫」の諧謔はスウィフトの影響があるともいわれるから、漱石がイギリス文学を捨てたというわけではないだろう。しかし、漱石が英詩を作ることをやめた後
も漢詩を作り続けたことは事実である。
○修善寺の大患
明治四三年胃潰瘍で療養中、大量に吐血し生死の際をさまよった。いわゆる修善寺の大患は漱石の人を見る目、世の中を見る目、自然を見る目をも変える人生
の大事だった。以降漱石は老荘に近づいて行く。いわゆる「即天去私」つまり「天に則(のっと)り、私を去る」という思想である。天とはつまり自然である。
自然に従い己を去る、という意味である。『思いだす事など』には漱石自身の作った次のような漢詩がみられる。
黙然見大空
黙
然として大空を見る
大空雲不動
大
空に雲動かず
終日杳相同
終
日杳(よう)として相(あい)同じ
「則天去私」の思想については専門家の間でも見
方が分かれる。漱石の弟子の小宮豊隆が「則天去私」に純化していった、と考えるのに対して江藤淳は「それから」を経て「明暗」に至る彼の一貫した我執の主
題の原動力になっていると主張して、見解を異にしている。小宮には、漱石は「則天去私」の悟達をめざして、これを達成した聖人と見えた。漱石が晩年、弟子
たちとの会合で、しばしば「則天去私」を話題の中心にしていたことは、阿倍能成もくわしく書いているから、漱石が東洋の思想に傾いていたことは否定できな
いだろう。齢五十にして達した「則天去私」と青春時代に身につけた「近代自我」が漱石のなかで葛藤し、作品の創造に結びついている。いつの時代にも、古い
酒袋の酒を新しい酒でけに詰めかえることはそう簡単ではない。
○漱石の個人主義
大正五年(1916)、晩年の漱石は『明暗』連載開始し、午後は日課と
して漢詩を作る。一方で『明暗』執筆中の漱石は大正三年(1914)は学習院で『私の個人主義』という講演もしてい
る。その記録をみると、漱石が西洋流の個人主義を肯定していることがわかる。
私はこの自己本位という言葉を自分の手に握ってから大変強くなりました。彼ら何する
者ぞという気概が出てきました。いままで茫然と自失していた私に、ここに立って、こ
の道からこう行かなければならないと指図をしてくれたものは実にこの自我本位の四字
なのであります。
晩年の漱石は東洋文明に先祖がえりして、西洋文
明のことは忘れてしまったのかというと、それはそう簡単ではない。漱石は漢学を受け入れる時には何の疑問ももたなかった疑問を、英学について持ってしまっ
たのです。『明暗』は「則天去私」ということばも「個人主義」ということばも一回もでてこない。
しかし、晩年の漱石
は個人主義への懐疑のために、禅家風な虚無主義を他方の端に描いてみる。日本の近代化の必然性をみてとっている反面、近代の個性の発達をめざす積極主義へ
の懐疑に立たされる。そして、老荘的無為を半信半疑の間にあこがれる。
ご存じの通り英吉利(イギリス)という国は大変自由を尊ぶ国であります。それほど自
由を愛する国でありながら、また英吉利ほど秩序の調(ととの)った国はありません。
実をいうと私は英吉利を好かないのです。嫌いではあるが事実だから仕方なしに申しあ
げます。あれほど自由でそうしてあれほど秩序の行き届いた国は恐らく世界中にないで
しょう。日本などは比較にもなりません。しかし彼らはただ自由なのではありません。
自分の自由を愛するとともに他の自由を尊敬するように、小供の時分から社会的教育を
ちゃんと受けているのです。
○老荘への回帰
『行人』連載中の大正三年頃から、漱石はしきりに南画風の水彩画をたしなみ、また良寛の書に傾倒していく。つてを求めて良寛の書を手に入れたときの喜び
を漱石は書簡に次のように書いている。「良寛上人の筆跡はかねてより希望にて、年来御依頼致置候処今回非常の御奮発にて、、、漸く御入手下され候由、近来
になき好報、感謝のことばもなく、ひたすら恐縮致候」。漱石が入手した良寛の書は七言絶句と和歌であったという。
芳草連天春将暮 桃花乱点水悠々 我亦従来忘機者 悩乱光風殊未休
わがやどを たづねてきませ あしひきの やまのもみぢを たよりがてらに
漱石は『明暗』を書きながら、毎日午後は漢詩の 詩作を楽しんでいた。大正五年十二月九日死去の二十日前の詩(十一月十九日)である。
五十春秋瞬息程
五
十の春秋 瞬息(しゅんそく)の程(てい)
觀道無言只入静
道
を観(み)るに 言(げん)無くしてただ静に入り
拈詩有句獨求清
詩
を拈(ひね)りて句有れば独(ひと)り清(せい)を求む
迢迢天外去雲影
迢
迢(ちょうちょう)たり天外去雲(きょうん)の影
籟籟風中落葉聲
籟
籟(らいらい)たり風中落葉(ちょうよう)の声
忽見閑窓虚白上
忽
(たちま)ち見る閑窓(かんそう)虚白(きょはく)の上
東山月出半江明
東
山(とうざん)月出でて半江(はんこう)明(あ
きら)か
なり
漱石は明治四四年「文芸と道徳」と題する講演の
なかで、「私は明治維新の丁度前の年に生れた人間でありますから、どちらかといふと中途半端な教育を受けた海陸両棲動物のような怪しげなものでありま
す。」とも述べている。漱石は江戸の道徳や思想を受け継ぎ近代の思想との間で悩み抜き、それを一身に受け止めたために神経衰弱にもなった。漱石は漢学を愛
していた。英文学の世界が漢学にかわりうるものであるかについては晩年になっても懐疑的であった。明治維新の革命と反革命が漱石のなかでは、最後までせめ
ぎ合っていた。
漱石の心情は子規とともに楽しんだ俳句のなかに 残されている。それは漢学的でもなく、英学的でもなく、まさに日本人漱石の心のうちを映している。そのことも見逃してはなるまい。漱石は漢学をおさめ、英 学をおさめ、ついに文人になった。
有る程の菊抛(な)げ入れよ棺の中
古里に帰るは嬉し菊の頃
肩に来て人懐かしや赤蜻蛉
思う事只一筋に乙鳥(つばめ)かな
朝寒も夜寒も人の情かな
