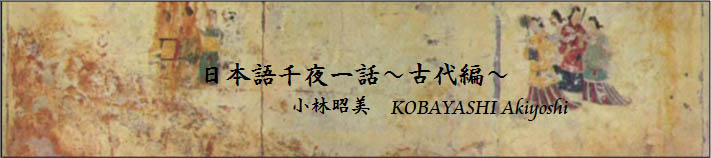
第
155話 良寛禅師の言語生活
○良寛「儒」を学ぶ
良寛は十二歳の頃から約六年間、大森子陽という儒者について漢籍を主とする基礎的な教養を身につけた。学んだ本は『論語』や『文選』だろうという。
江戸時代は学問といえば漢学の時代であるといえる。幕府の学校や藩校では朱子学(儒学)が講じられ、僧侶たちは漢訳仏典によって仏教を学んだ。頼山陽は
『日本外史』を漢文で書いた。庶民の間でも和漢混淆文で書かれた『太平記』がもてはやされていた。『太平記』はまた、講談の世界でも喝采を博していた。講
談の世界もまた耳で聞く漢文の世界であった。詩吟の世界では頼山陽の「川中島」がもてはやされていた。
鞭聲粛々夜過河
鞭
聲粛々夜河(かわ)を過(わた)る
暁見千兵擁大牙
暁
(あかつきん)に見る千兵の大牙を擁するを
遺恨十年磨一剣
遺
恨なり十年一剣を磨(みが)き
流星光底逸長蛇
流
星光底長蛇を逸す
良寛が大森子陽の塾に通い「論語」を愛読したこ
とは、後年のおびただしい論語抄録の遺墨が証明している。
一思少年時
一
たび思う、少年の時、
讀書在空堂
書
を読んで空堂(人気ない部屋)に在り。
燈火數添油
燈
火、数々(しばしば)、油を添へ、
未厭冬夜長
未
だ厭(いと)わざりき、冬夜の長きを。
良寛は、やがて十八の頃、尼瀬の曹洞宗光照寺に入って禅僧としての修業をはじめる。儒教的世界から仏教的世界への転身である。さらに二十二歳のとき、國
仙和尚に随行して備中玉島の圓通寺に行き、そこで三十四歳にいたるまで修業した。禅の修行の中心は坐禅である。仏教の経典はいわゆる漢訳仏典である。中国
を経て伝えられた仏教の世界もまた漢文の世界である。坐禅をくみ、仏典を読んで、そのなかで自分をみつめる。その心のうちが漢詩となって表される。
自來圓通寺
円
通寺に来たってより
幾度經冬春
幾
度か冬春を経たる
衣垢聊自濯
衣
垢(あか)づけば聊(いささか)自ら濯い
食盡出城闉
食
尽くれば城闉(じょういん)を出づ
門前千家邑
門
前千家の邑(むら)
更不知一人
更
に一人を知らず
曾讀高僧傳
曽
(かつ)て高僧伝を読む
僧伽可清貧
僧
伽は清貧を可とす
良寛は円通寺で道元の『永平禄』を読み、『法華
経』を読み、『論語』を読んだ。そして『寒山詩』に親しんだ。『六祖伝』や『龐居士語禄』もとりだして読んでいたと思われる。なかでも道元の『正法眼蔵』
は必読書であった。良寛は円通寺で独り『永平禄』すなわち道元の著作に没入した。「讀永平録」という長い漢詩を残している。その冒頭の部分は次のようには
じまる。
春夜蒼茫二三更
春
夜蒼茫たり二三更
春雨和雪灑庭竹
春
雨、雪に和して庭竹に灑(そそ)ぐ
欲慰寂寥良無由
寂
寥を慰めんと欲するも良(まこと)に由なく
背手模索永平禄
背
手に模索す永平禄
曹洞禅の祖道元は、只管打坐、ひたすら坐禅をす
ることをすすめる。一方、曹洞宗では、一に作務、二に座禅、三に看経といわれ、日常の勤労を重視していた。宋の時代、中国では仏教自体が老荘的発想を同化
していた。
憶在圓通時
憶
う、円通に在りし時
恆歎吾道孤
恒
に吾が道の孤なるを歎ぜしを
般柴懐龐公
柴
を般(はこ)んでは龐公(ほうこう)を懐(おも)い
踏碓思老盧
碓
(うす)を踏んでは老盧を思う
入室非敢後
入
室、敢て後(おく)るるに非ず
朝參常先徒
朝
参、常に徒(と)に先んず
一自從散席
一
たび席を散じてより
悠々三十年
悠
々たり三十年
山海隔中州
山
海、中州を隔て
消息無人傳
消
息、人の伝ふるなし
感恩竟有涙
恩
に感じて竟(つい)に涙あり
寄之水潺湲
之
れ寄す水の潺湲(せんえん)たるに
龐公は中国の馬祖一の弟子で、いつも柴運びをし
ていたといわれる。老盧は唐の時代八カ月ひたすら米をついていたという。ともに作務実践の禅者である。入室とは、師に問うために室に入ることで、朝参と
は、早朝に方丈の義礼に参加することをいう。
良寛は三十三歳の冬、師から印可を受け、その証として偈うけた。師の国仙は良寛について漢詩を残している。
良也如愚道轉寛 良
や、愚の如く、道轉(うたた)寛(ひろ)し
騰々任運得誰看 騰
々任運、誰か看るを得ん
爲附山形爛藤杖 為
に山形爛藤の杖を付す
到處壁間午睡閒 到
る処の壁間午睡閒(閑)たり
「愚」ということばは荘子にも出てくることばのようであるが、悟達のひとつの手がかりであった。愚であることは、まず己への執着を捨てることである。良
寛自身の心境は次の詩に表わされている。
辛苦描虎猫不成
辛
苦、虎を描いて猫も成らず
箇中意志人倘問
箇
中の意志、人倘(も)し問はば
只是從來榮蔵生
只
是れ従来の栄蔵生
○良寛「万葉」を学ぶ
良寛は仏教の世界での栄達は求めず、托鉢僧になる道を選ぶ。そしてやがて良寛は故郷越後に帰り五合庵の住人となる。ここでは良寛は万葉集を愛読し、万葉
調の歌を作る。良寛が万葉集に親しみ、万葉調の歌を詠むようになったのは、五合庵に移ってからのことだと考えられている。良寛の書簡には万葉集を貸してほ
しいという依頼などが残されている。
あしびきの
國
上の山の
山もとに
い
ほりをしつつ
朝ゆふに
岩
のかげ道
踏みわけて
い
往き還(かへ)らひ
山みれば
山
も見がほし
里みれば
里
も賑(にぎ)はし
春されば
椿
花さき
秋べには
野
べに妻(つま)とふ
小男鹿(さをしか)の 聲をともしみ
あらたまの
年
の十(と)とせは
過ぎにけるかも
五合庵は国上(くがみ)山の山腹、寺泊の東北、
海の見えるところにある。建て坪は四坪半、八畳一間の庵である。五合庵は良寛の生き方を具現した庵でもある。良寛には国上山や五合庵を詠った歌や詩がいく
つかある。
あしひきの国上の山を今もかも鳴いて越ゆらむ山ほととぎず
あしひきの国上の山の山畑に蒔きし大根(おほね)ぞあさず食(を)せ君
山かげの岩間に伝ふ苔水のかすかに我はすみわたるかも
月よみの光を待ちてかへりませ山路は栗のいがの多きに
水や汲まむ薪や伐(こ)らむ菜やつまむ朝のしぐれの降らぬその間に
和可布留散束
我
が古里
波あ礼耳け理
は
荒れにけり
尓者裳萬閑起もお
庭
も真垣も落
知者能みし天
ち
葉のみして
か多み登あ散
形
見と朝
由ふ尓佐渡能
夕
に佐渡の
志まべ遠宇ち見
島
べをうち見
都る可母
つ
るかも
末之良奴東
ま
じらぬと
爾者
に
は
安羅禰止毛
あ
らねども
非登利安処非曾 ひ
とり遊びぞ
和礼は
我
は
末左礼留
ま
される
良寛は備中玉島の円通寺で二十二歳から三十四歳まで十二年間禅の修行をした。その後、越後に帰り五合庵などに住まい托鉢僧として過ごした。良寛さんはよ
く歌を詠み、漢詩を作った。
里にい行けば玉鉾(たまほこ)の 道のちまたに子供らが いまを春べと手まりつく
ひふみよいむな 汝(な)がつけば あはうたひ あがつけば 汝はうたひ
つきて歌ひて霞たつ 永き春日を暮らしつるかも
反歌
霞たつ永き春日を子供らと手毱つきつつこの日暮らしつ
この里に手毬(てまり)つきつつ子どもらと遊ぶ春日はくれずともよし
歌もよまむ手毬もつかむ野にも出む心ひとつをさだめかねつも
良寛は儒を学び、禅を学び、万葉を学び、漢詩を作り、歌を詠んだ。それは天下国家のためでもなく、立身出世のためでもなかった。そのなかで良寛がついに
見つけたものは何だったのだろうか。
少年參禅不傳燈
少
年、禅に参ずれど燈を伝えず
今結草庵爲宮守
今、
草庵を結んで宮守(みやもり)と為(な)る
半似社人半似僧
半
ばは社人に似、半ばは僧に似たり
騰々任天眞
騰
々、天眞に任(まか)す
嚢中三升米
嚢
中、三升の米
爐邊一束薪
爐
邊、一束(いっそく)の薪(たきぎ)
誰問迷悟跡
誰
か問はん、迷悟の跡
何知名利塵
何
ぞ知らん、名利の塵
夜雨草庵裡
夜
雨、草庵の裡(うち)
雙脚等閒伸
雙
脚、等閒に伸ばす
災難をのがるる妙法にて候
