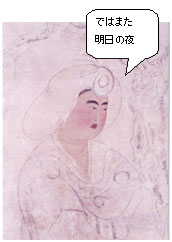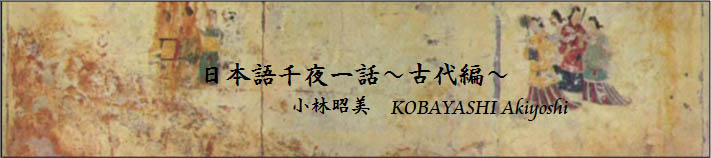
【あ・あれ(我・吾)】
吾
(あ)を待(まつ)と君(きみ)が沾(ぬれ)けむあしひきの山(やま)の四附(しずく)に成(なら)益(まし)物(もの)を(万108)
紫 草(むらさき)の尓保敝類(にほへる)妹(いも)をにくく有(あら)ば人嬬(ひとづま)故(ゆえ)に吾(あれ)戀(こひ)めやも(万21)
春
(はる)去(され)ば水草(みづくさ)の上(うへ)に置(おく)霜(しも)の消(け)つつも我(あれ)は戀(こひ)度(わたる)かも(万1908)
「我」「吾」の古代中国語音は我[ngai]、吾[nga]である。日本漢字音は我(ガ)、吾(ゴ)でとかん
がえられている。しかし、中国語の原音は鼻濁音(我<カ゜>吾<コ゜>であり、日本語では鼻濁音が語頭にくることがない。そのため、中国語の疑母[ng-]は脱落して我・吾(あ)となって万葉集にはあらわ
れている。朝鮮漢字音では中国語の疑母[ng-]規則的に脱落して、我(a)、吾(o)となる。古代日本語の音韻体系は朝鮮語に近く、我
(あ)、吾(あ)は我(a)、吾(o)に近い。
語頭の[ng-]が脱落した例としては魚(うお)御(お)などがあ
る。魚(うお)、御(お)の朝鮮漢字音は魚(eo)、御(eo)である。
「我」「吾」は我・吾(あれ・われ)としても使わ
れる。音表記の歌では「阿礼、安礼、阿例、 和礼、和例」のような表記もみられる。中国語の疑母[ng-]は合口音であり、発音の方法が日本語のワ行に近
い。
○同源語:
君(きみ)、沾(ぬれる・濡)、山(やま)、草
(くさ)、妹(いも)、嬬(つま・妻嬬)、春(はる)、置(おく)、霜(しも)、消(きえる)、度(わたる・渡)、
【あか(赤)】
赤
帛(あかきぬ)の純裏衣(ひたうらごろも)長(ながく)欲(ほり)我(わが)思(おもふ)君(きみ)が不レ所レ見
(みえぬ)ころかも(万
2972)
例:脱[thuat]・悦[jiuat]、抽[thiu]・由[jiu]、多[tai]・侈[thjiai]・移[jiai]、除[dia]・餘[jia]、秩[diet]・佚[jiet]、 台[də]・飴[jiə]、除[dia]・予[jia]、澤[deak]・驛[jyak]、談[dam]・炎[jiam]、誕[dan]・延[jian]、濯
[diôk]・躍[jiôk]、桶[dong]・甬[jiong]など
○同源語:
帛(きぬ・巾)、裏(うら)、長(なが)き、我
(われ)、思(おもふ・念)、君(きみ)、見(みる)、
未
通女(をとめ)等(ら)が放(はなりの)髪(かみ)を木綿山(ゆふのやま)雲(くも)莫(な)蒙(たなびき)家(いへの)當(あたり)将レ見
(みむ)(万
1244)
飛
鳥(とぶとりの)明日香(あすか)の里(さと)を置(おき)て伊奈(いな・去)ば君(きみ)が當(あたり)は不レ所レ見
(みえず)かもあらむ(万
78)
古代日本語の地名に當麻というのがある。万葉集
の時代には「當麻」は「たぎま」と読んだ。現在では「當」は「たぎ」とは読めなくなり、「当麻寺」は「たいまでら」である。「當」の読みは「たぎ」→「あ
たり」→「たい」あ
るいは「とう」と変化してきたのであろう。
○同源語:
未通女(をとめ・女)、放(はな)つ、山(や
ま)、雲(くも)、莫(な)、家(いへ)、見(みる)、飛(とぶ・跳飛)、鳥(とり)、置(おく)、伊奈(いな・行)ば、君(きみ)、
二
並(ふたならぶ) 筑波(つくば)の山(やま)を 欲レ見
(みまくほり) 君(きみ)來(き)座(ませり)と 熱(あつげく)に 汗(あせ)かきなげ 木根(このね)取(とり)、、
(万1753)
例:熱(yeol)、肉(yuk)、児(a)、耳(i)、乳(yo)、日(il)、若(yak)、柔(yu)、譲(yang)、入(ip)など、
日本語の熱(あつい)、若(わかい)、柔(やわ
ら)、譲(ゆずる)、入(いる)などは中国語の日母[nj-]の脱落したものである。
同源語:
山(やま)、見(みる)、君(きみ)、来(く
る)、熱(あつ)き、木(き・枝)、根(ね)、取(とる)、
【あはれ([忄可]*怜)】
家
(いへ)有(なら)ば妹(いも)が手(て)将レ纏
(まかむ)草枕(くさまくら)客(たび)に臥有(こやせる)此(この)旅人(たびびと)[忄
可]*怜
(あはれ)(万
415)
住
吉(すみのえ)の崖(きし)に向有(むかへる)淡路嶋(あはぢしま)[忄
可]*怜
(あはれ)と君(きみ)を不レ言
(いはぬ)日(ひ)は无(なし)(万3197)
○同源語:
家(いへ)、妹(いも)、手(て)、草(くさ)、
臥(こやす)、此(こ)れ、住(すむ)、向(むか)ふ、嶋(しま・洲)、君(きみ)、無(な)し、
【あふ(相・合・
逢・會・遇)】
左
散難弥乃(ささなみの)志我(しが)の大和太(わだ)与杼六(よどむ)とも昔人(むかしのひと)に亦(また)も相(あは)めやも(万31)
戀 (こひし)けく氣(け)長(ながき)物(もの)を可レ合 有(あふべかる)夕(よひ)だに君(きみ)が不二來 益一有 (きまさざる)らむ(万 2039)
風 (かぜ)不レ吹 (ふかぬ)浦(うら)に浪立(なみたち)無(なき)名(な)をも吾(われ)は負(おへる)か逢(あふ)とは無(なし)に(万2726)
月 かさね吾(わが)思(おもふ)妹(いもに)會(あへる)夜(よ)は今(いま)し七夜(ななよを)續(つぎ)こせぬかも(万2057)
中
々(なかなか)に 辭(こと)を下延(したばへ)不レ遇
(あはぬ)日(ひ)の 數多(まねく)過(すぐれ)ば、、(万1792)
万葉集では日本語の「あふ」に相[siang]・合[həp]・逢[biong]・會[huat]・遇[ngio]が使われている。「相」がもっとも多く使われてい
るが、「相」は日本語の「あふ」とは音が乖離している。相[siang]は省[sieng]と音義が近く、「視る」という意味である。万葉集
で多く使われている相(あふ)は訓借である。日本語の「あふ」は古代中国語の合[həp]の語頭音が脱落したものであろう。中国語の[h-]、[x-]は喉音であり脱落することもある。
例:回(カイ・ヱ)、懐(カイ・ヱ)、禍(カ・
ワ)、黄(コウ・オウ)、行(コウ・ゆく)、横 (オウ・ゆく)、恨(コン・うらむ)、
○同源語:
難弥・浪(なみ)、与杼六(よどむ・澱)、長(な
がい)、物(もの)、夕(よひ・夜)、君(きみ)、來(くる)、立(たつ)、無(な)き、名(な)、吾(われ・わが)、思(おもふ・念)、妹(いも)、夜
(よる)、今(いま)、續(つぐ)、辭(言・こと)、
【あふぐ(仰)】
ひ
さかたの天(あめ)見(みる)如(ごとく)仰(あふぎ)見(み)し皇子(みこ)の御門(みかど)の荒(あれ)まく惜(をし)も(万168)
韻尾の[-ng]の上古音は[-g]に近かった。日本漢字音でも北(ホク)が北条(ホ
ウジョウ)、卓が追悼(ツイトウ)などと音便化することがある。
天(あめ)、見(みる)皇子(みこ・御子)、御
(み)、門(かど)、
【あま(天)】
秋
風(あきかぜの)吹(ふき)ただよはす白雲(しらくも)は織女(たなばたつめ)の天(あま)つ領巾(ひれ)かも(万2041)
天
原(あまのはら)振(ふり)放(さけ)見(みれ)ば大王(おほきみ)の御壽(みいのち)は長(ながく)天足(あまたらし)たり(万147)
「天」の古代中国語音は天[thyen]である。中国語の声母[th-]は有気音(閉鎖音のあと強い吐気を発する)であ
り、日本語にはない音である。声母[th-]は後に[-y-]などの介音が来るとき脱落することがある。日本語
の天(あま)は古代中国語の声母透[th-]が脱落したものである。同じ声符をもった漢字でも
口蓋化の影響で頭音の
脱落したものがみられる。
声母[th-]脱落の例:脱[thuat]・悦[jiuat]、痛[thong]・俑[jiong]、他[thai]・也[jia]、湯[thang]・ 陽[jiang]、
抽[thiu]・由[jiu]、
○同源語:
雲(くも)、女(め)、天(あめ)、原(はら)、
見(みる)、大王(おほきみ・君)、御(み)、長(なが)き、
【あま(海子・海部)】
網
引(あびき)する海子(あま)とや見(みらむ)飽浦(あくのうらの)清(きよき)き荒礒(ありそを)見(みに)來(こし)吾(われを)(万1187)
後
(おくれ)居(ゐて)戀(こひ)つつ不レ有(あらずは)田籠(たご)の浦(うら)の海部(あま)ならましものを玉藻(たまも)苅(かる)苅(かる)(万3205)
海女(あま)は海[muə]の頭音に母音(あ)を添加したものであろう。マ行
音の語頭には母音(う)が添加されることもある。海(うみ)、梅(うめ)、馬(うま)、などがその例である。
○同源語:
網(あみ)、見(みる)、清(きよき)、荒(あ
れ)る、來(くる)、吾(われ)、居(ゐ)る、田(た)、籠(こ)、苅(かる)、
【あみ(網)】
ひ
さかたの天(あま)歸(ゆく)月(つき)を網(あみ)に刺(さし)我大王(わごおほきみ)は蓋(きぬがさ)にせり(万240)
霍
公鳥(ほととぎす)雖レ聞
(きけども)不レ足
(あかず)網取(あみとり)に獲(とり)てなづけなかれず鳴(なく)がね(万4182)
○同源語:
天(あめ)、歸
(ゆく・行)、刺
(さ)す、我(わが)、大王(おほきみ・君)、
霍公鳥(ほととぎす・隹)、取(とる)、鳴(なく)、
【あも(母)】
都
乃久尒(津の國)の宇美(うみ・海)の奈伎佐(なぎさ)に布奈餘曾比(ふなよそひ・船装)たしでも等技(とき・時)に阿母(あも)が目(め)もがも(万4383)
○同源語:
津(つ)、久尒(くに・國)、宇美(うみ・海)、
布奈(ふな・盤)、等技(とき・時)、目(め)、
【あや(綾)】
錦
(にしき)綾(あや)の 中(なか)につつめる 齊兒(いはひご)も 妹(いも)に将レ及
(しかめや)、、(万
1807)
例:柳(やなぎ)、梁(やな)、陸(をか)、陵
(をか)、良(よき)、
朝鮮漢字音では中国語の[l-]は次に介音[-i-]を伴う場合は規則的に脱落する。(介音[-i-]を伴わない場合は[n-]に転移する。)
例:柳(yu)、梁(yang)、陸(yuk)、良(yang)、両(yang)、旅(yeo)、力(yeok)、歴(yeok)、連(yeon)、練
(yeon)、
戀(yeon)、列(yeol)、劣(yeol)、猟(yeop)、領(yeong)、零(yeong)、例(ye)、
○同源語:
中(なか)、兒(こ)、妹(いも)、
【あゆ(鮎・年魚)】
毎
年(としのはに)鮎し走(はしら)ば左伎多河(さきたがは)鸕(う)八頭(やつ)可頭氣(かづけ)て河瀬(かはせ)多頭祢(たづね)む(万4158)
櫻
田(さくらだ)へ鶴(たづ)鳴(なき)渡(わたる)年魚市方(あゆちがた)塩(しほ・潮)干(ひ)にけらし鶴(たづ)鳴(なき)渡(わたる)(万271)
鮎を年魚と書くのは年[nyen]と鮎[niem]と通じるかである。鮎が一年で生を終えるからとい
のは俗説であろう。鮎は中国では「なまず」のことであるが、日本では鮎(あゆ)は万葉集の時代から食用として珍重されてきた。鸕(う)で鮎をとる漁法も今
と同じである。
○同源語:
河(かは)、鸕(う・烏)、瀬(せ・湍)、田
(た)、鳴(なく)、渡(わたる)、塩(しほ・潮)、干(ひる)、
【あらし(下風・嵐)】
窓
(まど)超(ごし)に月(つき)おし照(てり)てあしひきの下風(あらし)吹(ふく)夜(よ)は公(きみ)をしぞ念(おもふ)(万2679)
○同源語:
照(てる)、夜(よ)、公(きみ)、念(おもふ)
【あれる(荒)】
風
吹(かぜふきて)海荒(うみはあるとも)明日(あすと)言(いはば)應レ久
(ひさしかるべき)公(きみが)随(まにまに)(万1309)
荒[xuang]は日本語では荒(コウ・あれる)となる。日本語に
は喉音[x-]がないので日本漢字音ではカ行であらわれる。訓の
荒(あれる)は中国語の喉音[x-]が脱落したものである。
喉音[h-][x-]が脱落した例:顕[xian](あらはす)、漢[xan](あや)、現[hyan](あらはす)、合[həp]・
会[huai](あふ)、或[hiuək](ある)、汚垢[hiua-ko](あか)、など
○同源語:
海(うみ)、公(きみ)、
【あらはす(顕)】
隠
(こもり)耳(のみ)戀(こふれ)ば辛苦(くるし)山葉(やまのは)ゆ出(いで)來(くる)月(つき)の顕(あらはさ)ば如何(いかに)(万3803)
顕[xian]の日本漢字音は顕(ケン)である。古代中国語音の
喉音は日本漢字音ではカ行であらわれる。しかし、古代日本語には喉音がないから訓(弥生時代・古墳時代の借用音)では頭音が脱落している。頭音は次に[-y-]あるいは[-i-]の介音が続くときに脱落しやすい。
例:許[xia](キョ・ゆるす)、訓[xiuən](クン・よみ)、穴[hyuet](ケツ・あな、休[xiu](キュウ・やす む)、など
○同源語:
隠(こもる・籠)、苦(くる)し、山(やま)、出
(いで)、來(くる)、如何(いか)に、
【いき(息・氣)】
日
(ひる)は うらさび 晩(くら)し 夜(よる)は息(いき)衝(づき)明(あか)し雖レ歎
(なげけども) 為便(せむすべ)不レ知
(しらに)、、(万
213)
黒
(くろ)かりし 髪(かみ)も白(しら)けぬ ゆなゆなは 氣(いき)さへ絶(たえ)て 後(のち)遂(つひに) 壽(いのち)死(しに)ける、、(万1740)
万葉集では「いき」は息、伊企、伊伎、伊吉、氣
などと表記されているが、日本語の「いき」は中国語の息[siək]と同源であろう。心母[s-]、山母[sh-]などの頭音は脱落しやすい。
頭音が[-i-]介音の前で脱落した例:秈[shean](セン・いね)、山[shean](セン・やま)、色[shiək] (ショク・いろ)、生[sheng](セイ・ショウ・いく・いきる)、宵[siô](ショウ・よい)、夕
[zyak](セキ・ゆう)、矢[sjiei](シ・や)、世[sjiat/sjiai](セ・よ)、逝[zjiat/zjiai](セイ・ゆく)、 洗 [syən](セン・あらう)、舎[sjia](シャ・や)、相[siang](ソウ・あふ)など
例:射[djyak/djyai](シャ・いる)、折[tjiat](セツ・おる)、織[tjiək](ショク・おる)、植(ショク・ うえる)など
同じ声符の漢字をサ行とヤ行に読みわけている漢
字もある。同じ声符号の漢字の音に頭音の脱落したものとそうでないものがあることから、このような頭音の脱落は日本に来てからおこったものではなく、なく
中国で隋唐の時代以前に起こっていたものと考えられる。
例:除(ジョ)・餘(ヨ)、序(ジョ)・予
(ヨ)、施(シ)・也(ヤ)、侈(シ)・移(イ)、
失(シツ)・佚(イツ)など
○同源語:
夜(よる)、衝(つく)、歎(なげ)く、知(し)
る、黒(くろ)い、絶(たえる)、死(し)ぬ、
【いきる(生)】
生
死(いきしに)の二海(ふたつのうみ)を厭(いとはし)み潮干(しほひ)の山(やま)を之努比(しのび)つるかも(万3849)
死
(しに)も生(いき)も 公(きみ)がまにまと 念(おもひ)つつ 有(あり)し間(あひだ)に、、(万1785)
古代中国語の「生」は生[sheng]である。日本漢字音は生(セイ・ショウ・いきる)
である。中国語の[sh-][sj-][si]などの音は口蓋化によって頭音が脱落することが多
い。
例:釋[sjyak]・驛、舒[sjia]・預[jia]、錫[syek]・易、秀[siu]・誘[jiu]、詳[ziang]・羊[jiang]、誦[ziong]・
甬[jiong]、涎[zian]・延[jian]、
日本漢字音でも訓では頭母音が脱落した例がいく
つかみられる。
例;山[shean](セン・やま)、矢[sjiei](シ・や)、世[sjiat](セ・よ)、宵[siô](ショウ・よひ)、
洗 [syən](セン・あらふ)、相[siang](ソウ・あふ)、赦[sjyak](シャク・ゆるす)、逝[zjiat]
(セイ・ゆく)、
日本語の「いきる」も、生[sheng]の頭音が脱落し、韻尾の[-ng]がカ行に転移したと考えれば、中国語の「生」と同
系のことばである可能性がある。
○同源語:
死(しに)す、海(うみ)、厭(いとふ)、潮(し
ほ)、干(ひる)、山(やま)、公(きみ)、念(おもふ)、
【いく(幾)】
相
(あひ)見(み)ては幾日(いくか)も不レ經
(へぬ)をここだくも久流比(くるひ)に久流必(くるひ)所レ念
(おもほゆる)かも(万
751)
白
浪(しらなみ)の濱松(はままつ)が枝(え)の手向(たむけ)草(くさ)幾代(いくよ)までにか年(とし)を經(へ)ぬらむ(万34)
○同源語:
相(あふ・合)、見(みる)、經(へる)、久流
比・久流必(くるひ・狂)、念(おも)ふ、浪(なみ)、濱(はま)、枝(え)、手(て)、向(むけ)る、草(くさ)、代(よ・世)、
【いたし(痛)】
今
朝(けさ)の旦開(あさけ)鴈(かり)が鳴(ね)聞(きき)つ春日山(かすがやま)黄葉(もみちに)けらし吾(わが)情(こころ)痛(いた)し(万1513)
霞
(かすみ)立(たつ) 長(ながき)春日(はるひ)の 晩(くれに)ける わづきも之良受(しらず) 村(むら)肝(きも)の 心(こころ)を痛(いた)
み、、、(万
5)
「痛」の古代中国語音は痛[thong]である。日本語の痛(い+たし)は中国語の痛[thong]の語頭に母音「い」を添加したものであろう。悼
(い+たむ)も悼[dô]の語頭に母音「い」が添加されたものである。
古代日本語では濁音が語頭にくることはなかっ
た。そのため、語頭に濁音のある語には母音が添加された。出[thiuət] は出(い+づる)となり、泉[dziuan] は泉(い+づみ)となったと考えることができる。
○同源語:
鴈(かり)、鳴(ね・音)、山(やま)、吾
(わ)、情(こころ・心)、霞(かすみ・霞霧)、長(なが)い、晩(くれ・昏)、知(し)る、村(むら・郡)、肝(きも)、
【いたる(至・到・及)】
渡
守(わたりもり)船(ふね)度(わた)せをと呼(よぶ)音(こゑ)の不レ至
(いたらね)ばかも梶聲(かぢのおと)の不レ為
(せぬ)(万
2072)
将レ待 (まつらむ)に到(いたら)ば妹(いも)が懽(うれしみ)と咲(ゑまむ)儀(すがた)を徃(ゆき)て早(はや)見(みむ)(万2526)
吾
(わが)背子(せこ)が著(はける)衣(きぬ)薄(うすし)佐保風(さほかぜ)は疾(いたく)莫(な)吹(ふきそ)及レ家
(いへにいたる)まで(万
979)
○同源語:
渡(わたる)、守(もり・護)、船(ふね・盤)、
音(こゑ・聲)、聲(おと・音)、妹(いも)、徃(ゆく・行)、見(みる)、吾(わが)、背子(せこ)、衣(きぬ・巾)、家(いへ)、
【いづ(出)】
あ
しひきの従レ山
(やまより)出(いづ)る月(つき)待(まつ)と人(ひと)には言(いひ)て妹(いも)待(まつ)吾(われ)を(万3002)
椋
橋(くらはし)の山(やま)を高(たかみ)か夜隱(よごもり)に出(いで)來(くる)月(つき)の光(ひかり)乏(ともし)き(万290)
母音を添加する例は梅(バイ・うめ)、馬(バ・
うま)などにもみられる。出(いづる)の「る」は中国語の韻尾[-t]の転移したものである。
○同源語:
山(やま)、妹(いも)、吾(われ)、椋(くら・
倉)、夜(よる・よ)、隠(こもる・籠)、來(くる)、光(ひかり)、
【いづみ(泉)】
家
人(いへひと)に戀(こひ)過(すぎ)めやも川津(かはづ)鳴(なく)泉(いづみ)の里(さと)に年(とし)の歴(へ)去(ぬれ)ば(万696)
山
代(やましろ)の泉(いづみの)小菅(こすげ)なみなみに妹(いもが)心(こころを)吾(わが)不レ念
(おもはなくに)(万
2471)
古代中国語の「泉」は泉[dziuan]である。日本語の「いづみ」は一般に「出(いづ)
+水(みづ)」と解釈されているが、音韻的には古代中国語の泉[dziuan]の語頭に「い」が添加されたものであろう。
○同源語:
家(いへ)、過(すぎる)、川津(かはづ・蝦)、
鳴(なく)、歴(へる・經)、山(やま)、小(こ)、菅(すげ)、妹(いも)、心(こころ)、吾(わが)、念(おもふ)、
【いとふ(猒・厭)】
何
為(なにす)とか君(きみ)に将レ猒
(いとはむ)秋芽子(あきはぎ)の其(その)始花(はつはな)の歎(うれし)き物(もの)を(万2273)
霍
公鳥(ほととぎす)厭(いとふ)時(とき)無(なし)菖蒲(あやめぐさ)蘰(かづらに)将レ為
(せむ)日(ひ)従レ此
(こゆ)鳴(なき)度(わた)れ(万1955)
例:除・余、脱・悦、桃・姚、湯・陽、蝶・葉、
談・炎、
中国語の韻尾[-p]は日本漢字音ではタ行で現われることが多い。
例:立[liəp]・リツ、湿[siəp]・シツ、接[tziap]・セツ、摂[siap]・セツ、など
○同源語:
君(きみ)、芽子(はぎ)、其(そ)の、花(は
な)、物(もの)、霍公鳥(ほととぎす・隹)、時(とき)、無(な)し、蘰(かづら・葛)、此(こ)れ、鳴(なく)、度(わたる・渡)、
【いぬ(犬・狗)】
吾
(わが)待(まつ)公(きみを) 犬(いぬ)莫(な)吠(ほえ)そね(万3278)
狗
上(いぬかみ)の鳥籠山(とこのやま)なる不知也河(いさやがは)不知(いさ)二五(とを)寸許瀬(きこせ)余(わが)名(な)告(のらす)な(万2710)
頭音脱落の例:弓[kiuəm]・(キュウ・ゆみ)、丘[khiuə]・(キュウ・おか)、今[kiəm]・(コン・
いま)、寄[kiai]・(キ・よる)、居[kia]・(キョ・ゐる)、挙[kia]・(キョ・あげる)、吉[kiet]・ (キツ・よき・よし)、禁[kiəm]・(キン・いむ)など
同じ声符をもった漢字でカ行とア行に読みわける
ものもいくつかあげることができる。
例:奇[kiai](キ)・椅[iai](イ)、季[kiuet/kiuei](キ)・委[iuai](イ)、貴[kiuəi](キ)・遺[jiuəi] (イ・ユイ)などである。国[kuək](コク)・域[hiuək](イキ)、廣[kuang](コウ)・黄 [huang] (コウ・オウ)・横[hoang](オウ・よこ)
日本語の「いぬ」は犬[khyuan]の頭音が脱落したものであり、「犬」と同源であ
る。狗[ko]は現代の中国語では「犬」一般に使われているが、
原義は「子犬」である。
○同源語:
吾(わが)、公(きみ)、莫(な)、吠(ほえ)
る、鳥(とり)、籠(こ)、山(やま)、川(かは・河)、余(わが・我)、名(な)、
【いぬ・ぬる(寐)】
阿
騎(あき)の野(の)に宿(やどる)旅人(たびびと)打(うち)靡(なびき)寐(い)も宿(ね)らめやも古部(いにしへ)念(おもふ)に(万46)
山 (やま)越(こし)の風(かぜ)を時(とき)じみ寐(ぬる)夜(よ)不レ落 (おちず)家(いへ)なる妹(いも)を懸(かけ)てしのびつ(万6)
例:無[miua]ない、名[mieng]な、鳴[mieng]なく、眠[myen]ねむる、
日本語の「ねる」に近いことばには眠[myen]がある。「眠」は「ねむる」ことである。
○同源語:
野(の)、打(うつ)、靡(なびく)、念(おも
ふ)、山(やま)、越(こす)、時(とき)、夜(よる)、落(おちる・堕)、家(いへ)、妹(いも)、懸(かける)、
【いね(稲・秈)】
住
吉(すみのえ)の岸(きし)を田(た)に墾(はり)蒔(まきし)稲(いね)さて及レ苅
(かるまでに)不二相
見一(あ
はぬ)公(きみ)かも(万
2244)
戀
(こひ)つつも稲葉(いなば)搔(かき)別(わけ)家(いへ)居(をれ)ば乏(ともしくも)不レ有
(あらず)秋(あき)の暮(ゆふ)風(かぜ)(万2230)
例:山[shean](サン・やま)、色[shiək](シキ・いろ)、生[sheng](セイ・ショウ・いきる)、
矢[sjiei](シ・や)、舎[sjya](シャ・や)、世[sjiat](セ・よ)、小[siô](ショウ・を)、
宵[siô](ショウ・よひ)、夕[zyak](セキ・ゆうべ)、石[zjyak](セキ・いし)、相[siang]
(ソウ・あ
ふ)、息[siək](ソク・いき)、
同じ声符をもった漢字でもサ行の頭音が脱落する
ものがみられる。
例:説・悦、徐・余、舒・野、涎・延、詳・羊、
同源語:
田(た)、墾(はり)、蒔(まく・播)、苅(か
る)、相(あふ・合)、公(きみ)、葉(は)、搔(かく)、家(いへ)、居(を)る、暮(ゆふ・夜)、
【いのる(禱・祈)】
哭
澤(なきさは)の神社(もり)に三輪(みわ)すゑ雖二禱
祈一(い
のれども)我王(わごおほきみ)は高日(たかひ)所レ知
(しらし)ぬ(万
202)
乾
坤(あめつち)の神(かみ)を禱(いのり)て吾(わが)戀(こふる)公(きみ)い必(かならず)不レ相
在(あはざらめ)やも(万
3287)
○同源語:
哭(なく・泣)、我王(わごおほきみ、君)、知
(しる)、乾坤(あめつち、天・地)、神(かみ)、吾(わが)、公(きみ)、相(あふ・合)、
【いへ(家)】
此
(この)岳(をか)に 菜(な)採(つま)す兒(こ) 家(いへ)吉閑(きかな) 名(な)告(のら)さね、、(万1)
戀
死(こひしなば)戀(こひも)死(しねと)や我妹(わぎもこが)吾家(わぎへの)門(かどを)過(すぎて)行(ゆくらむ)(万2401)
例:姫[kiə](キ・ひめ)、機[kiei](キ・はた)、蓋[kat](ガイ・ふた)、干・乾[kan](カン・
ひる)、果[kuai](カ・はて)、光[kuang](コウ・ひかり)、広[kuang](コウ・ひろい)、
經[kyeng](ケイ・へる)、頬[kyap](キョウ・ほお)、
日本語の「いへ」は家(へ)の語頭に母音が添加
されたものである可能性がある。二番目の歌(万2401)では吾家(わぎへ)で
あり、「家」は家(へ)である。万葉集では家(いへ)は単語の語頭にあらわれ、語中では家(へ)となる。
○同源語:
此(こ)の、岳(をか)、菜(な)、兒(こ)、死
(しぬ)、我・吾(われ)、過(すぎる)、行(ゆく)、
【いま(今)】
今
更(いまさらに)何(なに)をか将レ念
(おもはむ)打(うち)靡(なびく)情(こころ)は君(きみ)に縁(より)にし物(もの)を(万505)
月
(つき)累(かさね)吾(わが)思(おもふ)妹(いもに)會(あへる)夜(よ)は今(いま)し七夕(ななよを)續(つぎ)こせぬかも(万2057)
○同源語:
念・思(おもふ)、打(うつ)、靡(なび)く、情
(こころ・心)、君(きみ)、縁(よる・寄)、物(もの)、吾(わが)、妹(いも)、會(あふ・合)、夜・夕(よ)、續(つぐ)、
【いまだ(未)】
暁
(あかとき)と夜烏(よがらす)雖レ鳴
(なけど)此(この)山上(もり)の木末(こぬれ)の於(うへ)は未(いまだ)静(しづけ)し(万1263)
妹
(いもが)門(かど)入(いり)出見(いづみ)川(かは)の床奈馬(とこなめ)に三雪(みゆき)遺(のこれり)未(いまだ)冬(ふゆ)かも(万1695)
「未」の古代中国語音は未[miuət]である。中国語の明母[m-]は古代日本語では語頭に母音が添加されることが多
い。
例:夢[miuəng]いめ、妹[muət]いも、馬[mea]うま、味[miuət]うまし、美[miei]うまし、梅[muə]うめ、
海[(h)muə*]うみ、埋[məi]うもる、
日本語の「いまだ」は中国語の「未」と音義ともに
近く、同源である。
○同源語:
暁(あかとき・暁時)、夜(よる)、烏(からす・
鴉+隹)、鳴(なく)、此(こ)の、木(き・枝)、静(しづか)、妹(いも)、門(かど)、入(いる)、出(でる)、見(みる)、川(かは・河)、床(と
こ)、馬(うま・め)、
【いむ(忌・禁)】
隠
沼(こもりぬ)の従レ裏
(したゆ)戀(こふれ)ば無乏(すべをなみ)妹(いもが)名(な)告(のりつ)忌(いむべき)物(もの)を(万2441)
「忌」の古代中国語音は忌[giə]である。記紀万葉では忌、斎などの文字が用いられ
ているが、『名義抄』には「禁、諱、忌、斎・イム」としてあり、日本語の「いむ」は音義ともに禁[kiəm]に近い。「いむ」は禁[kiəm]の頭音が脱落したものであろう。禁忌は成語であ
り、日本語の「いむ」は「禁」と同源であろう。
○同源語:
隠(こもる・籠)、無(な)む、妹(いも)、名
(な)、物(もの)、
【いめ(夢)】
夢
(いめ)の相(あひ)は苦有(くるしかり)けり覺(おどろき)て掻(かき)探(さぐれ)ども手(て)にも不レ觸
(ふれね)ば(万
741)
あ
しひきの夜麻(やま・山)伎(き・来)敝奈利(へなり・隔)て等保(とほ・遠)けども許己呂(こころ)し遊氣(ゆけ・行)ば伊米(いめ・夢)に美要(み
え)けり(万
3981)
○同源語:
相(あふ・合)、苦(くる)しき、掻(かく)、手
(て)、伎(き・來)、許己呂(こころ・心)、遊氣(ゆけ・行)、見(みる)、
【いも(妹)】
石
見乃(いはみの・野)や高角山(たかつのやま)の木際(このま)より我(わが)振(ふる)袖(そで)を妹(いも)見(み)つらむか(万132)
言
(こと)不レ問
(とはぬ)木(き)すら妹(いも)と兄(せ)と有(ありと)云(いふ)を直(ただ)獨子(ひとりご)に有(ある)が苦(くるし)さ(万1007)
古代日本語の「いも」は男から妻や恋人、姉妹な
どの親しい女性を呼ぶ名称である。「妹」古代中国語音は妹[muət]である。しかし、日本語の「いも」は中国語の
「妹」より意味の範囲が広いが、「妹」と同系のことばであろう。
○同源語:
乃(の・野)、山(やま)、木(き・枝)、我(わ
が)、袖(そで)、妹(いも)、見(みる)、言(こと)、子(こ)、苦(くるし)さ、
【いる(入)】
天
原(あまのはら)雲(くも)無(なき)夕(よひ)にぬばたまの宵(よ)度(わたる)月(つき)の入(いら)まく恡(を
し)も(万
1712)
古代中国語の「入」は入[njiəp]である。日母[nj-]は広東語や朝鮮語では脱落することが多い。また、
現代北京語では日本(ri
ben)の
ようにrに転移している。
古代中国語の韻尾[-p]は広東語や朝鮮語では保たれているが、上海語では[-p][-t][-k]の区別が失われている。現代北京語では入声韻尾[-p][-t][-k]は完全に失われている。日本漢字音では中国語の韻
尾[-p]はタ行で発音されることが多い。
例:厭[iap]アツ、立[liəp]・リツ、湿[siəp]シツ、接[tziap]セツ、摂[siap]セツ、
|
古代中国語音 |
広東語 |
上海語 |
北京語 |
朝鮮漢字音 |
|
入[njiəp] 日[njiet] 肉[njiek] |
yahp yuht yuhk |
zek zek nik |
ru ri rou |
ip il yuk |
同源語:
天(あめ)、原(はら)、雲(くも)、無(な)
き、宵(よひ・夜)、夕(よる・夜)、度(わたる・渡)、
【いや(弥)】
去
年(こぞ)見(み)てし秋(あき)の月夜(つくよ)は雖レ照
(てらせれど)相(あひ)見(み)し妹(いも)は弥(いや)年(とし)放(さかる)(万211)
従二蘆 邊一(あ しべより)満(みち)來(くる)塩(しほ・潮)の弥(いや)益(まし)に念(おもへ)か君(きみ)が忘(わすれ)かねつる(万617)
昔
(むかひ)見(み)し象(きさ)の小河(をがは)を今(いま)見(みれ)ば弥(いよよ)清(さやけく)成(なり)にけるかも(万316)
彌[miai]→(介音[-i-]の発達)→邇[njiei]→弥[jiai]
中国語の日母[nj-]が頭子音が失われることが多い。朝鮮漢字音では中
国語の日母[nj-]は規則的に脱落して爾(i)、邇(i)、 彌(i)になる。日本漢字音の彌(や)は朝鮮漢字音の影響
を受けたものである。古代日本語の音韻構造は朝鮮語のそれに似ている。
朝鮮漢字音の例:如(yeo)、入(ip)、弱い(yak)、柔(yu)、
日本語の例:如何[njia-]いかに、入[njiəp]いる、弱[njiôk]よわし、柔[njiu]やわら、
日本語の弥(や・いや)は弥[miai]が介音[-i-]の影響で弥[njiai]になり、さらにその頭音が脱落したものであろう。
○同源語:
見(みる)、夜(よる)、照(てる)、相(あふ・
合)、妹(いも)、邊(へ)、満(みつ)、來(くる)、潮(しほ)、念(おもふ)、君(きみ)、忘(わす)る、小(を)、河(かは)、今(いま)、清(さ
やけ)し、
【いる・いゆ(射)】
大
夫(ますらを)の得物矢(さつや)手挿(たばさみ)立(たち)向(むかひ)射(い)る圓方(まとかた)は見(みる)に清潔(さやけ)し(万61)
所レ射
(いゆ)鹿(しし)をつなぐ河邊(かはべ)の和草(にこぐさの)身(みの)若(わか)かへに佐宿(さね)し兒(こ)らはも(万3874)
○同源語:
矢(や)、插(はさむ・挟)、立(たつ)、向(む
か)ふ、見(みる)、清潔(さやけし)、河(かは)、邊(へ)、和(にこ・柔)、草(くさ)、身(み)、若(わか)き、宿(ねる・寐)、兒
(こ)、
【いろ(色)】
秋
時(あきの)花(はな)種(くさぐさ)に有(あれ)ど色(いろ)ごとに見(め)し明(あき)らむる今日(けふ)の貴(たふと)さ(万4255)
色
(いろに)出(いで)て戀(こひ)ば人(ひと)見(み)て應レ知
(しりぬべし)情(こころの)中(うち)の隠妻(こもりづま)はも(万2566)
「色」の古代中国語音は色[shiək]である。日本語の色(いろ)は語頭子音が脱落した
もので、韻尾の[-k]は[-l]に転移している。
同源語:
花(はな)、見(みる)、今日(けふ)、出(い
づ)、知(し)る、情(こころ・心)、隠(こもる・籠)、妻(つま・妻女)、
【うぐひす(鸎・鶯)】
春
野(はるのの)に霞(かすみ)たなびきうら悲(かなし)この暮影(ゆふかげ)に鸎(うぐひす)奈久(なく)も(万4290)
春 山(はるやま)の霧(きり)に惑(まと)へる鸎(うぐひすも)我(われに)益(まさりて)物(もの)念(おもはめ)や(万1892)
「ス」は隹[tjiuəi]で鳥を意味する。朝鮮語では鳥のことを(sae)という。朝鮮語の鳥(sae)も「ウグヒス」の「ス」も中国語の「隹」と同源で
あろう。「ス」のつく鳥には鴉「カラス」、雉「キギス」、百舌鳥「モズ」、「カケス」、「ホトトギズ」などがある。「ウグヒス」の「ヒ」は不明である。
例:相模(さがみ)、相楽(さがらか)、伊香(い
かごが)、當麻(たぎま)、望多(まぐた)、
本居宣長は『地名字音転用例』で、地名を二字で
書くようになったために、漢字音を転じて用いるようになったとしている。
尋常(ヨノツネ)の假字ノ例ニテハ。二字に約(ツゞ)メガタク。字ノ本音ノマゝニテ
ハ、其名ニ 叶ヘ難キガ多キ故ニ。字音ヲサマザマニ轉ジ用ヒテ。尋常ノ假字ノ例トハ。異ナルガ多キコオト。相 模(サガミ)の相(サガ)、信濃(シナノ)
の信(シナ)ナドノ
如シ。
○同源語:
野(の)、霞(かすみ・霞霧)、暮(ゆふ・夜)、
影(かげ)、奈久(なく・鳴)、惑(まと)ふ、我(われ)、物(もの)、念(おもふ)、
【うし(牛)】
馬
(うま)にこそ 布毛太志(ふもだし・絆)可久(かく・掛)物(もの) 牛(うし)にこそ 鼻縄(はななは)はくれ、、、(万3886)
新羅の万葉集といわれる郷歌(ヒヤンガ)には両
点といって中国語+朝鮮語訳を併記する方法がしばしば用いられている。日本でも『千字文』の冒頭にある「天地玄黄 宇宙洪荒」を「テンチのあめつちは ク
エンクワウとくろく・きなり。ウチウのおほぞらは コウクワウとおほいにおほきなり」などと読んだ。これも朝鮮半島の両点と同じく音訓両読で、「文選読
み」といった。
○同源語:
馬(うま)、布毛(ひも・絆)、可久(かく・
懸)、物(もの)、
【うし(厭)】
鸎
(うぐひす)の徃来(かよふ)垣根(かきね)の宇(う・卯)の花(はな)の厭(うき)事(こと)有(あれ)や君(きみ)が不二來
座一(き
まさぬ)(万
1988)
○同源語:
鸎(うぐひす、隹)、根(ね)、花(はな)、君
(きみ)、來(くる)、
【うぢ(氏)】
伊
尒之敝(いにしへ)よ 伊麻(いま)の乎追通(をつつ・現)に 奈我佐敝流(ながさへる・流) 於夜(おや・親)の子(こ)等毛(ども)ぞ 大伴(おほと
も)と佐伯(さへき)の氏(うぢ)は、、(万4094)
物 乃部(もののふ)の八十氏(やそうぢ)河(かは)の阿白木(あじろぎ)にいさよふ浪(なみ)の去邊(ゆくへ)白不(しらず)も(万264)
なお、中国語音は氏[zjie]であるが、日本語では氏(うじ)となることが期待
されるのだが、万葉集では氏(うぢ)とタ行になっている。同じ声符の文字に底[tyei]がある。「氏」の祖語(上古音)は氏[tjie*]であった可能性がある。タ行音とサ行イ段の音は万
葉集の時代から混同されることがあったようである。現代の日本語では「ジ」と「ヂ」の区別は失われている。
○同源語:
伊麻(いま・今)、子(こ)、物(もの)、河(か
は)、浪(なみ)、去(ゆく・行)、邊(へ)、白(しら・知)ず、
【うつ(打)】
面
(おも)忘(わすれ)だにも得為(えす)やと手(た)握(にぎり)て雖レ打
(うてども)不レ寒
(こりず)戀(こひと)云(いふ)奴(やつこ)(万2574)
打 (うつ)田(たに)稗(ひえは)數多(あまた)雖レ有 (ありといへども)擇(えらえ)し我(われそ)夜(よを)一人(ひとり)宿(ねる)(万2476)
「打」の古代中国語音は打[tyeng]である。日本漢字音は打(ダ・うつ)である。日本 漢字音が濁音の打(ダ)であることから、「打」は日本に入って来た時の音は打[dyeng]に近いものであったのではないかと考えられる。日 本語は濁音ではじまることばがなかったので、語頭に「う」を添加して打(うつ)とした可能性がある。
○同源語:
面(おも)、忘(わす)る、手(て)、田(た)、
稗(ひえ)、我(われ)、夜(よる)、宿(寐・ねる)、
【うま・むま(馬)】
日
雙斯(ひなみしの)皇子(みこの)命(みこと)の馬(うま)副(なめ)て御(み)獦(かり)立(たた)しし時(とき)は來(き)向(むかふ)(万49)
馬 音(うまのおと)のとどともすれば松陰(まつかげ)に出(いでて)そ見(み)つる若(けだし)君(きみ)かと(万2653)
朝鮮語では「馬」はmalである。「馬」は本来騎馬民族であるアルタイ系の
ことばであろう。古代日本語では馬(むま)であった。万葉集には馬(むま)という表記もみられる。鼻濁音である[m-]は古代日本語では語頭に立ちにくかった。「うま」
は「宇麻」「宇万」「牟麻」とも表記されている。
○同源語:
皇子(みこ・御子)、命(みこと・命人)、獦(か
り)、立(たつ)、時(とき)、來(くる)、都米(つめ・爪)、居(ゐ)る、音(おと)、陰(かげ・影)、出(いづ)、見(みる)、君(きみ)、佐伎(さ
き・崎)、阿礼(あれ・我)、
【うまし(味)】
飯
(いひ)喫(はめ)ど味(うまく)も不レ在
(あらず)雖二行
徃一(ゆ
きゆけど)安(やす)くも不レ有
(あらず)あかねさす君(きみ)が情(こころ)し忘(わすれ)かねつも(万3857)
古代日本語では「うましくに」などということば
もある。「美しい国」の意味である。「うまし国」の「うまし」はやはり中国語の美[miei]と同源である。
○同源語:
君(きみ)、情(こころ・心)、忘(わする)、
【うみ(海)】
有
(あり)通(かよふ)難波(なには)の宮(みや)は海(うみ)近(ちか)み漁(あま)童女(をとめ)らが乗船(のれるふね)所レ見
(みゆ)(万
1063)
樂 浪(ささなみ)の平山(ひらやま)風(かぜ)の海(うみ)吹(ふけ)ば釣(つり)為(する)海人(あま)の袂(そで)變(かへる)所レ見 (みゆ)(万 1715)
宮田一郎編著『上海語常用同音字典』(光生館) によると上海語では現在でも「毎」「美」「馬」などの前に入り渡り音[?](咽頭閉鎖音)が聞こえるという。同じ声符の漢字 がマ行とカ行に読み分けられているものには物[miuət]・惚[xuət]]、黒[xək]・黙[mək]・墨[mək]などがある。これらのことから古代中国語の[m-]には語頭に入り渡り音があり[hm-]に近い音であったことが想定できる。
また、古代中国語音の[m-]の前に入り渡り音があったと想定されるものに、米[mei]・(ベイ・マイ・こめ)、門[muən](モン・かど)、買[me](バイ・かふ)、毛[mô](モウ・け)などがある。
○同源語:
宮(みや)、漁・海人(あま・海女)、童女(をと
め・女)、乗(のる)、船(ふね・盤)、見(み)ゆ、浪(なみ)、平(ひら)、山(やま)、釣(つり)、袖(そで)、
【うめ(梅)】
吾
(わが)勢子(せこ)に令レ見
(みせむ)と念(おもひ)し梅花(うめのはな)それとも不レ所レ見
(みえず)雪(ゆき)の零(ふれ)れば(万1426)
引
(ひき)攀(よぢ)て折(をら)ば可レ落
(ちるべみ)梅花(うめのはな)袖(そで)にこき入(れ)つ染(しま)ば雖レ染
(しむとも)(万
1644)
古代中国語の「梅」は梅[muə]であった。日本語の「うめ」は梅[muə]に母音を添加したものである。[m-]は鼻濁音であり、古代日本語では語頭に立つことが むすかしかった。現代の日本語でも五十音図の最後の「ン」は語頭に立つことはない。馬(うま・むめ)のように、「梅」も梅(うめ)として日本語に受け入れ られた。万葉集では「うめ」は梅、烏梅、宇梅、宇米、汙米、などと表記されている。
○同源語:
吾(わが)、勢子(せこ・背子)、見(みる)、念
(おもふ)、花(はな)、零(ふる・降)、折(をる)、落(ちる・散)、袖(そで)、入(いる)、染(しむ)、
【うも(宇毛・芋蕪)】
蓮
葉(はちすは)は如是(かく)こそある物(もの)意吉麻呂(おきまろ)が家在(いへなる)物(もの)は宇毛(うも)の葉(は)に有(あら)し(万3826)
「芋」の古代中国語音は芋[hiua]である。上古中国語の頭音の喉音[h-]が随唐の時代になって介音[-i]の影響で脱落したものが芋(ウ)である。
また、芋[hiua]には入りわたり音があり、「芋」の祖語は芋[hmiua*]であったと考えることもできる。スウェーデンの言
語学者カールグレンは古代中国語には語頭に二重子音があったと考えている。音ではカ行で読み、訓ではま行で読む漢字がいくつかある。
例:見[kyan](ケン・みる)、観[kuan](カン・みる)、京[kyang](キョウ・みやこ)、宮[kiuəm] (キュウ・みや)、看[khan](カン・みる)、曲[khiok](キョク・まがる)、群[giuən](グン・
むれ)、御[ngia](ギョ・み)、迎[ngyang](ゲイ・むかえる)、眼[ngean](ガン・め)、元 [ngiuan](ゲン・もと)、詣[ngyei](ケイ・もうでる)、胸[xiong](キョウ・むね)、向[xiang]
(コウ・むかふ)、護[hoak](ゴ・まもる)、丸[huan](ガン・まる)、回[huəi](カイ・まわ る)、廻[huəi](カイ・めぐる)、
これらの漢字の祖語は入りわたり音[h-]があり、入りわたり音が発達したものがカ行にな り、入りわたり音が脱落したものがま行になったと考えると整合的に説明ができる。 日本語の「いも」は芋[hmiua]の入り渡り音が脱落して芋[miua]になり、馬(うま)や梅(うめ)のように母音が添 加されたものであると考えることができる。
もう一つの想定は、日本語の「いも」は中国語の 芋[hiua]+蕪[miua]ではないかと考えることもできる。「蕪」は現代中 国語では大根である。
○同源語:
蓮(はす・荷子)、葉(は)、家(いへ)、物(も
の)
【うもる(埋)】
真
鉇(まかな)持(もち)弓削(ゆげの)河原(かはら)の埋木(うもれぎ)の不レ可レ顕
(あらはるましじき)事(こと)に不レ有
(あらな)くに(万
1385)
例:苅[ngiat]かる、出[thjiuət]でる、拂[piuət]はらう、祓[buat]はらう、滅[miat]ほろぶ、絶[dziuat]たえ
る、越[huat]こえる、列[liat]つらなる、擦[tsheat]する、
○同源語:
真(ま)、弓(ゆみ)、河(かは)、原(はら)、
木(き・枝)、顕(あらは)る
【うら(裏)】
夏
影(なつかげ)の房(つまや)の下(した)に衣(きぬ)裁(たつ)吾妹(わぎも)裏(うら)まけて吾(わが)為(ため)裁(たた)ばやや大(おほに)裁
(たて)(万
1278)
○同源語:
影(かげ)、衣(きぬ・
巾)、吾(わが)、妹(いも)、
【うらむ(怨・恨)】
黄
葉(もみち)をば
取
(とり)てぞ思努布(しのぶ)
青
(あをき)をは
置
(おき)てぞ歎(なげ)く
そ
こし恨(うらめ)し
秋
山(あきやま)吾(われ)は(万
16)
不レ相 (あはず)とも吾(われ)は不レ怨 (うらみじ)此(この)枕(まくら)吾(われ)と念(おもひ)て枕(まき)て左宿座(さねませ)(万2629)
古代中国語の怨[iuan]、恨[hən]は音義ともに近い。日本語の「うらむ」は中国語の
怨[iuan]と同源であろう。「うらむ」は恨[hən]の頭音[h-]は脱落したものでもある。韻尾[-n]がラ行に転移した。韻尾の[-n]は[-l]と調音の位置が同じであり、転移しやすい。
例:巾[kiən]きれ、群[giuən]むれ、春[thjiuən]はる、昏[xuən]くれ、玄[hyuen]くろ、閏[njiuən]うるふ、
潤[njiuən]うるおふ、濡[njio]ぬれる、練[lian]ねる、見[hmyan*]みる、
○同源語:
取(とる)、置(おく)、歎(なげ)く、山(や
ま)、吾(われ)、相(あふ・合)、此(こ)れ、念(おもふ)、宿(ね・寐)る、
【うれふ(憂)】
草
枕(くさまくら) 客(たび)の憂(うれへ)を 名草漏(なぐさもる) 事(こと)も有(あり)やと、、(万1757)
妻 子(めこ)等母(ども)は 足(あと)の方(かた)に 圍(かくみ)居(ゐ)て憂(うれへ)さまよひ、、(万892)
○同源語:
妻子(めこ・女子)、居(ゐ)る、
【うを(宇乎・魚)】
思
可能宇良(しかのうら・浦)に伊射里(いざり)する安麻(あま)伊敝妣等(いへびと)の麻知(まち)古布(こふ)らむに安可思(あかし)都流(つる・釣)
宇乎(うを・魚)(万
3653)
○同源語:
海人(あま)、家(いへ)、釣(つる)、
【え・えだ(枝)】
槻
木(つきのき)の こちごちの枝(え)の 春葉(はるのは)の 茂(しげき)が如(ごと)く、、(万210)
古 (いにしへ)に樑(やな)打(うつ)人(ひと)の無有(なかり)せば此間(ここに)も有益(あらまし)柘(つげ)び枝(えだ)はも(万387)
漢字の「支」は中国語の音韻史を象徴するような 文字である。「支」は「シ」であり、「技術」の「技」は技(ギ)である。そして、「枝」は音が枝(シ)、訓が枝(え・えだ)である。「枝」の古代中国語音 は枝[tjie]であり、「技」は技[gie]であるとされている。同じ声符「支」がカ行とサ行 に読み分けられている。
埼玉県の稲荷山古墳から出土した鉄剣の銘の「獲 加多支鹵」は「ワカタケル」と解読されている。「支」は古墳時代には「カ」と読まれていたことが分かる。声符「支」次のように音価が変化したと考えられ る。 日本語の木(き)は古代中国語の枝[gie]である可能性がある。また、樹[zjio]も祖語(上古音)は樹[gio*]であった可能性がある。万葉集の時代の日本語では 「枝」は枝(シ・え・えだ)であり、「枝」を枝(き)とは読めなくなっていたに違いない。
枝[gie*](き)→(口蓋化)→枝[tjie](シ)→(頭音脱落)→枝[jie](え)
日本語の枝(え)は中国語の枝[tjie]の頭音が日本に来てから脱落したものであろう。正 確にいえば枝(え)はア行の「え」ではなく、古代日本語にあったヤ行の「イエ」である。「えだ」の「だ」は不明である。
○同源語:
木(き・枝)、春(はる)、葉(は)、樑(や
な)、打(うつ)、無(な)き、此(こ)れ、
【おきる(起・興)】
吾
(わが)門(かど)に千鳥(ちどり)數(しば)鳴(なく)起(おき)よ起(おき)よ我(わが)一夜妻(いとよづま)人(ひと)に所レ知(しらゆ)な(万3873)
人 眼(ほとめ)守(もる)君(きみ)がまにまに余(われ)さへに夙(つとに)興(おき)つつ裳裾(ものすそ)所レ沾 (ぬれぬ)(万 2563)
起[khiə]の頭音は有気音であり、興[xiəng]の頭音は喉音であり、いずれも日本語にはない音で
ある。そのため語頭に母音(お)をつけて、日本語として発音しやすくした。
○同源語:
吾・我(わが)、門(かど)、千(ち)、鳥(と
り)、鳴(なく)、夜(よる)、妻(つま・妻女)、知(しる)、眼(め)、守(まもる・護)、君(きみ)、余(われ・我)、沾(ぬれ・濡)る、
【おく・おき(奥)】
奥
山(おくやま)の於レ石
(いはに)蘿(こけ)生(むし)恐(かしこみ)と思(おもふ)情(こころ)を如何(いかにか)もせむ(万1334)
淡
海(あふみ)の海(み)邊多(へた)は人(ひと)知(しる)る奥浪(おきつなみ)君(きみ)を置)(おきて)は知(しる)人(ひと)も無(なし)(万3027)
日本語の「沖」もまた、語源は中国語の「澳」で
ある。また、今はもう使われなくなったことばであるが燠(おき)もまた中国語語源である。「燠」は火種を火鉢の灰の中などに貯えておくもので、マッチの普
及とともに死語になってしまった。
○同源語:
山(やま)、思(おもふ・念)、情(こころ・
心)、如何(いか)に、海(うみ)、邊(へ)、知(し)る、浪(なみ)、君(きみ)、無(な)し、
【おく(置)】
夕
凝(ゆふごりの)霜(しも)置(おきに)来(けり)朝(あさ)戸(と)出(で)に甚はなはだ)踐(ふみ)て人(ひと)に所レ知
(しらゆ)な(万
2692)
宇
(う・卯)の花(はな)の過(すぎ)ば惜(をしみ)か霍公鳥(ほととぎす)雨間(あまま)も不レ置
(おかず)従レ此
間(こゆ)喧(なき)渡(わたる)(万1491)
例:灼[tjiôk](シャク・やく)、射[djyak](シャ・いる)、織[tjiək]おる、折[tjiat]をる、熟[tjiuk]
(ジュク・うれる)、真[tjien]ま、矢[sjiei](シ・や)、舎[sjya](シャ・や)、赦[sjyak](シャ・ゆ るす)、淑[zjiuk](シュク・よき)、身[sjien]み、色[shiək]いろ、山[shean]やま、
○同源語:
夕(ゆふ・夜)、霜(しも)、出
(で・でる)、知(し)る、花(はな)、過(すぎ)る、霍公鳥(ほととぎす・隹)、間(ま)、喧(なく・鳴)、渡(わた)る、
【おす(押)】
春
日山(かすがやま)押(おし)て照有(てらせる)此(この)月(つき)は妹(いも)が庭(にはに)も清有(さやけかり)けり(万1074)
○同源語:
山(やま)、照(てる)、此(こ)れ、清(さや
か)、
【おつ(堕・落)】
其
(その)雪(ゆき)の 時無(ときなきが)如(ごと) 其(その)雨(あめ)の 間無(まなきが)如(ごと) 隈(くま)も不レ堕
(おちず) 念(おもひ)つつぞ來(こし) 其(その)山道(やまみち)を(万26)
狛
錦(こまにしき)紐(ひもの)片方(かたへ)ぞ床(とこ)に落(おち)にける明夜(あすのよ)し将レ來
(こむ)と云(いは)ば取(とり)置(おきて)待(またむ)(万2356)
○同源語:
其(そ)の、時(とき)、間(ま)、無(な)き、
思(おもふ・念)、來(くる)、山(やま)、取(とる)、置(おく)、紐(ひも・繙・絆)、方(へ)、床(とこ)、夜(よる)、
【おと(音・聲)】
大
王(おほきみ)の御笠山(みかさのやま)の帯(おび)に為(せ)る細谷川(ほそたにがは)の音(おと)の清(さやけ)さ(万1102)
一
松(ひとつまつ)幾代(いくよ)か歴(へぬ)る吹風(ふくかぜ)の聲(おと)の清(きよき)は年(とし)深(ふかみ)かも(万1042)
古代中国語の「音」は音[iəm]である。日本語では音[iəm]も恩[en]も「オン」であり、中国語の韻尾[-m]・[-n]は弁別されていない [-n]は調音の位置が[-t]と同じであり、転移しやすい。日本語の音(おと)
は古代中国語の音[iəm]と同源でああろう。琴[giəm](キン・こと)なども韻尾の[-m]がタ行に転移した例である。
二番目の歌では聲[thjieng]が日本語の「おと」にあてられている。借訓であ
る。
○同源語:
大王(おほきみ、君)、御(み)、山(やま)、川
(かは・河)、清(さやか)、幾(いく)、代(よ・世)、歴(へる・經)、
【おと(弟)】
父
母(ちちはは)が 成(なし)のまにまに 箸(はし)向(むかふ) 弟(おと)の命(みこと)は、、(万1804)
古代中国語の「弟」は弟[dyei]である。古代日本語は濁音ではじまることばはな
かったので語頭に母音が添加されて弟(おと)となった。男女の別なく、弟と妹について使われたという。現代日本語の「おとうと」は「弟人」、「いもうと」
は「妹人」である。
○同源語:
母(はは)、向(むか)ふ、命(みこと・命人)、
【おふ(負)】
此
(これ)や是(こ)の倭(やまと)にしては我(わが)戀(こふ)る木路(きぢ)に有(ありと)云(いふ)名(な)に負(おふ)背(せ)の山(やま)(万35)
名
(な)耳(のみ)を 名兒山(なごやま)と負(おひ)て 吾(わが)戀(こひ)の千重(ちへ)の一重(ひとへ)裳(も)なぐさめなくに(万963)
最初の歌(万35)では「名に負(おふ)背の
山」は「あの有名な背(兄)の山」と「背(兄)に会うという名の山」の両方の意味が込められているのであろう。
○同源語:
此(こ)れ、是(こ)の、我(わが)、名(な)、
背(せ)、山(やま)、兒(こ)、千(ち)、
【おみ(臣)】
物
部(もののふ)の臣(おみ)の壮士(をとこ)は大王(おほきみ)の任(まけ)のまにまに聞(きく)と云(いふ)物(もの)ぞ(万369)
○同源語:
物(もの)、部(ふ)、臣(おみ)、大王(おほき
み、君)、
【おも(母・乳母)】
祖
名(おやのな)も 繼(つぎ)徃(ゆく)物(もの)と 母父(おもちち)に 妻(つま)に子等(こども)に 語(かたらひ)て 立(たち)にし日(ひ)よ
り たらちねの 母(ははの)命(みこと)は、、(万443)
緑
兒(みどりご)の為(ため)こそ乳母(おも)は求(もとむと)云(いへ)乳(ち)飲(のめ)や君(きみ)が於毛(おも・乳母)求(もとむ)らむ(万2925)
「おも」には「乳母」という表記も使われてい
る。「乳」の古代中国語音は乳[njia]である。乳[njia]の祖語(上古音)は乳[mia*]に近い音であったものと考えられる。母[mə]と乳[mia*]は同系のことばであろう。
母(おも)が最もふるく、母(はは)→母(ボ)
と変化したものと考えられる。
○同源語:
名(な)、繼(つぎ・續)、徃(ゆく・行)、物
(もの)、妻(つま・妻女)、子(こ)、語(かたる)、立(たつ)、命(みこと・命人)、緑(みどり)、兒(こ)、飲(のむ・呑)、君(きみ)、今(い
ま)、哭(なく・泣)、其(そ)、吾(あ)、
【おも(面)】
陸
奥(みちのく)の真野(まの)の草原(かやはら)雖レ遠
(とほけれど)面影(おもかげに)為(し)て所レ見
(みゆと)云(いふ)物(もの)を(万396)
對
面(あひみて)は面(おも)隠(かくさる)る物(もの)からに繼(つぎ)て見(み)まくの欲(ほしき)公(きみ)かも(万2554)
古代中国語の「面」は面[mian]である。日本語の面(おも)は語頭に母音(お)が
添加されたものである。
「面」は面(おもて)ともいう。面を面(おも
て)と読んだ例はま万葉集にはないが、音表記の例がある。中国語の祖語(上古音)面[miat*]を継承したものである。歴史的には[-t]が古く[-n]が新しい。韻尾の上古入声音[-t*]は隋唐の時代に入って[-n]に変化した。
久
礼奈為(くれなゐ)の 意母提(おもて)の宇倍(うへ)に 伊豆久由(いづくゆ)か 斯和(しわ・皺)が伎多利(きたり)し、、(万804)
奥(おく)、真(ま)、野(の)、草(くさ)、原
(はら)、影(かげ)、見(みる)、物(もの)、隠(かく)す、繼(つぎ・續)、公(きみ)、斯和(しわ・皺)、伎多利(きたり・來)、
【おもふ(思・念・憶)】
霜
(しも)雪(ゆき)も未(いまだ)過(すぎね)ば不レ思
(おもはぬ)に春日里(かすがのさと)に梅花(うめのはな)見(み)つ(万1434)
阿 騎(あき)の野(の)に宿(やどる)旅人(たびびと)打(うち)靡(なびき)寐(い)も宿(ね)らめやも古部(いにしへ)念(おもふ)に(万46)
春
鳥(あるとり)の さまよひぬれば 歎(なげき)も 未(いまだ)過(すぎぬ)に 憶(おもひ)も 未(いまだ)不レ盡
(つきね)ば、、(万
199)
「思」「念」「憶」はいずれも義(意味)は日本
語の「おもふ」に近いが、音が一番近いのは念[niəm]であろう。音義ともに近いことばは同源である。
○同源語:
霜(しも)、未(いまだ)、過(すぎ)る、梅(う
め)、花(はな)、見(みる)、野(の)、靡(なびく)、寐(ねる)、鳥(とり)、歎(なげ)く、
【おる(織)】
為レ我
(わがため)と織女(たなばたつめ)の其(その)屋戸(やど)に織(おる)白布(しろたへは)織(おり)てけむかも(万2027)
未
通女(をとめ)等(ら)が織(おる)機(はた)の上(うへ)を真(ま)櫛(くし)もち掻上(かかげ)𣑥嶋(たくしま)波間(なみのま)従(ゆ)所レ見
(みゆ)(万
1233)
例:腹[piuk]はら、原[ngiuan]はら、色[shiək]いろ、黒[xək]くろ、夜[jyak]よる、殻[khək]から、悪[ak]わ
るい、或[hiuək]ある、
○同源語:
我(わが)、女(め)、其(そ)の、真(ま)、島(しま・洲)、波(なみ・浪)、間(ま)、見(みる)、
【あ行のまとめ】
古代日本語のア行のことばを整理してみるとつぎ
のようになるのではあるまいか。
1.古代中国語の頭音が母音であるもの。
鶯[eng]うぐひす、厭[iap]うし・いとふ、怨[iuan]うらむ、憂[iu]うれふ、奥[uk]おく、押[eap]おす、音[iam]おと、
2.中国語の声母が口蓋化などの影響で脱落したもの。
○(日母[nj-]、疑母[ng-]、明母[m-]、来母[l-]の脱落)
我[ngai]あ、吾[nga]あ、仰[ngiang]あふぐ、牛[ngiuə]う+し<朝鮮語・牛(so)>、魚[ngia]うを、
熱[njiat]あつし、入[njiəp]いる、乳母[njia]おも、
綾[liəng]あや、鮎[niəm]あゆ<鮎魚>、彌[mia]いや、
○(喉音[h-][x-]の脱落)
可[hai]怜[lieng]あはれ、合[həp]あふ、会[huat]あふ、荒[xuang]あらし、恨[hən]うらむ、
海子・海部[xmuə*]あま、顕[xian]あらはす、
○(介音[-i-]などによる頭音の脱落)
赤[thjyak]あか、天[thyen]あま・あめ、息[siək]いき、生[sheng]いきる、犬[khyuan]いぬ、秈[shean] いね、今[kiəm]いま、禁[kiəm]いむ、射[djyak]いる・いゆ、色[shiək]いろ、枝[tjie]え・えだ、置 [tjiək]お く、臣[sjien]おみ、織[tjiek]おる、
3.語頭に母音が添加されたもの。
○(頭音が濁音などの場合)
痛[thong]いたし、出[thiuət]いづ、泉[dziuan]いづみ、氏[djie*]うぢ、堕[duai]おつ、弟[dyei]おと、
負 [biua]おふ、
當[tang]あたり、至[tjiet]・到[tô]いたる、禱[tu]いのる、打[tyeng]うつ、
幾[kiəi]いく、家[kea]いへ、起[khia]おきる、興[xiəng]おきる、
○(頭音が[m-]の場合)
海女[(h)muə*]あま、網[miuang]あみ、寐[muət]いぬ、未[miuət]いまだ、夢[miuəng]いめ、妹[muəi]
いも、馬[mea]うま・むま、味[miuəi]うまし、海[(h)muə*]うみ、梅[muə]うめ、蕪[miuə]うも、埋 [məi]うもる、母[mə]おも・あも、面[mian]おも、念[niəm]おもふ、
○(頭音が[l-]の場合)
嵐[ləm]あらし、裏[liə]うら、
*は再構した上古音をあらわす。
日本語のア行音は上古中国語の頭子音が脱落した
ものや、頭音に母音が添加されたものがあるので見逃されやすい。しかし、言語のたどった長い歴史のなかで、中国語音も変化し、日本語の音韻構造も変化し
た。そして、音韻構造の違う日本語の音韻構造に合わせて中国語原音は転移して受け入れられてきた。
日本語は母音では
じまることばが多い。『広辞
苑』では2588ページ中ア行は375ページで14.5%をしめている。これにたいして中国語は、小学館
の『中日辞典』では1%にもみたない。そのため、中国語の語彙が日本語に借用されるときは、中国語の頭母音が脱落するか、頭に母音を添加することが多くな
る。朝鮮語ではア、ヤ、ワ行を合わせて15%で、日本語に近い。
岩波の古語辞典ではア行が18%あり、時代別国語大辞典(上代編)では20%ある。古代日本語の方が現代の日本語より、母音
ではじまることばが多い傾向がみられる。
◎か行
【か(香)】
宇
梅(うめ)の波奈(はな)香(か)を加具波之美(かぐはしみ)等保(とほ)けども己許呂(こころ)もしのに伎美(きみ)をしぞ於毛布(おもふ)(万4500)
神
風(かむかぜ)の伊勢(いせ)の國(くに)は奥(おき)つ藻(も)も靡(なびき)足(し)波(なみ)に塩氣(しほけ・潮)のみ香乎礼流(かをれる)國(く
に)に味凝(うまこり)あやに乏(とも)しき高照(たかてらす)日(ひ)の御子(みこ)(万162)
古代中国語の「香」は香[xiang]である。喉音[x-]は日本語ではカ行で現われる。現代中国語の[x-]は摩擦音であるが、古代中国語では破裂音であった
と考えられる。香(か)は中国語の韻尾[-ng]が脱落したものである。日本語は開音節(母音で終
わる音節)なので中国語の韻尾[-ng]は脱落しやすい。
万葉集では香久山を「香具山」「香來山」「香
山」んどと表記しているが、「香山」は香[xiang]を「かぐ」と読んだものであり、「香具山」「香來
山」は香[xiang]の韻尾[-ng]を「具」あるいは「來」であらわしたものである。
万葉集の時代には、すでに香[xiang]の韻尾が失われかけていたことが分かる。
○同源語:
宇梅(うめ)、波奈(はな・花)、加具波之美(か
ぐはしみ・香)、己許呂(こころ・心)、君(きみ)、思(おもふ・念)、神(かみ)、國(くに)、奥(おき・澳)、靡
(なび)く、波(なみ・浪)、塩(しほ・潮)、氣(き・け)、香乎礼流(かをれる、香)、味(うま)し、照(てる)、御
(み)、子(こ)、
【かがみ(鏡)】
白
銅鏡(まそかがみ)手(て)に取(とり)持(もち)て見(みれ)ど不レ足(あかぬ)君(きみ)に所レ贈
(おくれ)て生(いけり)とも無(なし)(万3185)
日本語では頭音節が濁音や喉音[h-]などの場合、語頭に清音をつけて、濁音が語頭にこ
ないようにすることがある。
例:鑑[heam](カン・かがみ)、懸[hiuen](ケン・かかる)、限[hean](ゲン・かぎり)、續[ziok]
(ゾク・つづく)、
また、韻尾の[-ng]は[-m]と調音の方法が同じ(鼻音)であり、転移しやす
い。
例:灯[təng](トウ・ともる)、停[dyeng](テイ・とまる)、醒[syeng](セイ・さめる)、霜[shiang] (ソウ・しも)、公[kong](コウ・きみ)、
○同源語:
手(て)、取(とる)、見(みる)、君(きみ)、
生(いきる)、無(な)し、
【かぎり(限)】
袖
(そで)振(ふらば)可レ見
(みゆべき)限(かぎり)吾(われは)雖レ有
(あれど)其(その)松枝(まつがえに)隠在(かくれたりけり)(万2485)
古代中国語の「限」は限[hean]である。頭音の[h-]は日本語にはない喉音であり、濁音なので清音を先
に立てて日本語として発音しやすくした。韻尾の[-n]は[-l]に転移した。
○同源語:
袖(そで)、見(みる)、吾(われ)、枝(え)、
隠(かくれ)る、
【かく(畫、可伎・かき)】
和
我(わが)都麻(つま)も畫(ゑ)に可伎(かき)等良無(とらむ)伊豆麻(いづま・暇)もが多妣(たび)由久(ゆく)阿礼(あれ)は美(み・見)つつ志努
波牟(しのばむ)(万
4327)
書[sjia]は「畫」と字体は似ているが音が対応していない。
「書」も上古音は喉音で書[xjia*]に近い音であった可能性がある。しかし、これはも
う少し漢字の音韻史の研究が進まないと確証を得られそうにない。
○同源語:
和我(わが)、都麻(つま・妻女)、畫(ゑ・
絵)、可伎(かく・畫)、等良無(とらむ・取)、由久(ゆく・行)、阿礼(あれ・我)、美(み・見)る、
【かく・かける(闕)】
千
歳(ちとせ)に 闕(かくる)事(こと)無(なく) 万歳(よろづよ)に 有(あり)通将(かよはむ)と、、(万3236)
世
間(よのなか)は空(むなしき)物(もの)と将レ有(あらむ)とそ此(この)照(てる)月(つき)は満(みち)闕(かけ)為(し)ける(万442)
韻尾[-t]は日本語ではカ行に転移している。王力は『同源字
典』のなかで遞・逓[dyek]と迭[dyet]は音が近く同源である、としている。中国語でも江
南音では[-p][-t][-k]は区別されていない。
最初の歌(万323)の「通将(かよはむ)と」
は日本語の語順であり、二番目の歌(万442)の「将レ有(あらむ)とそ」はレ点があり、中国語
の語順で表記されている。
○同源語:
千(ち)、無(な)き、世(よ)、間(なか・
中)、物(もの)、此(こ)の、照(てる)、満(みちる)、
【かくる・かくす(隠)】
茜
(あかね)刺(さ)す日(ひ)は雖二照
有一(て
らせれど)烏玉(ぬばたま)の夜(よ)渡(わたる)月(つき)の隠(かく)らく惜(をし)も(万169)
三
輪山(みわやま)を然(しか)も隠(かくす)か雲(くも)だにも情(こころ)有(あら)なも可苦佐布(かくさふ)べしや(万18)
例:雲[hiuən](くも・ウン)、熊[hiuəm](くま・ユウ)、媛[hiuan](ひめ・エン)、羽[hiuə](は・ ウ)、煙[hyen*](けむり・エン)、
また、音に両方の読みがある例もみられる。
例:絵[huat](カイ・ヱ)、回[huəi](カイ・ヱ)、黄[huəng](コウ・オウ)、
○同源語:
刺(さ)す、照(てる)、夜(よる)、渡(わた)
る、三(み)、山(やま)、雲(くも)、情(こころ・心)、
【かげ(影)】
度
(わたる)日(ひ)の陰(かげ)も隠(かくら)ひ照(てる)月(つき)の光(ひかり)も不レ見
(みえず)、、(万
317)
燈
(ともしび)の陰(かげ)にかがよふ虚蝉(うつせみ)の妹(いも)が咲(ゑ)まひし面影(おもかげ)に所レ見
(みゆ)(万
2642)
古代日本語の「かげ」には影(日の当らないとこ
ろ)と光(日のあたるところ)という二つの意味がある。現代の日本語でも「月影」といえば「月の光」のことである。中国語には売買(バイバイ)、授受
(ジュジュ)などのように同じ音で反対の意味をもつことばがある。
古代中国語の影[yang]は景[kyang]と声符が同じである。「影」もまた「景」と同じ頭
音をもっていたことがあると考えられる。日本語の「かげ」は中国語の影[kyang*]に依拠したものである。
一方、「光」の古代中国語音は光[kuang]であり、影[kyang*]と音が近い。「かぐや姫」の「かぐ」は光[kuang]であり、「光姫」ということになる。「陰」は陰[iəm]であり、隠[iən]、暗・闇[əm]に音義が近い。
○同源語:
度(わたる・渡)、陰(かげ・影)、照(てる)、
見(みる)、燈(ともしび・燈火)、妹(いも)、面(おも)、
【かける・かかる(懸・繋)】
天
原(あまのはら)振(ふり)離(さけ)見(みれ)ば白眞弓(しらまゆみ)張(はり)て懸有(かけたり)夜路(よみち)は将レ吉
(よけむ)(万
289)
吾
(わが)戀(こひ)は千引(ちびき)の石(いは)を七(なな)ばかり頸(くび)に将レ繋
(かけむ)も神(かみ)のまにまに(万743)
例:限[heən]かぎり、係[hye]かかり、鏡[kyang]かがみ、鑑[keam]かがみ、懸[huen]かかり、掲[kiat]か かげる、掛[kyue]かける、鉤[ko]かぎ、
韻尾の[-n]は[-l]と調音の位置が同じであり、転移した。
例:漢・韓(カン・から)、雁(ガン・かり)、昏
(コン・くれ)、邊(ヘン・へり)、
玄(ゲン・くろい)、嫌(ケン・きらう)、薫(ク
ン・かをり)、
○同源語:
天(あめ)、原(はら)、見(みる)、真(ま)、
弓(ゆみ)、夜(よる)、吾(わが)、千(ち)、頸(くび)、神(かみ)、
【かざし(頭刺・挿頭)】
孫
星(ひこほしの)頭刺玉(かざしのたま)の嬬戀(つまごひに)乱(みだれに)けらし此(この)川(かはの)瀬(せに)(万1686)
古
(いにしへ)に有(あり)けむ人(ひと)も如二吾
等一(わ
がごと)か弥和(みわ)の檜原(ひばら)に挿頭(かざし)折(をり)けむ(万1118)
○同源語:
星(ほし)、嬬(つま・妻嬬)、乱(みだれ)、此
(こ)の、川(かは・河))、吾(わが)、檜(ひ)、原(はら)、折(をる)、
【かざる(餝・華飾)】
大
殿(おほとの)を 振(ふり)放(さけ)見(みれ)ば 白細布(しろたへに) 餝(かざり)奉(まつり)て、、(万3324)
す
がるの如(ごと)き 腰細(こしぼそ)に 取(とり)餝(かざら)ひ 真十鏡(まそかがみ) 取(とり)雙(なめ)懸(かけ)て、、(万3791)
「餝」は「飾」の異字である。古代中国語の
「飾」は飾[sjiək]である。古事記では「厳餝」と表記されているもの
もみられる。日本語の「かざる」は「厳餝」あるいは華飾[hoa-sjiək]に由来することばであろう。
○同源語:
殿(との)、見(みる)、取(と)る、真(ま)、
鏡(かがみ)、懸(かけ)る、
【かし(樫・橿)】
橿
實(かしのみ)の 獨(ひとり)か将レ宿
(ぬらむ) 問(とは)まくの 欲(ほしき)我妹(わぎも)が 家(いへ)の不レ知
(しらな)く(万
1742)
麻
衣(あさごろも)著(けれ)ば夏樫(なつかし)木國(きのくに)の妹背(いもせ)の山(やま)に麻(あさ)蒔(まく)吾妹(わぎも)(万1195)
堅[kyen]の祖語(上古音)は堅[kyet*]に近い音であったと考えられている。中国語の韻尾
には[-s]はないが、日本語の「かし」は堅[kyet*]を継承したものであろう。
○同源語:
宿(ねる・寐)、我・吾(われ)、妹(いも)、家
(いへ)、知(し)る、木(き・枝)、國(くに)、背(せ)、山(やま)、蒔(まく・播)、
【かすみ(霞)】
霞
(かすみ)立(たち) 春日(はるひ)の霧(きれ)る 百磯城(ももしき)の 大宮處(おおみやどころ) 見(みれ)ば悲(かなし)も(万29)
都
奇(つき・月)餘米婆(よめば)伊麻太(いまだ)冬(ふゆ)なりしかすがに霞(かすみ)たなびく波流(はる)多知奴(たちぬ)とか(万4492)
白川静は『字訓』の「かすみ」の項で次のように
述べている。『華厳音義私記』に「晨霞 可須美」、『最勝王経音義』に「霧 加須美」とあって、霞と霧との区別も明らかでないところがあるという。
○同源語:
立(たつ)、宮(みや)、見(みる)、伊麻太(い
まだ・未)、波流(はる・春)、多知(たち・立)、
【かた(肩)】
木
綿(ゆふ)手次(たすき) 肩(かた)に取(とり)懸(かけ) 忌戸(いはひべ)を 齊(いはひ)穿(ほり)居(すゑ)、、(万3288)
綿
(わた)も奈伎(なき) 布(ぬの)可多(かた・肩)衣(ぎぬ)の 美留(みる・海松)の其等(ごと・如) わわけさがれる かかふのみ 肩(かた)に打
懸(うちかけ)、、(万
892)
例:本(ホン)・鉢(ハチ)、吻(フン)・物(モ
ツ・ブツ)、因(イン)・嗚咽(オエツ)、 産(サン)・薩摩(サツマ)など、
中国語音韻史では、入声音[-t]の多くが隋唐の時代には[-n]に転移したことが知られている。肩[kyan]の祖語は肩[kyat*]に近い音であったと思われる。日本語の「かた」は
中国語の上古音、肩[kyat*]に依拠したものであろう。
例:腕[uan](ワン・うで)、楯[djiuən](ジュン・たて)、幡[phiuan](バン・はた)、堅[kyen](ケン・ かたい)など
○同源語:
取(とる)、懸(かける)、穿(ほる・掘)、綿
(わた)、奈伎(なき・無)き、打(うつ)、
【かた・(形)】
夕
(ゆふ)附(づく)日(ひ)指(さ)すや河邊(かはへ)に構(つくる)屋(や)の形(かた)を宜(よろし)み諾(うべ)所レ因
(よそり)けり(万
3820)
「形」の古代中国語音は形[hyeng]である。中国語の韻尾[-ng]はカ行であらわれることが多い。しかし、江南音で
は[-ng]と[-n]の区別が失われており、「形」の江南音が形[hyen]に近い音であったとすれば、タ行であらわれても不
思議はない。[-n]と[-t]は調音の位置が同じであり、転移しやすい。
韻尾[-ng]がタ行であらわれる例:龍[liong](たつ)、糧[liang](かて)、幸[kang](さち)、
日本語の「かた」は「形」と同系のことばである 可能性がある。
○同源語:
夕(ゆふ・夜)、指(さ)す、河(かは)、邊
(べ)、構(つくる・作)、屋(や)、
【かたし(堅)】
在
有(ありあり)て後(のち)も将レ相
(あはむ)と言(こと)耳(のみ)を堅(かたく)要(いひ)つつ相(あふ)とは無(なし)に(万3113)
寒
(さむく)し安礼婆(あれば) 堅塩(かたしほ)を 取(とり)つづしろひ、、(万892)
○同源語:
相(あふ・合)、言(こと)、耳(のみ・みみ)、
無(な)し、取(とる)、嶋(しま・洲)、兒(こ)、釣(つる)、
【かたる(語・言)】
不
聴(いなと)雖レ謂
(いへど)語礼(かたれ)々々(かたれ)と詔(のらせ)こそ志斐(しい)いは奏(まをせ)強語(しいがたり)と言(いふ)(万237)
あ しひきの山橘(やまたちばな)の色(いろ)に出(いで)よ語言(かたらひ)繼(つぎ)て相(あふ)事(こと)も将レ有 (あらむ)(万 669)
大
夫(ますらを)の弓上(ゆずゑ)振(ふり)起(おこし)射(い)つる矢(や)を後(のち)将レ見
(みむ)人(ひと)は語(かたり)繼(つぐ)がね(万364)
日本語の「かたる」には語[ngia]、語[ngia]言[ngian]などが使われている。王力の『同源字典』による
と、「語」と「言」は同源であるという。言(こと)は名詞であり、言(かたる)は動詞である。日本語の「かたる」は言[ngian]の韻尾[-n]がタ行に転移したものであろう。
○同源語:
山(やま)、色(いろ)、出(いで)、繼(つぐ・
續)、相(あふ・合)、弓(ゆみ)、起(おこ)す、射(い)る、矢(や)、見(みる)、
【かづら(葛)】
玉
葛(たまかづら)花(はな)耳(のみ)開(さき)て不レ成
有(ならざる)は誰(たが)戀(こひ)尓有(なら)め吾(あ)は孤悲(こひ)念(おもふ)を(万102)
○同源語:
葛(かずら)、花(はな)、開(さき・咲)、吾
(あ)、念(おもふ)、
【かつを(堅魚)】
水
江(みづのえ)の 浦嶋兒(うらしまのこ)が 堅魚(かつを)釣(つり) 鯛(たひ)釣(つり)矜(ほこり)、、(万1740)
例:本[puən](もと)、元[ngiuan](もと)、盾[djiuən](たて)、幡[piuan](はた)、管[kuan]
(くだ)、肩[kyan](かた)、腕[uan](うで)、言[ngian](こと)、満[muan](みつる)、断[duan] (たつ)、
魚[ngia]を「うを」と読むのは中国語の疑母[ng-]が脱落したものである。古代日本語では濁音が語頭
に立つことがなかったので鼻濁音の[ng-]が脱落した。朝鮮漢字音では「魚」は魚(eo)である。古代日本語の音韻構造は朝鮮語に近かっ
た。
例:顎[ngak](あご)、岳[ngək](をか)、御[ngia](お)、吾[nga]・我[ngai](あ・あれ)、暁[ngyô] (あか+とき・時)、牛[ngiuə](う+し<朝鮮語so>)、蟻[ngiai](あ+り)、鰐[ngak](わ+ に・魚)、
○同源語:
嶋(しま・洲)、兒(こ)、魚(う
お)、釣(つる)、鯛(たひ)、
【かぬ(兼)】
真
玉(またま)付(つく)をちこち兼(かね)て言(こと)は五十戸(いへ)ど相(あひ)ての後(のち)こそ悔(くい)には有(あり)と五十戸(いへ)(万674)
真
玉(またま)就(つく)をちこち兼(かね)て結(むすび)つる言(わが)下紐(したひも)の所レ解
(とくる)日(ひ)有米(あらめ)や(万2973)
現代の北京語では[-m]と[-n]の区別は失われている。広東語、朝鮮漢字音などで
は韻尾の[-m]と[-n]は弁別されているが、日本語では弁別されない。日
本語の五十音図には最後は「ン」であり、中国語韻尾の[-n]と[-m]の両方に用いられている。
○同源語:
真(ま)、言(こと)、相(あふ・合)、悔(く
い)、就(つく・衝)、紐(ひも・絆・繙)、.言(わが・我)、
【かね(金)】
銀
(しろがね)も金(くがね)も玉(たま)も奈尓(なに)せむに麻佐礼留(まされる)多可良(たから)古(こ・子)にしかめやも(万803)
皆
(みな)人(ひと)を宿(ね)よとの金(かね)は打(うつな)れど君(きみ)をし念(おもへ)ば寐(いね)不レ勝
(かてぬ)かも(万
607)
古代中国語の「金」は金[kiəm]である。日本語の「かね」は中国語の「金」の韻尾[-m]に母音を添加したものである。日本語は開音節(母
音で終わる音節)であり、古代日本語には[-m]も[-n]で終わる音節はなかったので、母音を添加した。
例:兼[hyam](かねる)、稔[njiəm](みのる)、闇[əm](やみ)、苫[sjiam/tjiam](とま)、染[njiam] (そめる)、渗[shiəm](しみる)など
「金」は金属一般であり、黄金(くがね)、銀
(白金)、鉄(眞金)、銅(赤金)などと区別された。二番目の歌の「金」は「鐘」である。
○同源語:
子(こ)、真(ま)、宿(ねる・
寐)、打(うつ)、君(きみ)、念(おもふ)、寐(いぬ)、
【かは(河)】
隠
國(こもりく)の 泊瀬(はつせ)の川(かは)に 舼(ふね)浮(うけ)て 吾(わが)行(ゆく)河(かは)の 川(かは)隅(くま)の 八十(やそ)阿
(くま)不レ落
(おちず)、、
(万
79)
も ののふの八十氏(やそうでぢ)河(かは)の阿白木(あじろぎ)にいさよふ浪(なみ)の去邊(ゆくへ)白不(しらず・知)も(万264)
天
漢(あまのがは)棚橋(たなはし)渡(わたせ)織女(たなばた)のい渡(わたら)さむに棚橋(たなはし)渡(わたせ)(万2081)
河(かは)古代中国語の「河」は河[hai]である。日本語の「かは」は中国語の河[hai]と同源であろう。中国語の「かは」には河[hai]のほかに、川[thjyuən]、江[kong]があって、河(カ)と江(コウ)は似ているが、川
(セン)は「河」や「江」とは違う系統のことばのようにみえる。
しかし、川と同じ声符をもった漢字に訓[xiuən]があり、「川」の上古音も川[xiuən*]に近い音をもっていたものと考えられる。現代中国
語のxは摩擦音だが、上古音は喉音の破裂音である。川[xiuən*]、江[kong]も河[hai]と同義であり、音も上古音までさかのぼれば同系の
ことばであるとみることができる。
「天漢」は「あまのがは」に使う漢字であり、古代
中国語音は漢[xan]である。「漢」は「漢水」というごとく、もともと
川の名である。漢[xan]も川[xiuən*]・河[hai]に近い。
○同源語:
隠(こもる・籠)、國(くに)、泊(はつ)、舼(ふね・盤)、吾(わが)、行(ゆく)、落(おちる・堕)、物(もの)、木(き・枝)、浪(なみ)、去(ゆ
く・行)、邊(へ)、白(しる・
知)、天(あめ)、渡(わたる)、
【かはづ(蝦・河蝦・河津・川豆)】
朝
(あさ)霞(かすみ)鹿火屋(かひや)が下(した)に鳴(なく)蝦(かはづ)聲(こゑ)だに聞(きか)ば吾(われ)将レ戀
(こひめ)やも(万
2265)
吾 (わが)畳(たたみ)三重(みへ)の河原(かはら)の礒(いその)裏(うら)に如(かく)しもがもと鳴(なく)河蝦(かはづ)かも(万1735)
秋 (あき)の夜(よ)は 河(かは)し清(さやけ)し 旦雲(あさぐも)に 多頭(たづ)は乱(みだれ) 夕霧(ゆふぎり)に 河津(かはづ)は驟(さわ く)、、(万 324)
川
豆(かはづ)鳴(なく)清(きよき)川原(かはら)を今日(けふ)見(み)ては何時(いつ)か越(こえ)來(き)て見(み)つつ偲(しの)ばむ(万1106)
万葉集では「かはづ」は「蝦」「河蝦」「河津」
などと表記されている。「蝦」の古代中国語音は蝦[hea]である。「蝦」は中国語では「えび」のことだが、
「蝦蟆」ということばもあって「ひきがえる」である。日本語の「かはづ」は「蝦蟆+づ」であろう。それが「河」の連想で「河蝦」「河津」となったものであ
ろう。「つ」は不明である。
○同源語:
霞(かすみ・霞霧)、鹿(か)、火(ひ)、屋
(や)、鳴(なく)、聲(こゑ)、吾(われ)、畳(たたみ)、河・川(かは)、原(はら)、裏(うら・浦)、夜(よる)、清(さやか・きよき)、雲(く
も)、乱(みだれ)、夕(ゆふ・夜)、津(つ)、今日(けふ)、越(こえる)、來(くる)、
【かひ(峡)】
旦
今日(けふ)々々々(けふ)と吾(わが)待(まつ)君(きみ)は石水(いしかは)の貝(かひ)に<一云 谷(たに)に>交(まじり)て有(あり)と不レ言
(いはず)やも(万
224)
夜
麻我比迩(やまがひに)佐家流(さける)佐久良(さくら・櫻)を多太(ただ)比等米(ひとめ)伎美(きみ)に弥西(みせ)てば奈尓(なに)をか於母(お
も)はむ(万
3967)
古代中国語の「峡」は峡[heap]である。古代日本語では[-p]は蝶[thyap](てふ)のようにハ行であらわれる。万葉集は平安
時代にはすでに解読できなくなっていて、源順などが注釈したことが知られている。「峡」は音で峡(キョウ)と読まれるようになっていたので「かひ」には
「貝」ではないかという解釈が生まれたのであろう。
高知県の「いぶすき」は「揖宿」と書いていたが
「いぶすき」とは読めなくなってしまったので、「指宿」と表記するようになった。また、地名の「甲斐」は「山峡」の「峡」であったと思われるが好字を選ん
で甲[keap]となり、「甲」一字では「かひ」と読めなくなって
しまったので、甲斐(かひ)と漢字の韻尾を「斐」で表記したものである。「斐」は「甲」の末音添記である。甲[keap]府は峡[heap]府と音が近い。
○同源語:
旦今日(けふ)、君・伎美(きみ)、佐家流(さ
く・咲)、多太(ただ・直)、米(め・目)、弥西(みせ・見)、於母(おも・念)ふ、
【かひ(貝・蛤)】
伊
勢(いせ)の白水郎(あま)の朝(あさ)な夕(ゆふ)なに潜(かづくと)云(いふ)鰒(あはびの)貝(かひ)の獨念(かたもひ)にして(万2798)
暇
(いとま有(あら)ば拾(ひりひ)に将レ徃
(ゆかむ)住吉(すみのえ)の岸(きし)に因(よると)云(いふ)戀(こひ)忘(わすれ)貝(かひ)(万1147)
中国語の韻尾[-p]は旧仮名使いでは蝶(テフ)、答(タフ)、甲(カ
フ)、合(ガフ)などのようにハ行であらわれる。
○同源語:
白水郎(あま・海女)、夕(ゆふ・夜)、貝(か
ひ・蛤)、念(おもふ)、徃(ゆく・行)、住む(すむ)、因(よる)、忘(わすれ)る、
【かひこ(蠶・蛺蠱)】
た
らちねの母(ははが)養子(かふこ)の眉(まよ)隱(ごもり)隠在(こもれる)妹(いもを)見(みむ)依(よしも)がも(万2495)
た
らちねの母(はは)が養蚕(かふこ)の眉隱(まよこもり)馬聲蜂音石花蜘蛛(いぶせくも)あるか異母(いも・妹)に不レ相
(あはず)て(万
2991)
「養子」あるはい「養蚕」と書いて「かひこ」と
読ませるのは、恐らく民間語源説(フォーク・エティモロジー)に近いであろう。日本語の「かひこ」の語源は蛺蠱[heap-ka]ではなかろうか。蛺(かひ)は蝶であり、蠱(こ)
は虫である。万葉集の時代にはすでに「蛺」を蛺(かひ)とは読めなくなっていたので、「養子」あるいは「養蚕」という漢字をあてたのであろう。
○同源語:
母(はは)、子(こ)、眉(まよ)、隠(こもる・
籠)、妹・異母(いも)、見(みる)、相(あふ・合)、母(はは)、
【かへる(還)】
手
(て)もすまに殖(うゑ)し芽子(はぎ)にや還(かへり)ては雖レ見
(みれども)不レ飽
(あかず)情(こころ)将レ盡
(つくさむ)(万
1633)
真
十鏡(まそかがみ)取(とり)雙(なめ)懸(かけ)て己(おの)が杲(かほ)還氷(かへらひ)見(み)つつ、、(万3791)
例:漢・韓(カン・から)、雁(ガン・かり)、塵
(ジン・ちり)、昏(コン・くれ、、算盤
(ソロバン)など、、
○同源語:
手(て)、芽子(はぎ)、見(みる)、情(ここ
ろ・心)、真(ま)、鏡(かがみ)、取(とる)、懸(かける)、杲(かほ・顔)、
【かほ(皃・容・顔貌)】
石
走(いはばしる)間々(ままに)生有(おひたる)皃花(かほばな)にし有(あれ)けり在(あり)つつ見(みれ)ば(万2288)
容
艶(かほよきに)縁(より)てぞ妹(いも)は、、(万1738)
○同源語:
間(ま)、花(はな)、見(みる)、縁(より)、
妹(いも)、
【かま(鎌)】
玉
掃(たまばはき)苅(かり)來(こ)鎌麻呂(かままろ)室(むろ)の樹(きと)與二棗
本一(な
つめがもとと)かき将レ掃
(はかむ)為(ため)(万
3830)
鎌は農機具であり、あまり万葉集の歌に出てくる
ことばではない。この歌の場合も「鎌」は擬人化されて鎌麻呂と呼ばれている。「鎌麻呂よ、玉箒を刈りとって来い。室の木と棗の木の下を掃き清めるために」
の意である。
古代中国語の「鎌」は鎌[liam]であり、日本漢字音は鎌(レン・かま)である。
「鎌」と同じ声符をもった漢字に二通りの読み方がある。兼(ケン)・嫌(ケン):廉(レン)・簾(レン)である。
スウェーデンの言語学者カールグレンは古代中国
語には複合子音があって、語頭の子音は複合子音で[kl-*]だったのではないかと提案している。確かに同じ声
符をもった漢字でカ行とラ行に読みわけるものは多い。
例:各(カク)・落(ラク)、監(カン)・藍(ラ
ン)、京(キョウ)・涼(リョウ) 剣(ケ ン)・斂(レン)、果(カ)・裸
(ラ)、樂(ガク・ラク)など、、
「鎌」の祖語は鎌[hliam*]のような入りわたり音をもっていたと考えられる。
鎌(レン)は鎌[hliam*]の入り渡り音が脱落したものであり、鎌(かま)は
入り渡り音が発達したものである。
中国の音韻学者、王力は『漢語語音史』のなか
で、[l-]の前に入り渡り音がくる漢字としてつぎのようなも
のをあげている。
例:果・裸、監・藍、兼・廉、験・斂、京・涼、
格・洛、諫・練、楽(ガク・ラク)、
○同源語:
苅(かる)、來(くる)、鎌(かま)、樹(き)、
本(もと)、
【かみ(神)】
皇
(おほきみ)は神(かみ)にし坐(ませ)ば真木(まき)の立(たつ)荒山中(あらやまなか)に海(うみ)を成(なす)かも(万241)
韓
国(からくに)の 虎(とらと)云(いふ)神(かみ)を 生取(いけどり)に 八頭(やつ)取(とり)持(もち)來(き) 其(その)皮(かは)を 多々
弥(たたみ・畳)に刺(さし)、、
(万
3885)
古代中国語の「神」は神[djien]である。神(シン)と神(かみ)とは関係なさそう
に見えるが、「神」と声符が同じ漢字に「坤」があり、「坤」は坤[khuən]である。天地乾坤の「坤」である。「神」の祖語
(上古音)に神[khuən*]という音があったとすれば、日本語の「かみ」は神[khuən*]と同源である可能性がある。
サ行音は一般にタ
行音(前口蓋音)が摩擦音化し
たものだと考えられているが、カ行音(後口蓋音)が摩擦音化したものも多くある。同じ声符号をもった漢字をカ行とサ行に読み分ける漢字がいくつかある。
例:技(ギ)・枝(シ)、耆(キ)・旨(シ)、期
(キ)・斯(シ)、庫(コ)・車(シャ)、赫
(カク)・赤(セキ・シャク)、牙(ガ)・邪
(ジャ)、合(ゴウ)・拾(シュウ)、嗅(キ
ュウ)・臭(シュウ)、屈(クツ)・出(シュ
ツ)、訓(クン)・川(セン)、拠(キョ)・處
(ショ)、公(コウ)・松(ショウ)、狭(キョ
ウ)・陝(セン)、暁(ギョウ)・焼(ショ ウ)、宦(カン)・臣(シン)、言(ゲ
ン)・信
(シン)、勘(カン)・甚(ジン)、感
(カン)・ 箴・鍼(シン)、賢(ケン)・腎(ジン)、
埼玉県行田市の稲荷山鉄剣の刻銘には「獲加多支
鹵大王」というのがあって、「ワカタケル」と読めることが判明した。5世紀の日本では「支」をカ行で読んでいたのである。
また、インド・ヨーロッパ語族では「百」をあら
わすことばカ行であらわすかサ行であらわすかでcenntum
languagesとsatem
languagesの
大きな語群に分けることが行われている。インド・ヨーロッパ語族は百(英語のhundred)をcenntum
(ケ
ンタム)と発音する系統のことばとsatem
(サ
テム)と摩擦音で発音する系統のことばに大きく二つに分けられ、インド・イランなどのことばはsatem系であり、ラテン語などはcentum系である。
○同源語:
皇(おほきみ・君)、真(ま)、木(き・枝)、立
(たつ)、山(やま)、中(なか)、海(うみ)、韓国(からくに)、取(とる)、來(き)、其(そ)の、多々弥(たたみ・畳)、刺(さ)す、
【かめ(亀)】
我
國(わがくに)は 常世(とこよ)に成(なら)む 圖(ふみ)負(おへ)る 神(くすしき)龜(かめ)も 新代(あらたよ)と 泉(いづみ)の河(かは)
に 持(もち)越(こせ)る 真木(まき)の嬬手(つまで)を、、(万50)
千
磐破(ちはやぶる) 神にも莫(な)負(おはせ) 卜部(うらべ)座(すゑ) 龜(か
め)も莫(な)焼(やき)曾(そ) 戀(こひ)しくに 痛(いたき)吾(わが)身(み)ぞ、、
(万3811)
亀は中国でも日本でも吉祥の印とされていた。
「龜」の古代中国語音は龜[kiuə]である。藤堂明保の『学研漢和大辞典』によれは
「亀」には
亀(キ)のほかに亀(グ・キュウ・コン・キン)という読みもあるという。日本語の「かめ」は中国語の「亀」と同系のことばであろう。
「かめ」はまた、甲[keap]とも関係の深いことばである。[-p]は[-m]と調音の位置が同じであり転移しやすい。
○同源語:
我・吾(わが)、國(くに)、常(とこ)、世
(よ)、圖(ふみ・文)、負(おふ)、代(よ・世)、泉(いづみ)、河(かは)、越(こす)、真(ま)、木(き・枝)、嬬(つま・妻嬬)、手(て)、千
(ち)、破(やぶ)る、莫(な)、焼(やく)、痛(いたき)、身(み)、
【かめ([瓦缶]*・瓦瓶)】
陶
人(すゑひと)の 所レ作
(つくれる)[瓦
缶]*(か
め)を 今日(けふ)往(ゆきて) 明日(あす)取(とり)持(もち)來(き)、、(万3886)
「かめ」には「瓶」という漢字があたられること
もある。「瓶」の古代中国語音は瓶[pieng]であり、日本漢字音は瓶(ヘイ・かめ)である。漢
字の「瓶」は并[pieng]と瓦[ngiuai]からできており、日本語の「かめ」は瓦[ngiuai]+瓶[pieng]と認識されたのであろう。中国語にも瓦瓶というこ
とばがある。
○同源語:
作(つく)る、今日(けふ)、徃(ゆく・行)、取
(とる)、來(くる)、
【かも(鴨)】
水
鳥(みづとり)の鴨(かも)の羽色(はいろ)の春山(はるやま)のおぼつか無(なく)も所レ念
(おもほゆる)鴨(かも)(万
1451)
あ
しひきの山川水(やまかはみづ)の音(おと)に不レ出
(いでず)人(ひと)の子(こ)ゆゑに戀(こひ)渡(わたる)青頭鶏(かも)(万3017)
○同源語:
鳥(とり)、羽(は)、色(いろ)、春(はる)、
山(やま)、念(おもふ)、川(かは・河)、音(おと)、出(いづ)、子(こ)、渡(わたる)、
【から(漢・韓)】
漢
人(からひと)も筏(いかだ)浮(うかべ)て遊(あそぶと)云(いふ)今日(けふ)そ和我(わが)勢故(せこ・背子)花蘰(はなかづら)せな(万4153)
鴈
(かりが)鳴(ね)の來(き)鳴(なき)しなへに韓(から)衣(ころも)裁田之山(たつたのやま)は黄(もみち)始有(そめたり)(万2194)
古代中国語の「韓」「漢」は韓[han]、漢[xan]である。[h-][-x]はいずれも日本語の発音にはない喉音であり、調音
の位置が近いことから日本語ではカ行であらわれる。韻尾の[n]は調音の位置が[-l]と同じであり、訓ではラ行であらわれることが多
い。
○同源語:
韓・漢(から)、今日(けふ)、和我(わが)、勢
故(せこ・背子)、花(はな)、蘰(かづら・葛)、鴈(かり)、鳴(ね・音)、來(き)、鳴(なく)、田(た)、山(やま)、
【からし(辛)】
樂
浪(ささなみ)の思賀(しが)の辛碕(からさき)雖二幸
有一(さ
きくあれど)大宮人(おほみやびと)の船(ふね)麻知(まち)兼(かね)つ(万30)
壮
鹿(しかの)海部(あま)の火氣(けぶり)焼(やき)立(たて)て燎(やく)塩(しほ)の辛(から)き戀(こひを)も吾(われは)為(する)かも(万2742)
漢字のローマ字表記は現在は拼音(ピンイン)によって行われているが、それまではWade式という表記法が行われていた。「辛」はWade式では辛(hsin)である。拼音で(x)と表記されている音はWade式では(hs-)と表記される。Wade式で(hs-)と表記される漢字のなかには音がカ行で訓がサ行て
あらわれるものが多い。
音がサ行で訓がカ行の例:消(hsiao)(ショウ・きえる)、小(hsiao)(ショウ・こ)、屑(hsie)(セツ・ くづ)、削(hsue)(サク・けづる)、心(hsin)(シン・こころ)、臭(hsiu)(シュウ・くさい)
中国語音のカ行とサ行の関係については「神」の
項ですでにふれたが、日本語の訓がか行で音がサ行の漢字にはつぎのようなものがある。古代中国語音は日本語のカ行音に対応し、日本漢字音は中国語における
口蓋化の結果をあらわしているものと思われる。
例:神(シン・かみ)、辛(シン・からい)、子
(シ・こ)、此(シ・これ)、斯(シ・これ)、
事(ジ・こと)、車(シャ・くるま)、樹
(ジュ・き)、鐘(ショウ・かね)、小(ショ
ウ・こ)、消(ショウ・きえる)、焦(ショ
ウ・こげる)、心(シン・こころ)、是(ゼ・
これ)、声(セイ・こえ)、清(セイ・きよ
い)、切(セツ・きる)、屑(セツ・くづ)、
川(セン・かは)、
○同源語:
浪(なみ)、碕(さき)、幸(さき)、宮(み
や)、船(ふね)、兼(かねる)、海部(あま)、火氣(けぶり・煙)、焼・燎(やく)、吾(われ)、
【からす(烏・鴉)】
暁
(あかとき)と夜烏(よがらす)雖レ鳴
(なけど)此(この)山上(もり)の木末(こぬれ)の於(うへ)は未(いまだ)静(しづけ)し(万1263)
可
良須(からす)等布(とふ・云)於保(おほ)乎曾(おそ・愚)杼里(どり)のまさでにも伎(き)まさぬ伎美(きみ)を許呂久(ころく)とぞ奈久(なく)(万3521)
日本語で「ス」のつく鳥には「からす」のほか
「かけす」「うぐひす」「きぎす(雉)」「はやぶさ」などがある。
○同源語:
暁(あかとき・暁時)、夜(よる)、木(こ・
枝)、未(いまだ)、静(しづか・静寂)、杼里(とり・鳥)、伎(き・來)、伎美(きみ・君)、奈久(なく・鳴)、
【かり(獵・獦)】
朝
獵(あさかり)に今(いま)立(たた)すらし暮獵(ゆふかり)に今(いま)たたすらし御(み)執(とらし)の梓(あづさの)弓(ゆみ)の加奈(かな)弭
(はず)の音(おと)為(す)なり
(万3)
日 雙斯(ひなみしの)皇子命(みこのみこと)の馬(うま)副(なめ)て御獵(みかり)立(たた)しし時(とき)は來(き)向(むかふ)(万49)
か
きつはた衣(きぬ)に須里(すり)つけ麻須良雄(ますらを)の服曾比(きそひ)獦(かり)する月(つき)は伎(き・來)にけり(万3921)
古代中国語の獵は獵[liap]である。スウェーデンの言語学者カールグレンは古
代中国語の[l-]には複合子音があり、獵[kliap*]という原型があったのではないかと分析している。
日本語の「かり」は上古中国語の獵[kliap*]の痕跡を留めているものと考えることができる。
中国語の[l-]が日本語でラ行であらわれるものとしては、鎌[liam]かま、廉[liam]かど、栗[liet]くり、來[lə]くる、などをあげることができる。
「獦」の古代中国語音は獦[kat]である。獵[kliap*]と獦[kat]の古代中国語音は音価が近く、日本語の「かり」は
「獵」「獦」と同系のことばであろう。
○同源語:
今(いま)、立(たつ)、暮(ゆふ・夜)、御
(み)、執(とる)、弓(ゆみ)、加奈(かな・金)、音(おと)、皇子(みこ・御子)、命(みこと・命人)、馬(うま)、時(とき)、來・伎(き)、向
(むかふ)、衣(きぬ・巾)、須里(すり・摺)、雄(を)、
【かり(雁・鴈)】
離レ家
(いへさかり)旅(たび)にしあれば秋風(あきかぜの)寒(さむき)暮(ゆふべ)に鴈(かり)喧(なき)度(わたる)(万1161)
○同源語:
家(いへ)、暮(ゆふ・夜)べ、喧(なく・鳴)、
度(わたる・渡)、
【かる(苅)】
こ
のころの戀の繁(しげ)くは夏草(なつくさ)の苅(かり)掃(はらへ)ども生(おひ)しく如(ごとし)(万1984)
中
々(なかなか)に君(きみ)に不レ戀
(こひず)は枚浦(ひらのうら)の白水郎(あま)ならましを玉藻(たまも)苅(かり)つつ(万2743)
○同源語:
草(くさ)、掃(はらふ・拂)、中(なか)、君
(きみ)、白水郎(あま・海人)、
【かれる(涸・枯・干)】
無
耳(みみなし)の池(いけ)し恨(うらめ)し吾妹兒(わぎもこ)が來(き)つつ潜(かづか)ば水(みづ)は将レ涸
(かれなむ)(万
3788)
夕 (ゆふ)去(されば)野邊(のべ)の秋(あき)芽子(はぎ)末(うら)若(わかみ)露(つゆに)枯(かれけり)金(あき)待(まち)難(がてに)(万2095)
う
れたきやしこ霍公鳥(ほととぎす)今(いま)こそは音(こゑ)の干(かる)がに來(き)喧(なき)響(とよめ)め(万1951)
○同源語:
無(なし)、耳(みみ)、恨(うら)む、我妹兒
(わぎもこ)、來(くる)、涸・枯(かれる)、夕(ゆふ・夜)、野(の)、邊(へ)、芽子(はぎ)、若(わかい)、霍公鳥(ほととぎす・隹)、今(い
ま)、音(こゑ・聲)、干(かる)、喧(なく・鳴)、
【き・こ(木・樹・枝)】
木
高(こだかく)はかつて木(き)不レ殖
(うゑじ)霍公鳥(ほととぎす)来(き)鳴(なき)令レ響
(とよめ)て戀(こひ)令レ益
(まさらしむ)(万
1946)
玉
葛(たまかづら)實(み)不レ成
(ならぬ)樹(き)ははちはやぶる神(かみ)ぞ著(つく)と云(いふ)不レ成
(ならぬ)樹(き)ごとに(万
101)
『續後紀承和』12年の条に「草も支(き)も栄
ゆる時に」という表現がある。声符「支」をもった漢字には枝[tjie]、技[gie]があり、「枝」の祖語(上古音)は枝[gie*]に近い音をもっていた可能性がある。日本語の
「き」は中国語の枝[gie*]と同源である可能性がある。
埼玉県の稲荷山古墳から出土した鉄剣には「獲多
支鹵」という印刻があり「わかたける」と解読されている。
○同源語:
霍公鳥(ほととぎす・隹)、来(くる)、鳴(な
く)、葛(かづら)、神(かみ)、著(つく)、
【き(牙)】
莵
原壮士(うなひをとこ)い 仰レ天(あめあふぎ) 叫(さけび)おらび あしずりし 牙(き)喫(かみ)建怒(たけび)て、、(万1809)
古代中国語の「牙」は牙[ngea]である。現代中国語では歯医者のことを「牙医」と
いい、歯科のことを「牙科」という。万葉集では「芽子」とかいて「はぎ」と読む例が数多くみられる。中国語の疑母[ng]は調音の位置が喉音[h-]に近く、音価も近い。臥[ngua](ふす)などもその例である。
○同源語:
原(はら)、天(あめ)、仰(あふぐ)、
【きさ(象)】
昔
(むかし)見(み)し象(きさ)の小河(をがは)を今(いま)見(みれ)ば弥(いよよ)清(さやけく)成(なり)にけるかも(万316)
三
吉野(みよしの)の象山(きさやま)の際(ま)の木末(こぬれ)にはここだも散和口(さわく)鳥(とり)の聲(こゑ)かも(万924)
象山は吉野にある山の名前である。「象」の古代
中国語音は象[ziang]である。象は日本にはいなかった動物であるが、そ
の存在は古くから知られ、『和名抄』には「象、岐佐(きさ)、、、大耳、長鼻、眼細、牙長者也」とある。
日本語の「き+さ」は、「牙[ngea]+so<朝鮮語の牛>」から派生したものである可能性が
ある。「象」の祖語(上古音)は喉音[hiang*]であり、それが摩擦音化して象[ziang]になったと考えることもできる。
○同源語:
見(みる)、小河(をがは)、今(いま)、清(さ
やけ)し、野(の)、山(やま)、際(ま・間)、木(き・枝)、散和口(さわく・騒)、鳥(とり)、聲(こゑ)、
【きつね(狐)】
刺
(さし)名倍(なべ・鍋)に湯(ゆ)和可世(わかかせ)子等(こども)櫟津(いちひつ)の檜橋(ひはし)従(より)來(こ)む狐(きつね)に安牟佐武(あ
むさむ・浴)(万
3824)
○同源語:
刺(さ)す、湯(ゆ)、和可世(わか・沸)せ、子
(こ)、津(つ)、檜(ひ)、來(くる)、
【きぬ(絹・衣・巾)】
西
市(にしのいち)にただ獨(ひとり)出(いで)て眼(め)不レ並
(ならべず)買(かひ)てし絹(きぬ)の商(あき)じこりかも(万1264)
山 藍(やまあゐ)もち 摺(すれる)衣(きぬ)服(き)て 直(ただ)獨(ひとり) い渡(わたら)為(す)兒(こ)は、、(万1742)
衣
(きぬ)こそば 其(それ)破(やれぬれ)ば 継(つぎ)つつも またも相(あふ)と言(いへ)、、(万3330)
古代中国語の「絹」は絹[kyuan]である。日本語の「きぬ」は中国語と同源である。
「絹」は蚕とともに中国からもたらされた。
万葉集では「きぬ」に「絹」のほかに「衣」とい
う字を使っている。衣(きぬ)は絹(きぬ)と発音は同じだが、意味が少し違う。衣(きぬ)は巾[kiən]であろう。布巾(ふきん)、雑巾(ぞうきん)の
「巾」である。衣(きぬ)も中国語の巾[kiən]と同源であろう。
○同源語:
酉(とり)、出(いで)、眼(め)、山(やま)、
摺(する)、直(ただ)、渡(わた)る、兒(こ)、其(そ)れ、継(つぐ・續)、相(あふ・合)、
【きはみ・きはまる(極)】
吾
(わが)命(いのち)の生(いけらむ)極(きはみ)戀(こひ)つつも吾(われ)は将レ度
(わた)らむ、、(万
3250)
将レ言
(いはむ)為便(すべ)将レ為
便(せむすべ)不レ知
(しらず)極(きはまりて)貴(たふとき)物(もの)は酒(さけ)にし有(ある)らし(万342)
○同源語:
吾(われ)、度(わたる・渡)、知
(し)る、物(もの)、酒(さけ)、
【きみ(君・公)】
茜
草(あかね)指(さす)武良前(むらさき)野(の)逝(ゆき)標野(しめの)行(ゆき)野守(のもり)は不レ見
(みずや)君(きみ)が袖(そで)ふる(万20)
昨
日(きのふ)こそ公(きみ)は在(あり)しか不レ思
(おもはぬ)に濱松(はままつ)が於(うへに)雲(くもに)棚引(たなびく)(万444)
例:濱[pien](はま)、肝[kan](きも)、絆[puan](ひも)、文[miuən](ふみ)、雲[hiuən](くも)、
呑[thən](のむ)、困[khuən](こまる)、混[huən](こむ)、
「公」の古代中国語音は公[kong]である。公(きみ)は韻尾[-ng]がマ行に転移したものである。[-ng]は[-m]と調音の方法が同じ(鼻音)であり、転移しやす
い。[-ng]も日本語にはない音節である。
例:浪[lang](なみ)、霜[shiang](しも)、状[dziang](さま)、灯[tang](ともる)、澄[diang]
(すむ)、停[dyeng](とまる)、渟[dyeng](たまる)、醒[syeng](さめる)、
日本語の五十音図はサンスクリットの音図などの
影響を受けて平安時代に僧侶が作ったものだが、その最後に「ン」がある。「ン」は中国語の韻尾[-n]と[-m]の両方に用いられている。日本語では韻尾の[-n]と[-m]を弁別しない。サンスクリットの音図でも[-m]は音図の最後にある。
日本語に「ン」という音節があらわれるように
なったのは中国語音の影響で、平安時代以降のことであろう。日本語には今でも「ン」ではじまることばはない。
○同源語:
指(さ)す、野(の)、逝・行(ゆく)、守(まも
る・護)、見(みる)、袖(そで)、公(きみ)、思(おもふ・念)、濱(はま)、雲(くも)、棚(たな・壇・段)、
【きも(肝)】
霞
(かすみ)立(たつ)長(ながき)春日(はるひ)の晩(くれに)けるわづ肝(きも)之良受(しらず・知)村肝(むらきも)の心(こころ)を痛(いた)
み、、(万
5)
村
肝(むらきも)の情(こころ)くだけて如此(かく)ばかり余(わが)戀(こふ)らくを不レ知
(しらず)かあるらむ(万
720)
○同源語:
霞(かすみ・霞霧)、立(たつ)、長(なが)き、
春(はる)、晩(くれ・昏)、知(し)る、村(むら・群)、心・情(こころ)、痛(いたむ)、余(わが・我)、
【きゆ(消)】
暮
(ゆふべ)置(おき)て旦(あした)は消(きゆ)る白露(しらつゆ)の可レ消
(けぬべき)戀(こひ)も吾(われ)は為(する)かも(万3039)
雪
(ゆき)こそは春日(はるひ)消(きゆ)らむ心(こころ)さへ消失(きえうせ)たれや言(こと)も不二徃
來一(か
よはぬ)(万
1782)
例:小[siô](こ・ショウ)、子[tzia](こ・シ)、之[tjiə](これ・シ)、此[tsie](これ・シ)、狩
[sjiu](かり・シュ)、首[sjiu](くび・シュ)、樹[zjio](き・ジュ)、臭[thjiu](くさい・シュ ウ)、醸 [njiang](かもす・ジョウ)、書[sjia](かく・ショ)、削[siôk](けずる・サク)、焦 [tziô](こげる・ショウ)、鐘(かね・ショウ)、
浄[dzieng](きよい)、情[dziəng](こころ・
ジョウ)、心[siəm](こころ・シン)、辛[sien](からい・シン)、
また、同じ声符をカ行とサ行に読み分けるものも
ある。カ行が古く、サ行が新しい。
例:技(ギ)・枝(シ)、祇(ギ)・氏(シ)、耆
(キ)・指(シ)、期(キ)・斯(シ)、睨(ゲ
イ)・児(ジ)、庫(コ)・車(シャ)、坤
(コン)・神(シン)、言(ゲン)・信(シン)、
○同源語:
暮(ゆふ・夜)べ、置(おく)、吾(われ)、春
(はる)、心(こころ)、言(こと)、
【きよし(清・浄)】
千
鳥(ちどり)鳴(なく)佐保(さほ)の河門(かはと)に清(きよき)瀬(せ)を馬(うま)打(うち)和太思(わたし・渡)何時(いつ)か将レ通
(かよはむ)(万
715)
大
瀧(おほたき)を過(すぎ)て夏箕(なつみ)に傍(そばり)居(ゐ)て浄(きよき)川瀬(かはせを)見(みる)が明(さやけ)さ(万1737)
「清」の現代北京語音は清(qing)である。現代中国語音がqでらわれる漢字のなかには日本漢字音がカ行のもの
とサ行のものがみられる。
現代北京語音qがカ行であらわれる例;期(qi)、其(qi)、旗(qi)、企(qi)、乞(qi)、起(qi)、棄(qi)、器(qi)、 氣(qi)、謙(qian)、乾(qian)、強(qiang)、橋(qiao)、巧(qiao)、勤(qin)、琴(qin)、郷(qing)、
軽(qing)、慶(qing)、窮(qing)、丘(qiu)、求(qiu)、球(qiu)、區(qu)、屈(qu)、去(qu)、圏(quan)、
権(quan)、犬(quan)、群(qun)、
現代北京語音qがサ行であらわれる例;漆(qi)、七(qi)、栖・棲(qi)、妻(qi)、凄(qi)、齊(qi)、千(qian)、
前(qian)、潜(qian)、銭(qian)、浅(qian)、槍(qiang)、切(qie)、親(qin)、侵(qin)、秦(qin)、寝(qin)、
情(qing)、晴(qing)、請(qing)、秋(qiu)、取(qu)、全(quan)、泉(quan)、鵲(que)、雀(que)、
現代北京語音と日本漢字音の関係を解明すること
はむずかしいが、「清」が訓で清(きよい)であらわれ、音で清(セイ)とカ行とサ行にわたってあらわれることと関係があるかもしれない。
漢字は基本的に象形文字であるため、古代の漢字
音を復元することは容易ではない。しかし、中国語には同じ声符がカ行とサ行にあらわれる漢字がいくつかある。
例:堅(ケン)・臣(シン)、感(カン)・鍼(シ
ン)、坤(コン)・神(シン)、庫(コ)・車
(シャ)、嗅(キュウ)・臭(シュウ)、喧
(ケン)・宣(セン)、など
また、訓がカ行で、音がサ行であるわれる漢字も
ある。
例:神(かみ・シン)、辛(からい・シン)、臭
(くさい・シュウ)、など
「清・浄」の上古音が清[xieng*]・浄[hiəng*]であったとすれば、清(きよい・セイ)、浄(きよ
い・ジョウ)、についても整合的に説明ができる。
清[tsieng]には「さやか」という読みもある。清(きよし)の
方が古く、清(さやか)の方が新しい。
中国語音韻学では反切という表音法があり、漢字 の頭音と韻尾に分けてその音価を示す方法が古くからおこなわれている。例えば「清」の反切は「七情」であり、「浄」の反切は「疾政」であるという。しか し、反切に使われている文字(例えば、七、疾、情、政)の音価が定まっているわけでもないので、循環論になってしまうことが多い。
同じ声符に二つの読み方があることについては、言語学者のなかにも疑問を持つ人が多い。それは、西洋言語学では「音韻法則に例外なし」という青年文法家た ちの主張があるからである。しかし、数千年にわたって広い地域で起ころ音韻変化はその転移の方向が複数にわたることがあるのではなかろうか。
例えば言語学者の小泉保は『縄文語の発見』のなかで「複合対応について納得のいく説明がなされない限り、規則的対応と認めることはできない。」
(p.73)としている。しかし、同じ時代に同じ地域で起こった音韻変化については例外はないにしても、実際にはどうであろうか。「絵」は「カイ」であ
り、「ヱ」である。英語でもhundredはcentam系であるが、centuryはsatem系である。
千鳥(ちどり)、鳴(なく)、河・川(かは)、馬(うま)、打(うつ)、和太思(わたし・渡)、瀧(たき)、過(すぎ)、見(みる)、明・清(さやか)
さ、吾(わが)、背子(せこ)、挿
(さす)、芽子(はぎ)、置(おく)、照(てる)、
【きる(鑚・斬)】
然
有(しかれ)こそ 年(とし)の八歳(やとせ)を 鑚髪(きりかみ)の 吾同子(よちこ)を 過(すぎ)、、(万3307)
汝
(な)は如何(いか)に念(おもふ)や 念(おもへ)こそ 歳(としの)八年(やとせ)を 斬髪(きりかみの) 与知子(よちこ)を過(すぎ)、、(万3309)
古代中国語の[ts-]はさらに時代をさかのぼると[x-][h-]系の音であった可能性がある。「鑚」「斬」の祖語(上古音)は 鑚[xuan*]・斬[heam*]に近い音であったと思われる。漢字のなかには同じ
声符をカ行とサ行に読み分けるものがたくさんある。
例:活[huat](カツ)・舌[djiat](ゼツ)、訓[xiuən](クン)・川[thjyuan](セン)、技[gie](ギ)・
枝[tjie](シ)、期[giə](キ)・斯[sie](シ)、耆[giei](キ)・脂[tjiei](シ)、祇[gie]・氏[zjie]、
屈[khiuət](クツ)・拙[tjiuat](セツ)、庫[kha](コ)・車[kia](シャ)、睨[ngye](ゲイ)・児
[njie](ジ)、
また、古代中国語音が摩擦音系の漢字の訓がカ行
であらわれるものがいくつか見られる。
例:此[tsie]これ、子[tziə](こ)、草[tsu]くさ、叢[dzong]くさ、桑[sang]くは、焦[tziô]こげる、
蔵[dzang]くら、倉[tsang]くら、清[tsieng]きよき、
日本語の「きる」は「鑚」「斬」あるいは「切」
の上古音を継承したことばであろう。
○同源語:
過(すぎ)る、汝(な)、如何(いか)に、念(お
もふ)、
【くがね(黄金)】
銀
(しろがね)も金(くがね)も玉(たま)もなにせむにまされる多可良(たから)古(こ・子)にしかめやも(万803)
須 賣呂伎(すめろぎ)の御代(みよ)佐可延牟(さかえむ)と阿頭麻(あづま)なる美知乃久(みちのく)夜麻(やま)に金(くがね)花(はな)佐久(さく)(万4097)
吾
大王(わごおおほきみ・君)の 毛呂比登(もろびと)を 伊射奈比(いざなひ・誘)多麻比(たまひ) 善(よき)事(こと)を 波自米(はじめ・始)多麻
比弖(たまひて) 久我祢(くがね・黄金)かも 多之氣久(たしけく)あらむと、、、(万4094)
日本語の「かね」は中国語の金[kiəm]である。「かね」は金属一般をさす。金(キン)は
金(くがね)であり、銅は「あかがね」、鉄は「くろがね」ということになる。
「くがね」とは黄金[huang-kiəm]のことである。「黄」の日本漢字音は黄(コウ・オ
ウ・き)であり、訓では韻尾の[-ng]は脱落している。
○同源語:
金・久我祢(くがね・黄金)、古(こ・子)、御
(み)、代(よ・世)、佐可延(さかえ・榮)、夜麻(やま・山)、花(はな)、佐久(さく・咲)、吾(わが)、大王(おほきみ・君)、
【くき(莖)】
大
夫(ますらを)と念在(おもへる)吾(われ)や水莖(みづくき)の水城(みづき)の上(うへ)に泣(なみだ)将レ拭
(のごはむ)(万
968)
秋
風(あきかぜ)の日(ひ)に異(け)に吹(ふけ)ば水莖(みづくき)の岡(をか)の木葉(このは)も色(いろ)づきにけり(万2193)
古代中国語の「莖」は莖[heng]である。語頭の喉音[h-]は日本語ではカ行であらわれる。韻尾の[-ng]は隋唐の時代以前の上古語では[-k]に近かったと考えられている。日本語の「くき」の
語源は中国語の「莖」である。
同じ声符の漢字でも二通りの読み方のある漢字が
みられる。この場合、拡(カク)、較(カク)のほうが広(コウ)、交(コウ)より古い。
例:広(コウ):拡(カク)、交(コウ):較(カ
ク)など
また、日本語の訓が韻尾[-k]の痕跡を留め、音は音便化ているものもみられる。
例:嗅(キュウ・かぐ)、景・影(エイ・ケイ・か
げ)、塚(チョウ・つか)、双六(ソウ すごろ く)、相模(ソウ・さがみ)など、
○同源語:
念(おもふ)、吾(われ)、岡(をか・岳)、木 (き・枝)、葉(は)、色(いろ)、
【くさ(草)】
開
木代(やましろの)來背(くぜの)社(やしろの)草(くさ)勿(な)手折(たをりそ)己(わが)時(ときと)立(たち)雖レ榮
(さかゆとも)草(くさ)勿(な)手折(たをりそ)
(万
1286)
白
浪(しらなみ)の濱松(はままつ)が枝(え)の手向草(たむけくさ)幾代(いくよ)までにか年(とし)の經(へ)ぬらむ(万34)
「草」の古代中国語音は草[tsu]であり、日本漢字音は草(ソウ・くさ)である。日
本漢字音では訓がカ行音で音がサ行音であらわれるものがいくつかある。
例:小[siô](ショウ・こ)、心[siəm](シン・こころ)、辛[sien](シン・からい)、桑[sang]
(ソウ・くは)、屑[syet](セツ・くず)、削[siôk](サク・けづる)、消[siô](ショウ・けす)、 勝[sjiəng](ショウ・かつ)、是[zjie](ゼ・これ)、樹[zjiu](ジュ・き)、狩[sjiu](シュ・かり)、 書[sjia](ショ・かく)、此[tsie](シ・これ)、切[tsiet](セツ・きる)、清[tsieng](セイ・
きよい)、倉[tsang](ソウ・くら)、子[tziə](シ・こ)、焦[tziô](ショウ・こげる)、叢
[dzong](ソウ・くさ)、蔵[dzang](ゾウ・くら)、情[dzieng](ジョウ・こころ)、浄[dzieng] (ジョウ・きよい)、 之[tjiə](シ・これ)、鐘[tjiong](ショウ・かね)、神[djien](シン・
かみ)、声[thjieng](セイ・こえ)、臭[thjiu](シュウ・くさい)、車[kia](シャ・くるま)、児 [njie](ジ・こ)、
これらの対応には規則性がないようにもみえる
が、同じ声符をカ行とサ行に読み分ける漢字もあるかおとから、サ行音はカ行音が介音[-i-]の影響で摩擦音化したものであろう。
例:支[tjie]・技[gie]、川[thjyuən]・訓[xiuən]、神[djien]・坤[khuan]、鍼[tjiəm]・感[həm]、
宣[siuan]・喧[xiuan]、腎[zjiuən]・監[keam]、児[njie]・睨[ngye]、杵[thjia]・午[nga]、
草[tsu]の祖語(上古音)は草[xu*]に近い音であった可能性がある。日本語の「くさ」
は上代中国語音の喉音[x-]の痕跡を留めてものであろう。
○同源語:
來(くる)、背(せ)、手(て)、折(をる)、己
(わが・吾)、時(とき)、立(たつ)、榮(さかえ)、浪(なみ)、濱(はま)、枝(え)、向(むけ)る、幾(いく)、代(よ・世)、經(へ)る、
【くし(串)】
五
十(いつ)串(くし)立(たて)神酒(みわ)すゑ奉(まつる)神主部(はふりべ)のうずの玉(たま)蔭(かげ)見(みれ)ば乏(ともし)も(万3229)
籠
(こ)もよ 美(み)籠(こ)母乳(もち) 布久思(ふくし・串)もよ 美(み)夫久志(ふくし・串)持(もち)、、(万1)
例:咽(エツ)→因(イン)、鉢(ハツ)→本
(ホ
ン)、薩(サツ)→産(サン)など
中国語には[-s]という韻尾はないが、「串」に串[hoat*]という音があったとすれば、日本語では「くし」は
「串」と同源であろう。中国語の韻尾[-n]はサ行であらわれることがある。
例:岸(ガン・き
し)、賢(ケン・かしこい)、干(カン・ほす)、など
大野晋は岩波の『日本古典文学大系・萬葉集一』
の頭注で「クシは朝鮮語kos(串)と同源」(p.8) としているが、朝鮮語のkosも中国語の串[hoan]と同源である可能性がある。
○同源語:
立(たて)る、神(かみ)、酒(さけ)、座(す
わ)る、蔭(かげ・影)、見(み)る、籠(こ・かご)、美(み)、
【くず・かづら(葛)】
鴈
鳴(かりがね)の寒(さむく)鳴従(なきしゆ)水莖(みづぐき)の岡(をか・岳)の葛葉(くずは)は色(いろ)づきにけり(万2208)
玉
葛(たまかづら)花(はな)耳(のみ)開(さき)て不レ成
有(らざる)は誰(たが)戀(こひ)ならめ吾(あは)孤悲(こひ)念(おもふ)を(万102)
現代の日本語では「づ」と「ず」の弁別は失われ
て「ず」に合流しているが、万葉集の時代にも葛(くず)は「久受」と表記され、葛(かづら)は「づ」である。万葉集の時代にも「づ」と「ず」は必ずしも正
確に弁別されていたとは言い難い。
旧かなづかいでは「屑」は屑(くづ)、「葛」は
葛(くず)として区別している。葛(くず)は韻尾[-t]が摩擦音化してサ行に転移したものである。
○同源語:
鴈(かり)、鳴(ね・なく)、莖(くき)、岡(を
か・岳)、葉(は)、色(いろ)、花(はな)、開(さく・咲)、吾(あ)、念(おもふ)、
【くすし(奇・霊・神)】
如レ聞
(きくがごと)真(まこと)貴(たふと)く奇(くすしく)も神(かむ)さび居(をる)かこれの水嶋(みずしま)(万245)
言 (いひも)不レ得 (えず) 名(なづけも)不レ知 (しらず) 霊(くすしく)も 座(います)神(かみ)かも、、(万319)
我
國(わがくに)は 常世(とこよ)に成(なら)む 圖(ふみ)負(おへ)る 神(くすしき)龜(かめ)も 新代(あらたよ)と 泉(いづみ)の河(かは)
に 持(もち)越(こせ)る 真木(まき)の嬬手(つまで)を、、(万50)
古代中国語の「奇」は奇[kiai]であり、「霊」は霊[lying]である。「奇」音義ともに日本語の「くすし」に近
い。「霊」の祖語(上古音)は霊[hlying*]のような入りわたり音を伴っていた可能性がある。
霊[hlying*]の頭音[h*]がカ行であらわれたとすれば「霊」もまた「くす
し」と関係のあることばである可能性がある。
○同源語:
神(かみ)、居(を)る、嶋(しま・洲)、名
(な)、知(しる)、我(わが)、常世(とこよ)、龜(かめ)、代(よ・世)、泉(いづみ)、河(かは)、越(こす)、真木(まき・枝)、嬬(つま・妻
嬬)、手(て)、
【くち(口)】
暮
(ゆふ)獵(かり)に鶉雉(とり)履(ふみ)立(たて)大御馬(おほみま)の口(くち)おさへとめ、、(万478)
波
流(はる・春)の野(の)に久佐(くさ)波牟(はむ)古麻(こま)の久知(くち)やまず安(あ・吾)をしのぶらむ伊敝(いへ)の兒(こ)ろはも(万3532)
○同源語:
暮(ゆふ・夜)、獵(かり・獦)、鶉雉(とり・
鳥)、履(ふむ)、立(たてる)、御(み)、馬(うま)、波流(はる・春)、野(の)、久佐(くさ・草)、古麻(こま・駒)、安(あ・吾)、伊敝(いへ・
家)、兒(こ)、
【くつ(履・靴)】
髪
(かみ)だにも 搔(かき)は不レ梳
(けづらず) 履(くつ)をだに 不レ著
(はかず)雖レ行
(ゆけども)、、(万
1807)
信
濃道(しなのぢ)は伊麻(いま)の波里美知(はりみち・墾)可里(かり)ばねに安思(あし)布麻之牟奈(ふましむな)久都(くつ)はけ和我(わが)世
(せ・背)(万
3399)
万葉集では履[liei]が「くつ」にあてられている。「履」は主に儀礼用
の「くつ」であり、「靴」は革靴である。日本語の「くつ」は中国語の靴[xuai]+沓[dəp]である可能性がある。
「履」の祖語にもし、入りわたり音があり、履[hliei*]のような音があったとすれば、「履」も「靴」と音
義ともに近いことばであった可能性もある。
また、「履」の声符が復[biuk]であることから「履」は「はく」と関係のありこと
ばである可能性もある。中国語では声調をかえることによって、名詞から動詞を作る造語法がある。一番目の歌では「はく」に「着」があてられているが訓借で
あろう。
○同源語:
著(はく・履)、行(ゆく)、伊麻(いま・今)、
波里(はり・墾)、可里(かる・刈)、和我(わが)、世(せ・背)、
【くつ(朽)】
獨
(ひとり)寝(ぬ)と茭(こも)朽(くち)めやも綾(あや)席(むしろ)緒(を)に成(なる)までに君(きみ)をし将レ待
(またむ)(万
2538)
○同源語:
寝(ぬ・寐)、茭(こも)、綾(あや)、君
(きみ)、
【くに(國・地祇・本郷)】
志
貴嶋(しきしまの)倭(やまとの)國(くに)は事霊(ことだま・言)の所レ佐
(たすくる)國(くに)ぞ真福(まさきく)在(あり)こそ(万3254)
天 神(あまつかみ) 阿布藝(あふぎ)許比(こひ)乃美(のみ・禱) 地祇(くにつかみ) 布之弖(ふして)て額(ぬか)つき、、(万904)
燕 (つばめ)来(くる)時(とき)に成(なり)ぬと鴈(かり)が鳴(ね)は本郷(くに)思(おもひ)つつ雲(くも)隠(がくり)喧(なく)(万4144)
王力は『同源字典』のなかで「莫[mak]と晩[miuan]は同源である。」(p.16)。卑近な例では雀(ジャク)・麻雀(マージャ
ン)などがあげられるかもしれない。同じ声符の韻尾をカ行とナ行に読み分ける例としては次のようなもの
をあげることができる。
例:柵(サク)・冊(サツ)、益(エキ)・溢(イ
ツ)、陸(リク)・睦(むつむ)、泊(ハク・
はつ)、克(コク・かつ)、など
中国語の「國」は日本語の「くに」と同源である
可能性がある。一方、スウェーデンの言語学者カールグレンは日本語の「くに」の語源は郡[giuən]ではないかとしている。朝鮮半島には漢の時代から
楽浪郡、帯方郡などが置かれて行政の単位として機能していた。
『名義抄』には「郡 クニ、コホリ」とある。郡[giuən]ばかりでなく県[huen]も日本語の「くに」に近い。「県」は王畿以外の集
落、農耕地で、郡県制が敷かれてからは郡も県も地方行政の単位である。日本語の「くに」は郡[giuən]、県[huen]と同系のことばであろう。國[kuək]は義(意味)が日本語の「くに」にもっとも近く、
日本語の「くに」は國[kuək]から派生した可能性もある。
○同源語:
嶋(しま・洲)、事(こと・言)、真(ま)、福
(さき・幸)く、天(あめ)、神(かみ)、阿布藝(あふぐ・仰)、布之弖(ふして・伏)、額(ぬか)、來(くる)、
時(とき)、鴈(かり)、鳴・喧(なく・ね)、思(おもふ・念)、雲(くも)、隠(かくる)、
【くび(頸)】
吾
(わが)戀(こひ)は千引(ちひき)の石(いは)を七許(ななばかり)頸(くび)に将レ繋
(かけむ)も神(かみ)のまにまに(万743)
古代中国語の「頸」は頸[kieng]である。日本語の「くび」は音義ともに中国語の
「頸」に近い。韻尾の[-ng]は鼻音であり、同じく鼻音である[-m]に転移することも多い。
例:霜(ソウ・しも)、灯(トウ・ともる)、醒
(セイ・さめる)、統(トウ・すめる)、
登(トウ・のぼる)など
○同源語:
吾(わが)、千(ち)、繋(かけ)る、神(か
み)、
【くま(熊)】
荒
熊(あらくま)の住(すむと)云(いふ)山(やま)の師齒迫(しはせ)山(やま)責(せめ)て雖レ問
(とふとも)汝(なが)名(な)は不レ告
(のらじ)(万
2696)
「熊」の古代中国語音は熊[hiuəm]である。日本語漢字音の熊(ユウ)は熊[hiuəm]の頭音[h-]が脱落した唐代の漢字音に対応している。 日本語
の熊(くま)は古代中国語の喉音[h-]の痕跡を留めたものである。
日本語の訓では古代中国語の喉音[h-]がカ行であらわれる例として、雲[hiuən](くも・ウン)、越[hiuat](こえる・エツ)などをあげることができ。いずれ
の場合も訓は喉音[h-]を受け継いでいて、音は喉音[h-]はが脱落したものである。
同じ声符をもつ漢字でカ行とア行に読み分けるも
のもいくつかみられる。
例:緩(カン)・援(エン)、軍(グン)・運(ウ
ン)、渇(カツ)・謁(エツ)、禾(カ)・和
(ワ)、黄(コウ・オウ)
朝鮮語では「くま」のことを(kom)という。日本語の「くま」の語源は朝鮮語の(kom)であるとする説もあるが、朝鮮語の熊(kom)も日本語の熊(くま)も古代中国語の熊[hiuəm]から派生したものであり、同源であろう。
○同源語:
荒(あらい)、住(すむ)、山(やま)、汝
(な)、名(な)、
【くも(雲)】
三
輪山(みわやま)を然(しか)も隱(かくす)か雲(くも)だにも情(こころ)有(あら)なも可苦佐布(かくさふ)べしや(万18)
瀧
上(たきのうへ)の三船(みふね)の山(やま)に居(ゐる)雲(くも)の常(つね)に将レ有
(あらむ)と和我(わが)念(おもは)なくに(万242)
古代中国語の「雲」は雲[hiuən]である。中国語の頭音[h-]は次にくる介音[-iu-]の影響で脱落して唐代には雲[jiuən]となった。訓の雲(くも)は、唐代以前の上古中国
語の喉音[h-]の痕跡を留めている。同じような例として熊[hiuəm](ユウ・くま)、運[hiuən]・軍[hiuən]などをあげることができる。
○同源語:
三(み)、山(やま)、隠(かく)す、情(ここ
ろ・心)、瀧(たき)、船(ふね・盤)、居(ゐ)る、常(つね)、和我(わが)、念(おもふ)、
【くやし・くい(悔)】
悔
(くやしく)も満(みち)ぬる塩(しほ・潮)か墨江(すみのえ)の岸(きし)の浦廻(うらみ)従(ゆ)行(ゆか)まし物(もの)を(万1144)
真
玉(またま)つくをちこち兼(かね)て言(こと)は五十戸(いへ)ど相(あひ)て後(のち)こそ悔(くい)には有(あり)と五十戸(いへ)(万674)
○同源語:
相(あふ・合)、満(みち)る、塩(しほ・潮)、
行(ゆく)、物(もの)、真(ま)、兼(かね)る、言(こと)、
【くら(倉)】
枳
(からたち)の棘原(うばら)苅(かり)そけ倉(くら)将レ立
(たてむ)屎(くそ)遠(とほく)まれ櫛(くし)造(つくる)刀自(とじ)(万3832)
荒
城(あらき)田(だ)の子師(しし)田(だ)の稲(いね)を倉(くら)に挙蔵(あげ)てあな干稲(ひね)々々(ひね)し吾(わが)戀(こふ)らくは(万3848)
「蔵」は蔵[dzang]であり、倉[tsang]と音義ともに近い。また、「くら」には庫[kho]も使われることがある。庫(コ)・車(シャ)の関
係も、庫(コ)が古い音であり、車(シャ)は介音[-i-]の発達によって摩擦音化したものである。
○同源語:
原(はら)、苅(かる)、立(たて)る、造(つく
る)、荒(あら)き、田(た)、稲(いね・秈)、干(ひる)、吾(わが)、
【くり(栗)】
宇
利(うり・瓜)はめば 胡(こ・子)ども意母保由(おもほゆ) 久利(くり・栗)はめば ましてしのばゆ いづくより 枳多利斯(きたりし・来)物能(も
の)そ、、(万
802)
『和名抄』には
「栗 久利、一名撰子」とある。
栗は縄文時代以来重要な食糧源だったと思われる。万葉集には「くり」を「栗」と表記した例はないが、古代中国語音は栗[liet]である。「栗」の祖語(上古音)には入りわたり音があり栗[hliet*]のような音であったと推定される。日本語の「く
り」は入りわたり音の[h-]をカ行音であらわしたものであり、日本漢字音の栗
(リツ)は入りわたり音[h-]が失われたものであろう。同じような例としては来[hlə*](くる)、輪[hliuən*](くるま)をあげることができる。
中国語には同じ声符の漢字をカ行とラ行に読みわ
けているものがいくつかみられる。
例:果(カ)・裸(ラ)、各(カク)・落(ラ
ク)、監(カン)・藍(ラン)、剣(ケン)・斂(レ
ン)、兼(ケン)・簾(レン)、京(キョ
ウ)・涼(リョウ)など、、
○同源語:
胡(こ・子)、意母保由・(おもほ・念)ゆ、枳多
利斯(きたりし・來)し、物能(もの)、
【くる(來)】
倭
(やまと)には鳴(なき)てか来(く)らむ呼兒鳥(よぶこどり)象(きさ)の中山(なかやま)呼(よび)ぞ越(こゆ)なる(万70)
将レ來
(こむと)云(いふ)も不レ来
(こぬ)時(とき)有(ある)を不レ來
(こじと)云(いふ)を将レ來(こむ)とは不レ待
(またじ)不レ來
(こじと)云(いふ)物(もの)を(万527)
古代中国語の「來」は來[lə]である。來[lə]の祖語は來[hlə*]に近い発音だったと考えられる。日本語の「くる」
は古代中国語の來[hlə*]と同源であろう。
○同源語:
鳴(なく)、來(くる)、兒(こ)、鳥(とり)、
象(牙(き)+<朝鮮語の牛so>)、中山(なかやま)、越(こゆる)、時(と
き)、物(もの)、
【くるし(苦)】
念
(おもひ)絶(たえ)わびにし物(もの)を中々(なかなか)になにか辛苦(くるし)く相(あひ)見(み)始(そめ)けむ(万750)
す
べも無(な)く苦志久(くるしく)阿礼(あれ)ば出(いで)波之利(はしり)去(いな)なと思(おもへ)ど許(こ・子)らに佐夜利奴(さやりぬ)(万899)
○同源語:
念(おもふ)、絶(たえる)、物(もの)、中(な
か)、辛苦・苦志(くるし)、相(あふ・合)、見(みる)、無(な)き、出(いで)、去(いく・往)、思(おもふ・念)、許(こ・子)、佐夜利(さやり・
障)、
【くるふ(狂)】
相
(あひ)見(み)ては幾日(いくか)も不レ経
(へぬ)をここだくも久流比爾久流必(くるひにくるひ)所レ念
(おもほゆる)かも(万
751)
例:経[kyeng](へる)、萌[meang](もえる)、軽[kyeng](かるい)、広[kuang](ひろい)、
平[being](ひら)、幌[huang](ほろ)、頃[khiueng](ころ)、香[xiang](かをり)、
○同源語:
相(あひ・合)、見(みる)、幾(いく)、経(へ
る)、念(おもふ)、
【くるま(車)】
古
部(いにしへ)の 賢(さかしき)人(ひと)も 後(のち)の世(よ)の 竪監(かがみに)将レ為
(せむ)と 老人(おいびと)を 送(おくり)為(し)車(くるま) 持(もち)還(かへり)けり(万3791)
戀
草(こひくさ)を力車(ちからぐるま)に七車(ななくるま)積(つみ)て戀(こふ)らく吾(わが)心(こころ)から(万694)
一方、「輪」の祖語(上古音)には入りわたり音
があり輪[hliuən*]に近い音であったと考えられる。日本語の「くる
ま」は上代中国語の輪[hliuən*]に由来するものであると考えることもできる。
○同源語:
賢(さか)し、世(よ)、竪監(かがみ・鏡)、送
(おくる)、還(かへる)、吾(わが)、心(こころ)、
【くれ(晩・闇・昏)】
霞
(かすみ)立(たつ) 長(ながき)春日(はるひ)の 晩(くれに)ける、、(万5)
明 (あけ)闇(くれ)の朝霧(あさぎり)隠(がくり)鳴(なき)て去(ゆく)鴈(かり)は言戀(あがこひ)於レ妹 (いもに)告(つげ)こそ(万 2129)
豊
國(とよくに)のきくの長濱(ながはま)去(ゆき)晩(くらし)日(ひ)の昏(くれ)去(ゆけ)ば妹(いもに)をしぞ念(おもふ)(万3219)
晩[miuan] の祖語(上古音)には入りわたり音[h-]があった可能性があり、晩[hmiuan*]の入りわたり音[h-]が発達したものであると考えることもできる。
○同源語:
霞(かすみ・霞霧)、立(たつ)、長(なが)き、
春(はる)、隠(かく)れる、鳴(なく)、去(ゆく・行)、鴈(かり)、言(わが・我)、妹(いも)、國(くに)、濱
(はま)、念(おもふ)、
【くろ(黒・玄)】
若
有(わかかり)し 皮(はだ)も皺(しわみ)ぬ 黒有(くろかり)し 髪(かみ)も白斑(しらけ)ぬ ゆなゆなは 氣(いき)さへ絶(たえ)て、、(万1740)
黒
玉(ぬばたま)の玄髪山(くろかみやま)を朝(あさ)越(こえ)て山下(やました)露(つゆ)に沽(ぬれに)けるかも(万1241)
中国語の喉音[h-][-x-]は日本語にはない音であり、日本語ではカ行であら
われることが多い。また、韻尾の[-n]は[-l]と調音の位置が同じであり、転移しやすい。黒[xək]の韻尾[-k]は江南音では[-t]に合流するので、[-l]に転移することがある。
例:夜[jyak]よる、腹[piuk]はら、色[shiək]いろ、織[tjiək]おる、
○同源語:
若(わか)い、皺(しわ)、黒・玄(くろい)、氣
(いき・息)、絶(たえ)る、山(やま)、越(こえる)、沽(ぬれ・濡)る、
【け(毛)】
吾
(わが)毛(け)等(ら)は 御(み)筆(ふで)はやし 吾(わが)皮(かは)は 御(み)箱(はこの)皮(かは)に、、(万3885)
日本語の毛(け)は入りわたり音[h-]が発達したものであり、毛(モウ)は入りわたり音[h-]が脱落したものである可能性がある。
○同源語:
吾(わが)、等(ら)、御(み)、筆
(ふで)、箱(はこ・筐)、
【けだし(蓋)】
山
主(やまもり)は蓋(けだし)雖レ有
(ありとも)吾妹子(わぎもこ)が将レ結
(ゆひけむ)標(しめ)を人(ひと)が将レ解
(とかめ)やも(万
402)
人
目(ひとめ)太(おほみ)直(ただ)不レ相
(あはず)して蓋(けだし)くも吾(わが)戀(こひ)死(しな)ば誰(たが)名(な)将レ有(ならむ)も(万3105)
「蓋」の古代中国語音は蓋[kat]である。日本語の「けだし」は漢文訓読風のニュア
ンスがあり、「仮に」というような場合に使われる。音義ともに中国語の蓋[kat]に近く、同源であろう。
○同源語:
山(やま)、主(もり・護)、吾妹子(わぎも
こ)、標(しめ)、目(め)、直(ただ)、相(あふ・合)、死(し)ぬ、名(な)、
【けふ(今日・今)】
川
豆(かはづ)鳴(なく)清(きよき)川原(かはら)を今日(けふ)見(み)ては何時(いつ)か越(こえ)來(き)て見(み)つつ偲(しの)ばむ(万1106)
秋 津野(あきづの)に朝(あさ)居(ゐる)雲(くも)の失(うせ)去(ゆけ)ば前(きのふ)も今(けふ)も無(なき)人(ひと)所レ念 (おもほゆ)(万 1406)
た まかぎる昨(きのふの)夕(ゆふべ)見(みし)物(ものを)今(けふの)朝(あしたに)可レ戀 (こふべき)物(ものか)(万 2391)
「今」の祖語(上代中国語音)は今[kiəp*]に近い音であったと思われる。「今」はそれ自体で
今(けふ)という読みがあったと思われるが、今[kiəm]の頭音が脱落して、今(いま)と読まれるように
なったため、「けふ」は「今日」と表記するようになったのではあるまいか。
「今日(けふ)」の「日」の朝鮮語は日(hae)であり、「け+ふ」の「ふ」は日(hae)の連想である可能性もある。
○同源語:
川豆(かはづ・蝦)、鳴(なく)、清(きよき)、
川(かは・河)、原(はら)、見(みる)、越(こえる)、來(くる)、津(つ)、野(の)、居(ゐ)る、雲(くも)、去(ゆく・行)、今(けふ・今日)、
無(な)き、念(おもふ)、夕(ゆふべ・夜)、物(もの)、
【けぶり(煙・烟)】
天
(あめ)の香具山(かぐやま) 騰(のぼり)立(たち) 國見(くにみ)を為(すれ)ば 國原(くにはら)は 煙(けぶり)立(たち)龍(たつ・立)、、(万2)
我
(わが)王(おほきみ)を 烟(けぶり)立(たつ) 春日(はるのひ)暮(くらし)、、
(万3324)
春
日野(かすがの)に煙(けぶり)立(たつ)所レ見
(みゆ)[女
感]*嬬
(をとめ)等(ら)し春野(はるの)のう芽子(はぎ)採(つみ)て煑(に)らしも(万1879)
日本漢字音には同じ声符がカ行とア行であらわれ
るものがある。ア行音は頭音が脱落したものである。
例:國・域、奇・椅、貴・遺、軍・運、乞・乙、
緩・援、景・影、区・欧、甲・鴨 絵(カイ・ ヱ)、懐(カイ・ヱ)、黄(コウ・
オウ)、
○同源語:
天(あめ)、香(か)、山(やま)、騰(のぼる・
登)、立・龍(たつ)、國(くに)、見(みる)、原(はら)、我(わが)、王(おほきみ・君)、春(はる)、野(の)、[女感]*嬬(をとめ・嬬)、等(ら)、芽子(はぎ)、煑
(にる・茹)、
【こ(籠)】
籠
(こ)もよ美籠(みこ)母乳(もち) 布久思(くし・串)もよ 美夫君志(みふくし・串)持(もち) 此(この)岳(をか)に 菜(な)採(つま)す兒
(こ)、、(万
1)
万葉集の第一番目に載せられている歌である。
「籠」の古代中国語音は籠[long]である。「籠」の祖語には入りわたり音があって、
「籠」は籠[hlong*]に近い音であったと想定できる。日本語の籠(こ)
は上代中国語音籠[hlong*]の入り渡り音[h-]が発達したものであろう。
「籠」は「かご」の意味であり、「籠」は籠
(こ、こも、かご、こもる)などと読む。籠(こもる)は韻尾の[-ng]がマ行に転移したものであり、籠(かご)は韻尾の[-ng]がカ行に転移したものである。[-ng]は鼻音であり[-m]と調音の方法が同じである。[-ng]はまた、調音の位置が[-k][-g]と同じであり、カ行に転移しやすい。籠(こ、こ
も、かご、こもる)はいずれも中国語の籠[hlong*]から派生したことばである。唐の時代には籠(ロ
ウ)という発音になっていたので、「籠毛」と「毛」をつけて韻尾の読み方を示したものであろう。
○同源語:
美(み・御)、此(こ)の、岳(をか)、兒
(こ)、
【こ(子・兒)】
秋
芽子(あきはぎ)を 妻(つま)問(とふ)鹿(か)こそ 一子(ひとりご)に 子(こ)持有(もてり)と五十戸(いへ) 鹿兒(かこ)じ物(もの) 吾
(わが)獨子(ひとりご)の 草枕(くさまくら) 客(たび)にし徃(ゆけ)ば、、(万1790)
直 (ただ)獨(ひとり) い渡為(わたらす)兒(こ)は 若草(わかくさ)の 夫(つま)か有(ある)らむ、、(万1742)
子[tziə]の祖語(上古音)は子[xiə*]のような音であった可能性がある。子[xiə*]は摩擦音化して子[tziə]になったと考えられる。漢字には同じ声符をもった
文字がカ行とサ行に読み分けられるのもがある。サ行音はカ行音の口蓋化したものである。
例:嗅(キュウ)・臭(シュウ)、庫(コ)・車
(シャ)、感(カン)・鍼(シン)、喧伝(ケ ン)・宣伝(セン)、など
「兒」と同じ声符をもった漢字に「睨」があり、
睥睨(へいげい)などに使われる。「睨」の古代中国尾音は睨[ngye]である。日母[nj-]と疑母[ng-]とは音が近い。児(こ)は上代中国語の兒[ngiə*]に依拠したものであろう。
○同源語:
芽子(はぎ)、妻(つま・妻女)、鹿(か)、吾
(わが)、物(もの)、徃(ゆく・往)、直(ただ)、渡(わたる)、若(わか)き、草(くさ)、
【こ(蚕・蛺蠱)】
た
らちねの母(はは)が養(かふ)蚕(こ)の眉(まよ)隠(ごもり)いぶせくもあるか異母(いも・妹)に不レ相
(あはず)して(万
2991)
○同源語:
母(はは)、眉(まゆ)、隠(こもる・籠)、異母
(いも・妹)、相(あふ・合)、
【こ(小)】
浪
間従(なみのまゆ)所レ見
(みゆる)小嶋(こじま)の濱(はま)久木(ひさぎ)久(ひさ)しく成(なり)ぬ君(きみ)に不レ相
(あはず)して(万
2753)
真 野(まのの)池(いけ)の小菅(こすげ)を笠(かさ)に不レ縫 (ぬはず)為(して)人(ひと)の遠名(とほな)を可レ立 (たつべき)物(もの)か(万 2772)
古代中国語の「小」は小[siô]である。現代北京語の「小」は小(xiao)であり、中国語の「小」の祖語(上古音)は小[xiô*]であったものと考えられる。現代中国語の(x-)は摩擦音であるが、古代中国語の喉音[x-]は閉鎖音であった。日本語の小(こ)も小[xiô*]から発達したものであろう。
サテム語群というのは[s-]であらわす語群である。サテム語群はインド・イラ
ン語、アルメニア語、アルバニア語、リトアニア語、バルト語、ロシア語、アヴェスト語などである。アヴェスタ語(イラン語系の言語)で「百」をsatemというところからサテム語群と名づけられた。カ行
音がサ行音に変化することは世界の言語でかなり多くみられる現象なのである。
「小」には小(を)という読みもある。小(を) は小[xiô*]の頭音が脱落したものでる。
浪(なみ)、間(ま)、見(みる)、嶋(しま・
洲)、濱(はま)、木(き・枝)、君(きみ)、相(あふ・合)、真(ま)、野(の)、名(な)、立(たつ)、物(もの)、塗(ぬる)、小(を)、船(ふ
ね・盤)、
【こころ(心・情)】
他
辭(ひとごと)を繁(しげみ)言痛(こちたみ)不レ相
有(あはざり)き心(こころ)在(ある)如(ごと)莫(な)思(おもひ)吾(わが)背子(せこ)(万538)
淡 海(あふみ)の海(み)夕浪(ゆふなみ)千鳥(ちどり)汝(なが)鳴(なけ)ば情(こころ)もしのに古(いにしへ)所レ念 (おもほゆ)(万 266)
中国語の喉音[x-][h-]は日本語にはない発音である。そのため、日本語で
は「ここ・ろ」とカ行音を二つ重ねて、日本語の音韻体系になじむように発音した。また、韻尾の[-n]は[-l]と調音の位置が同じであり転移した。
「情」の古代中国語音は情[dzieng]である。「心情」ということばがあるごとく「心」
と「情」は義(意味)が近い。情[dzieng]の上古音は情[hieng*]に近い音であった可能性があり、情[dzieng]は介音[-i-]の影響で摩擦音化したものであると考えることもで
きる。
○同源語:
辭・言(こと)、痛(いた)し、相(あふ・合)、
莫(な)、思・念(おもふ)、吾(わが)、背子(せこ)、海(うみ)、夕(ゆふ・夜)、浪(なみ)、千鳥(ちどり)、汝(な)、鳴(なく)、
【こたへ(答・解答)】
不レ答
(こたへぬ)に勿(な)喚(よび)動(とよめ)そ喚子鳥(よぶこどり)佐保(さほ)の山邊(やまべ)を上(のぼり)下(くだり)に(万1828)
道 守(みちもり)の 将レ問 (とはむ)答(こたへ)を 言(いひ)将レ遣 (やらむ) 為便(すべ)を不レ知 (しらに)と 立(たち)て爪(つま)衝(づく)(万543)
○同源語:
子(こ)、鳥(とり)、山(やま)、邊(へ)、上
(のぼる・登)、守(もり・護)、知(し)る、立(たつ)、爪(つめ)、衝(つく)
【こと(琴)】
琴
(こと)取(とれ)ば嘆(なげき)先立(さきだつ)蓋(けだしく)も琴(こと)の下樋(したび)に嬬(つま・妻嬬)や匿(こも・籠)れる(万1129)
○同源語:
取(とる)、歎(なげ)く、立(たつ)、蓋(けだ
し)、嬬(つま・妻嬬)、匿(こも・籠)る、
【こと(言・事・辞)】
吾
(われ)耳(のみ)ぞ君(きみ)には戀(こふ)る吾(わが)背子(せこ)が戀(こふと)云(いふ)事(こと)は言(こと)の名具左(なぐさ)ぞ(万656)
松 影(まつかげ)の浅茅(あさぢ)が上(うへ)の白雪(しらゆき)を不レ令レ消 (けたずて)将レ置 (おかむ)言者(ことば)かも奈吉(なき・無)(万1654)
葦 原(あしはらの) 水穂(みづほの)國(くに)は 神(かむ)ながら 事擧(ことあげ・言)不レ為 (せぬ)國(くに) 雖レ然 (しかれども) 辞擧(ことあげ・言)ぞ吾(わが)為(する) 言(こと)幸(さきく) 真(ま)福(さきく)座(ませ)と つつが無(なく) 福(さき く)座(いまさ)ば 荒礒(ありそ)浪(なみ) 有(ありて)も見(みむ)と 百重(ももへ)波(なみ) 千重(ちへ)浪(なみ)に敷(しき) 言上(こ とあげ)為(す)吾(われは) 言上(ことあげ)為(す)吾(われは)(万3253)
「ことば」の「こと」も「言」である。また、 「かたる」も言[ngiat*]の動詞化したことばである。
○同源語:
吾(われ)、君(きみ)、背子(せこ)、影(か
げ)、置(おく)、奈吉(なき・無)、穂(ほ)、神(かみ)、事・辞(こと・言)、真(ま)、浪・波(なみ)、見(みる)、千(ち)、
【こま(駒)】
青
駒(あをこま)の足掻(あがき)を速(はやみ)雲居(くもゐに)そ妹(いも)が當(あたり)を過(すぎ)て来(きに)ける(万136)
乞 (いで)吾(わが)駒(こま)早(はやく)去(ゆき)こそ亦打(まつち)山(やま)将レ待 (まつらむ)妹(いも)を去(ゆき)て速(はや)見(み)む(万3154)
宮田一郎編著の『上海語常用同音字典』(光生
社)によると、現代上海語音では「馬」には入りわたり音があり、「馬」は馬(hma)と聞こえるという。「馬」の古代中国語音は馬[mea]であるが、「馬」の祖語(上古音)には入りわたり
音があって馬[hmea*]に近い音であったと思われる。日本語の馬(こま)
の「こ」は江南音の馬(hma)あるいは中国語上古音の馬[hmea*]の入りわたり音[h-]をカ行であらわしたものである可能性が高い。
馬(うま)馬[hmea*]の入りわたり音[h-]が失われたものであり、駒(こま)は馬[hmea*]の入りわたり音[h-]が唐代には失われて「馬」は「こま」とは読めなく
なってしまったため、「句」を添加して「句+馬」としたものであろう。
上代の中国語音に入りわたり音があったことは 「海」についてもいえる。「海」の古代中国語音は海[xuə]である。同じ声符をもた「毎」は毎[muə]である。海の祖語(上古音)は海[hmuə*]のような音であり、海(カイ)は入りわたり音[h-]の痕跡を留めたものであり、毎(マイ)は入りわた り音[h-]の失われたものである。日本語の海(うみ)は海[muə]の前に母音「う」が添加されたものである。
○同源語:
雲(くも)、居(ゐる)、妹(いも)、當(あた
り)、過(すぎ)る、來(くる)、吾(わが)、去(ゆく・行)、打(うつ)、山(やま)、見(みる)、
【こま(高麗)】
高
麗(こま)錦(にしき)紐(ひも)の結(むすび)も解(とき)不レ放
(さけず)齊(いはひ)て待(まて)ど驗(しるし)無(なき)かも(万2975)
「高麗」の古代中国語音は高麗[kô-lyai]である。古代日本語ではラ行音が語頭に来ることが
なかったので、マ行に転移したものと思われる。[l-]と[m-]は調音の位置が近く転移しやすい。
例:陸(リク)・睦(ムツ)、來(ライ)・麥(バ
ク)、令(レイ)・命(メイ)、漏(ロウ
もる)、戻(レイ・もどる)、乱(ラン・みだ
る)、両(リョウ・もろ)、緑(リョク
みどり)、嶺(レイ・みね)、
一方、古代中国語の[m-]は、時代を更に遡ると、入りわたり音[h-]を持っていたと考えらる。麗[hmyai*]は一字だけで麗(こま)と読めた時代があったので
はなかろうか。「高麗」の「高」は入りわたり音[h-]が失われてから後の添加である可能性がある。
例:海[xuə]・毎[muə]、買[hme*](バイ・かふ)、米[hmei*](ベイ・こめ)、門[hmuən*]
(モン・か
ど)、毛[hmô](モウ・け)、馬[hmea*](バ・こま)、黙[hmək*]・黒[xək]、
○同源語:
紐(ひも・絆・繙)、無(な)き、
【こめ(米)】
巻
向(まきむく)の檜原(ひばら)に立(たて)る春霞(はるがすみ)おほにし思(おもは)ば名積(なづみ)米(こめ・来)やも(万1813)
万葉集の歌の「米」は訓借の助動詞で「なづみ来
めやも」という意味である。米(こめ)は歌の題になりにくかったのか、万葉集には米(こめ)を読んだ歌はない。しかし、この歌から万葉集の時代に「米」と
いう字を米(マイ)ではなく米(こめ)と読んでいたことがわかる。
「米」の古代中国語音は米[myei]である。「米」の祖語には語頭に入り渡り音[h-]があって、「米」は米[hmyei*]だったと考えられる。日本語の「こめ」は祖語(上
古音)の米[hmyei*]の痕跡を留めたことばであり、米(ベイ・マイ)は
入りわたり音の脱落したものである。日本書紀歌謡には次のような歌がある。これは音表記であるが、「渠梅」は「米」である。
○同源語:
向(むく)、檜(ひ)、原(はら)、
立(たつ)、春(はる)、霞(かすみ・霞霧)、思(おもふ・念)、名(な)、米(こめ)、來(くる)
【こもる(隠)】
た
らちねの母(はは)が養(かふ)蚕(こ)の眉(まよ)隠(こもり)隠在(こもれる)妹(いも)を見(みむ)依(よしも)がも(万2495)
色 (いろに)出(いで)て戀(こひ)ば人(ひと)見(み)て應レ知 (しりぬべし)情(こころ)の中(なか)の隠妻(こもりづま)はも(万2566)
例:緩[huan](カン)・援[hiuan](エン)、禾[hua](カ)・和[huai](ワ)、曷[hat](カツ)・
謁[iat](エツ)、
日本漢字音でも同じ声符をカ行とア行(あるいは
ワ行)に読み分けるものがある。
例:黄[huang](オウ・コウ)、絵・會[huat](ヱ・カイ)、回[huəi](ヱ・カイ)、壊[hoəi](ヱ・
カイ)、
また、音と訓でカ行とア行(またはヤ行、ワ行)
に読み分けるものがある。
例:雲[hiuən](ウン・くも)、熊[hiuəm](ユウ・くま)、越[hiuat](エツ・こえる)、恨[hən]
(コン・うらむ)、行[heang](コウ・ゆく)、合[həp](ゴウ・あふ)、
このことは隠[iən]の祖語(上古音)に隠[hiən*]に近い音があったことを示唆している。日本語の 「こもる」は中国語の隠[hiən*]と同源であろう。
「隠」は「かくる」にも使われている。喉音[h-]は濁音であり、日本語にはない音なので清音を重ね たものであろう。
母(はは)、養蚕(かふこ・蛺蠱)、眉(まよ)、
妹(いも)、見(みる)、色(いろ)、出(いづ)、知(し)る、情(こころ・心)、中(なか)、妻(つま・妻女)、刺(さ)す、照(てる)、夜(よる)、
渡(わたる)、
【こやす(臥)】
お
とづれの狂言(たはごと)とかも高山(たかやま)の石穂(いほ)の上(うへ)に君(きみ)が臥有(こやせる)(万421)
「臥」には「ふす」という読みもある。「ふす」
は臥[ngai]の頭音[ng-]がハ行に転移したものである。疑母[ng-]は調音の位置が喉音[h-]に近く、転移することがある。
言(こと)、山(やま)、穂(ほ)、君(きみ)、
奈胡也(なごや・柔)、妹(いも)、宿(ねる・寐)、
【こゆ(越)】
川
豆(かはづ)鳴(なく)清(きよき)川原(かはら)を今日(けふ)見(み)ては何時(いつ)か越(こえ)來(き)て見(み)つつ偲(しの)ばむ(万1106)
泊 瀬川(はつせかは)流(ながるる)水尾(みを)の湍(せ)を早(はやみ)井提(いで)越(こす)浪(なみ)の音(おと)の清(きよけ)く(万1108)
例:雲[hiuən](くも・ウン)、熊[hiuəm](くま・ユウ)、羽[hiuə](は・ウ)、
また、同じ声符をもった漢字でも喉音[h-]が脱落したものと発音されるものがみられる。
例:軍[hiuən](グン)・運[hiuən](ウン)、國[kuək](コク)・域[hiuək](イキ)、完[huan](カン)・
院[hiuan](イン)など
○同源語:
鳴(なく)、清(きよき)、川(かは・河)、原
(はら)、今日(けふ)、來(くる)、見(みる)、流(ながるる)、尾(を)、浪(なみ)、音(おと)、
【これ(此・是)】
五
更(あかとき)の目不酔草(めさましぐさ)と此(これ)をだに見(み)つつ座(いまし)て吾(われ)を偲(しのば)せ(万3061)
此 (これ)や是(こ)の倭(やまと)にしては我(わが)戀(こふ)る木路(きぢ)に有(ありと)云(いふ)名(な)に負(おふ)勢能山(せのやま)(万35)
二番目の歌の「名に負ふ勢(せ)の山」というの
は「有名な背の山」で山の名前に男性に対する親愛の呼称である兄(せ)をかけたものである。
○同源語:
五更(あかとき・暁時)、目(め)、不酔(さめ
る・醒)、草(くさ)、見(みる)、吾(われ)、我(わが)、木(き・枝)、名(な)、負(おふ)、勢(せ・背)、山(やま)、
【こゑ(聲)】
朝
霞(あさがすみ)鹿火屋(かひや)が下(した)に鳴(なく)蝦(かはづ)聲(こゑ)だに聞(きか)ば吾(われ)将レ戀
(こひめ)やも(万
2265)
氏 河(うぢかは)は与杼(よど)湍(せ)無(なから)し阿自呂(あじろ)人(ひと)舟(ふね)召(よばふ)音(こゑ)をちこち所レ聞 (きこゆ)(万 1135)
董同龢は『上古音韻表稿』のなかで「聲」の上古
音を聲[xieng]と再構している。
○同源語:
霞(かすみ・霞霧)、鹿(か)、火(ひ)、屋
(や)、鳴(なく)、蝦(かはづ)、吾(われ)、氏(うぢ)、川(かは・河)、与杼(よど・淀)、無(な)き、舟(ふ
ね・盤)、音(こゑ・聲)
【か行のまとめ】
ここで古代中国語と日本語のカ行の関係を整理して みると次のようになる。
1.古代中国語の後口蓋音[k-][kh-][g-][ng-]に依拠したもの。
鏡[kyang]かがみ、闕・欠[khiuat]かく、影[(k)yang*]かげ、冠[kuan]挿[tsheap]かざし、樫[kyen]かし、肩[kyan]かた、堅[kyen]かたい、葛[kat]かづら、堅魚[kyen gnia]かつを、金[kiəm]かね、蛺[kyap]蠱[ka]かひこ、、龜[kiuə]かめ、鴨[(k)eap*]かも、獦[kat]かり、干[kan]かれる、絹[kyuan]きぬ、巾[kien]きぬ、公[kong]きみ、肝[kan]きも、葛[kat]くづ・かずら、奇[kiai]くし、國[kuək]くに、頸[kieng]くび、軍[kiuən]くめ、車[kia]輪[liuən]くるま、蓋[kat]けだし、今日[kiəm/kiəp*]けふ、煙[yen/(k)yen*]けぶり、解[ke]答[təp]こたへ、駒[kio]こま、高麗[kô lyai]こま、枯[kha]かる、口[kho]嘴[tziue]くち、枯[kha]かれる、苦[kha]くるし、
木(枝[tjie/gie*])き、窮[giuəm]・極[giək]きはむ、君[giuən]きみ、,狂[giuang]くるふ、琴[giəm]こと、
言[ngian]かたる、顔[ngean]貌[mau]かほ、瓦[nguai]瓶[pieng]かめ、鴉[(ng)ea*]からす、雁・鴈[ngean]かり、苅[ngiat]かる、牙[ngea]き・は、象(牙[ngea](き)・牛(so)<朝鮮語>)きさ、兒[njie/ngye*]こ、言[ngian]こと、臥[ngai]こやす、
2.古代中国語の喉音[x-][h-]が日本語ではカ行であらわれるもの。
香[xiang]か、漢[xan]から、靴[xuai]沓[dəp]くつ、朽[xiu]くつ、悔[xuə]くゆ、昏[xuən]くれ、黒[xək]くろ、限[hean]かぎる、懸[hiuen]かける、華[hoa]飾[sjiək]かざる、霞[hea]霧[miu]かすみ、兼[hyam]かぬ、河[hai]かは、蝦[hea]かはづ、峡[heap]かひ、蛤[həp]かひ、蛺蠱[heap-ka]かひこ、還[hoan]かへる、韓[han]から、涸[hak]かる、狐[hua]きつね、黄[huang]金[kiəm]くがね、莖[heng]くき、串[hoan]くし、熊[hiuəm]くま、雲[hiuən]くも、玄[hyen]くろ、越[(h)iuat*]こゆ、
3.中国語上古音が喉音[x-][h-]であり、日本語の訓ではカ行であらわれ、音では摩 擦音化してサ行であらわれるもの。
神[djien/khuan*](シン・かみ)、辛[sien/xien*](シン・からし)、樹[zjio/hio*](ジュ・き)、
消 [siô/xio*](ショウ・きゆ)、清[tsieng/xieng*](セイ・きよし)、浄[dzieng/hieng*](ジョウ・
きよし)、鑚[tzuan/xuan*](サン・きる)、斬[tzheam/heam*](ザン・きる)、草[tsu/xu*](ソウ・ くさ)、倉[tsang/xang*](ソウ・くら)、蔵[dzang/hang*](ゾウ・くら)、子[tziə/xiə*](シ・ こ)、小[siô/xiô*](ショウ・こ)、心[siəm/xiəm*](シン・こころ)、此[tsie/xie*](シ・これ)、
是[zjie/hie*](ゼ・これ)、聲[thjieng/hjieng*](セイ・こゑ)、
4.上古中国語の[m-]の前の入り渡り音[h-]の痕跡を留めたもの。
隠[(h)iəm*]かくす・かくれる、門[(h)muən*]かど、毛[(h)mô*]け、駒[(h)mea*]こま、米[(h)myei*]
こめ、
5.上古中国語の[l-]の前の入り渡り音[h-]の痕跡を留めたもの。
鎌[(h)liam*]かま、猟[(h)liap*]かり、履[(h)liei*]くつ、栗[(h)liet*]くり、來[(h)lə*]くる、輪[(h)liuən*]くるま、梳[(h)liu*]けづる、籠[(h)long*]こ・こもる、駒(馬[(h)ma*])こま、
*は再構した祖語の上古音をあらわす。
鏡[kyang](かがみ)、限[hean](かぎる)、懸[hiuen](かける)、などはカ行音が繰り返されている。中 国語と日本語では音韻構造が違うので、中国語で一音節のことばが日本語でも一音節になるというわけではない。英語の場合でもstrike、streetなどは英語では一音節だが、日本語では「ストライ ク」「ストリート」のように五音節になる場合もある。
ことばは声として発音された瞬間に消えてしま う。古代の中国語や日本語がどうのように発音されていたかを知る手がかりは漢字の音を復元することによってしかできない。復元は仮説をともなうから、かな り確実に復元できるものと、検証のむずかしいものとがでてくる。音韻変化には法則性があるから、いくつかの例をあげて法則性を探しだすことが必要である。 法則性が立証できれば仮説の蓋然性は高まる。
◎ さ
行
【さか(尺)】
玉
(たま)相(あは)ば 君(きみ)來(き)ますやと 吾(わが)嗟(なげく) 八尺(やさか)の嗟(なげき)、、(万3276)
朝 霧(あさぎり)の 思(おもひ)惑(まどひ)て 杖(つゑ)不レ足 (たらず) 八尺(やさか)の嘆(なげき) 嘆(なげけ)ども、、(万3344)
声符「尺」の読み方は択(タク)、尺(シャ
ク)、訳(ヤク)、駅(エキ)などがある。択(タク)が古く、尺(シャク)は[-i-]介音の影響で後に発達した音である。
「尺」の朝鮮漢字音は尺(sak)で直音である。古代日本語の音韻構造は朝鮮語に近
かったようである。
○同源語:
相(あふ・合)、君(きみ)、來(くる)、吾(わ
が)、嗟・嘆(なげく)、思(おもふ・念)、杖(つゑ)、
【さか(逆)】
是
川(うぢかはの)水阿和(みなあわ)逆(さか)纏(まき)行(ゆく)水(みずの)事(こと)不レ反
(かへらずぞ)思(おもひ)始(そめ)たる(万2430)
保 里江(ほりえ)より美乎(みを・澪)佐香能保流(さかのぼる)梶(かぢの)音(おと)の麻(ま・間)奈久(なく)そ奈良(なら)は古井(こひ・戀)しかり ける(万 4461)
「逆」の古代中国語音は逆[ngyak]であると考えられている。日本漢字音には「逆立
ち」などのように逆(さか)という読み方もある。
「逆」と同じ声符を持つ漢字に、朔(サク)、
遡・溯(ソ)がある。逆[ngyak]の頭音[ng-]は喉音[x-]に調音の位置が近く、逆[xyak*]に近い音価をもっていたものと思われる。中国語の
喉音[x-]の上古音は破裂音でカ行であらわれるが、現代の北
京音では摩擦音でサ行であらわれる。
○同源語:
川(かは・河)、行(ゆく)、反(かへる・還)、
思(おもふ・念)、佐香(さか・遡)、能保流(のぼる・登)、音(おと)、麻(ま・間)、奈久(なく・無)、
【さかし(賢)】
古
(いにしへ)の七(ななの)賢(さかしき)人等(ひとたち)も欲(ほり)せし物(もの)は酒(さけ)にし有(ある)らし(万340)
賢 (さかしみ)と物(もの)言(いふ)よりは酒(さけ)飲(のみ)て酔(ゑひ)哭(なき)するし益(まさり)たるらし(万341)
「賢」の古代中国語音は賢[hyen]である。日本漢字音は賢(ケン・かしこい・さか
し)で、音はカ行だが、訓ではカ行とサ行にあらわれる。漢字には同じ声符をカ行とサ行に読みわけるものがいくつかある。サ行音はカ行音が介音[-i-]の発達によって摩擦音化したものであろう。
例:賢[hyen](ケン)・腎[zjiən](ジン)、宦[huan](カン)・臣[sjien](シン)、感[həm](カン)・
鍼[tjiəm](シン)、活[huat](カツ)・舌[djiat](ゼツ)、狭[heap](キョウ)・陝[thjiam](セン)、 喧[xiuan](ケン)・宣[siuan](セン)、逆[ngyak](ギャク)・朔[sak](サク)、牙[ngea](ガ)・ 邪[zya](ジャ)、言[ngian](ゲン)・信[sjien](シン)、勘[khəm](カン)・甚[zjiəm](ジン)、
嗅[thjiuk](キュウ)・臭[thjiu](シュウ)、
日本語の賢(さかし)は臣[sjien](シン)のサ行音の要素と賢[hyen](ケン)のカ行音の要素を重複させたものではある
まいか。
音韻変化の法則の一般論としてはカ行音(喉音ま
たは後口蓋音)からのサ行音への転移とサ行音からカ行音への転移が同時に起こることはない。むしろ、カ行音からサ行音への転移([h-][k-]などの摩擦音化)が起これば、それによって押し出
されたサ行音がタ行音など前口蓋音に転移するのが一般的である。
漢字音に訓がカ行で音がサ行のものと、訓がサ行
で音がカ行のものがあるということは、中国語の音韻史に二つの逆の流れがあったということであろうか。それとも長い中国語音韻史のなかで、こと二つの流れ
は別の時代に、別々の地域でおこったものだろうか。
インド・ヨーロッパ語族でも「百」をラテン語の ようにとカ行(またはハ行)で発音するcentum語群と、サ行で発音するsatem語群がある。この場合は地域による違いが明らかで ある。
○同源語:
物(もの)、酒(さけ)、飲(のむ・呑)、哭(な
く・泣)、
【さかり・さかゆ(盛・榮)】
吾
(わが)瀬子(せこ)に吾(わが)戀(こふ)らくは奥山(おくやま)の馬酔木(あしびの)花(はな)の今(いま)盛(さかり)なり(万1903)
酒
(さか)見附(みづき・宴) 榮(さかゆ)る今日(けふ)の あやに貴(たふと)さ
(万4254)
開
木代(やましろの)來背(くぜの)社(やしろの)草(くさ)勿(な)手折(たをりそ)己(わが)時(ときと)立(たち)雖レ榮(さかゆとも)草(くさ)勿
(な)手折(たをりそ)
(万
1286)
日本語の「さかり」には盛[zjieng]が使われている。古代中国語語の「盛」は盛[zjieng]、であり、盛(さかり)は盛[zjieng]の韻尾[-ng]がカ行であらわれたものである。
一方、「榮(エイ)」は榮[hiueng]の語頭の喉音[h-]が介音[-i-]の影響で摩擦音化したものであろう。 日本漢字音 の盛(セイ)と榮(エイ)はかなり違 うが、古代中国語音では音価は近い。日本語の「さかり」は中国語の盛[zjieng]・榮[hiueng]と同系のことばであろう。
○同源語:
吾(わが)、瀬子(せこ・背子)、奥(おく)、山
(やま)、花(はな)、今(いま)、酒(さけ)、今日(けふ)、來(くる)、手(て)、折(をる)、己(わが・我)、時(とき)、草(くさ)、立(た
つ)、
【さき(埼・前・先)】
三
埼(みさき)廻(み)の荒礒(ありそ)に縁(よする)五百重(いほへ)浪(なみ)立(たちて)も居(ゐて)も我(わが)念(おもへ)る吉美(きみ・君)(万568)
礒 (いその)前(さき)榜(こぎ)手廻(たみ)行(ゆけ)ば近江(あふみ)の海(うみ)八十(やそ)の湊(みなと)に鵠(たづ)さはに鳴(なく)(万273)
辱 (はぢ)を忍(しのび)辱(はぢ)を黙(もだして)無レ事 (こともなく)物(もの)不レ言 (いはぬ)先(さき)に我(われ)は将レ依 (よりなむ)(万 3795)
「埼」「前」「先」の古代中国語はそれぞれ埼[kiai]、前[tzian]、先[syen]である。前[tzian]、と先[syen]は音義ともに「さき」に近い。韻尾の[-n]が[-k]に転移するのはやや変則だが、王力の『同源字典』
によると、間[kean]・隙[khyak]、顔[ngean]・額[ngeak]、暮[mak]・晩[miuan]、近[kiən]・迫[peak]などは音義ともに近く同源だという。
埼[kiai]を埼(さき)と読むことについては少し説明が必要 である。同様の例は賢[hyen](さかし)、栄[hiueng](さかゆ)、幸[heang](さき・さち)、などにもみられる。中国語の喉音[h-]は上代には破裂音であったものが唐代以降に摩擦音 化した。埼(さき)も摩擦音化の痕跡を留めたものであろう。
地名の埼玉(さいたま)は古代には埼玉(さきた ま)であった。しかし「埼」は埼(キ)は埼(さき))とは読めなくなってしまった。そこで埼玉県は「埼玉県」と書くが「埼玉市」は「さいたま市」とひらが なで書かれるようになった。
○同源語:
三(み)、埼(さき)、廻(みる)、縁(よする・
寄)、浪(なみ)、立(たつ)、居(ゐ)る、我(わが)、念(おもふ)、吉美(きみ・君)、手(て)、行(ゆく)、海(うみ)、鳴(なく)、黙(もだ)
す、事(こと・言)、無(な)く、物(もの)、依(よる)、
【さき・さち(幸・福)】
言
(こと)幸(さきく) 真(ま)福(さきく)座(ませ)と 恙(つつが)無(なく) 福(さきく)座(いまさ)ば 荒礒(ありそ)浪(なみ) 有(あり
て)も見(みむ)と、、(万
3253)
「福」を「さき」と読ませているのは訓借であ
る。「福」は「幸福」であり、「幸」と「福」は同義である。
○同源語:
言(こと)、真(ま)、無(な)く、荒(あら
き)、浪(なみ)、見(みる)、
【さぎ(鷺・鵲)】
池
神(いけがみの)力士(りきし)儛(まひ)かも白鷺(しらさぎ)の桙(ほこ)啄(くひ)持(もち)て飛(とび)渡(わたる)らむ(万3831)
白 鳥(しらとり)の鷺坂(さぎさか)山(やま)の松影(まつかげに)宿(やどり)て徃(ゆか)な夜(よ)も深(ふけ)徃(ゆく)を(万1687)
動物や植物の名前は必ずしも現代の生物学的分類 の一致しないことがある。例えば、鮎は「なまず」であり、羊は「やぎ」であり、「こほろぎ」は現代の「きりぎりす」である。「朝顔」は現代の「桔梗」であ り、「あやめぐさ」は「しょうぶ」であり、「うのはな」は「うつぎ」であるという。
○同源語:
神(かみ)、力士(リキシ)、儛(まひ)、桙(ほ
こ)、飛(とぶ)、渡(わたる)、鳥(とり)、山(やま)、影(かげ)、徃(ゆく・往)、夜(よる)、
【さく(咲)】
青
丹(あをに)吉(よし)寧樂(なら)の京師(みやこ)は咲(さく)花(はな)の薫(にほふが)如(ごとく)今(いま)盛(さかり)なり(万328)
日本漢字音でも猫[miô]ねこ、暁[ngiô]あけ・あかつき、焼[ngyô]やく、焦[tziô]こげる、など宵韻[ô]の漢字の韻尾がカ行であらわされている。日本語の
「さく」は中国語の咲[syô]と同源であろう。
○同源語:
京師(みやこ・京)、花(はな)、今(いま)、盛
(さかり)、
【さけ(酒)】
中
々(なかなか)に人(ひと)と不レ有
(あらず)は酒壺(さかつぼ)に成(なり)にてしかも酒(さけ)に染(しみ)なむ(万343)
酒 (さけの)名(な)を聖(ひじり)と負(おはせ)し古昔(いにしへの)大(おほき)聖(ひじり)の言(こと)の宣(よろし)さ(万339)
「酒」の古代中国語は酒[tziu]である。「酒」の祖語(上古音)は酒[tziuk*]に近かったのではなかろうか。
白川静の『字通』によると「酒[tziu]は就[dziuk]、造[dzuk]と旁紐・対転の関係の字ではあるが、声義において
通ずるところはない」という。王力の『同源字典』によると柔[njiu]と弱[njiôk]、臭[thjiu]と嗅[thjiuk]、捜[shiu]と索[sheak]、報[pu]と復[biuk]は音義ともに近く同源だという。つまり、韻尾の[-k]は脱落することがあるということである。日本語の
「さけ」は中国語の酒[tziuk*]と同源であろう。
○同源語:
中(なか)、染(しむ)、名(な)、負(おふ)、
言(こと)、
【さす(紗・刺・挿・指)】
渡
津海(わたつみ)の豐旗雲(とよはたぐも)に伊理比(いりひ)紗(さ)し今夜(こよひ)の月夜(つくよ)清明(きよらけく)こそ(万15)
秋 芽子(あきはぎ)は盛(さかり)過(すぐる)をいたづらに頭刺(かざし)に不レ挿 (ささず)還去(かへりな)むとや(万1559)
葛 城(かづらぎ)の高間(たかまの)草野(かやの)早(はや)知(し)りて標(しめ)指(ささ)ましを今(いまぞ)悔(くや)しき(万1337)
中国語には動詞の活用はないが、日本語の動詞は
活用するので「-す」を添加して日本語として活用するようになった。また、古代日本語には紗(シャ)、挿(ソウ)などの音節はなかったので紗(さ)す、挿
(さ)す、となった。
○同源語:
津(つ)、海(うみ)、旗(はた・幡)、雲(く
も)、伊理(いり・入)、紗(さし・射)、今夜(こよひ)、夜(よ)、清(きよき)、芽子(はぎ)、盛(さか)り、過(すぐ)る、頭刺(かざし・冠刺)、
挿(さす)、還去(かへる)、葛(かづら)、間(ま)、草(くさ)、野(の)、知(し)る、標(しめ)、指(さす)、今(いま)、悔(くや)し、
【さつや(矢)】
大
夫(ますらを)が得物矢(さつや)手(た)挿(はさみ)立(たち)向(むかひ)射(いる)圓方(まとかた)は見(みる)に清潔(さやけ)し(万61)
あ しひきの山(やまに)も野(のに)も御(み)獦人(かりびと)得物矢(さつや)手(た)挟(はさみ)さわきて有(あり)所レ見 (みゆ)(万 927)
○同源語:
手(て)、挿・挟(はさむ)、立(たつ)、向(む
かふ)、射(いる)、見(みる)、清潔(さやか・清)、山(やま)、野(の)、御(み)、獦(かり)、
【さはる・さやる(障)】
湊
(みなと)入(いり)の葦別(あしわけ)小舟(をぶね)障(さはり)多(おほ)み吾(わが)念(おもふ)公(きみ)に不レ相
(あはぬ)頃者(ころ)かも(万
2745)
他 言(ひとごと)は真(まこと)言痛(こちたく)成(なりぬ)ともそこに将レ障 (さはらむ)吾(われ)に不レ有 (あらな)くに(万 2886)
毛
々可(ももか・百日)しも由加奴(ゆかぬ)麻都良遅(まつらぢ・松浦)家布(けふ)由伎(ゆき)て阿須(あす)は吉奈武(きなむ・來)を奈尓可(なにか)
佐夜礼留(さやれる・障)
(万
870)
入(いり)、小(を)、舟(ふね・盤)、吾(わ
が)、念(おもふ)、公(きみ)、相(あふ・合)、言痛(こちた)き、越(こえる)、情(こころ・心)、代(よ・世)、
可多利(かたり・言)、都具(つぐ・續)、名(な)、多都(たつ・立)、毛々可(ももか・百日)、由伎(ゆき・行)、家布(けふ・今日)、吉(來・き)、
【さやか(清)】
小
竹(ささ)の葉(は)は三山(みやま)も清(さや)に乱(みだる)とも吾(われ)は妹(いも)思(おもふ)別(わかれ)來(きぬ)れば(万133)
吾 (わが)背子(せこ)が挿頭(かざし)の芽子(はぎ)に置(おく)露(つゆ)を清(さやかに)見(み)よと月(つき)は照(てる)らし(万2225)
「清」は清(きよし)という読みもある。清(き
よし)は上古音の清[xieng*]を継承したことばであり、清[tsieng]は清[xieng*]が摩擦音化したものである。清(きよし)のほうが
清(さやか)あるいは清(すがし)より古い。
○同源語:
葉(は)、三(み・御)、山(やま)、乱(みだ
る)、吾(われ)、妹(いも)、思(おもふ・念)、來(くる)、背子(せこ)、挿頭(かざし・冠挿)、芽子(はぎ)、置(おく)、見(みる)、照(て
る)、
【さる(猿)】
あ
な醜(みにく)賢(さかし)らを為(す)と酒(さけ)不レ飲
(のまぬ)人(ひと)をよく見(みれ)ば猿(さる)にかも似(にる)(万344)
頭音[h-]がサ行であらわれる例としては、園[hiuan](エン・その)、狭[heap](キョウ・せまい)、寒[han](カン・さむい)、幸[hiəng](コウ・さき・さち)、などをあげることができ
る。喉音[h-]が介音などの影響で摩擦音化したものである。干支
では「さる」には申[sjien]である。申[sjien]も音義ともに「さる」に近い。
○同源語:
賢(さか)し、酒(さけ)、飲(のむ・呑)、見
(みる)、似(に)る、
【しか・か(鹿)】
暮
(ゆふ)去(され)ば小倉(をぐら)の山(やま)に鳴(なく)鹿(しか)は今夜(こよひ)は不レ鳴
(なかず)寐宿(いねに)けらしも(万1511)
頃 者(このごろ)の朝開(あさけ)に聞(きけ)ばあしひきの山(やま)呼(よび)令レ響 (とよめ)狭尾壮鹿(さをしか)鳴哭(なくも)(万1603)
山 妣姑(やまびこ)の相(あひ)響(とよむ)まで妻戀(つまごひ)に鹿(か)鳴(なく)山邊(やまべ)に獨(ひとり)耳(のみ)して(万1602)
「鹿」の祖語(上古音)には入りわたり音[h-]があり鹿[hlok*]の[h-]が日本語の「か」になったと考えることができる。
朝鮮語では「鹿」のことをsa seumという。「しか」の「し」は朝鮮語の鹿sa seumと関係のあることばである可能性もある。
○同源語:
暮(ゆふ・夜)、小(を)、倉(くら)、山(や
ま)、鳴(なく)、今夜(こよひ)、寐宿(いぬ)、相(あふ・合)、妻(つま・妻女)、邊(へ)、耳(みみ・のみ)、
この歌は鹿狩りに行って、打たれる鹿の立場に たって詠んだという珍しい歌である。万葉集の時代には、鹿の角は笠の飾りにして、耳は墨壺にし、目は鏡となし、爪は弓の弦をはる時の留め具として使い、毛 は筆に仕立て、皮は箱に張り、宍(肉)は鱠(なます)の材料にし、肝(きも)も鱠(なます)にし、胘(胃)は塩辛にする、とある。鹿の肉は狩猟時代から日 本人の大切な食糧だった。
○同源語;
居(ゐる)、時(とき)、來(くる)、立(た
つ)、嘆(なげく)、吾(われ)、死(しぬ)、王(おほきみ・君)、御(み)、耳(みみ)、目(め)、真墨(ますみ・澄)、鏡(かがみ)、爪(つめ・
爪)、弓(ゆみ)、毛(け)、筆(ふで)、箱(はこ・筐)、伎毛(きも・肝)、塩(しほ・潮)、身(み)、花(はな)、佐久(さく・咲)、
【しし(鹿猪)】
朝
(あさ)獦(かり)に 鹿猪(しし)踐(ふみ)起(おこし) 暮(ゆふ)獦(かり)に 鶉雉(とり)履(ふみ)立(たて)、、(万478)
朝 (あさ)獦(かり)に 十六(しし)履(ふみ)起(おこ)し 夕(ゆふ)狩(かり)に十里(とり)蹋(ふみ)立(たて)、、(万926)
戯書とはいっても戯れに書いたものではない。例
えば、有名は広開土王碑には「國岡上廣開土境平安好太王二九登祚號永樂太王」とあり、広開土王は「二九」つまり2x9=18、つまり「十八歳で王位についた」とあり、正式の
碑文にも用いられている書記法なのである。
「猪」の古代中国語音は猪[tjio]である。古代日本語には猪(チョ)という音節はな
かったので、猪(し)として受け入れられたのであろう。日本語の「しし」は「鹿(しか)+猪(し)」である可能性がある。
朝鮮語では「鹿」のことを鹿(sa seum)という。これも、日本語の「しし」と同系のことば であろう。
○同源語:
獦・狩(かり)、起(おこ)す、暮・夕(ゆふ)、
鶉雉・十里(とり・鳥)、立(たつ)、
【した(舌)】
百
年(ももとせ)に老(おい)舌(した)出(いで)てよよむとも吾(われ)は不レ猒
(いと)はじ戀(こひ)は益(ます)とも(万764)
○同源語:
出(いで)、吾(われ)、猒(いと)ふ、
【しづか(静)】
静
(しづけく)も岸(きしに)は波(なみ)は縁(よせ)けるか此(この)屋(いへ)通(とほし)聞(きき)つつ居(をれ)ば(万1237)
暁 (あかとき)と夜烏(よがらす)雖レ鳴 (なけど)此(この)山上(をか)の木末(こぬれ)の上(うへ)は未(いまだ)静(しづけ)し(万1263)
「幽
宮(かくれみや)を淡路の洲(くに)に構(つく)りて寂然(しづか)に長く隠れましき。」
(神代紀上)
○同源語:
静(しづか・静寂)、波(なみ・浪)、縁(よせ・
寄)る、此(こ)の、屋(いへ・家)、通(とはる)、居(を)る、暁(あかとき・暁時)、夜(よる)、烏(からす・隹)、鳴(なく)、山上(をか・岳)、
木(き・枝)、未(いまだ)、
【しづむ(沈)】
難
波(なには)方(がた)塩(しほ)干(ひ)勿(な)有(あり)そね沈(しづみに)し妹(いも)が光儀(すがた)を見(み)まく苦(く)るしも(万229)
古
(ふりに)し嫗(をみな)にしてや如此(かく)ばかり戀(こひ)に将レ沈
(しづまむ)如二手
童
兒一(た
わらわのごと)(万
129)
○同源語:
塩(しほ・潮)、干(ひる)、妹(いも)、見(み
る)、苦(く)るしい、古(ふる)き、嫗(をみな・女)、手(て)、
【しづめ(鎮)】
真
木(まき)柱(ばしら)太(ふとき)心(こころ)は有(あり)しかど此(この)吾(わが)心(こころ)鎮(しづ)めかねつも(万190)
例:浜[pien]はま、君[giuən]きみ、文[miuən]ふみ、雲[hiuən]くも、困[khun]こまる、眠[myen]ねむる、呑[thən]のむ、など
○同源語:
真(ま)、木(き・枝)、心(こころ)、此(こ)
れ、吾(わが)、
【しぬ(死)】
鯨
魚(いさな)取(とり)海(うみ)や死(しに)する山(やま)や死(しに)する死(しぬれ)こそ海は潮(しほ)干(ひ)て山(やま)は枯(かれ)すれ(万3852)
戀
(こひ)死(しなば)戀(こひ)も死(しねと)や我妹(わぎもこが)吾家(わぎへ)の門(かど)を過(すぎて)行(ゆくらむ)(万2401)
○同源語:
魚(な)、取(とる)、海(うみ)、山(やま)、
潮(しほ)、干(ひる)、枯(かれ)る、我・吾(われ)、家(いへ)、妹(いも)、過(す
ぎる)、行(ゆく)、
【しね・いね(秈・稲)】
「右
の一首は、或は云はく、吉野の人味稲(うましね)の柘枝(つみのえ)の仙媛(やまひめ)に与へし歌なり。」(万385左注)
住 吉(すみのえ)の岸(きし)を田(た)に墾(はり)蒔(まきし)稲(いね)さて及レ苅 (かるまでに)相(あは)ぬ公(きみ)かも(万2244)
伊
祢(いね・稲)都氣(つけ)ばかかる安我(あが)手(て)を許余比(こよひ)かも等能(との)の和久胡(わくご)が等里(とり)て奈氣可武(なげかむ)(万3459)
スウェーデンの言語学者カールグレンは”Philology
and Ancient
China”(1920)の
なかで、日本語の「いね」は中国語の「秈」と関係のあることばではないかとしている。「秈」はうるち米のことで、古代中国語音は秈[shean]である。頭音が脱落して日本語の「いね」になった
可能性がある。サ行音はイ段では[-i-]介音の影響で脱落することが多い。
例:赤[thyjak](シャク・あか)、上[zjiang](ジョウ・あがる)、枝[tjie](シ・え)、臣(シン・お み)、織[tjiək](ショク・おる)、射[djyak](シャ・さす)、折[thjiat](セツ・をる)、矢[sjiei] (シ・や)、世[sjiatt](セ・よ)、山[shean](サン・やま)、
弥生時代の初期に稲作が伝わってきたとすれば、
ことばも一緒に使わってきた可能性がある。日本語の「いね」は中国語の「秈」と同源であると考えるのが穏当であろう。
○同源語:
野(の)、味(うまし)、枝(え)、仙(やま)、
媛(ひめ)、田(た)、墾(はり)、蒔(まく・播)、苅(かる)、相(あふ・合)、公(きみ)、都氣(つき・舂)、安我(あが)、手(て)、許余比(こよ
ひ・今夜)、等能(との・殿)、和久胡(わくご・王子)、等里(とり・取)、奈氣可武(なげか・歎)む、
【しば(柴)】
住
吉(すみのえの)出見(いづみの)濱(はまの)柴(しば)莫(な)苅(かり)そね未通女(をとめ)らが赤裳(あかもの)下(すその)閏(ぬれて)将レ徃
(ゆかむ)見(みむ)(万
1274)
○同源語:
出(いづ)、見(みる)、濱(はま)柴(しば)、
莫(な)、苅(かる)、未通女(をとめ・女)、
赤(あか)い、閏(ぬれる・濡)、徃(ゆく・
行)、
【しひ(椎)】
家
(いへに)有(あれ)ば笥(け)に盛(もる)飯(いひ)を草枕(くさまくら)旅(たび)にし有(あれ)ば椎(しひ)の葉(は)に盛(もる)(万142)
片
岡(かたをか)の此(この)向(むかつ)峯(をに)椎(しひ)蒔(まか)ば今年(ことしの)夏(なつ)の陰(かげ)に将レ化
(ならむ)か(万
1099)
「椎」の古代中国語の「椎」は椎[diuəi]である。声符の「隹」には隹[tjiuəi]、推[thuəi]、堆[tuəi]、唯・惟・維[jiuəi]、などの発音もある。中国語の[t-][d-]は介音[-i-]の前では口蓋化してサ行に転移することが多い。日
本語の「しひ」は古代中国語の椎[diuəi]から派生したことばであろう。「し+ひ」の「ひ」
については不明である。
○同源語:
家(いへ)、草(くさ)、葉(は)、岡(をか・
岳)、此(こ)の、向(むか)ふ、蒔(まく・播)、夏(なつ・熱)、陰(かげ・影)、
【しぶし(澁)】
衣
手(ころもで)に水澁(みしぶ)つくまで殖(うゑ)し田(た)を引板(ひきた)吾(わが)はへ眞守有(まもれる)栗子(くるし・苦)(万1634)
澁
谿(しぶたに)の二上山(ふたかみやま)に鷲(わし)ぞ子(こ)産(む)と云(いふ)指羽(さしは)にも君(きみ)の御(み)為(ため)に鷲(わし)ぞ子
(こ)生(む)と云(いふ)
(万
3882)
手(て)、田(た)、吾(わが)、真守(まもる・
護)、栗子(くるし・苦)、山(やま)、鷲(わし・鵞鷲)、子(こ)、云(いふ)、指(さ)す、羽(は)、君(きみ)、御(み)、
【しほ(潮・塩)】
𤎼
田津(にぎたつ)に船(ふな)乗(のり)せむと月(つき)待(まて)ば潮(しほ)もかなひぬ今(いま)はこぎ乞(いで)な(万8)
櫻 田(さくらだ)へ鶴(たづ)鳴(なき)渡(わたる)年魚市方(あゆちがた)塩(しほ・潮)干(ひ)にけらし鶴(たづ)鳴(なき)渡(わたる)(万271)
古代中国語の「潮」は潮[diô]である。日本語の潮(しほ・うしほ)は古代中国語
の潮[diô]の頭音が介音[-i-]の影響で摩擦音化したものであろう。「し+ほ」の
「ほ」は不明であるが、古代中国語の母音[ô]が日本語でハ行であらわれる例としては鯛[dyô](たひ)宵[siô](よひ)をあげることができる。
「潮」は「う+しほ」ともいう。古代日本語では
語頭に濁音がくることがなかったので、潮[diô]の前に「う」をつけて潮(う+しほ)として、日本
語の音韻構造になじむ形で受け入れたものである。日本語の「しほ」には「塩」も使われる。
志 賀の安麻(あま)の一日(ひとひ)もおちず也久(やく)之保(しほ)の可良伎(からき)戀をも安礼(あれ)はするかも(万3652)
志 賀の海人(あま)は軍布(め)苅(かり)塩(しほ)焼(やき)暇(いとま)無(な)み髪梳(くしげ)の小櫛(をぐし)取(とり)も見(み)なくに(万278)
「塩」の古代中国語音は塩[iem]であるとされているが、董同龢は「塩」の上古音を
塩[d’iɔg*]と再構している。日本漢字音では潮(チョウ)・塩
(エン)でかなりかけ離れているが、上古音にさかのぼると潮[diô]・塩[d’iɔg*]であり、ほとんど同系統のことばである。
○同源語:
𤎼(にき・柔)、田(た)、津(つ)、船(ふ
ね・盤)、乗(のる)、今(いま)、乞(でる・出)、鳴(なく)、渡(わたる)、年魚(あゆ)、干(ひる)、安麻・海人(あま)、也久・焼(やく)、可良
伎(からき・辛)、安礼(あれ・我)、苅(かる)、無(な)み、小(を)、取(とる)、見(みる)、
【しま(嶋・洲)】
を
ちこちの 嶋(しま)は雖レ多
(おほけど) 名(な)ぐはし 狭岑(さみね)の嶋(しま)の 荒礒面(ありそも)に 廬作(いほり)て見(みれ)ば、、(万220)
春 (はる)去(され)ばををりにををり鸎(うぐひす)の鳴(なく)吾(わが)嶋(しま)そ不レ息 (やまず)通(かよは)せ(万 1012)
董同龢によれは「州」「島」の上古中国語音は州[tiog*]、島[tog*]であり、「島」と「州」は音義ともに近い。島[tog*]は[-i-]介音の発達によって州[tiog*]になったものと考えることができる。
日本語の島(しま)はまた、朝鮮語のseomと同源だとも言われている。
○同源語:
名(な)、狭(せまい)、岑(みね・嶺)、荒(あ
ら)き、面(も・おも)、見(みる)、春(はる)、鸎(うぐひす・隹)、鳴(なく)、吾(わが)、
【しむ・そむ(染)】
中
々(なかなか)に人と不レ有
(あらず)は酒壺(さかつぼ)に成(なり)にてしかも酒(さけ)に染(しみ)なむ(万343)
浅 緑(あさみどり)染(そめ)懸有(かけたり)と見(みる)るまでに春楊(はるのやなぎ)は目生(もえに)けるかも(万1847)
日本漢字音の日(ニチ)は唐代の中国語音に依拠
しており、「元日」の日(ジツ)は唐代以降の中国語音に依拠しているものである。日本をJapanとするのも日(ジツ)に依拠したものである。
○同源語:
中(なか)、酒(さけ)、懸(かける)、見(み
る)、春(はる)、楊(やなぎ)、目生(もえる・萌)、
【しめ(標)】
茜
草(あかね)指(さす)武良前(むらさき)野(の)逝(ゆき)標野(しめの)行(ゆき)野守(のもり)は不レ見
(みずや)君(きみ)が袖(そで)布流(ふる)(万20)
葛 城(かづらき)の高間(たかま)の草野(かやの)早(はや)知(しり)て標(しめ)指(ささ)ましを今(いまぞ)悔(くや)しき(万1337)
例:秒(ビョウ)・少(ショウ)、品(ヒン・し
な)、
○同源語:
指(さ)す、野(の)、逝・行(ゆく)、守(まも
る・護)、見(みる)、君(きみ)、袖(そで)、葛(かづら)、間(ま)、草(くさ)、知(しる)、今(いま)、悔(くや)し、
【しも(霜)】
葦
邊(あしべ)行(ゆく)鴨(かも)の羽(は)我比(がひ・交)に霜(しも)零(ふり)て寒(さむき)暮夕(ゆふべは)倭(やまと)し所レ念
(おもほゆ)(万
64)
在 (あり)つつも君(きみ)をば将レ待 (またむ)打(うち)靡(なびく)吾(わが)黒髪(くろかみ)に霜(しも)の置(おく)までに(万87)
例:醒[syeng](さめる)、公[kong](きみ)、相[siang](さま)、灯[təng](ともる)、弓[kiuəng]
(ゆみ)、夢[miuəng](ゆめ)、浪[lang](なみ)、
○同源語:
邊(へ)、行(ゆく)、鴨(かも)、羽(は)、我
比(がひ・交)、霜(しも)、零(ふる・降)、暮夕(ゆふべ・夜)、念(おもふ)、君(きみ)、打(うつ)、靡(なび)く、吾(わが)、黒(くろ)、
【しる(知)】
借
(かり)薦(こも)の 心(こころ)もしのに 人(ひと)不レ知
(しれず) 本名(もとな)ぞ戀(こふ)る 氣(いき)の緒(を)にして、、(万3255)
葛 城(かづらぎ)の高間(たかまの)草野(かやの)早(はや)知(しり)て標(しめ)指(さし)ましを今(いまぞ)悔(くや)しき(万1337)
古代中国語の「知」は知[tie]である。日本語の「しる」は中国語の知[tie]が介音[-i-]の影響で摩擦音化してサ行に転移したものである。
日本漢字音でも同じ声符の文字をタ行とサ行に読み分ける例を数多くあげることができる。サ行音はタ行音が摩擦音化したものである。
例:多・侈、他・施、途・除、都・者、陀・蛇、
楕・随、堆・推、隊・墜、唾・垂 澤・釋、
脱・説、獨・蜀、直・植、的・酌、
秩・失、窒・室、蟄・執、探・深 壇・氈、単・戦、
探・深、傳・専、顛・真、
屯・純、冬・終、透・秀、統・充 湯・場、抽・袖、
二番目の歌の「知(しり)」は治[diə]で「治める」「占有する」の意味である。
○同源語:
借(かり・苅)、心(こころ)、知
(しる)、本(もと)、名(な)、氣(いき・息)、葛(かづら)、間(ま)、草(くさ)、野(の)、標(しめ)、指(さ)す、今(いま)、悔(くや)し、
【しわ(皺)】
若
有(わかかり)し 皮(はだ)も皺(しわみ)ぬ 黒有(くろかり)し 髪(かみ)も白斑(しらけ)ぬ、、(万1740)
同源語:
若(わか)き、黒(くろ)き、
【す(栖)】
可
麻度(かまど・竈)には 火氣(ほけ)布伎(ふき・吹)多弖(たて・立)ず 許之伎(こしき・甑)には 久毛(くも・蜘蛛)の須(す・巣)かきて、、(万892)
鳥 座(とくら)立(たて)飼(かひ)し鴈(かり)の兒(こ)栖(す)立(たち)なば檀(まゆみの)岡(をか)に飛(とび)反(かへり)来(こ)ね(万182)
二番目の歌では「栖(す)立(たち)」とあるか
ら現代の日本語では「巣立ち」である。古代中国語の「栖」は栖[syei]である。「栖」は現代では栖(すむ)に使われてい
るが、「栖」は「木+酉(とり)」であり「鳥の巣」のことである。
万葉集には用例はないが、現在よく用いられてい
る巣[dzheô]も鳥の巣である。日本語の「す」は栖[syei]、巣[dzheô]と同系のことばである。
○同源語:
火氣(ほけ)、多弖・立(たて)、須・栖(す・
巣)、鳥(とり)、鴈(かり)、兒(こ)、岡(をか・岳)、飛(とぶ)、反(かへる・還)、來(くる)、
【す(洲・渚)】
夏
麻(なつそ)引(ひく)海上(うなかみ)滷
(かた)の
奥(おきつ)洲(す)に鳥(とり)は簀(す)だけど君(きみ)は音(おと)も不レ為
(せず)(万
1176)、
三 沙呉(みさご)居(ゐる)渚(す)に居(ゐる)舟(ふね)の榜(こぎ)出(で)なばうら戀(こひ)しけむ後(のち)は會(あひ)ぬとも(万3203)
古代中国語の「洲」「渚」は洲[tjiu]・渚[tjia]である。古代日本語には洲(シュウ)、渚(ショ) という音節はなかったので、日本語では直音で洲(す)、渚(す)として定着した。「渚」は現代の日本語では渚(なぎさ)と読まれている。日本語の 「なぎさ」は「浪+渚」であろう。
多 麻(たま)之家流(しける)伎欲吉(きよき)奈藝佐(なぎさ)を之保(しほ)美弖婆(みてば・満)安可受(あかず)和礼(われ)由久(ゆく)可反流(かへ る)さに見(み)む(万 3706)
○同源語:
海(うみ)、奥(おき・澳)、鳥(とり)、簀
(す・巣)、君(きみ)、音(おと)、居(ゐ)る、舟(ふね・盤)、出(でる)、會(あふ)、伎欲吉(きよき・清)、之保(しほ・潮)、美弖婆(みつ・
満)ば、和礼(われ・我)、由久(ゆく・行)、可反流(かへる・還)、見(み)る、
【す(酢)】
醤
(ひしほ)酢(す)に蒜(ひる)つき合(かて)て鯛(たひ)願(ねがふ)吾(われ)に勿(な)所レ見
(みせそ)水葱(なぎ)の煮物(あつもの)(万3829)
古代中国語の「酢」は酢[dzak]である。日本語の酢(す)は古代中国語の酢[dzak]の韻尾[-k]が脱落したものである。日本漢字音には同じ声符を
もった漢字を入声音[-k]で読むものと、[-k]が脱落するものが数多くみられる。
例:悪・亞、億・意、獲・護、核・該、割・害、
式・試、祝・呪、的・約、特・時 莫・墓、
福・富、壁・避、北・背、
○同源語:
鯛(たひ)、酢(す)、願(ねがふ)、吾(わ
れ)、見(みる)、煮(あつ・熱)、物(もの)、
【す(簀)】
夏
麻(なつそ)引(びく)く海上滷(うなかみがた)の奥洲(おきつす)に鳥(とり)は簀(す)だけど君(きみ)は音(おと)も不レ為
(せず)(万
1176)
簀竹(すだく)は借訓で「集まってさわぐ」とい
うほどの意味だという。『和名抄』によれば「簀須乃古、床上藉レ竹名也」とある。
古代中国語の「簀」は簀[tzhek]である。日本語の簀(す)は中国語の簀[tzhek]の韻尾[-k]が脱落したものである。日本語の簀(す)は中国語
の簀[tzhek]と同源である。
○同源語:
夏(なつ・熱)、海(うな・うみ)、奥(澳・お
き)、州(す)、鳥(とり)、簀(す・巣)、君(きみ)、音(おと)、
【すぎる(過)】
春
(はる)過(すぎ)て夏(なつ)來(きたる)らし白妙(しろたへ)の衣(ころも)乾有(ほしたり)天(あめ)の香來山(かぐやま)(万28)
「過」の古代中国語音は過[kuai]である。中国語中国語では同じ声符の漢字がカ行と
サ行にわたってあらわれることがある。
例:技[gie](ギ)・枝[tjie](シ)、逆[ngyak](ギャク・さからふ)、遡[sak](ソ・さかのぼる)、
また、日本漢字音では音ではカ行音であらわれ、
訓ではサ行音であらわれるものがある。
例:救[kiu](キュウ・すくふ)、菅[kean](カン・すげ)、境[kyang](キョウ・さかい)、界[keat]
(カイ・さかい)、埼[kiai](キ・さき)、幸[hiəng](コウ・さき・さち)、
カ行音は介音[-i-]などの影響で摩擦音化して、サ行音に転移した。過[kuai](カ・すぎる)はカ行音がサ行音を重ね合わせたこ とばである可能性がある。
○同源語:
春(はる)、夏(なつ・熱)、來(きたる)、乾
(ほす)、天(あめ)、香(か)、山(やま)、
【すくなし・すこし(少・小)】
塩
(しほ・潮)満(みて)ば入(いりぬ)る礒(いそ)の草有(くさなれ)や見(み)らく少(すくなく)戀(こふ)らくの太(おほ)き(万1394)
さ につらふ色(いろに)は不レ出 (いでず)小(すくなく)も心(こころの)中(うちに)吾(わが)念(おもは)なくに(万2523)
古代中国語の「少」「小」は少[sjiô]・小[siô]である。「少」「小」の祖語(上古音)は少[xiôk*]、小[xiôk*]に近い発音であったと思われる。少(すく‐な)、
小(すく‐な)は上古音[x-]と[s-]を重ねたものと思われる。
日本語の「すくな
し」は、上代中国語の少[xjiôk*]・小[siôk*]に音義ともに近く、中国語の「少」「小」から派生
してできたことばであろう。「小」は日本語では「すこし」にも使われる。
○同源語:
塩(しほ・潮)、満(みつ)、入(いる)、草(く さ)、見(みる)、色(いろ)、出(いづ)、心(こころ)、吾(わが)、念(おもふ)、雲(くも)、箱(はこ・筐)、常(とこ)、世(よ)、 邊(へ)、棚(たな・壇・段)、
【すげ(菅)】
押
(おし)照(てる) 難波(なには)の菅(すげ)の 根(ね)もころに、、(万619)
見 渡(みわたしの)三室山(みむろのやまの)石穂(いはほ)菅(すげ)ねもころ吾(われは)片念(かたもひぞ)為(する)(万2472)
同じ声符をもった漢字でカ行とサ行に読み分ける
ものも多く、漢字音の歴史のなかではかなり早い時期から摩擦音化が始まったことを示唆している。
例:期・斯、技・枝、祇・氏、企・止、貴・遺、
拠・處、睨・児、耆・指、坤・神 訓・川、言・ 信、感・鍼、活・舌、賢・腎、
勘・甚、宦・臣、牙・邪、絢・旬、など
中国語の[k-][h-]などが摩擦音化して日本語のサ行音になったと考え
られるものには次のようようなものがある。
例:賢[hyen](ケン・さかし)、幸[hiəng](コウ・さき・さち)、寒[han](カン・さむい)、
狭[heap](キョウ・せまい)、懸[hien](ケン・さがる)、埼[kiai](キ・さき)、
吸[xiəp](キュウ・すふ)、去[khia](キョ・さる)、逆[ngiak](ギャク・さか)、
菅(カン・すげ)もこの一連の流れのなかに位置 づけられるものであろう。
○同源語:
押(おす)、照(てる)、根(ね)、見(み
る)、渡(わたす)、三(み)、山(やま)、穂(ほ・恵)、吾(われ)、念(おもふ)、
【すごろく(雙六)】
吾
妹兒(わぎもこ)が額(ぬか)に生(おふ)る雙六(すぐろく)のことひの牛(うし)の倉(くらの)上(うへ)の瘡(かき)(万3838)
一 二(いちに)の目(め)耳(のみに)不レ有 (あらず)五六三(ごろくさむ)四(し)さへ有(あり)けり雙六(すごろく)の佐叡(さえ)(万3827)
古代中国語の「雙六」は雙六[sheong-liuk]である。しかし、同じ声符をもった漢字に隻[tjyak](セキ)がある。日本語の「すごろく」は中国語の
上古音、雙六[sheong-tjyak]に依拠したものであろう。
地名の相模(さがみ)なども上古音を継承してい
る。日本漢字音には訓がカ行であらわれ、音が音便化しているものが多い。
例:床(とこ・ショウ)、影(エイ・かげ)、茎
(くき・ケイ)、筺(かご・キョウ)、
塚(つか・チョウ)、丈(たけ・じょう)、楊(や
ぎ・やなぎ・ヨウ)、桶(おけ・トウ)、
○同源語:
吾妹兒(わぎもこ)、額(ぬか)、目(め)、耳
(のみ)、佐叡(さえ・賽)、
【すすぐ(濯)】
小
螺(しただみ)を い拾(ひりひ)持(もち)來(き)て 石(いし)以(もち) 都追伎(つつき)破夫利(やぶり) 早川(はやかは)に 洗(あらひ)濯
(すすぎ)、、(万
3880)
中国語の濁音の頭音を日本語では清音を重複させ
て対応する例もいくつかみられる。
例:静[dzieng](しずか)、沈[diəm](しずむ)、畳[dyap](たたみ)、停[dyeng](とどめる)、
続[ziok](つづく)、雀[tziok](すずめ)、進[tzien](すすむ)、限[hean](かぎり)、
響[xiang](ひびく)、
○同源語:
來(くる)、都追伎(つつき・突)、川(かは・河)、
【すすむ(進)】
思レ家
(いへおもふ)と情(こころ)進(すすむ)莫(な)風候(かざまもり)好(よく)為(し)ていませ荒(あらし)其(その)路(みち)(万381)
○同源語:
家(いへ)、思(おもふ・念)、情(心・ここ
ろ)、莫(な)、候(まもる・護)、好(よく・良)、荒(あらし)、其(そ)の、
【すむ(住)】
御
(み)立為(たたし)の嶋(しま)をも家(いへ)と住(すむ)鳥(とり)も荒(あら)び勿(な)行(ゆきそ)年(とし)替(かはる)まで(万180)
荒
熊(あらくま)の住(すむと)云(いふ)山(やま)の師歯迫(しはせ)山(やま)責(せめ)て雖レ問
(とふとも)汝(なが)名(な)は不レ告
(のらじ)(万
2696)
○同源語:
御(み)立(たつ)、嶋(しま・洲)、家(い
へ)、住(すむ)、鳥(とり)、荒(あら)ぶる、勿(な)、行(ゆく)、熊(くま)、山(やま)、汝(な)、名(な)、
鴨
頭草(つきくさ)に服(ころも)色(いろ)取(どり)揩(すら)めども移變(うつろふ)色(いろ)と偁(いふ)が苦(くるし)さ(万1339)
古代中国語の「摺」は摺[ziuəp]である。日本語の「する」には擦[tziat]、刷[shoat]がある。韻尾の[-t]は[-l]と調音の位置が同じであり、転移しやすい。「摺」
の韻尾は摺[ziuəp]であるが、日本漢字音では、中国語の韻尾[-p]はタ行であらわれることが多い。
例:立[liəp](リツ)、湿[sjiəp](シツ)、雜[dziəp](ザツ)、接[tziap](セツ)、
日本漢字音では中国語の韻尾[-p]も[-t]が弁別されない場合が多い。日本語の「する」は中
国語の摺[ziuəp]、擦[tziat]、刷[shoat]などと音義ともに近く、同系のことばであろう。
○同源語:
草(くさ)、色(いろ)、取(とる)、苦(くる
し)、
【せき・せく(塞・關)】
出
(いでて)行(ゆく)道(みち)知(しら)ませば豫(あらかじめ)妹(いも)を将レ留
(とどめむ)塞(せき)も置(おか)ましを(万468)
愛 (うつくし)と吾(わが)念(おもふ)情(こころ)速河(はやかは)の雖二塞 々一(せ きにせく)とも猶(なほ)や将レ崩 (くえなむ)(万 687)
關 (せき)無(なく)は還(かへり)にだにも打(うち)行(ゆき)て妹(いも)が手枕(たまくら)卷(まき)て宿(ね)ましを(万1036)
「塞」は名詞(せき)にも動詞(せく)にも使わ れている。日本語の「ふさぐ」は中国語の「閉塞」から派生したことばであろう。關[koan](せき)が現在では常用されているが借訓である。
○同源語:
出(いづ)、行(ゆく)、知(し)る、妹(い
も)、留(とどめ・停)る、置(おく)、吾(わが)、念(おもふ)、情(こころ・心)、河(かは)、無(な)き、還(かへる)、打(うつ)、手(て)、宿
(ねる・寐)、
【せこ(背子・兄子)】
我
(わが)背子(せこ)が朝明(あさけの)形(すがた)よく不レ見
(みずて)今日(けふの)間(あひだを)戀(こひ)暮(くらす)かも(万2841)
人 言(ひとごと)を繁(しげ)みこちたみ我(わが)兄子(せこ)を目(めに)は雖レ見 (みれども)相(あふ)因(よし)も無(なし)(万2938)
「背」の古代中国語音は背[puək]である。中国語の古語辞典にあたる『説文』による
と「背は脊(せき)なり」とある。「脊」の古代中国語音は脊[tziek]であり、万葉集では「背」を「せ」と読ませている
が、日本語の「せ」にあたる中国語は脊[tziek]であろう。しかし、脊[tziek]子[xiə*]では日本語の「せこ」と音は対応するが、義(意
味)が対応しない。「背子」は音借であろう。
「兄」の古代中国語音は兄[xyuang]である。「兄」の現代北京音は兄(xiong)であり、摩擦音である。中国語の喉音[h-][x-]の上古音は摩擦音であるが、介音[-i-]などの発達により、しだいに摩擦音化した。兄
「せ」は兄[xyuang]が摩擦音化したものである可能性がある。
「せこ(兄子)」は「いも(妹)」に対すること
ばである。中国語と日本語では使われる意味の範囲が多少違うが、「せこ」も「いも」も古代中国語の「兄」「妹」と同系のことばであろう。
○同源語:
我(わが)、明(あけ・暁)、見(みる)、今日
(けふ))、言(こと)、目(め)、相(あふ・合)、無(な)し、
【せばし・せし(狭・迫)】
天
(あめ)地(つち)は比呂之(ひろし)と伊倍(いへ)ど 安我(あが)多米(ため)は狭(さく)や奈里(なり)ぬる 日(ひ)月(つき)は安可之(あか
し)と伊倍(いへ)ど 安我(あが)多米(ため)は 照(てり)や多麻波(たまは)ぬ、、(万892)
谷 (たに)迫(せばみ)峯(みね)邊(へに)延(はへ)る 玉葛(たまかづら) 令レ蔓 (はへて)し有(あら)ば 年(とし)に不レ來 (こず)とも(万 3067)
例:技・枝、企・止、期・斯、耆・旨、臼・舅、
嗅・臭、拠・処、暁・焼、
狭[heap]の韻尾[-p]はバ行であらわれている。韻尾の[-p][-m]が日本語でバ行・マ行であらわれる例としては次の
ようなものをあげることができる。
例:渋[shiəp]しぶい、甲兜[keap-to]かぶと、鴨[keap]かも、甲[keap]かぶと、湿[sjiəp]しめる、
粘[tjiam]ねばる、三[səm]郎さぶろう、
○同源語:
天(あめ)、地(つち)、比呂之(ひろし・広)、
安我(あが)、照(てる)、峯(みね・嶺)、邊(へ)、葛(かづら)、來(くる)、
【せみ(蝉)】
伊
波婆之流(いはばしる)多伎(たき・瀧)もとどろに鳴(なく)蝉(せみ)の許恵(こゑ・聲)をし伎氣(きけ・聞)ば京師(みやこ)し於毛保由(おもほゆ)(万3617)
マ行の例:肝[kan]きも、浜[pien]はま、文[miuən]ふみ、君[kiuən]きみ、
ナ行の例:絹[kyuan]きぬ、殿[dyən]との、段[duan]たな、秈[shean]しね・いね、
○同源語:
多伎(たき・瀧)、鳴(なく)、許恵(こゑ・
聲)、京師(みやこ)、於毛保由(おもほゆ・念)、
【そで(袖)】
茜
(あかね)指(さす)武良前(むらさき)野(の)逝(ゆき)標野(しめの)行(ゆき)野守(のもり)は不レ見
(みず)や君(きみ)が袖(そで)布流(ふる)(万20)
敷 妙(しきたへ)の袖(そで)易之(かへし)君(きみ)玉垂(たまだれ)の越野(をちの)過去(すぎゆく)またも将レ相 (あはめ)やも(万 195)
日本語の「そで」は古代中国語の袖[ziəu]から派生したことばであろう。「そで」は「袖」+ 「手」の類推から生まれたことばである可能性がある。同じような造語の例として、楊[jiang]から派生した「やなぎ」などをあげることができ る。「やなぎ」は「楊(ヨウ・やぎ)の+木」の連想から生まれている。
○同源語:
指(さす)、野(の)、逝・行・去(ゆく)、標
(しめ)、守(もり・護)、見(みる)、君(きみ)、垂(たれ)る、越(をち)、過(すぎ)る、相(あふ・合)、
【その(苑)】
春
(はる)の苑(その)紅(くれなゐ)尓保布(にほふ)桃(ももの)花(はな)下照(したてる)道(みち)に出(いで)立(たつ)[女
感]*嬬
(をとめ)(万
4139)
古代中国語の「苑」は苑[iuan]である。「苑」は北京音では苑(yuan)であり、苑(yuan)と同じ発音の漢字に園、遠、猿、怨、縁、援、媛、
淵、院、員、圓、元、原、願などがあることがわかる。
これらの漢字の古代中国語音は、園[hiuan]、遠[hiuan]、猿[hiuan]、援[hiuan]、媛[hiuan],院[hiuan]、員[hiuən]、圓[hiuən]、元[ngiuan]、原[ngiuan]、願[ngiuan]、縁[djiuan]、淵[yuen]、怨[iuan]であり、頭音が脱落したものが多いことがわかる。
中国語の「苑」にも語頭に喉音[h-]があった可能性がある。「苑」の祖語(上古音)は
苑[hiuan*]であり、頭音[h-]が摩擦音化して苑(その)となったものであろう。
日本語の「その」には「苑」のほかに「園」があ てられることもある。「園」の古代中国語は園[hiuan]であり、日本漢字音は園(エン・その)である。園 (その)も園[hiuan]の頭音が摩擦音化したものであろう。
○同源語:
春(はる*)、花(はな)、照(てる)、出(い
づ)、立(たつ)、[女感]*嬬(をとめ・嬬)、
【さ行のまとめ】
ここで、日本語のサ行音の形成について整理して みると、摩擦音系、破擦音系のもののほか[t-][d-]から転移したもの、喉音[h-][x-]、後口蓋音[k-][ng-]が摩擦音化したものがみられる。
1. 古代中国語の摩擦音[s-][z-]にあたるもの。
盛[zjiəng]さかゆ・さかる、先[syen]さき、鵲[syak]さぎ、咲[syô]さく、矢[sjiei]さつや、死[siei]しす・しぬ、秈[shean]しね・いね、澁[shiəp]しぶし、霜[shiang]しも、栖[syei]す・すむ、雙[sheong]六・すごろく、摺[ziuəp]する、塞[sək]せき、蝉[zjian]せみ、袖[ziəu]そで、
2.古代中国語の破擦音[tz][ts]にあたるもの。
前[tzian]さき、酒[tziu(k)*]さけ、挿[tsheap]さす、刺[tsiek]さす、清[tsyeng]さやか、、猪[tjio]しし、静[dzieng]寂[tzyek]しづか、柴[dzhe]しば、皺[tzhio]しわ、酢[dza(k)*]す、簀[tzhek]す、進[tzien]すすむ、
3.上古中国語の[t-][d-]などが[-i-]介音の影響で摩擦音化したもの。
尺[thjyak]さか、指[tjiei]さす、障[tjiang]さはる・さやる、猪[tjio]しし、舌[djiat]した、沈[diəm]しづむ、鎮[tien]しづめ、椎[diuəi]しひ、潮[diô]しほ、島[tô]・洲[tjiu]しま、知[tie]しる、洲[tjiu]す・しま、渚[tjia]す、濯[diôk]すすぐ、住[dio]すむ、
4. 中国語の喉音[h-][x-]が[-i-]介音の影響で摩擦音化したもの。
賢[hyen](ケン・さかし)、栄[hiueng](エイ・さかゆ)、幸[heang](コウ・さき・さち)、猿[hiuan](エン・さる)、狭[heap](キョウ・せばし)、兄[xyuang](ケイ・せ)、塩[(h)iem*](エン・しほ)、苑[(h)iuan*](エン・その)、
5.中国語の喉音[h-][x-]が口蓋化して訓では(サ行音+カ行音)であらわれ るもの。
盛[zjiəng/hiəng*](セイ・さかゆる・さかん)、 少[sjiô/xiô*](ショウ・すくなし)、小[siô/xiô*](ショウ・すくなし・すこし)、
6.中国語の後口蓋音[k-][ng-]などが訓では(サ行音+カ行音)であらわれるも の。
崎[kiai](キ・さき)、過[kuai](カ・すぎる)、菅[kean](カン・すが)、逆[ngyak](ギャク・さか)、
中国語の喉音[h-][x-]は破裂音であったものが摩擦音に変化したものと考 えられる。日本語の訓のなかにはカ行音とサ行音を重ね合わ せた発音がいくつかみられる。これらは摩擦音化の過程を示しているのではあるまい か。
◎た行
【た(田)】
秋
田(あきのたの)吾(わが)苅(かり)婆可(ばか)の過去(すぎぬれ)ば鴈(かり)が喧(ね)所レ聞
(きこゆ)冬方(ふゆかた)設(まけ)て(万2133)
秋
田(あきのた)の穂田(ほだ)の苅(かり)ばか香(か)縁(より)相(あは)ば彼所(そこ)もか人(ひと)の吾(わ)を事(こと・言)将レ成
(なさむ)(万
512)
古代中国語の「田」は田[dyen]である。日本語の「た」は中国語の田[dyen]の韻尾が脱落したものである。古代日本語には濁音
ではじまることばはなかったので田[dyen]の頭音は清音になった。古代日本語には[-n]で終わる音節はなかった。
韻尾の[-n][-m]が脱落した例:眼[ngean] め、千[tsyen] ち、津[tzien] つ、辺[pyen] へ、
帆[biuəm] ほ、など
古事記、日本書紀には歌謡がそれぞれ120首あ
まりおさめられており、すべて漢字の音だけで書かれているが、漢字の韻尾[-n][-m]は失われている例が多い。
韻尾[-n][-m]の喪失例:存・鐏 ぞ、傳 で、幡・泮・絆 は、弁 べ、本 ほ、煩 ぼ、綿 め、
延 イエ、涴 わ、遠・袁・惋 を、
○同源語:
吾(わが)、苅(かり)、過(すぎ)る、鴈(か
り)、喧(ね・音)、穂(ほ)、縁(より)、相(あふ・合)、事(こと・言)、
【たき(瀧)】
田
跡河(たどかは)の瀧(たき)を清(きよ)みか従レ古
(いにしへゆ)官仕(みやつかへ)けむ多藝(たぎ)の野(の)の上(うへ)に(万1035)
高
山(たかやま)の石本(いはもと)瀧千(たぎち)逝(ゆく)水(みづ)の音(おと)には不レ立
(たてじ)戀(こひ)て雖レ死
(しぬとも)(万
2718)
例:龍[liong](リュウ・たつ)、立[liəp](リツ・たつ)、陵[liəng](リョウ・つか)、
蓼[liu](リョウ・たで)、粒[liəp](リュウ・つぶ)、留(リュウ・とどまる)、
霊[lyeng](レイ・たま)、嶺[lieng] (レイ・たけ)、列[liat](レツ・つらなる)、
連[lian](レン・つらなる)、など
また、漢字音でも禮[lyei]・體[thyei]、頼[lat]・獺[that]などのように同じ声符を[l-]と[t-]に読み分けられるものがある。
○同源語:
田(た)、河(かは)、清(きよ)き、官(みや・
宮)、野(の)、山(やま)、本(もと)、千(ち)、逝(ゆく・行)、音(おと)、立(たつ)、死(し)ぬ、
【たけ(竹)】
御
苑布(みそのふ)の竹(たけの)林(はやし)に鸎(うぐひす)は之浪(しば)奈吉(なき)にしを雪(ゆき)は布利(ふり・降)つつ(万4286)
烏
梅(うめ)の波奈(はな)知良(ちら)まく怨之美(をしみ)和我(わが)曾乃(その)の多氣(たけ)の波也之(はやし)に于具比須(うぐひす)奈久(な
く)くも(万
824)
これに対して国語学者の亀井孝は「竹は日本人の
祖先が日本列島に住み始めた太古の時代から日本にあったものである。日本人の祖先は筍を食べていたに違いなく、竹には日本古来の名前がついていたはずであ
る。」だから竹(たけ)が中国語からの借用語であることは多分に疑わしい、と反論している。カールグレンは音韻論で立証しようとしているのに対して亀井孝
は文化論で反論している。
「竹」の古代中国語音は竹[tiuk]であり、日本語の「たけ」とは母音が一致しない。
しかし、介音[-i-]は隋唐の時代に発達っしてきたものでり、日本語の
竹(たけ)は介音[-i-]が発達する前のかなり古い時代の中国語音を反映し
ている可能性がある。
○同源語:
御(み)、苑・曾乃(その)、鸎・于具比須(うぐ
ひす・隹)、奈吉・奈久(なき・なく・鳴)、布利(ふり・降)、烏梅(うめ)、波奈(はな・花)、知良(ちら・散)まく、和我(わが)、
中国文明は古代において東アジア唯一の文字を
もった高度な文明であり、弥生時代から古墳時代にかけて、記紀万葉が成立するまでの約千年の間に日本列島に大きな影響を与え続けた。縄文時代には「たけ」
に対して別のことばがあったとしても、弥生時代の日本語では中国語から入って来た語彙に置き換えられた可能性が高い。「たけ」は音義ともに「竹」に近く、
中国語との同源語であろう。
【ただ(直)に】
直
(ただに)相(あは)ば相(あひ)不レ勝
(かつましじ)石川(いしかは)に雲(くも)立(たち)渡(わた)れ見(み)つつ将レ偲
(しのばむ)(万
225)
三
熊野(みくまの)の浦(うら)の濱(はま)木綿(ゆふ)百重(ももへ)成(なす)心(こころ)は雖レ念
(おもへど)直(ただ)に不レ相
(あはぬ)かも(万
496)
例:雀(ジャク・すずめ)、續(ゾク・つづく)、
畳(ジョウ・たたみ)、限(ゲン・かぎり)、
○同源語:
相(あふ・合)、川(かは・河)、雲(くも)、立
(たつ)、渡(わたる)、見(みる)、三(み・御)、熊(くま)、野(の)、濱(はま)、心(こころ)、念(おもふ)、
【たたみ(畳)】
畳
(たたみ)薦(こも)隔(へだて)編(あむ)數(かず)通(かよはさ)ば道(みち)の柴草(しばくさ)不レ生有(おひざら)ましを(万2777)
韓 國(からくに)の 虎(とらと)云(いふ)神(かみ)を 生取(いけど)りに 八頭(やつ)取(とり)持(もち)來(き) 其(その)皮(かは)を 多々 弥(たたみ・畳)に刺(さし) 八重(やへ)畳(だたみ) 平群(へぐり)の山(やま)に、、(万3885)
吾
(わが)畳(たたみ)三重(みへ)の河原(かはら)の礒(いその)裏(うら)に如(かく)しもがもと鳴(なく)河蝦(かはづ)かも(万1735)
古代中国語の「畳」は畳[dyap]である。語頭の濁音は清音を重ねて畳音としたもの
である。、韻尾の[-p]はマ行に転移した。
○同源語:
柴(しば)、草(くさ)、韓(か
ら)、國(くに)、神(かみ)、生(いきる)、取(とる)、來(くる)、刺(さ)す、平群(へぐり)、山(やま)、吾(わが)、三(み)、河(かは)、原
(はら)、裏(うら)、鳴(なく)、河蝦(かはづ)
【たち(大刀・刀薙)】
大
御身(おほみみ)に 大刀(たち)取(とり)帯(はか)し 大御手(おほみて)に 弓(ゆみ)取(とり)持(もた)し 御(み)軍士(いくさ)を あども
ひ賜(たまひ) 齊(ととのふ)る 鼓(つづみ)の音(おと)は 雷(いかづち)の 聲(こえ)と聞(きく)くまで、、(万199)
古代中国語の「太刀」は太[dat]刀[tô]である。日本語の「たち」は中国語の太[dat]刀[tô]あるいは、刀薙[tô-thyei]であろう。「薙」は日本語では「なぎなた」に用い
られている。
○同源語:
御(み)、身(み)、取(とる)、手(て)、弓
(ゆみ)、音(おと)、聲(こえ)、
【たつ(龍)】
白
雲(しらくも)の 龍田山(たつたのやま)の 露(つゆ)霜(しも)に、、春(はる)去(さり)行(ゆか)ば 飛(とぶ)鳥(とり)の 早(はやく)御來
(きまさね) 龍田道(たつたぢ)の 岳邊(をかべ)の路(みち)に、、(万971)
多
都(たつ・龍)の馬(ま)も伊麻(いま・今)も愛(え・得)てしか阿遠尓(あをに)よし奈良(なら)の美夜古(みやこ)に由吉(ゆき・行)て己牟(こむ・
来)ため(万
806)
「多都(たつ)の馬(ま)」は「龍馬」で、駿馬
のことである。龍は中国で古代から神獣とされた動物である。中国の「龍」が日本漢字音は龍(リュウ)である。日本に古代から龍(たつ)という動物があっ
て、中国語の龍(リュウ)にあてたというものではなく、日本語の「たつ」は古代中国語の龍[liong]が転移したものである。
例:立(リツ・たつ)、瀧(ロウ・たき)、留
(リュウ・とどまる)、粒(リュウ・つぶ)、
同じ声符をもった漢字でもラ行とタ行に読み分け
るものがみられる。
例:禮(レイ)・體(タイ)、頼(ライ)・獺(ダ
ツ)、
○同源語:
雲(くも)、田(た)、山(やま)、霜(しも)、
春(はる)、行(ゆく)、飛(とぶ)、鳥(とり)、來(くる)、岳(をか)、邊(へ)、馬(うま)、伊麻(いま・今)、美夜古(みやこ・京)、由伎(ゆ
き・
行)、己牟(こむ・來)、
【たつ(立)】
吾
(わが)勢祜(せこ)を倭(やまと)へ遣(やる)と佐夜(さよ)深(ふけ)て鶏鳴(あかとき)露(つゆ)に吾(あが)立(たち)所レ霑
(ぬれ)し(万
105)
三
吉野(みよしの)の御船(みふね)の山(やま)に立(たつ)雲(くも)の常(つねに)将レ在
(あらむ)と我(わが)思(おもは)莫(な)くに(万244)
例:立[liəp]リツ、湿[sjiəp]シツ、執[tiəp]シツ、接[tziap]セツ、摂[siap]セツ、雜[dzəp]ザツ、
○同源語:
吾・我(われ)、勢祜(せこ・背子)、遣(や
る)、夜(よ)、鶏鳴(あかとき・暁時)、立(たつ)、霑(ぬれる・濡)、三・御(み)、野(の)、船(ふね・盤)、山(やま)、雲(くも)、常(つ
ね)、思(おもふ・念)、莫(な)く、
【たつ・たゆ(絶・断)】
人
(ひとの)子(こ)は 祖(おやの)名(な)不レ絶
(たたず) 大君(おほきみ)に まつろふ物(もの)と 伊比(いひ)都雅(つげ)る、、(万4094)
吾
妹兒(わぎもこ)が結(ゆひ)てし紐(ひも)を将レ解(とかめ)やも絶(たえ)ば絶(たゆ)とも直(ただ)に相(あふ)までに(万1789)
古代中国語の「絶」は絶[dziuat]である。「絶」の祖語(上古音)は絶[diuat*]に近かったものと考えられる。白川静の『字通』に
よると「絶[dziuat]、斷[duan]は声義近く、糸などの切断をいう字」であるとい
う。日本語の「たゆ」「たつ」は上古中国語絶[diuat*]あるは斷[duan]と同源であろう。中国語は同義語を重ねて強調する
ことが多く、「断絶」という成句もある。
○同源語:
子(こ)、名(な)、君(きみ)、物(もの)、都
雅(つげる・續)、吾妹兒(わぎもこ)、紐(ひも・絆・繙)、直(ただ)、相(あふ・合)、
【たて(楯)】
大
夫(ますらを)の鞆(とも)の音(おと)為(す)なり物部(もののふ)の大臣(おほまへつきみ)楯(たて)立(たつ)らしも(万76)
古代中国語の「楯」は楯[djiuən]である。「楯」と同じ声符をもつ漢字に遁[duən]がある。「楯」の祖語(上古音)は楯[duən*]あるいは楯[duət*]のような音であったと思われる。日本語の「たて」
は中国語の楯[duət*]と同源である。韻尾の[-n]がタ行であらわれる漢字は数多くある。
例:断(ダン・たつ)、管(カン・くだ)、幡(ハ
ン・はた)、肩(ケン・かた)、腕(ワン・
うで)、堅(ケン・かたい)、言(ゲン・こと)、満(マン・みちる)、など
○同源語:
音(おと)、物(もの)、部(ふ)、大臣(おほま
へつきみ・君)、楯(たて)、立(たつ)、
【たな(棚・壇・段)】
海
(あま)未通女(をとめ)棚(たな)無(なし)小舟(をぶね)榜(こぎ)出(づ)らし客(たび)の屋取(やどり)に梶(かぢの)音(おと)所レ聞
(きこゆ)(万
930)
天
漢(あまのがは)棚橋(たなはし)渡(わたせ)織女(たなばた)のい渡(わたら)さむに棚橋(たなはし)渡(わたせ)(万2081)
○同源語:
海(あま)、未通女(をとめ・女)、無(なし)、
小(を)、舟(ふね・盤)、出(いづ)、音(おと)、天漢(あまのかは)、棚(たな・壇・段)、渡(わたす)、
【たね(種)】
水
(みづ)を多(おほみ)上(あげ)に種(たね)蒔(まき)比要(ひえ・稗)を多(おほみ)擇擢(えらえ)し業(わざ)ぞ吾(わが)獨(ひとり)宿(ぬる)(万2999)
韻尾の子音[-ng]は調音の方法(鼻濁音)がナ行と同じであり、ナ行
であらわれることがある。
例:常[zjiang]つね、嶺[lieng]みね、梁[liang]やな、胸[hmiong*]むね、舫[piuang]ふね、
○同源語:
蒔(まく・播)、比要(ひえ・稗)、吾(わが)、宿(ぬる・寐)、
【たふ(塔)】
香
(こり)塗(ぬれ)る塔(たふ)に莫(な)依(よりそ)川(かは)隅(くま)の屎鮒(くそふな)喫有(はめる)痛(いたき)女(め)奴(やつこ)(万3828)
大
海(おほうみ)に嶋(しま)も不レ在
(あらなく)に海原(うなばらの)絶(たゆ)塔(たふ)浪(なみ)に立有(たてる)白雲(しらくも)(万1089)
二番目歌の「絶塔(たゆたふ)浪(なみ)」は訓
というよりはむしろ音表記であろう。
○同源語:
香(こり)、塗(ぬ)る、莫(な)、依(よる・
寄)、川(かは・河)、鮒(ふな・付魚)、痛(いたき)、女(め)、海(うみ)、嶋(しま・洲)、原(はら)、絶(たゆ・断)る、浪(なみ)、立(た
つ)、雲(くも)、
【たふ(堪)】
吾
(わが)郷(さと)に今(いま)咲(さく)花(はな)の娘部四(をみなへし)不レ堪
(たへぬ)情(こころ)に尚(なほ)戀(こひ)にけり(万2279)
○同源語:
吾(わが)、今(いま)、咲(さく)、花(は
な)、娘部四(をみなへし・女)、情(こころ・心)、
【たまる(渟)】
御
(み)佩(はかし)を 劔(つるぎ)の池(いけ)の 蓮(はちす)葉(ば)に 渟有(たまれる)水(みづ)の 徃方(ゆくへ)無(なみ)、、(万3289)
ひ
さかたの雨(あめ)も落(ふら)ぬか蓮荷(はちすば)に渟在(たまれる)水(みづ)の玉(たま)に似有(にたる)将レ見
(みむ)(万
3837)
古代中国語の「渟」は渟[dyeng]である。韻尾の[-ng]は[-m]と調音の方法が同じであり転移しやすい。日本語の
渟(たまる)は上古中国語の「渟」と同源であろう。
また、停[dyeng]は日本語では停「とまる」である。渟(たまる)、
停(とまる)は同系のことばであろう。
○同源語:
御(み)、佩(はく)、劔(つるぎ)、蓮(はち
す・はす・荷子)、葉(は)、徃(ゆく・往)、方(へ)、無(な)き、落(ふる・降)、似(に)る、見(みる)、
【たる(足・満)】
佛
(ほとけ)造(つくる)真朱(まそほ)不レ足
(たらず)は水(みづ)渟(たまる)池(いけだ)の阿曾(あそ)が鼻上(はなのうへ)を穿(ほ)れ(万3841)
山 振(やまぶき・吹)の立(たち)儀(よそひ)足(たる)山清水(やましみづ)酌(くみ)に雖レ行(ゆかめど)道(みち)の白鳴(しらなく・不知)(万158)
天
地(あめつち) 日(ひ)月(つき)とともに 満(たり)将レ行
(ゆかむ) 神(かみ)の御面(みおも)と 次(つぎ)來(きたる)、、(万220)
朝鮮語では「足」を足(ta-ri)という。日本語の「たる」は朝鮮語の足(ta-ri)と同源であろうともいう。しかし、朝鮮語の足(ta-ri)も日本語の足(たる)も上古中国語音の足[tiok*]と同源である可能性もある。
「満」も満(たる)に用いられている。「満足」
ということばがあるごとく、「満」と「足」は義(意味)が近い。満(たる)は訓借であろう。
○同源語:
佛(ほとけ)、造(つく)る、真(ま)、渟(た
ま)る、田(た)、穿(ほる・掘)、山(やま)、立(たつ)、行(ゆく)、白(しる・知)、天(あめ)、地(つち)、神(かみ)、御(み)、面(おも)、
次(つぐ・續)、來(くる)、
【たる(垂)】
石
(いは)激(ばしる)垂見(たるみ)の上(うへ)の左和良妣(さわらび)の毛要(もえ)出(いづる)春(はる)に成(なりに)けるかも(万1418)
袖
(そで)垂(たれ)て伊射(いざ)吾(わが)苑(その)に鸎(うぐひす)の木傳(こづたひ)令レ落
(ちらす)梅花(うめのはな)見(み)に(万4277)
二番目の歌(万4277)では「令レ落(ちら
す)」のように中国語の語順に従って表記された部分がある。また、「梅花(バイカ)」のように中国語で成句になっているものは「梅(うめ)の花(はな)」
の「の」は省かれていて、表記されていない。語彙に中国語と同源のことばが使われているばかりでなく、表記法もかなり中国語の影響を強く受けている。
○同源語:
毛要(もえ・萌)る、出(いづ)、春(はる)、袖
(そで)、吾(わが)、苑(その)、鸎(鶯(うぐひす・隹)、木(き・枝)、傳(つた)ふ、落(ちる・散)、梅(うめ)、花(はな)、見(みる)、
【たれ(誰)】
水
門(みなとの)葦(あしの)末葉(うらばを)誰(たれか)手折(たをりし)吾(わが)背子(せこが)振(ふる)手(てを)見(みむと)我(われぞ)手折
(たをりし)(万
1288)
○同源語:
葉(は)、手折(たをる)、吾・我(われ)、背子
(せこ)、見(みる)、
【ち(千)】
百
(もも)に千(ち)に人(ひと)は雖レ言
(いふとも)月(つき)草(くさ)の移(うつろふ)情(こころ)吾(われ)将レ持
(もため)やも(万
3059)
「千」の古代中国語音は千[tsyen]である。千[tsyen]の祖語(上古音)は千[tyen*]に近い音価をもっていたものと考えられる。タ行イ
段の音は摩擦音化によってえサ行に転移しやすい。日本語の「ち」は「千」と同源であろう。日本漢字音は千(セン)は唐代の音を規範としたもので、訓の千
(ち)は上古音に依拠している。
同源語:
草(くさ)、情(こころ・心)、吾(われ)、
【ちり(塵・散)】
吾
(わが)岡(をか)のおかみに言(いひ)て令レ落
(ふらしめし)雪(ゆき)の摧(くだけ)しそこに塵(ちり)けむ(万104)
此
(この)夕(ゆふべ)零(ふり)來(くる)雨(あめ)は男星(ひこぼし)の早(はや)滂(こぐ)船(ふね)の賀伊(かい)の散(ちり)かも(万2052)
「塵」の古代中国語音は塵[dien]であり、「塵」の日本漢字音は塵(ジン・ちり)で
ある。タ行のイ段の「ヂ」とサ行のイ段の「ジ」とは音価が近く、現代の日本語では弁別されていない。日本語の「ちり」は中国語の塵[dien]と同源であろう。韻尾の[-n]は調音の位置が[-l]と同じであり、日本語ではラ行に転移することが多
い。
例:雁(ガン・かり)、巾(キン・きれ)、漢(カ
ン・から)、など
「散」の古代中国語音は散[san]である。散[san]が塵[dien]と同じように使われていることから、「散」にほ散[sian]あるいは散[tian]に近い音であったのではないかと推定できる。日本
語の散(ちる)も中国語の散[san]と同系のことばである可能性がある。
○同源語:
吾(わが)、岡(をか・岳)、落・零(ふる・
降)、此(こ)の、夕(ゆふ・夜)べ、來(くる)、星(ほし)、船(ふね・盤)、
【つ(津)】
熟
田津(にぎたづ)に船(ふな)乗(のり)せむと月(つき)待(まて)ば潮(しほ)もかなひぬ今(いま)は許藝(こぎ)乞(いで)な(万8)
奥
浪(おきつなみ)邊波(へなみ)莫(な)越(こしそ)君(きみ)が舶(ふね)許藝(こぎ)可敝里(かへり)來(き)て津(つ)に泊(はつる)まで(万4246)
例:田(た・デン)、千(ち・セン)、邊(へ)、
帆(ほ・ハン)、
○同源語:
田(た)、津(つ)、船・舶(ふね・盤)、乗(の
る)、潮(しほ)、今(いま)、乞(いづ・出)、奥(おき・澳)、浪・波(なみ)、邊(へ)、莫(な)、越(こす)、君(きみ)、可敝里(かへり・還)、
來(くる)、泊(はつ)る、
中国語の韻尾[-n]は日本語では脱落する場合のほか、ナ行・マ行・タ
行・ラ行に転移する場合などがある。マ行は調音の方法が同じ(鼻音)であり、タ行・ナ行は調音の位置が同じであり、音価も近く転移しやすい。古代日本語に
は「ン」で終わる音節はなかった。
(1) 脱落の例:津[tzien] つ、田[dyen] た、眼[ngean] め、千[tsyen] ち、津[tzien] つ、邊[pyen] へ、
(2) ナ行の例:絹[kyuan] きぬ、殿[dyən] との、秈[shean] しね・いね、苑[iuan] その、
(3) マ行の例:浜[pien] はま、肝[kan] きも、君[kiuan] きみ、文[miuən] ふみ、
マ行[-m]とナ行[-n]はいずれも鼻音であり、調音の方法が同じ音は転移
しやす。現代の北京音では韻尾の[-n]と[-m]は弁別されず、[-n]に吸収されててる。
(4) タ行の例:楯[djiuən] たて、幡[phiuan] はた、肩[kyan] かた、堅[kyen] かたい、
タ行[-t]とナ行[-n]は調音の位置が同じ(前口蓋)であり、調音の位置
が同じ音は転移しやすい。唐代に韻尾が[-n]であった漢字のうち去声のものの上古音は[-t*]であったと考えられている。
(5) ラ行の例:漢[xan] から、雁[ngean] かり、猿[hiuan] さる、塵[dien] ちり、
ラ行[-l] とナ行[-l]は調音の位置が同じ(前口蓋)であり、転移しやす
い。しかし、中国語には[-l] で
終わる音節はないから、この転移は日本に来てか
ら起こったことになる。朝鮮漢字音では中国語の韻尾[-t] は規則的に[-l] に転移する。
「音韻変化に例外なし」というのが西欧音韻学、
特に青年文法家と呼ばれる人々の主張である。しかし、これには同じ時代に同じ地方で、しかも同じ音韻環境のなかでという制限がついている。
中国語の音韻史についてみると、時代は数千年に
わたり、地域も長安ばかりでなく、江南、さらには越南、朝鮮半島、日本列島におよび、同じ日本漢字音のなかでも呉音と漢音では絵(カイ・ヱ)というくらい
に違いがある。漢字の同源語はさまざまな時代、さまざまな地域の発音を反映しているので、綿密に検証していく必要がある。
【つか(冢)】
玉
桙(たまほこ)の 道邊(みちのへ)近(ちかく) 磐(いは)構(かまへ) 作(つくれる)冢(つか)を、、、(万1801)
○同源語:
桙(ほこ)、邊(へ)、構(かまへ)る、作(つ
く)る、
【つか(束)】
紅
(くれなゐ)の淺(あさ)葉(ば)の野良(のら)に苅(かる)草(くさ)の束(つか)の間(あひだ)も吾(われ)を忘(わすら)すな(万2763)
夏
野(なつの)去(ゆく)小牡鹿(をしか)の角(つの)の束間(つかのま)も妹(いも)が心(こころ)を忘(わすれ)て念(おもへ)や(万502)
一番目の歌では「間」は間(あいだ)と読み、二
番目の歌(万502)では間(ま)と読にならわしている。
○同源語:
葉(は)、野(の)、苅(かる)、草(くさ)、吾
(われ)、忘(わする)、去(ゆく・行)、小(を)、鹿(しか・猪鹿)、間(ま)、妹(いも)、心(こころ)、念(おもふ)、
【つく・つける(著・着)】
わ
すれ草(ぐさ)吾(わが)下(した)紐(ひも)に著(つけ)たれど鬼(しこ)のしこ草(ぐさ)事(こと・言)にしありけり(万727)
針
(はり)は有(あれ)ど妹(いも)し無(なけれ)ば将レ著(つけめ)やと吾(われ)を令レ煩
(なやまし)絶(たゆる)紐(ひも)の緒(を)(万2982)
○同源語:
草(くさ)、吾(わが)、紐(ひも・絆・繙)、著
(つけ)る、針(はり・箴)、妹(いも)、無(な)き、煩(なやむ・悩)、絶(たゆる)、
【つく(舂・衝・突)】
天
(あま)光(てる)や 日
(ひ)の異(け)に干(ほし) さ
ひづるや 辛
(から)碓(うす)に舂(つき) 庭(にはに)立(たつ) 手碓子(てうす)に舂(つき)、、(万3886)
鮪
(しび)衝(つく)と海人(あま)の燭有(ともせる)伊射里漁火(いさりび)の保尒可(ほにか)将レ出(いでなむ)吾(わ)が下念(したもひ)を(万4218)
○同源語:
天(あめ)、光(てる・照)、干(ほす)、辛(か
ら)、立(たつ)、手(て)、海人(あま)、燭(ともす)、火(ひ)、保(ほ・火)、出(いづ)、吾・我(わが)、念(おもひ)、塩(しほ・潮)、津
(つ)、山(やま)、打(うつ)、越(こえる)、去(ゆく・行)、乗(のる)、馬(うま)、爪(つめ)、家(いへ)、
【つくる(作・造)】
吾
(わが)勢子(せこ)は借廬(かりほ)作(つく)らす草(かや)無(なく)は小松(こまつが)下(もと)の草(かや)を苅(から)さね(万11)
大
夫(ますらを)の伏(ふし)居(ゐ)嘆(なげき)て造有(つくりたる)四垂(しだり)柳(やなぎ)の蘰(かづら)為(せ)吾妹(わぎも)(万1924)
○同源語:
吾(わが)、勢子(せこ・背子)、借(かり・
假)、草(かや)、無(な)き、小(こ)、苅(かる)、伏(ふす)、居(ゐ)る、嘆(なげ)く、四(し・枝)、垂(たれる)、柳(やなぎ)、蘰(かづら・
葛)、妹(いも)、
【つくゑ(机)】
机
(つくゑ)の嶋(しま)の 小螺(しただみ)を い拾(ひりひ)持(もち)來(き)て、、高坏
(たかつき)に盛(もり) 机(つくゑ)に立(たて)て 母(はは)に奉(まつり)つや、、
(万3880)
○同源語:
嶋(しま・洲)、拾(ひりふ)、來(くる)、立
(たて)て、母(はは)、
【つたふ(傳)】
ぬ
ばたまの宵(よ)霧(ぎりに)隠(こもり)遠(とほく)とも妹(いもが)傳(つたへは)速(はやく)告(つげ)こそ(万2008)
○同源語:
宵(夜・よ)、隠(こもる・籠)、妹(いも)、
【つち(土・地)】
吾
(わが)屋前(やど)の花(はな)橘(たちばな)を霍公鳥(ほととぎす)來(き)不レ喧
(なかず)地(つち)に令レ落
(ちらしてむ)とか(万
1486)
徊
徘(たもとほり)徃箕(ゆきみ)の里(さと)に妹(いも)を置(おき)て心(こころ)空(そら)なり土(つち)は蹈(ふめ)ども(万2541)
中国語では音義の近い漢字を併記して成語を作る
ことが多い。「土地」もそのひとつである。
○同源語:
吾(わが)、花(はな)、霍公鳥(ほととぎす・
隹)、來(くる)、喧(なく・鳴)、落(ちる・散)、徃(ゆく・往)、妹(いも)、置(おく)、心(こころ)、
【つつ(筒)】
妹
(いも)がりと馬(うま)に[木
安](く
ら)置(おき)て射駒山(いこまやま)撃(うち)越(こえ)來(くれ)ば紅葉(もみち)散(ちり)筒(つつ)(万2201)
○同源語:
妹(いも)、馬(うま)、置(おく)、射(い
る)、駒(こま)、山(やま)、撃(うつ・打)、越(こえる)、來(くる)、散(ちる)、入(いる・いれる)、中(なか)、
【つつき(都追伎・突)】
机
(つくゑ)の嶋(しま)の 小螺(しただみ)を い拾(ひりひ)持(もち)來(き)て 石(いし)もち 都追伎(つつき)破夫利(やぶり)、、(万3880)
○同源語:
机(つくゑ・卓)、嶋(す・洲)、拾(ひりひ)、
來(くる)、
【つづき(都々伎・續)】
年
月(としつき)は 奈何流々(ながるる)其等斯(ごとし) 等利(とり)都々伎(つづき・續) 意比(おひ・追)久留(くる・来)母能(もの)は、、(万804)
波 利(はり・針)夫久路(ぶくろ・袋)應 婢(お び・帯)都々氣(つづけ・續)ながら 佐刀(さと・里)其等迩(ごとに)、、(万4130)
血
沼(ちぬ)壮士(をとこ) 其夜(そのよ)夢見(いめにみ) 取(とり)次寸(つつき・續) 追(おひ)去(ゆき)ければ、、(万1809)
万葉集で「都々伎(つづき)」、「都都氣(つづ
け)」あるいは「次寸」とあるのは續[ziok] である。「續」の祖語(上古音)は續[diok*] であったと考えられる。古代日本語では濁音が語頭
に来ることはなかったので清音を語頭に添加して(つ+づく)とした。日本語の「つづく」は中国語の「續」と同源である。中国語には「継続」という成句が
あって、繼(つ
ぎ・つぐ)は「續」と義(意味)が近い。
○同源語:
奈何流(なが・流)る、等利・取(取・とり)意比
(おひ・追)、久留(くる・來)、母能(もの・物)、波利(はり・鍼)、都々氣(つづけ・續)、其(そ)の、夜(よ)、夢(いめ)、見(み)る、取(と
る)、次寸(つつき・續)、去(ゆく・行)、妹(いも)、家(いへ)、繼(つぐ・續)、嶋(しま・洲)、嶺(ね)
【つどふ(集)】
あ
どもひて 未通女(をとめ)壮士(をとこ)の 徃(ゆき)集(つど)ひ かがふ嬥謌(かがひ)に 他妻(ひとづま)に 吾(わ)も交(まじはら)む、、、(万1759)
「つどふ」の「ふ」は中国語の韻尾[-p]に対応している。日本語の「つどふ」は中国語の上
古音を継承している。
○同源語:
未通女(をとめ・女)、徃(ゆく・往)、妻(つ
ま・妻女)、吾(わ)、
【つね・とこ(常)】
常
磐(ときは)成(なす)石室(いはむろ)は今(いま)もありけれど住(すみ)ける人(ひと)ぞ常(つね)無(なか)りける(万308)
吾
(わが)御門(みかど)千代(ちよ)常(とこ)とばに将レ榮(さかえむ)と念(おもひ)て有(あり)し吾(われ)し悲(かなし)も(万183)
「常」は常(つね)という訓もある。常(つね)
は[djiang*] の韻尾[-ng]がナ行に転移したものである。日本漢字音の常(ジョウ)は唐代の中国語音であ
る常[zjiang] に唐代の音に依拠している。韻尾の[-ng] はナ行に転移した。[-ng] と[-n] はともに鼻音であり転移しやすい。
[-ng] がナ行であらわれる例:種(たね)、嶺(みね)、
梁(やな)、など
○同源語:
今(いま)、住(すむ)、無(なし)、吾(わ
が)、御(み)、門(かど)、千(ち)、代(よ・世)、榮(さかえ)る、念(おもふ)、
【つま(妻・嬬・夫)】
鴨
(かも)すらも己(おの)が妻(つま)どち求食(あさり)して所レ遺
(おくる)間(あひだ)に戀(こふると)云(いふ)物(もの)を(万3091)
千 早人(ちはやひと)宇治(うぢの)度(わたりの)速レ瀬 (せをはやみ)不レ相 (あはずこそ)有(あれ)後(のちも)我(わが)嬬(つま)(万2428)
若
草(わかくさ)の 夫(つま)か有(ある)らむ 橿實(かしのみ)の 獨(ひとり)か将レ宿(ぬらむ)(万1742)
古代日本語の「つま」は夫からは妻、妻からは夫
を呼ぶことばであった。後に夫から妻を呼ぶにだけ用いられるようになった。
古代中国語の「妻」「嬬」「夫」はそれぞれ妻[tsyei]、嬬[njio]、夫[piua]である。日本語の「つま」は古代中国語の「妻+
嬬」、あるいは「妻+女」から派生したことばであろう。「嬬」上古音は嬬[mjio*]に近い音であり、「女」の上古音は女[mjia*]であったと考えられる。それが、唐代には口蓋化に
よって嬬[njio]、女[njia]になった。
日本語では古代中国語の日母[nj-] がマ行であらわれる例をいくつかあげることができ
る。
例:乙女[njia] をとめ、耳[njiə] みみ、乳[njia] 母 めのと、壬[njiəm] 生 みぶ、燃[njian] もえる、
認[njiən] みとめる、
○同源語:
鴨(かも)、物(もの)、千(ち)、度(わたり・
渡)、相(あふ・合)、我(わが)、嬬(つま・妻嬬)、若(わか)い、草(くさ)、橿(かし・樫)、宿(ぬる・寐)、
【つめ(爪)】
吾
(わが)爪(つめ)は御(み)弓(ゆみ)の弓波受(ゆはず)、、(万3885)
梓 弓(あづさゆみ)爪引(つまびく)夜(よ)音(おと)の遠(とほ)音(おと)にも君(きみ)が御幸(みゆき)を聞(きかく)し好(よし)も(万531)
塩
津山(しほつやま)打(うち)越(こえ)去(ゆけ)ば我(わが)乗有(のれる)馬(うま)そ爪突(つまづく)家(いへ)戀(こふ)らしも(万365)
万葉集では「爪」は爪引(つまびく)、爪突(つ
まづく)などの形でも使われている。古代中国語の「爪」は爪[tzheu] である。日本語の「つめ」の「つ」は中国語の
「爪」であろう。「つ+め」の「め」は小さいものに対する愛称で、中国語の「女」である可能性がある。
○同源語:
吾・我(わが)、御(み)、弓(ゆみ)、夜(よ
る)、音(おと)、君(きみ)、塩(しほ・潮)、津(つ)、山(やま)、打(うち)、越(こえる)、去(ゆく・行)、乗(のる)、馬(うま)、突(つ
く)、家(いへ)、
【つらぬ(列)】
河
上(かはのへ)の列々(つらつら)椿(つばき)都良々々(つらつら)に雖レ見
(みれども)安可受(あかず)巨勢(こせ)の春野(はるの)は(万56)
○同源語:
河(かは)、椿(つばき)、見(みる)、春(はる)、野(の)、
【つり(釣)】
朝
(あさ)開(びらき)滂(こぎ)出(いで)て我(われ)は湯羅(ゆらの)前(さき)釣(つり)為(する)海人(あま)を見(みて)反(かへり)将レ來
(こむ)(万
1670)
縄
(なはの)浦(うら)ゆ背向(そがひ)に所レ見
(みゆる)奥(おきつ)嶋(しま)滂(こぎ)廻(みる)舟(ふね)は釣(つり)為(する)らしも(万357)
中国語の韻尾[ô] がラ行であらわれる例としては、吊[tyô] つる、鳥[tyô] とり、照[tjiô] てる、倒[tô] たおれる、揺[jiô] ゆれる、などをあげることができる。
○同源語:
出(いづ)、我(われ)、湯(ゆ)、
海人(あま)、見(みる)、反(かへる・還)、來(こ)、背(せ・そ)、向(むかふ)、奥(おき・澳)、嶋(しま・洲)、廻(みる)、舟(ふね・盤)、
【つるぎ(劒)】
劒
(つるぎ)太刀(たち)身(み)に取(とり)副(そふ)と夢(いめに)見(み)つ何如(なに)の恠(さが)ぞも君(きみ)に相(あはむ)為(ため)(万604)
高
麗(こま)劒(つるぎ)己(な)が景迹(こころ)故(から)外(よそ)耳(のみに)見(み)つつや君(きみ)を戀(こひ)渡(わたり)なむ(万2983)
日本語の「つるぎ」は中国語の刀[tô]+劒[liam*] に由来することばではなかろうか。「つるぎ」の
「ぎ」は鼻濁音「キ゜」であろう。韻尾の[-m] は[-ng] と調音の方法が同じ(鼻音)であり、転移しやす
い。
○同源語:
太刀(たち・太薙)、身(み)、取(とる)、夢
(いめ)、見(みる)、君(きみ)、相(あふ・合)、高麗(こま)、景迹(こころ・心)、渡(わたる)、
【つゑ(杖)】
天
(あめ)地(つち)の 至(いたれ)るまでに 杖(つゑ)策(つき)も 不レ衝
(つかず)も去(ゆき)て、、(万420)
杖
(つゑ)衝(つき)も不レ衝
(つかず)も吾(われ)は行(ゆか)めども公(きみ)が将レ來
(きまさむ)道(みち)の不レ知
(しらな)く(万
3319)
「杖」の古代中国語音は杖[diang] である。日本語の「つゑ」は「杖」と同源であろ
う。同じ声符をもった漢字に丈[diang]があり、日本漢字音は丈(ジョウ・たけ)である。
「たけ」も丈[diang] と同源であろう。
○同源語:
天(あめ)、地(つち)、至(いたる)、衝(つ
く)、去・行(行・ゆく)、吾(われ)、公(きみ)、來(くる)、知(しる)、
【て(手)】
和
我(わが)勢故(せこ)は多麻(たま)にもがもな手(て)に麻伎(まき)て見(み)つつ由可牟(ゆかむ)を於吉氐(おきて)伊加婆(いかば)乎思(をし)(万3990)
去
来(いざ)兒等(こども)倭(やまと)へ早(はやく)白菅(しらすげ)の真野(まの)の榛原(はりはら)手折(たをり)て将レ歸
(ゆかむ)(万
280)
また、現在のベトナム漢字音は手(thue)で、古い中国語音の痕跡を伝えているものと考えら
れる。日本語の「て」は中国語の「手」と同源であろう。
○同源語:
和我(わが)、勢故(せこ・背子)、手(て)、見
(みる)、由可牟・伊加婆(ゆく・行)、於吉氐(おきて・置)、兒(こ)、菅(すげ)、真(ま)、野(の)、榛(はり)、原(はら)、折(をる)、歸(ゆ
く・行)、
【てら(寺)】
不レ相
念(あひおもはぬ)人(ひと)を思(おもふ)は大寺(おほでら)の餓鬼(がき)の後(しりへ)に額(ぬか)衝(つく)如(ごと)し(万608)
寺
々(てらでら)の女(め)餓鬼(がき)申(まをさ)く大神(おほみわ)の男(を)餓鬼(がき)被害レ給
(たばり)て其(その)子(こ)将レ播(うまはむ)(万3840)
寺(てら)は仏教伝来とともに日本にもたらされ
たものであろう。日本に仏教伝来以前から「やまとことば」に「てら」ということばがあって、その後中国から寺(ジ)ということばが入ってきたとは考えにく
い。
餓鬼(ガキ)は仏教用語で漢語である。古代日本
語では餓(ガ)のような濁音ではじまることばはなかったが、中国語の影響で語頭に濁音のくることばも使われるようになったきた。
○同源語:
相(あひ・合)、念・思(おもふ)、餓鬼(ガ
キ)、額(ぬか)、衝(つく)、女(め)、男(を・雄)、其(そ)の、子(こ)、
【てる(照)】
茜
(あかね)刺(さす)日(ひ)は雖二照
有一(て
らせれど)烏玉之(ぬばたまの)夜(よ)渡(わたる)月(つき)の隠(かく)らく惜(をし)も(万169)
味
酒(うまざけ)三輪(みわ)の祝(はふり)の山(やま)照(てらす)秋(あき)の黄葉(もみぢ)の散(ちら)まく惜(をし)も(万1517)
○同源語:
刺(さす)、照(てる)、夜(よる)、渡(わた
る)、隠(かくれ)る、味(うま)、酒(さけ)、三(み)、山(やま)、散(ちる)、
【とこ(床)】
彼
方(をちかた)の赤土(はにふの)少屋(をや)にこさめ零(ふり)床(とこ)さへ所レ沾
(ぬれぬ)於レ身
(みに)副(そへ)我妹(わぎも)(万2683)
蟋
蟀(こほろぎ)の吾(わが)床(とこの)隔(へ)に鳴
(なき)つつもとな起(おき)居(ゐ)つつ君(きみ)に戀(こふる)に宿(いね)不レ勝
(かてなく)に(万
2310)
「床」には床(ゆか)という読みもある。床(ゆ
か)は頭音が脱落したものである。
○同源語:
少(を)、零(ふる・降)、沾(ぬれる・)、身
(み)、我・吾(わが)、妹(いも)、隔(へ・邊)、鳴(なく)、起(おき)る、居(ゐ)る、君(きみ)、宿(いぬ・寐)、
【とし(利)】
劔
刀(つるぎたち)諸刃(もろはの)利(ときに)足(あし)蹈(ふみて)死々(しなばしなむよ)公(きみに)依(よりては)(万2498)
日本語で「リ」という音が語頭にくるようになっ
たのは外来語の影響で、轆轤(ろくろ)など当時の文明の利器とともに入ってきた。万葉集ではラ行ではじまることばが使われているのは「力士儛」だけであ
る。
○同源語:
劔(つるぎ)、刀(たち・刀薙)、死
(し)ぬ、公(きみ)、依(よ)る、神(かみ)、力士(リキシ)、儛(まひ)、鷺(さぎ・鵲)、桙(ほこ)、飛(とび)、渡(わたる)、
【とどむ・とどまる(停・留)】
離レ家
(いへさかり)います吾妹(わぎも)を停(とどめ)かね山(やま)隠(かくし)つれ情神(こころど)もなし(万471)
嶋
(しま)傳(づたひ) い別(わかれ)徃(ゆか)ば 留有(とどまれる) 吾(われ)は幣(ぬさ)引(ひき) 齊(いはひ)つつ 公(きみ)をば将レ待(ま
たむ) 早(はや)還(かへり)ませ(万1453)
古代っ中国語の「停」は停[dyeng] である。古代日本語は濁音が語頭に立つことがな
かったのでと清音を添加して「と+どむ」とした。韻尾の[-ng] は調音の方法が[-m] と同じなので、ま行に転移しやすい。
「留」の古代日本語音は留[liu]である。古代日本語にはラ行で始まる音節がなかっ
たので[l-]はタ行に転移した。[l-] と[t-] は調音の位置が同じ(前口蓋)であり、転移しやす
い。
中国語では音義の近いことばを重ねて成句をつく
ることがある。停留なども「停」と「留」を重ねている。停[dyeng]と留[liu]は同義であり、[d-] と[l-] は調音の位置が同じであるため、音価も近い。
○同源語:
家(いへ)、吾(われ)、妹(いも)、山(やま)、隠(かく)す、情(こころ・心)、嶋(しま・洲)、傳(つた)ふ、往(ゆく・行)、公(きみ)、還(か
へる)、
【との(殿)】
つ
れも無(なき) 城上(きのへの)宮(みや)に 大殿(おほとの)を 都可倍(つかへ)奉(まつり)て 殿(との)隠(こもり) 隠(こもり)座(いま
せ)ば、、(万
3326)
古代中国語の君[giuən] は古代日本語では君(きみ)になり、殿[dyən] は殿(との)になった。君(きみ)も殿(との)も
語源は中国語である。
○同源語:
無(な)き、宮(みや)、隠(こも
る)、
【とほる(通)】
石
(いはほ)すら行應レ通
(ゆきとほるべき)建男(ますらをも)戀(こひと)云(いふ)事(ことは)後(のちの)悔(くい)在(あり)(万2386)
隱
處(こもりどの)澤泉(さはいづみ)在(なる)石根(いはねゆも)通(とほして)念(おもふ)吾(わが)戀(こふらく)は(万2443)
有氣音がハ行音であらわれる例:禿[thuk] はげ、恥[thiə] はぢ、唾[thuai] つば、透[thu] とほる、
韻尾[-ng]がラ行であらわれる例:幌[huang] ほろ、平[bieng] ひら、軽[kieng] かるい、
広[kuang] ひろい、乗[djiəng] のる、凝[ngiəng] こる、
○同源語:
行(ゆく)、男
(を・雄)、悔(くい)、隠(こも
る)、泉(いづみ)、根(ね)、念(おもふ)、吾(わが)、
【とむ(止・留)】
御
(み)立為(たたし)の嶋(しま)を見(みる)時(とき)にはたづみ流(ながるる)涙(なみだ)止(とめ)そかねつる(万178)
打
(うち)日(ひ)指(さす)宮(みや)に行(ゆく)兒(こ)を真(ま)悲(かなし)み留(とむれ)ば苦(くるし)やれば為便(すべ)無(なし)(万532)
「留」の古代中国語音は留[liu]である。古代日本語ではラ行音が語頭に立つことが
なかったため、留[liu]はタ行に転移した。留[liu]と止[tiə*]は頭音の調音の位置が同じ(歯茎の裏)であり、音
価も近い。日本語の「とむ」は「止」「留」と同系のことばであろう。しかし、音韻の対応は不十分である。
日本語の「とむ」「とまる」にあたることばに
「停」があり、中国語には「停止」という成句もある。「停」の古代中国語音は停[dyeng]である。日本語の「とむ」「とまる」は「停」と音
義ともに近い。日本語の「とむ」は停[dyeng]と同源であろう。
中国語の韻尾[-ng]がマ行であらわれる例:澄[diəng] すむ、灯[təng] ともる、公 きみ、
弓[kiuəng] ゆみ、霜[shiang] しも、醒[syeng] さめる、鏡[kyang] かがみ、
○同源語:
御(み)、立(たつ)、嶋(しま・洲)、見(み
る)、時(とき)、流(ながる)、打(うつ)、指(さ)す、宮(みや)、行(ゆく)、兒(こ)、真(ま)、苦(くる)し、無(な)し、
【ども(等・等母)】
山
邊(やまのへ)の御井(みゐ)を見(み)がてり神風(かむかぜ)の伊勢(いせ)處女(をとめ)等(ども)相(あひ)見(み)つるかも(万81)
父
母(ちちはは)は 枕(まくら)のかたに 妻子(めこ)等母(ども)は 足(あと)の方(かた)に 圍(かくみ)居(ゐ)て、、(万892)
「等」には等(たち)、等(ら)という読みもあ
る。意味はいずれも複数をあらわすものである。等(ら)は等[təng] の頭音[t-] がラ行に転移したものである。[t-] と[l-] は調音の位置が同じ(歯茎の裏)であり、転移しや
すい。等(たち)はやはり等[təng] の転移したものであろう。
古 (いにしへ)の七(ななの)賢(さかしき)人(ひと)等(たち)も欲(ほり)為(せし)物(もの)は酒(さけ)にし有(ある)らし(万340)
嗚
呼(あ)見(み)の浦(うら)に船乗(ふなのり)為(す)らむ[女
感]*嬬
(をとめ)等(ら)が珠裳(たまも)の須十(すそ・裾)に四寶(しほ・潮)三都(みつ・満)らむか(万40)
山(やま)、邊(へ)、御(み)、見(みる)、神
(かみ)、處女・[女感]*嬬(をとめ・女)、相(あふ・合)、母(はは)、
妻子(めこ・女子)、居(ゐ)る、賢(さか)し、物(もの)、酒(さけ)、船(ふね・盤)、乗(のる)、四寶(しほ・潮)、三都(みつ・満)、
【ともす(燈・燭)】
燈
(ともしび)の陰(かげ)にかがよふ虚蝉(うつせみ)の妹(いも)が笑(ゑ)まひし面影(おもかげ)に所レ見
(みゆ)(万
2642)
鈴
寸(すずき)取(とる)海部(あま)の燭火(ともしび)外(よそに)だに不レ見
(みぬ)人(ひと)故(ゆえ)に戀(こふる)比日(このころ)(万2744)
日本語の「ともす」の「も」は燈[təng]の韻尾[-ng] である。古代中国語の韻尾[-ng]は調音の方法が[-m]と同じ鼻音であり、転移することが多い。
例: 霜[shiang] しも、状[dziang] さま、停[dyeng] とまる、澄[dtəng]
すむ、公[kong] きみ、
日本語の「ともる」には点[tyam]も使われることもある。日本語の「ともす」は中国
語の「燈」「燭」「点」と同系のことばであろう。
○同源語:
陰・影(かげ)、蝉(せみ)、妹(いも)、面
(おも)、見(みる)、取(とる)、海部(あま)、此(こ)の、
【とら(虎・寅)】
韓
國(からくに)の 虎(とらと)云(いふ)神(かみ)を 生取(いけどり)に 八頭(やつ)取(とり)持(もち)來(き) 其(その)皮(かは)を 多々
弥(たたみ)に刺(さし)、、
(万
3885)
吹
(ふき)響(なせ)る 小角(くだ)の音(おと)も 敵(あた)見有(みたる) 虎(とら)か叫吼(ほゆる)と 諸人(もろびと)の 恊(おびゆ)るまで
に、、(万
199)
古代中国語の「虎」は虎[xa] で、その吼える声によって虎[xa] と呼ばれたものと思われる。 虎は日本にはいない
動物だから、日本に「とら」という「やまとことば」があったとは考えにくい。
朝鮮語では「とら」は虎(ho-rang-i) である。朝鮮半島には虎が生息していて(ho-rang-i) の(ho) は中国語の虎[xa] と対応している。
大槻文彦は『言海』のなかで、「虎 朝鮮語ナラ
ムカ、人ヲ捕ル意ノ名トイフハイカガ。或云、支那ニテ、楚人、虎を於莵(オト)トイフ、於ハ發聲ニテ、〔越ノ於越ノ如
シ〕其莵を傳ヘテ、らノ助語ヲ添ヘテイヘルナリト云、此ノ説モ附會ナラムカ。」としている。
十二支に寅[jien]があって「とら」と読む。「寅」の祖語(上古音)
は寅[djien*] であった可能性がある。董同龢の『上古音韻表稿』
による「寅」の上古音は寅[djien*]であるという。日本語の「とら」は「寅」に関係の
あることばである可能性がある。
○同源語:
韓(から)、國(くに)、神(かみ)、生(いき
る)、取(とる)、來(くる)、多々弥(たたみ・畳)、刺(さ)す、音(おと)、見(みる)、叫吼(ほゆ)る、
【とり(鳥)】
淡
海(あふみ)の海(み) 夕浪(ゆふなみ)千鳥(ちどり) 汝(なが)鳴(なけ)ば 情(こころ)もしのに 古(いにしへ)所レ念
(おもほゆ)(万
266)
鳥[tyô]の韻尾[ô]は時代を遡れば鳥[tyôk*] に近い音であった。董同龢は『上古音韻表稿』で
「鳥」の祖語を鳥[tiog*]と再構している。鳥(とり)の「り」は上古音の韻
尾[-k] が転移したものであろう。
韻尾[ô]がラ行であらわれる例:倒[tô] たおれる、到[tô] いたる、
韻尾[-k*]がラ行であらわれる例:腹[piuk] はら、殻[khək] から、夜[jyak] よる、色[shiək] いろ、
織[tjiək] おる、赦[sjyak] ゆるす、など
○同源語:
海(うみ)、浪(なみ)、汝(な)、鳴(なく)、
情(こころ・心)、念(おもふ)、
【とる(取・執)】
不
レ開有(さかざり)し 花(はな)も佐家(さけ)れど 山(やま)を茂(しげみ) 入(いり)ても不レ取
(とらず) 草(くさ)深(ふかみ) 執(とり)ても不レ見
(みず)、、、(万
16)
伊
勢(いせの)海(うみ)の白水郎(あま)の嶋津(しまつ)が鰒玉(あはびたま)取(とり)て後(のち)もか戀(こひ)の将レ繁
(しげけむ)(万
1322)
「取」と同じ声符をもつ撮[tsuat] は韻尾に[-t] があり、「取」の祖語(上古音)にも取[tiot*] のような入声韻尾[-t]があった可能性がある。「とる」の「る」は中国語
の韻尾[-t]あるいは[-p]の転移したものである。
韻尾[-p]の転移例:汁[tjiəp] しる、入[njiəp] いる、貼[thiəp] はる、摺[tjiəp] する、
韻尾[-t]の転移例:出[thjiuət] でる、拂[piuət] はらふ、掘[giuət] ほる、擦[tsheat] する、
惚 [xuət] ほれる、括[kuat] くくる、
○同源語:
開・佐家(さく・咲)、花(はな)、山(やま)、
入(いる)、草(くさ)、見(みる)、海(うみ)、白水郎(あま・海人)、嶋(しま・洲)、津(つ)、
【た行のまとめ】
日本漢字音でサ行であらわれる漢字のなかには訓 がタ行であらわれるものが多い。日本語のタ行音は隋唐の時代に摩擦音化が起こるする以前の上古音の痕跡を留めている。
1.古代中国語の頭音が[t-][d-][th-]の例:
竹[tiuk] たけ、太刀(たち<刀[tô]薙[thyei]>)、塔[təp] たふ、堪[khəm/təm] たふ、冢[tiong] つか、
著[tia/diak] つく、卓[teôk] つくえ、釣[tyô] つり、等[təng] ども・ら、燈[təng]・燭[tiok] ともす、
鳥[tyô] とり、衝[thjiong] つく、突[thuət] つつく、通[thong] とほる、
田[dyen] た、直[diək] ただ、畳[dyəp] たたみ、段[duan]・壇[dan] たな、種[diong] たね、 渟[dyeng] たまる、塵[dien] ちり、杖[diang] つゑ、着[diak] つく、傳[diuen] つたふ、地[diet] つち、筒[dong] つつ、停[dyeng] とどむ・とどまる、殿[dyən] との、
古代日本語には濁音ではじまることばがなかっ
たため、中国語の原音が[d-]であるものについて は、語頭に清音を添加し
たものがみら
れる。
例:直 ただ、畳 たたみ、傳 つた )、續 つづく、筒 つつ、停 とどまる、
2.古代中国語音が[tz-][dz-]の例:
絶[dziuat/diuat*](ゼツ・たつ・たゆ)、足[tziok/tiok*](ソク・たる)、千[tsyen/tyen*](セン・ ち)、津[tzien] (シン・つ)、作[tzak](サク・つくる)、造[tzuk](ゾウ・つくる)、集[dziəp] (シュウ・つどふ)、妻[tsyei]嬬[nio](サイ・つま)、爪[tzheu](ソウ・つめ)、床[dziang/diang*] (ショウ・とこ)、取[tsio/tio] (シュ・とる)、執[tshiəp/thiəp*](シツ・とる)、
古代中国語音が[tz-][dz-] とされているもののなかには、祖語(上古音)の[t-*][d-*] が摩擦音化した ものがある。日本語の訓は摩擦 音 化する前の形を留めている。これらの漢字の日本漢字音はサ行で あらわれ、訓はタ行 であらわれる。タ行のほうが古い。
3.古代中国語音が[z-][s-]の例:
散[san/tiən*]ちる、續[ziok/diok*]つづく、寺[ziə/diək*]てら、
4.古代中国語音が口蓋化音[tj-][thj-][dj-]、[sj-][zj-]である場合
照[tjiô](ショウ・てる)、止[tjiə](シ・とむ)、楯・盾[djiuən](ジュン・たて)、 束[sjiok/tjiok*] (ソク・つか)、舂[sjiong/tjiong*](ショウ・つく、手[sjiu/tjiu*](シュ・て)、 垂[zjiuai/djiuat*](ス イ・たる・たれる)、誰[zjiəi/djiət*](スイ・だれ)、常[zjiang/djiang*](ジョウ・ つね・とこ)、 時[zjiə/diək*](ジ・とき)、寅[jien/djien*](エン・とら)、
これらの漢字の日本漢字音は音はサ行で、訓 はタ行であらわれる。タ行音は口蓋化する前の中国 語音(隋唐以前の音)の痕跡を留 めている。
5.古代中国語音が[l-]が転移した例:
瀧[liong](リュウ・たき)、龍[liong](リュウ・たつ)、立[liəp](リツ・たつ)、列[liat]・連[lian](レツ・レン・つらぬ)、剣(ケン・レン・つる ぎ、刀[tô] 剣[h(l)iam*])、利[liə](リ・とし)、留[liu](リュウ・とむ・とどむ・とどまる)、
古代日本語にはラ行音が語頭に立つことはなかった ので古代中国語の[l-]は日本語ではタ行に転移した。中国語の[l-]は[t-]と調音の位置が同じであり、音価も近い。
◎な行
【な・なむち(汝)】
淡
海(あふみ)の海(うみ)夕浪(ゆふなみ)千鳥(ちどり)汝(な)が鳴(なけ)ば情(こころ)もしのに古(いにしへ)所レ念
(おおほゆ)(万
266)
石 屋戸(いはやど)に立在(たてる)松(まつの)樹(き)汝(な)を見(みれ)ば昔(むかしの)人(ひと)を相(あひ)見(みる)如(ごと)し(万309)
大
汝(おほなむち)小(すくな)彦名(ひこな)の将レ座
(いましけむ)志津(しづ)の石室(いはや)は幾代(いくよ)将レ経(へぬらむ)(万355)
例:柔弱、強健、窮極、飢餓、読誦、冷涼、境界、
存在、分別、改革、報復、滅亡、
「汝」は万葉集では「なれ」としてあらわれるこ
ともある。
海(うみ)、夕(ゆふ・夜)、浪(なみ)、千鳥
(ちどり)、鳴(なく)、情(こころ・心)、念(おもふ)、立(たつ)、樹(き・枝)、見(みる)、相(あふ・合)、小(すくな)し、名(な)、津
(つ)、幾
(いく)、代(よ・世)、経(へる)、事(こと・言)、君(きみ)、來(くる)、霍公鳥(ほととぎす・隹)、
【な(魚・菜)】
籠
(こ)もよ 美籠(みこ)もち 布久思毛(ふくしも)よ 美夫君志(みぶくし)持(もち) 此(この)岳(をか)に 菜(な)採(つま)す兒(こ)、、(万1)
た らし比賣(ひめ・姫)可尾(かみ・神)の美許等(みこと・命人)の奈(な・魚)都良須(つらす・釣)と美(み・見)多々志(たたし・立)せりし伊志(い し・石)を多礼(たれ・誰)美吉(みき・見)(万869)
伊
勢(いせ)の白水郎(あま)の朝(あさ)魚(な)夕(ゆふ)菜(な)に潜(かづくと)云(いふ)鰒(あはびの)貝(かひ)の獨念(かたもひ)にして(万2798)
「魚」の中国語の魚[ngia] である。中国語の[ng-]は鼻濁音であり、日本語ではナ行またはマ行に転移す
ることが多い。[ng-] は調音の方法が[n-][m-] と同じであり、転移しやすい。
マ行の例:御[ngia] み、
眼[ngean] め、元[ngiuan] もと、迎[ngyang] むかへる、
ナ行の例:額[ngək] ぬか、業[ngiap] なり、偽[ngiuai] にせ、訛[nguai] なまり、
「な+まり」の「まり」は朝鮮語のmal(ことば)である。「魚」は魚(うを)ともいう。
魚(うを)は中国
語の頭音[ng]が[-i-]介音の影響で脱落したものである。「魚」の朝鮮漢
字音は魚(eo)である。
「菜」の古代中国語音は菜[tsə]である。古代中国語の[ts-]は上古中国語の[t-]が摩擦音化したものである可能性がある。古代中国
語音の[ts-]は訓ではタ行またはナ行であらわれるものが多い。
タ行とナ行は調音の位置が同じ(歯茎の裏)である。
タ行の例:作[tzak] つくる、絶[dziuat] たつ、取[tsio] とる、就[dziuk] つく、床[dzhiəng] とこ、
樽[tsuən] たる、
ナ行の例:憎[tzəng] にくむ、漆[tsiet] ぬる、載[tzə] のる、残[dzan] のこる、則[tzək] のり、
蚤[tzu] のみ、
菜(な)もまた、中国語の菜[tsə]と同源である可能性がある。
○同源語:
籠(こ)、美(み・御)、久思・君志(くし・串)、此
(こ)の、岳(をか)、兒(こ)、比賣(ひめ・姫)、可尾(かみ・神)、美許等(みこと・命人)、都良須(つら・釣)す、多々志(たたし・立)、多礼(た
れ・誰)、美吉(みき・見)、白水郎(あま・海女)、夕(ゆふ・夜)、貝(かひ・蛤)、念(おもふ)、
【な(名)】
妹
(いも)が名(な)喚(よび)て 袖(そで)ぞ振(ふり)つる(万207)
劔
(つるぎ)太刀(たち)名(な)の惜(をしけ)くも吾(われ)は無(なし)君(きみ)に不レ相
(あはず)て年の経(へ)ぬれば(万616)
頭音[m-]がナ行に転移した例:鳴[mieng] なく、苗[miô] なへ、猫[miô] ねこ、眠[myen] ねむる、
韻尾[-ng]が脱落した例:黄[huang] き、湯[thang] ゆ、網[miuang] あみ、夢[miuəng] いめ、
方[piuang] へ、
○同源語:
妹(いも)、袖(そで)、劔(つるぎ)、太刀(刀
薙・たち)、吾(われ)、無(な)し、君(きみ)、相(あふ・合)、經(へる)、
【な(勿・莫)】
秋
山(あきやま)に落(おつる)黄葉(もみちば)しましくは勿(な)散(ちり)亂(まがひ)そ妹(いも)が當(あたり)将レ見
(みむ)(万
137)
十 六(しし)待(まつ)如(ごとく) 床(とこ)敷(しき)て 吾(わが)待(まつ)公(きみを) 犬(いぬ)莫(な)吠(ほえ)そね(万3278)
今
日(けふ)耳(のみ)は 目(め)串(ぐし)も勿(な)見(みそ) 事(こと)も咎(とがむ)莫(な)(万1759)
中国語の頭音[m-] は日本語ではナ行であらわれることが多い。[m-] と[n-] は調音の方法が同じであり転移しやすい。
例:名(な)、苗(なへ)、猫(ねこ)、無(な
い)、鳴(なく)、眠(ねむる)、
「勿散り乱れそ」、「莫吠えそね」「勿見そ」は
いずれも係り結びであり、「咎(とが)む莫(な)」は通常の日本語の文法に従ったものである。万葉集の時代の日本語は語彙ばかりでなく、文法も中国語の影
響を受けていた。
最初の歌(万137)の原文と中国語訳と比較し
てみると次のようになる。中国語訳は銭稲孫『萬葉集精選』(中国友誼出版公司)による。簡体字は日本で使っている漢字に合わせて直してある。
日本語で「勿散乱曾」となっているところは中国
語では「且莫乱飛」となっていて、「莫」は動詞の前に置かれている。
[中国語訳] 秋山黄葉 且莫乱飛 我要看 妹子那辺
山(やま)、落(おちる・堕)、葉(は)、散(ち
る)、妹(いも)、當(あたる)、見(みる)、床(とこ)、吾(わが)、公(きみ)、犬(いぬ)、吠(ほえる)、今日(けふ)、目(め)、事
(こと・言)、
【なか(中)】
狭
夜(さよ)深(ふけ)て夜中(よなか)の方(かた)に鬱(おぼぼ)しく呼(よび)し舟人(ふなびと)泊(はてに)けむかも(万1225)
中
々(なかなか)に人(ひと)と不レ有
(あらず)は酒壺(さかつぼ)に成(なりに)てしかも酒(さけ)に染(しみ)なむ(万343)
「中」の古代中国語音は中[tiong] である。語頭の[t-]は[n-]と調音の位置が同じであり転移したものであろう。
韻尾の[-ng] は上古音では[-k*]に近かったと考えられている。日本語の「なか」は
中国語の「中」と同源であろう。
○同源語:
夜(よる)、舟(ふね・盤)、
泊(はつ)、酒(さけ)、染(しむ)、
【ながし(長)】
従レ今
(いまより)は秋風(あきかぜ)寒(さむく)将レ吹
(ふきなむ)を如何(いかにか)獨(ひとり)長(ながき)夜(よ)を将レ宿
(ねむ)(万
462)
ぬ
ばたまの昨夜(きそ)は令レ還
(かへしつ)今夜(こよひ)さへ吾(われ)を還(かへす)莫(な)路(みち)の長手(ながて)を(万781)
語頭の[d-]がナ行に転移した例:濁[diok] にごる、塗[do] ぬる、鈍[duən] にぶい、乗[djiəng] のる、
陳[dien] のべる、など
唐代の韻尾の[-ng] は唐代以前には[-k] に近かったと考えられている。中国語の韻尾[-ng] は訓ではカ行であらわれることが多い。
韻尾の[-ng]がガ行で現われる例:影[kyang*] かげ、塚[tiong] つか、楊[jiang] やぎ・やなぎ、
清[tsyeng] すがし、鳴[mieng] なく、咲[siong] さく、双六[sheong-] すごろく、相模・さがみ、
○同源語:
今(いま)、如何(いか)に、夜(よ)、宿(ね・
寐)る、還(かへ)す、莫(な)、今夜(こよひ)、吾(われ)、手(て)、
【ながる(流)】
石
走(いはばしり)たぎち流(ながる)る泊瀬河(はつせがは)絶(たゆる)事(こと)無(なく)またも來(き)て将レ見
(みむ)(万
991)
妹
(いも)が名(な)は千代(ちよ)に将レ流
(ながれむ)姫嶋(ひめしま)の子松(こまつ)が末(うれ)に蘿(こけ)生(むす)までに(万228)
例:梨[liet] なし、浪[liang] なみ、練[lian] ねる、
朝鮮語でもやはり、語頭に[l-]が立つ音節はないので、朝鮮漢字音では、[l-] は[n-] に転移し、[l-] のあとに[-i-] 介音を伴うときには規則的に[l-] は脱落する。
「な+がる」の「が」は上古中国語の韻尾の痕跡
を留めているものと思われる。董同龢は「流」の上古音を流[liog*] と再構している。また、王力は『同源字典』のなか
で捜[shiu]・索[sheak]、柔[njiu]・弱[njiôk]、報[pu]・復[biuk] はそれぞれ同源だとしている。日本語の「ながる」
は中国語の流[liu] と同源であろう。
○同源語:
泊(はつ)、河(かは)、絶(たゆ
る)、無(な)く、來(くる)、見(みる)、妹(いも)、名(な)、千(ち)、代(よ・世)、姫(ひめ)、嶋(しま・洲)、子(こ・小)、
【なく・なる(鳴)】
鸎
の 生卵(かひご)の中(なか)に 霍公鳥(ほととぎす) 獨(ひと)り所レ生
(うまれて) 己(な)が父(ちち)に 似(に)ては不レ鳴
(なかず) 己(な)が母(はは)に 似(に)ては不レ鳴
(なかず) 宇(う・卯)の花(はな)の 開有(さきたる)野邊(のべ)ゆ 飛(とび)び翻(かけ)り 來(き)鳴(な)き令レ響
(とよもし)、、(万
1755)
赤
根(あかね)刺(さす) 晝(ひる)はしみらに ぬばたまの 夜(よる)はすがらに 此(この)床(とこ)の ひしと鳴(なる)まで 嘆(なげき)つるか
も(万
3270)
○同源語:
鸎(鶯・うぐひす・隹)、中(なか)、霍公鳥(ほ
ととぎす・隹)、似(に)る、母(はは)、宇(う・卯)、花(はな)、開(さく・咲)、野(の)、邊(へ)、飛(とび)、來(くる)、根(ね)、刺(さ)
す、夜(よる)、此(こ)の、床(とこ)、嘆(なげく)、
【なげく(嘆・歎)】
大
夫(ますらを)や片戀(かたこひ)将レ為
(せむと)嘆(なげ)けども鬼(しこ)の益卜雄(ますらを)尚(なほ)戀(こひ)にけり(万117)
秋
山(あきやま)の 木葉(このは)を見(み)ては 黄葉(もみち)をば 取(とり)てぞしのふ青(あをき)をば 置(おき)てぞ歎(なげ)く、、(万16)
中国の音韻学者王力は『同源字典』のなかで「暮[mak] と晩[mian] は同源である。幕[mak] と幔 [muan] は同源である。」(p.293)としている。嘆・歎[than] については触れていないが、韻尾の[-n] と[-k] が転移することがあるとすれば、。嘆・歎[thak*] の韻尾が日本語でカ行にあらわれても不思議はな
い。日本語の「なげく」は「嘆」「歎」と同源である可能性がある。
○同源語:
大夫・益卜雄(ますらを・雄)、山(やま)、木
(き・枝)、葉(は)、見(みる)、取(とる)、置(おく)、
【なし(無)】
浦
(うら)も無(なく)去(いに)し君(きみ)故(ゆゑ)朝(あさな)旦(あさな)もとなそ戀(こふる)相(あふ)とは無(なけ)ど(万3180)
秋
津野(あきづの)に朝(あさ)居(ゐる)雲(くも)の失(うせ)去(ゆけ)ば前(きのふ)も今(けふ)も無(なき)人(ひと)所レ念
(おもほゆ)(万
1406)
二番目の歌(万1406)は原文では「無人所念」と表記されて
いる。無[miua] は亡[miuang] と同系のことばであり、「亡き人思ほゆ」である。
日本語の「なし」は中国語の「無」と同源であ
る。勿[miuə](な)、莫[mak](な)も無[miua]と音が近く、「無」と同じ意味に使われる。
○同源語:
無(な)く、君(きみ)、相(あふ・合)、津
(つ)、野(の)、居(ゐ)る、雲(くも)、去(ゆく・行)、今(けふ)、念(おもふ)、
【なし・梨】
露
(つゆ)霜(しも)の寒(さむき)夕(ゆふべ)の秋風に黄葉(もみち)にけらし妻(つま)梨(なし)の木(き)は(万2189)
十
月(かむなづき)之具礼(しぐれ)の常(つね)か吾(わが)世古(せこ)が屋戸(やど)の黄葉(もみちば)可レ落
(ちりぬべく)所レ見
(みゆ)(万
4259)
右
の一首は少納言大伴宿祢家持、當時(そのかみ)矚二梨
黄葉一(な
しのもみちをみて)作二此
歌一(こ
のうたをつくれり)。
朝鮮漢字音の例:浪(nang)、龍(nong)、楽天(nak-cheon)、洛陽(nak-yeong)、来年(nae-nyeon)、
労働(no-dong)、冷房(naeng-bang)、冷麺(naeng-myeon)、緑茶(nok-cho)、
日本語の「なし」は「梨子」と同源であろう。
○同源語:
霜(しも)、夕(ゆふべ・夜)、妻(つま・妻
女)、木(き・樹)、常(つね)、吾(わが)、世古(せこ・背子)、葉(は)、落(ちる・散)、見・矚(みる)、此(こ)の、作(つく)る、
【なづ(撫)】
老
人(おひひと)も 女(をみな)童兒(わらは)も しが願(ねがふ) 心(こころ)だらひに 撫(なで)賜(たまひ) 治(をさめ)賜(たまへ)ば、、、(万4094)
○同源語:
女(をみな)、願(ねがふ)、心(こころ)、
【なびく(靡)】
海
若(わたつみ)の奥(おき)津(つ)玉藻(たまも)の靡(なびき)将レ寐
(ねむ)早(はや)來(き)座(ませ)君(きみ)待(また)ば苦(くるし)も(万3079)
阿 騎(あき)の野(の)に宿(やどる)旅人(たびびと)打(うち)靡(なびき)寐(い)も宿(ね)らめやも古部(いにしへ)念(おもふ)に(万46)
「靡」の古代中国語音は靡[miai] である。古代日本語では鼻濁音である[m-] は語頭に来にくかったようで、語頭に母音を添加し
たり、靡(な+びく)のように鼻音を重ねたものであろう。ナ行とマ行はいずれも鼻音であり転移しやすい。
鼻音を重ねた例:南[nəm](ナン・みなみ)、眠[myen](ミン・ねむる)、免[mian](メン・
まぬがる)、
マ行とナ行の交替例:無[miua](ム・ない)、苗[miô](ビョウ・なえ)、猫[miô](ビョウ・ねこ)、
鳴[mieng](メイ・なく)、名[mieng](メイ・な)、
海若(わたつみ)、奥(おき・澳)、津(つ)、
寐・寝(ね)る、來(くる)、君(きみ)、苦(くる)し、野(の)、打(うつ)、念(おも)ふ、
【なへ(苗)】
三
嶋(みしま)菅(すげ)未(いまだ)苗(なへ)なり時(とき)待(また)ば不レ著
(きず)や将レ成
(なりなむ)三嶋(みしま)菅笠(すげがさ)(万2836)
○同源語:
三(み)、嶋(しま・洲)、菅(すげ)、未(いま
だ)、時(とき)、著(きる)
【なみ(浪・瀾・波)】
奥
浪(おきつなみ)邊波(へなみ)雖レ立
(たつとも)和我(わが)世故(せこ)が三船(みふね)の登麻里(とまり)瀾(なみ)立(たた)めやも(万247)
明
(あけ)來(くれ)ば 浪(なみ)こそ來(き)依(よれ) 夕(ゆふ)去(され)ば 風(かぜ)こそ來(き)依(よれ) 浪(なみ)の共(むた) 彼
(か)依(より)此(かく)依(よる) 玉藻(たまも)成(なす) 靡(なび)き吾(わが)宿(ね)し、、(万138)
韻尾[-ng]がマ行であらわれる例:公[kong] きみ、霜[siang] しも、鏡[gyang] かがみ、澄[diəng] すむ、
醒[tsyeng] さめる、停[dyeng] とまる、燈[təng] ともす、嘗[zjiang] なめる、など
韻尾[-n]がマ行であらわれる例:浜[pien] はま、君[giuən] きみ、文[miuən] ふみ、肝[kan] きも、
天[thyen] あめ、呑[thən] のむ、など
波(なみ)は「波浪」などの成句もあり、「浪」
と同義である。
○同源語:
奥(おき・澳)、邊(へ)、立(たつ)、和我・吾
(わが)、世故(せこ・背子)、三(み・御)、船(ふね・盤)、登麻里(とまり・停)、來(くる)、依(よ・寄)る、夕(ゆふ・夜)、此(かく)、靡(な
び)く、宿(ね・寐)し、
【なむ(嘗)】
中
々(なかなか)に人(ひと)とあらずは酒壺(さかつぼ)に成(なり)にてしかも酒(さけ)に染(しみ)嘗(なむ)(万343)
吉
野川(よしのがは)河浪(かはなみ)高(たか)み多寸(たき)の浦(うら)を不レ視(みず)か成(なり)嘗(なむ)戀(こひ)しけまくに(万1722)
語頭の[dj-][di-] がナ行であらわれる例:乗[djieng] のる、縄[djieng] なは、述[djiuət] のべる、
長[diang] ながい、陳[dien] のべる、中[tiuəm] なか、など
○同源語:
中(なか)、酒(さけ)、染(しむ)、野(の)、
川・河(かは)、浪(なみ)、多寸(たき・瀧)、視(みる・見)、
【なやむ(煩・脳)】
針
(はり)は有(あれ)ど妹(いも)し無(なけれ)ば将レ著
(つけめ)やと吾(われ)を令レ煩
(なやまし)絶(たゆる)紐(ひも)の緒(を)(万2982)
○同源語:
針(はり・箴)、妹(いも)、無(な)き、著(つ
ける)、吾(われ)、絶(たゆる)、紐(ひも・絆・繙)、
【なり(業・産業)】
吾
妹兒(わぎもこ)が業(なり)と造有(つくれる)秋田(あきのた)の早穂(わさほ)の蘰(かづら)雖レ見
(みれども)不レ飽
(あかぬ)かも(万
1625)
荒
雄(あらを)らは妻子(めこ)の産業(なり)をば不レ念
(おもはず)ろ年(とし)の八歳(やとせ)を待(まて)ど來(き)不レ座
(まさず)(万
3865)
語頭の[ng-]がナ行であらわれる例:魚[ngia] な、額[ngək] ぬか、偽[ngiuəi] にせ、贋[ngean] にせ、
願 [ngiuan] ねがふ、訛[nguai] なまり、
韻尾の[-p]がラ行であらわれる例:入[njiəp] いる、摺[ziuəp] する、汁[tjiəp] しる、執[tiəp] とる、など
○同源語:
吾妹兒(わぎもこ)、造(つく)る、田(た)、穂
(ほ)、蘰(かづら・葛)、見(みる)、荒(あれ)る、雄(を)、妻子(めこ・女子)、念(おもふ)、来(くる)、
【に(丹)】
山
跡(やまと)の宇陀(うだ)の真赤土(まはに)のさ丹(に)著(つか)ばそこもか人(ひと)の吾(われ)を言(こと)将レ成
(なさむ)(万
1376)
さ
丹(に)塗(ぬりの) 大橋(おほはし)の上従(うへゆ) 紅(くれなゐの) 赤裳(あかも)數十(すそ・裾)引(ひき)、、(万1742)
○同源語:
真(ま)、著(つく)、吾(われ)、言(こと)、
塗(ぬる)、赤(あか)い、
【にき・にこ(柔・和)】
靡
相(なびかひ)し 嬬(つま)の命(みこと)の たたなづく 柔膚(にきはだ)すらを 劔刀(つるぎたち) 於レ身
(みに)副(そへ)不レ寐
(ねね)ば ぬばたまの 夜床(よとこ)も荒(ある)らむ、、(万194)
所レ射
(いゆ)鹿(しし)をつなぐ河邊(かはべ)の和草(にこぐさの)身(み)の若(わか)かへにさ宿(ね)し兒(こ)らはも(万3874)
「にこ」には「和」も使われている。「和」の古
代中国語音は和[huai] であり、日本語の「にこ」とは音が対応していな
い。しかし、「柔和」ということばもあるごとく「柔」と「和」は意味が近い。「和」と書いて「にこ」と読むのは借訓である。
○同源語:
靡(なび)く、相(あふ・合)、嬬(つま・妻
嬬)、命(みこと・命人)、劔(つるぎ)、刀(たち・刀薙)、身(み)、寐(ね)る、夜(よる)、床(とこ)、荒(あれ)る、射(い)ゆ、河(かは)、邊
(へ)、草(くさ)、若(わか)き、宿(ねる・寐)、兒(こ)、
【にごる(濁)】
驗
(しるし)無(なき)物(もの)を不レ念
(おもはず)は一坏(ひとつき)の濁酒(にごれるさけ)を可レ飲
(のむべく)有(ある)らし(万
338)
價
(あたひ)無(なき)寶(たから)と言(いふ)とも一坏(ひとつき)の濁酒(のごれるさけ)に豈(あに)益(まさ)めやも(万345)
○同源語:
無(な)き、物(もの)、念(おもふ)、酒(さ
け)、飲(のむ・呑)、
【にる(似)】
痛
(あな)醜(みにく)賢(さか)しらを為(す)と酒(さけ)不レ飲
(のまぬ)人(ひと)をよく見(み)ば猿(さる)にかも似(にる)(万344)
吾
妹兒(わぎもこ)が家(いへ)の垣内(かきつ)の佐由理(さゆり)花(ばな)由利(ゆり)と云(いへる)は不欲(いなと)云(いふ)に似(にる)(万1503)
古代中国語音韻史の研究者は数少ないが、それぞ
れ研究者によって古代中国語語音の復元のしかたは違う。似(にる)の場合は似[diəg*]→[ziə] とする説に説得力がありそうである。
○同源語:
賢(さか)し、酒(さけ)、飲(のむ・呑)、見
(みる)、猿(さる)、吾妹兒(わぎもこ)、家(いへ)、花(はな)、
【にる(煑)】
春
日野(かすがの)に煙(けぶり)立(たつ)所レ見
(みゆ)[女
感]*
嬬
(をとめ)らし春野(はるの)の菟芽子(うはぎ)採(つみ)て煑(に)らしも(万1879)
例:灘[than] なだ、脱[thuat] ぬぐ、沾[tham] ぬれる、呑[thən] のむ、
煑[thya]は茹[njia]とも音義ともに近い。茹[njia] は「ゆでる」に使われる。日本語の「ゆでる」は茹[njia]の頭音が脱落したものである。
○同源語:
野(の)、煙(けむり)、立(たつ)、見(み
る)、[女感]*嬬(をとめ・嬬・女)、春(はる)、芽子(は
ぎ)、
【ぬ・ね(寐・睡・宿)】
紫
(むらさき)の名高(なだかの)浦(うら)の愛子(まなご)地(つち)袖(そで)耳(のみ)觸(ふれて)不レ寐
(ねず)か将レ成
(りなむ)(万
1392)
人
(ひとの)寐(ぬる) 味眠(うまいは)不レ睡
(ねず)て 大舟(おほふね)の 徃
(ゆ
く)ら行(ゆく)らに 思(おもひ)つつ 吾(わが)睡(ぬる)夜(よ)らを 讀(よみ)も将レ敢
(あへむ)かも(万
3274)
夕
霧(ゆふぎり)に衣(ころも)は沾(ぬれ)て 草枕(くさまくら) 旅宿(たびね)かも為(す)る 不レ相(あはぬ)君(きみ)故(ゆゑ)、、(万194)
「ねる」は母音が添加されて「いぬ」という形で
あらわれることがある。寐[muət] の前に母音が添加されたもので、馬(うま)、梅
(うめ)などに見られるものと同じである。
名(な)、子(こ)、地(つち)、袖(そで)、寐
(ね)る、味(うま)し、舟(ふね・盤)、徃・行(ゆく)、思(おもふ・念)、吾(わが)、夜(よる)、夕(ゆふ・夜)、沾(ぬれ・濡)る、草(くさ)、
相(あふ・合)、君(きみ)、床(とこ)、隔(へ・邊)、鳴(なく)、起(おき)る、居(ゐ)る、
【ぬか(額)】
肥
人(こまひと)の額(ぬか)髪(がみ)結在(ゆへる)染(しめ)木綿(ゆふ)の染(しみにし)心(こころ)我(われ)忘(わすれめ)や(万2496)
不二相
念一(あ
ひおもはぬ)人(ひと)を思(おもふ)は大寺(おほでら)の餓鬼(がき)の後(しりへ)に額衝(ぬかづく)如(ごとし)(万608)
現代の東京方言では鼻濁音が失われているが、東
北弁などでは語頭には「ガ」が来て語中・語尾では鼻濁音「カ゜」となる。音楽(オンカ゜ク)、学校(ガッコウ)である。 中国語の疑母[ng-] は日本語ではマ行であらわれることが多いが、ナ行
であらわれることもある。
例:魚[ngia] な、偽[ngiuai] にせ、業[ngiap] なり、訛[nguai] なまり、睨[ngye] にらむ、
願
[ngiuan] ねがふ、
○同源語:
染(しめる)、心(こころ)、我(われ)、忘(わ
する)、相(あふ・合)、念・思(おもふ)、寺(てら)、衝(つく)、
【ぬぐ(脱)】
夜
(よるも)不レ寐
(ねず)安(やすくも)不レ有
(あらず)白細布(しろたへの)衣(ころもも)不レ脱
(ぬかじ)及二直
相一(だ
だにあふまでに)(万
2846)
玉
有(たまなら)ば 手(て)に巻(まき)持(もち)て 衣有(きぬなら)ば 脱(ぬぐ)時(とき)も無(なく) 吾(わが)戀(こふる) 君(きみ)そ伎
賊(きぞ・昨)の夜(よ) 夢(いめに)所レ見(みえ)つる(万150)
韻尾の[-t]はカ行に転移している。中国語には時代により、地
域により同じ漢字にも異音があった。例えば、江南音では韻尾の[-p][-t][-k]
は
弁別されていない。入声音[-t]が[-k]の転移した例としては、匹(ヒキ・ヒツ)、冊(サ
ツ)・柵(さく)、叱(シツ・しかる)などをあげることができる。、
○同源語:
夜(よる)、寐(ねる)、直(ただ)に、相(あふ・
合)、手(て)、衣(きぬ・巾)、時(とき)、無(な)く、吾(わが)、君(きみ)、夢(いめ)、見(みる)、
【ぬらす・ぬれる(潤・霑・沾)】
は
しきやし不レ相(あはぬ)子(こ)故(ゆえに)徒(いたづらに)是川(うぢかは)の瀬(せ)に裳欄(もすそ)潤(ぬらしつ)(万2429)
雨
(あめ)零(ふら)ば将レ盖
(きむ・着)と念有(おもへる)笠(かさ)の山(やま)人(ひと)に莫(な)令レ蓋
(きせそ)霑(ぬれ)は漬(ひづ)とも(万374)
苞
(つと)もがと乞(こは)ば令レ取
(とらせむ)貝(かひ)拾(ひりふ)吾(われ)を沾(ぬらす)莫(な)奥津(おきつ)白浪(しらなみ)(万1196)
霑[tiam]、沾[tiam] は頭音[t-] がナ行であらわれたものである。[t-] と[n-] は調音の位置が同じであり、転移しやすい。韻尾の[-n][-m] はラ行に転移している。中国語には[-l]という韻尾はないが、[-n] と[-l] は調音の位置が同じであり、転移しやすい。
現代の日本語では濡[njio] が「ぬれる」にあてられるが、万葉集には用例がな
い。潤[njuən]、濡[njio]、霑[tiam]、沾[tiam] はいずれも音義ともに近く、同系のことばである。
○同源語:
相(あふ・合)、子(こ)、川(かは・河)、零(ふる・降)、念(おもふ)、山(やま)、取(とる)、貝(かひ・蛤)、吾(われ)、莫(な)、奥(おき・
澳)、津(つ)、浪
(なみ)、
【ぬる(塗・柒)】
陶
人(すゑひと)の 所レ作
(つくれる)[瓦
缶]*(か
め)を 今日(けふ)徃(ゆきて) 明日(あす)取(とり)持(もち)來(き) 吾(わが)目(め)らに 塩(しほ)柒(ぬ)り給(たまひ)腊(きた
ひ)賞(はや)すも、、(万
3886)
香
(こり)塗(ぬれる)塔(たふ)に莫(な)依(よりそ)川隅(かはくま)の屎鮒(くそぶな)喫有るはめる)痛(いたき)女奴(めやつこ)(万3828)
二番目の歌は「香を塗って清浄にしてある塔に
寄ってはいけない。厠のある川の曲がり角に住む屎鮒を食ったきたない女の奴は」である。
古代中国語の「塗」は塗[da] である。中国語音の[t-][d-][n-] は調音の位置が同じであり、転移しやすい。日本語
の「ぬる」は中国語の「塗」と音義ともに近く、同源であろう。中国語の動詞には活用はないが、日本語では「る」を活用させている。
「漆」の古代中国語音は漆[tsiet] である。「漆」の祖語(上古音)は漆[tiet*] に近い形であったと想定される。それが唐代に入る
と摩擦音化して漆[tsiet] になったと考えられる。上古中国語音の漆[tiet*] は塗[da] と音義ともに近かった。日本語の「ぬる」は中国語
の「塗」と同源であり、「漆」も同系のことばであろう。
○同源語:
作(つくる)、[瓦缶]*(かめ)、今日(けふ)、徃(ゆく・往)、取(と
る)、來(くる)、吾(わが)、目(め)、塩(しほ)、香(こり)、塔(たふ)、莫(な)、依(よる)、川(かは・河)、鮒(ふな・付魚)、痛(いた)
き、女(め)、
【ね(音・鳴)】
朝
(つと)に徃(ゆく)鴈(かり)の鳴(なく)音(ね)は如レ吾
(わがごとく)物(もの)念(おもへ)かも聲(こゑ)の悲(かなしき)(万2137)
高
(たか)知為(しらす) 布當(ふたぎ)の宮(みや)は 河(かは)近(ちか)み 湍音(せのと)ぞ清(きよき) 山(やま)近(ちか)み 鳥(とり)が
鳴(ね)慟(とよむ)、、
(万
1050)
「鳴」の古代中国語音は鳴[mieng] である。一番目の歌では鳴(なく)であり、二番目
の歌では鳴(ね)にあてられている。中国語では四声の違いによって、動詞が名詞になったり、名詞が動詞になったりすることがよくある。
徃(ゆく)、鴈(かり)、鳴(なく・ね)、吾(わ
が)、物(もの)、念(おもふ)、聲(こゑ)、知(しる・治)、宮(みや)、河(かは)、清(きよ)き、山(やま)、鳥(とり)、茎(くき)、
岡(をか・岳)、葛(くず)、葉(は)、色(いろ)、
【ね(根)】
奥
山(おくやま)の磐本菅(いはもとすげ)を根(ね)深(ふか)めて結(むすび)し情(こころ)忘(わすれ)かねつも(万397)
大
伴(おほとも)の高師(たかし)の濱(はま)の松(まつ)が根(ね)を枕(まくらき)宿(ぬれ)ど家(いへ)し所レ偲
(しのは)ゆ(万
66)
声符が同じ文字で頭音が脱落する例:國・域、區・
歐、軍・運、葛・謁、完・院、甲・鴨、
訓で頭音[k-]が脱落した例:甘[kam] あまい、犬[khyuan] いぬ、禁[kiəm] いむ、今[kiəm] いま、
居[kia] ゐる、弓[kiuəm] ゆみ、寄[kiai] よる、
○同源語:
奥(おく)、山(やま)、本(もと)、菅(す
げ)、情(こころ)、忘(わする)、濱(はま)、宿(ぬる・寐)、家(いへ)、
【ね・みね(嶺)】
妹
(いも)が家(いへ)も繼(つぎ)て見(み)ましを山跡(やまと)有(なる)大嶋嶺(おほしまのね)に家(いへ)も有(あら)ましを(万91)
山
際(やまのま)ゆ出雲兒(いづものこ)等(ら)は霧(きり)有(なれ)や吉野山(よしののやまの)嶺(みねに)霏{雨/微]*(た
なびく)(万
429)
マ行転移の例:乱[luan] みだる、覧[lam] みる、両[liang] もろ、戻[lyet] もどる、漏[lo] もる、
同じ声符を持った漢字をラ行とマ行に読み分ける
ものもみられる。
例:陸[liuk] リク・睦[miuk] むつ、令[lieng] レイ・命[mieng] メイ、勵[liat] レイ・萬[muan] マン、
嶺(ね)は嶺[lieng] の頭音[l-] がナ行に転移し、韻尾の[-ng] が脱落したものであろう。朝鮮漢字音では中国語の[l-] は[n-] に転移することが多い。
例:楽(nak)、落(nak)、蘭(nan)、乱(nan)、浪(nang)、狼(nang)、來(nae)、冷(naeng)、
老(no)、労(no)、路(no)、露(no)、緑(nok)、論(non)、籠(nong)、楼(nu)、漏(nu)、
妹(いも)、家(いへ)、繼(つぐ・續)、見(み
る)、山(やま)、嶋(しま・洲)、出(いづ)、雲(くも)、兒(こ)、野(の)、零(ふる・降)、草(くさ)、取(とる)、手(て)、
タ行に転移した例:龍 たつ、瀧 たき、立 たつ、粒 つぶ、蓼 たで、霊 たま、列・連 つらなる、
留 とどまる、溜 ためる、頼 たよる、利 とし、
ナ行に転移した例:浪 なみ、流 ながれ、梨 なし、練 ねる、臨 のぞむ
マ行に転移した例:乱 みだる、覧 みる、戻 もどる、両 もろ、
カ行に転移する例:來 くる、栗 くり、鎌 かま、廉 かど、糧 かて、籠 かご、猟 かり、
輪 くるま、
頭音脱落の例:柳 やなぎ、梁 やな、陵 をか 、良 よき・よい、
中国語の[l-] は[t-][n-] と調音の位置が同じであり、転移しやすい。[l-] は[m-] と調音の位置が近く、音価も近い。中国語音韻史で
は上古音の時代には[l-]には入りわたり音[h-] があったと考えられている。カ行音はその痕跡であ
り、上古の入りわたり音[h-]が発達したものである。朝鮮漢字音では[l-] は介音[-i-] がくる場合は脱落し、その他の場合は(n-) に転移する。
【ねがふ(願)】
今
夜(こよひ)の早(はやく)開(あけな)ば為便(すべ)を無(な)み秋(あきの)百夜(ももよ)を願(ねがひ)つるかも(万548)
た
らちねの母(はは)が其(その・園)なる桑(くわ)尚(すらに)願(ねがへ)ば衣(きぬ)に著(きる)と云(いふ)物(もの)を(万1357)
疑母[ng-]がナ行であわわれる例:額[ngək](ぬか)、業[ngiap](なり)、偽[ngiuai](にせ)、贋[ngan] (にせ)、訛[nguai](なまり)、など
○同源語:
今夜(こよひ)、無(な)き、夜(よ)、母(は
は)、衣(きぬ・巾・絹)、著(きる)、物(もの)
【ねる(練)】
百
千(ももち)遍(たび)戀(こふ)と云(いふ)とも諸弟(もろと)等(ら)が練(ねり)の言羽(ことば)は吾(われ)は不レ信
(たのまじ)(万
774)
焼
(やき)太刀(たち)の 手頴(たかみ)押(おし)弥利(ねり) 白檀弓(しらまゆみ) 靫(ゆき)取(とり)負(おひ)て、、(万1809)
練[lian] では韻尾の[-n] はラ行であらわれている。古代日本語ではラ行音が
語頭に立つことはなかったが、第二音節ではラ行音を許容した。
例:韓[han]・漢[xan]から、雁[ngean]かり、塵[dien]ちり、潤[njiuən]ぬらす、など。
日本語では韻尾の[-n] がラ行にてんいすることが多いが、朝鮮漢字音では
中国語の韻尾[-t]は規則的に[-l] に転移する。
朝鮮語の例:筆(phil)、日(il)、出(chul)、惚[hal]、拂(pul)、祓(pul)、滅(myeol)、越(wol)、悦(yeol)、
擦 (chal)、絶(cheol)、割[(hal)、鉄(cheol)、
○同源語:
千(ち)、弟(おと)、言(こと)、羽(は)、吾
(われ)、焼(やく)、太刀(たち・刀薙)、手(て・た)、押(おす)、弓(ゆみ)、取(とる)、負(おふ)、
【の(野)】
東
(ひむがしの)野(の)に炎(かぎろひ)の立(たつ)所レ見
(みえ)て 反(かへり)見(み)為(すれ)ば月(つき)西渡(かたぶきぬ)(万48)
金
野(あきのの)の美草(みくさ)苅(かり)葺(ふき)屋杼礼(やどれ)りし兎道(うぢ・宇治)の宮子(みやこ)の借(かり)五百(いほ)し所レ念
(おもほゆ)(万
7)
古事記歌謡の「杼」の例:蘇邇杼理
能(そにどりの)、袁佐閉比迦礼杼(をさへひかれど)、
袁登賣杼母
(をとめども)、知杼理(ちどり)、
伊耶古杼母(いざこども)、
このことから「野」の祖語(上古音)には野[dia*] に近い音があったのではないかという想定が成り立
つ。万葉集にも「杼」を杼(ど)に用いた用例がある。
さ さなみの志我(しが)の大和太(おほわだ)與杼六(よどむ)とも昔人(むかしのひと)にまたも相(あは)めやも(万31)
○同源語:
立(たつ)、見(みる)、反(かへる・還)、草
(くさ)、苅(かる)、宮(みや)、子(こ)、借(かり・假)、念(おもふ)、針(はり)、妹(いも)、無(ない)、著(つける)、吾(われ)、煩(なう
あむ・悩)、絶(たゆる・断)、紐(ひも・絆)、與杼六(よどむ・澱)、相(あふ・合)、
【のぼる(登・騰・上)】
筑
波嶺(つくばね)に 登(のぼり)て見(みれ)ば 尾花(をばな)散(ちる)、、
(万
1757)
山
常(やまと)には 村山(むらやま)有(あれ)ど 取(とり)よろふ 天(あま)乃(の)香具山(かぐやま) 騰(のぼり)立(たち) 國見(くにみ)を
為(すれ)ば、、(万
2)
之
加(しか)の白水郎(あま)の焼レ塩
(しほやく)煙(けぶり)風(かぜ)を疾(いたみ)立(たち)は不レ上
(のぼらず)山(やま)に軽引(たなびく)(万1246)
上[zjiang] も祖語(上古音)は上[diang*] に近い音であったと考えられるので、登[təng]、騰[dəng] と音義ともに近く、同系のことばといえるであろ
う。
○同源語:
嶺(みね)、見(みる)、尾(を)、花(はな)、
散(ちる)、村(むら・群)、山(やま)、取(とる)、天(あめ)、香(か)、立(たつ)、國(くに)、白水郎(あま・海女)、塩(しほ)、焼(やく)、
煙(けむり)、
【のむ(飲・呑)】
驗
(しるし)無(なき)物(もの)を不レ念
(おもはず)は一坏(ひとつき)の濁酒(にごれるさけ)を可レ飲
(むべく)有(ある)らし(万
338)
阿
乎夜奈義(あをやなぎ・楊)烏梅(うめ)との波奈(はな・花)を遠理(をり・折)可射之(かざし)能彌(のみ・飲)ての能知(のち・後)は知利奴(ちり
ぬ・散)ともよし(万
821)
万葉集には呑(のむ)の用例はないが、日本書紀
ではヤマタノオロチ退治の条で「呑」が「のむ」に使われている。
「毎
年(としごと)に八岐(やまたの)大蛇(をろち)の爲に呑(の)まれき。今此の少童(をとめ)且臨被呑(のまれ)むとす。」(神代紀上)
無(な)き、物(もの)念(おもふ)、濁(にご)
る、酒(さけ)、夜奈義(やなぎ・楊・柳)、烏梅(うめ)、波奈(はな・花)、遠理(をり・折)、可射之(かざし・冠挿)、知利奴(ちる・散)、
【のる(乗)】
塩
津山(しほつやま)打(うち)越(こえ)去(ゆけ)ば我(わが)乗有(のれる)馬(うま)ぞ爪突(つまづく)家(いへ)戀(こふ)らしも(万365)
春
(はる)去(されば)爲垂(しだり)柳(やなぎの)とををにも妹(いもは)心(こころに)乗(のりに)けるかも(万1896)
語頭の[d-] がナ行であらわれる例:長[diang] ながし、濁[diok] にごる、逃[do]にげる、塗[da] ぬる、
韻尾の[-ng] がラ行であらわれる例:狂[giuang] くるふ、凝[ngiəng] こる、通[[thong] とほる、
經[kyeng]へる、萌[məng]もえる、平[bieng]ひら、など。
○同源語:
塩(しほ・潮)、津(つ)、山(やま)、打(う
つ)、越(こえ)る、去(ゆく・行)、我(わが)、馬(うま)、爪(つめ)、突(つく)、家(いへ)、春(はる)、爲(し・枝)、垂(たれる)、柳(やな
ぎ)、妹(いも)、心(こころ)、
【な行のまとめ】
日本語のナ行は中国語の[t-][d-][n-]のほか[l-][m-]や[ng-][nj-]が合流してできあたっている。
1.中国語の[t-][d-][th-][n-] に依拠した例:
中[tiong](チュウ・なか)、丹[tan](タン・に)、登[təng](トウ・のぼる)、嘆・歎[than](タ ン・なげく)、煮[thya](シャ・にる)、脱[thuat](ダツ・ぬぐ)、呑[thən](ドン・のむ)、
長[diang](チョウ・ながし)、濁[diok](ダク・にごる)、塗[da](ト・ぬる)、野[jia/dia*](ヤ・ の)、騰[dəng](トウ・のぼる)、乗[djiəng](ジョウ・のる)、脳[nu](ノウ・なやむ)、
2.中国語の[l-]が転移した例:
流[liu](リュウ・ながる)、梨[liet]子(リ・なし)、浪[liang](ロウ・なみ)、瀾[lan](ラン・な み)、嶺[lieng](レイ・ね・みね)、練[lian](レン・ねる)、
[l-]と[n-]は調音の位置(前口蓋)が同じであり、転移しやす い。
3.中国語の[m-]がナ行に転移した例:
名[mieng](メイ・な)、勿[miuət](モチ・ブツ・な)、莫[mak](バク・な)、鳴[mieng](メイ・ なく・なる・ね)、無[miua](ム・なし)、撫[phiua/ miua*](ブ・なづ)、靡[miai](ミ・ビ・なび く)、苗[miô](ビョウ・なへ)、寐[muət](ミ・ビ・ぬ・ね)、
中国語の[n-][m-]はいずれも鼻音であり、調音の方法が同じであり、
転移しやすい。
4.中国語の日母[nj-] がナ行であらわれる例:
汝[njia](ニョ・ジョ・な・なむち)、柔[njiu](ニュウ・ジュウ・にこ・にき)、潤[njiuən](ジュ ン・ぬれる)、濡[njio](ジュ・ぬれる)、
5.中国語の疑母[ng-] がナ行であらわれる例:
魚[ngia](ギョ・な)、業[ngiap](ギョウ・なり)、額[ngək](ガク・ぬか)、願[ngiuan](ガン・ ねがふ)、
6.そのほかの例:
嘗[zjiang/djiəng*](ジョウ・なむ)、似[ziə/diəg*](ジ・にる)、
これらの漢字は祖語(上古音)の段階では摩擦 音化しておらず、[d-]に近い音であったものと考え られる。
根[kən](コン・ね)、音[iəm](オン・ね)、
これらの漢字は頭音が脱落して韻尾の[-n][-m] が一音節になったものである。
◎は行
【は(齒・牙)】
泊
瀬川(はつせがは)流(ながるる)水沫(みなわ)の絶(たえ)ばこそ吾(わが)念(おもふ)心(こころ)不レ遂
(ごげじ)と思(おも)歯(は)め(万1382)
中国語の歯[thjiə]は日本語のタ行音に近いが有気音[h]が含まれており、日本語の歯(は)は中国語の有気
音[h] が発達したものである可能性がある。
中国語の[th-] が日本語でハ行であらわれる例:春[thiuən] はる、禿[thuk] はげ、吐[tha] はく、
肚[tha] はら、太[that] ふとい、恥[thiə] はぢ、榛[tzhen] はる、など
中国語では「歯」に牙[ngea] も用いられる。現代の中国語では歯科医のことを牙
科という。日本語の「は」は牙[ngea] の転移したものである可能性もある。万葉集には
「はぎ」に「芽子」があれられている例もある。
ふす、芽[ngea]子・はぎ、など
日本語の「は」は中国語の「牙」あるいは「歯」
と同系のことばであろう。
○同源語:
泊(はつ)、川(かは・河)、流(な
がる)、絶(たえる・断)、吾(わが)、念・思(おもふ)、心(こころ)、娘(をみな・女)、芽子(はぎ)、野(の)、今日(けふ)、代
(よ・世)、見(みる)、
【は(葉)】
小
竹(ささ)の葉(は)は三山(みやま)も清(さや)に乱(さやげ)ども吾(われ)は妹(いも)思(おもふ)別(わかれ)來(き)ぬれば(万133)
橘
(たちばな)は實(み)さへ花(はな)さへ其葉(そのは)さへ枝(え)に霜(しも)雖レ降
(ふれど)いや常葉(とこは)の樹(き)(万1009)
中国語の韻尾[-p]は旧かなづかいでは、蝶[thyap](チョウ・てふ)、塔[təp](トウ・たふ)のようにハ行で表記された。また、
訓のなかには中国語の韻尾[-p]がハ行であらわれるものが多くみられる。
例:合[həp](カイ・あふ)、峡[heap](キョウ・かひ)、頬(キョウ・ほほ)、渋[shiəp](ジュウ・
しぶし)、吸[xiəp](キュウ・すふ)、粒[liəp(リュウ・つぶ)、
日本語の「は」は中国語の葉[jiap]の韻尾が独立したものである。
○同源語:
山(やま)、清(さや)か、吾(われ)、妹(い
も)、思(おもふ・念)、來(く)る、花(はな)、枝(え)、霜(しも)、降(ふる)、常(とこ)、樹(き)、
【は(羽)】
葦
邊(あしべ)徃(ゆく)鴨(かも)の羽音(はおと)の聲(おと)耳(のみに)聞(きき)つつもとな戀(こひ)度(わたる)かも(万3090)
水
鳥(みづとり)の可毛(かも・鴨)羽(は)伊呂(いろ・色)の青馬(あをうま)を家布(けふ・今日)美流(みる・見)人は可藝利(かぎり)奈之(なし)と
伊布(いふ)(万
4494)
同じ声符をもった漢字でも中国語の喉音[h-]がうしなわれたものと、カ行などであらわれるもの
がある。
例:例:域(イキ)・國(コク)、運(ウン)・軍
(グン)、
日本語の訓のなかに喉音[h-][x-]の痕跡をハ行で留めているものがいくつかみられ
る。
例:降[hoəm](コウ・ふる)、戸[ha](コ・へ)、火[xuəi](カ・ひ)、灰[huəi](カイ・はい)、匣 [heap](コウ・はこ)、挟[hyap](キョウ・はさむ)、閑[hean](カン・ひま)、花[xoa]・華[hoa] (カ・はな)、脛[hyeng](ケイ・はぎ)、惚[xuət](コツ・ほれる)、宏[heang](コウ・ひろ い)、弘[huang](コウ・ひろい)、
古代日本語のハ行は「ファ、フィ、フ、フェ、
フォ」のような両唇音であったと云われていが、記紀万葉の時代の用例で見る限り中国語の脣音[p-]系ばかりでなく喉音[h-][x-]系の音が合流している。
○同源語:
邊(へ)、往(ゆく)、鴨・可毛(かも)、羽
(は)、音・聲(おと)、度(わたる・渡)、鳥(とり)、伊呂(いろ・色)、馬(うま)、家布(けふ・今日)、美流(みる・見)、可藝利(かぎり・限)、
奈之(なし・無)、
【はか(墓・陵)】
墓
上(はかのうへ)の木(こ)の枝(え)靡有(なびけり)如レ聞
(ききしごと)陳奴(ちぬ)壯士(をとこ)にし依(よりに)けらしも(万1811)
や
すみしし 和期(わご)大王(おほきみ)の 恐(かしこき)や 御陵(みはか)奉仕(つかふ)る 山科(やましな)の 鏡山(かがみのやま)に、、(万155)
日本語の「はか」は中国語の墓[mak]と同源であろう。日本漢字音は墓(ボ)は墓[mak]の韻尾[-k]が脱落したものである。墓と声符を同じくする漢字
に、莫(バク)がある。莫(バク)は韻尾[-k]が保たれていて、墓(ボ)では失われている。しか
し、訓では墓(はか)と韻尾[-k]が保たれている。墓(はか)が古く、墓(ボ)が新
しい。日本語の墓(はか)は古い中国語音の痕跡を留めている。万葉集の時代の日本語では濁音が語頭にくることがなかったので、鼻濁音の墓[mak]の頭音はハ行であらわれている。
「陵」の古代中国語音は陵[liəng]である。「陵」は大墓のことであり、皇帝の墓など
に用いられる。「陵」の祖語には入りわたり音があり、陵[(h)liəng*]のような音であったと推定できる。陵(はか)は入
りわたり音[h-]が発達したものであろう。
○同源語:
木(き・枝)、靡(なび)く、依(よる)、和期
(わご・我)、大王(おほきみ・君)、御(み)、山(やま)、鏡(かがみ)、
【はぎ(芽子・芽)】
春
日野(かすがの)に咲(さき)たる芽子(はぎ)は片枝(かたえだ)は未(いまだ)含(ふふ)めり言(こと)勿(な)絶(たえ)そね(万1363)
[女 感]*嬬 (をとめ)等(ら)に行(ゆき)相(あひ)の速稲(わせ)を苅(かる)時(ときに)成(なりに)けらしも芽子(はぎの)花(はな)咲(さく)(万2117)
霍
公鳥(ほととぎす)音(こゑ)聞(きく)小野(をの)の秋風(あきかぜ)に芽(はぎ)開(さきぬ)れや聲(こゑ)の乏(ともし)き(万1468)
中国語のは牙音系([k-][kh-][g-][ng-])のことばは日本語でハ行にあらわれることがあ
る。
例:干・乾[kan](ほす)、姫[kiə](ひめ)、機[kiəi](はた)、古[ka](ふるい)、骨[kuət](ほね)、
広[kuang](ひろい)、光[kuang](ひかり)、経[kyeng](へる)、堀[khuət]、開[khei](ひらく)、 掘[giuət](ほる)、牙[ngea](は)、臥[ngua](ふす)、
○同源語:
野(の)、咲・開(さく)、枝(えだ)、未(いま
だ)、含(ふふむ)、言(こと)、勿(な)、絶(たえる・断)、嬬(め)、行(ゆく)、相(あふ・合)、苅(かる)、時(とき)、花(はな)、霍公鳥(ほ
ととぎす・隹)、音・聲(こゑ)、小(を)、
【はく(佩)】
御
(み)佩(はかし)を 劔池(つるぎのいけ)の 蓮葉(はちすは)に 渟有るたまれる)水(みづ)の 往方(ゆくへ)無(なみ)、、(万3289)
如
己(もころ)男(を)に 負(まけ)ては不レ有
(あらじ)と 懸(かき)佩(はき)の 小劔(をたち)取(とり)佩(はき)、、(万1809)
○同源語:
御(み)、劔(つるぎ)、蓮(はちす・荷子)、葉
(は)、渟(たまる)、往(ゆく)、方(へ)、無(な)き、男(を・雄)、懸(かける)、小(を)、劔(たち・刀薙)、取(と)る、
【はぐ(波伎・剥)】
あ
しひきの 此(この)片山(かたやま)の もむ尓礼(にれ・楡)を 五百枝(いほえ)波伎(はぎ・剥)垂(たれ)、、(万3886)
○同源語:
此(この)、山(やま)、垂(たれ)る、
【はこ(匣・筥・篋・箱)】
白
玉(しらたま)を手(て)には不レ纏
(まかず)に匣(はこ)耳(のみに)置有(おけり)し人(ひと)ぞ玉(たま)令レ詠
(なげかす)る(万
1325)
此
(この)筥(はこ)を開(ひらき)て見(み)てば 如レ本
(もとのごと) 家(いへ)は将レ有
(あらむ)と 玉篋(たまくしげ) 小(すこし)披(ひらく)に 白雲(しらくも)の 自レ箱
(はこより)出(いで)て 常世(とこよ)邊(へに) 棚引(たなびき)去(ぬれ)ば、、
(万1740)
万葉集では日本語のハ行に中国語の[p-]ばかりでなく、喉音[h-]もハ行であらわれる。日本語の「はこ」は匣[heap]、篋[khyap] と同系のことばであろう。
古代中国語の[k-]が日本語でハ行であらわれる例としてはつぎのよう
なものがある。
例:姫[kiə] ひめ、機[kiəi] はた、古[ka] ふるい、蓋[kat] ふた、骨[kuat] ほね、広[kuang] ひろい、
経[kyeng] へる、
箱[siang]の祖語(上古音)は箱[xiang*]であったのではないかと思われる。「箱」もまた
「匣」「篋」と同系のことばである可能性がある。
○同源語:
手(て)、置(おく)、此(こ)れ、見(みる)、
本(もと)、家(いへ)、小(すこ)し、雲(くも)、出(いづ)、常(とこ)、世(よ)、邊(へ)、棚(たな・壇・段)、
【はさむ(挾)】
緑
兒(みどりご)の 乞(こひ)哭(なく)ごとに 取(とり)まかす 物(もの)し無(なけれ)ば 男自物(をとこじもの) 腋(わき)挾(はさみ)持(も
ち) 吾妹子(わぎもこ)と 二(ふたり)吾(わが)宿(ね)し 枕(まくら)附(づく) 嬬屋(つまやの)内(うち)に、、
(万213)
喉音[h-][x-]がハ行であらわれる例:羽[hiua] は、戸[ha] へ、脛[hyeng] はぎ、荷子[hai] はす、
華[hoa] はな、灰[huəi] はひ、降[hoəm] ふる、宏[hoəng] ひろい、弘[huəng] ひろい、
花[xoa] はな、火[xuəi] ひ、惚[xuət] ほれる、揮[xiuəi] ふるふ、
韻尾の[-p]がマ行であらわれる例:汲[kiəp] くむ、湿[sjiəp] しめる、鴨[keap*] かも、
畳[dyap] たたみ、
○同源語:
兒・子(こ)、哭(なく・泣)、取
(とる)、物(もの)、無(なし)、腋(わき)、吾妹子(わぎもこ)、宿(ねる・寐)、嬬(つま・妻嬬)、
【はた(旗・幡)】
青
旗(あをはた)の木旗(こはた)の上(うへ)をかよふとは目(め)には雖レ視
(みれども)直(ただ)に不レ相
(あはぬ)かも(万
148)
諸
人(もろびと)の 恊(おびゆ)るまでに ささげたる 幡(はた)の靡(なび)きは、、
(万199)
例:腕[uan](ワン・うで)、肩[kyan](ケン・かた)、言[ngian](ゲン・こと)、断[duan](ダン・
たつ)、楯[djiuən](ジュン・たて)、満[muan](マン・みつ)、本[puən](ホン・もと)、
綿[mian](メン・わた)、鞭[bian](ビン・むち)、
○同源語:
木(こ・枝)、視(みる・見)、直(ただ)に、目
(め)、相(あふ・合)、靡(なび)く、
【はちす(蓮・荷子)】
ひ
さかたの雨(あめ)も落(ふら)ぬか蓮荷(はちすば)に渟(たま)れる水の玉(たまに)似(に)たる将レ見(みむ)(万3837)
勝
間田(かつまた)の池(いけ)は我(われ)知(しる)蓮(はちす)無(なし)然(しか)言(いふ)君(きみ)が鬚(ひげ)無(なき)如し(万3835)
御
佩(みはかし)を 劔池(つるぎのいけ)の 蓮葉(はちすは)に 渟(たま)れる水の 徃方(ゆくへ)無(なみ)、、(万3289)
韻尾の[-n]がタ行であらわれる例:本(もと)、元(もと)、
言(こと)、盾(たて)、
肩(かた)、腕(うで)、幡(はた)、管(くだ)、堅(かたい)、断(たつ)、満(みつ)、
記紀万葉の時代には「はちす」を「荷」と表記し
た例もあり、日本語の「はちす」「はす」は「荷子」から派生したことばである可能性もある。「荷」の古代中国語音は荷[hai] であり、羽[hiua] は、匣[heap] はこ、挟[hyap] はさむ、などでも日本語ではハ行であらわれる。意味は
「蓮」である。
○同源語:
落(ふる・降)、渟(たま)る、似(にる)、見
(みる)、間(ま)、田(た)、我(われ)、知(し)る、無(な)し、君(きみ)、御(み)、佩(はく)、劔(つるぎ)、葉(は)、往(ゆく)、方
(へ)、
【はつ(泊)】
吾
船(わがふね)は枚(ひら)の湖(みなと)に榜(こぎ)将レ泊
(はてむ)奥(おき)へ莫(な)避(さかり)佐夜(さよ)深(ふけ)にけり(万274)
濱
(はま)清(きよみ)浦(うら)愛(うるはし)み神世(かみよ)より千船(ちふねの)湊(はつる)大和太(おほわだ)の濱(はま)(万1067)
古代日本語でも中国語の韻尾[-k] は日本漢字音でタ行であらわれる例としては、柵[tshek](サク)・冊[tshek](サツ)、克[khək](コク・かつ)、睦[miuk](ボク・むつむ)、黙[mək](モク・もだす)、匹[phiet](ヒキ・ヒツ)、などをあげることができる。
○同源語:
吾(わが)、船(ふね・盤)、奥(おき・澳)、夜
(よる)、濱(はま)、清(きよい)、神(かみ)、世(よ)、千(ち)、
【はな(花)】
和
我(わが)夜度(やど)の花(はな)橘(たちばな)を波奈(はな)ごめに多麻(たま)にぞ安我(あが)奴久(ぬく)麻多(また)ば苦流之美(くるしみ)(万3998)
青
丹吉(あをによし)寧楽(なら)の京師(みやこ)は咲(さく)花(はな)の薫(にほふが)如(ごとく)今(いま)盛(さかり)有(なり)(万328)
○同源語:
和我(わが)、花(はな)、安
我(あが)、苦流之(くるし)、京師(みやこ)、咲(さく)、今(いま)、盛(さかり)、
【はひ(灰)】
汝
(なが)戀(こふる) 妹(いも)は座(ます)と 人(ひとの)云(いへ)ば 石根(いはね)割(さく)見(み)て なづみ來(こ)し 好(よけ)くもぞ
無(なき) うつそみと 念(おもひ)し妹(いも)が 灰(はひ)にて座(ませ)ば(万213)
紫
(むらさき)は灰(はひ)指(さす)物(もの)ぞ海石榴市(つばきち)の八十(やそ)の街(ちまた)に相(あへる)兒(こ)や誰(たれ)(万3101)
現代中国語音では広東音では花(fa)、火(fo)、灰(fui) である。日本漢字音は唐代の長安の音を正音として
いるが、日本語の発音は江南音の影響も無視できない。日本語の「はひ」は中国語の灰[huəi]と同源である。
○同源語:
汝(な)、妹(いも)、根(ね)、見(みる)、来
(くる)、無(な)き、念(おもふ)、指(さす)、物(もの)、相(あふ・合)、兒(こ)、
【はふ(匍匐)】
若
子(みどりこ)の匍匐(はひ)たもとほり朝夕(あさよひに)哭(ね)耳(のみ)ぞ吾(わが)泣(なく)君(きみ)無(なし)にして(万458)
○同源語:
子(こ)、夕(よひ・夜)、哭(ね・音)、吾(わ
が)、泣(なく)、君(きみ)、無(な)し、
【はま(濱)】
粟
路(あはぢ)の野嶋(のしま)の前(さき)の濱風(はまかぜ)に妹(いも)が結(むすびし)紐(ひも)吹(ふき)返(かへす)(万251)
大
夫(ますらを)は御獦(みかり)に立(たた)し未通女(をとめ)等(ら)は赤裳(あかも)須素(すそ)引(ひく)清(きよき)濱備(はまび)を(万1001)
中国語の韻尾[-n] がマ行であらわれる例:絹[kyuan] きぬ、肝[kan] きも、君[giuən] きみ、
文[miuən] ふみ、蝉[zjian] せみ、点[tyan] ともす、混[huən] こむ、困[khuən] こまる、
呑[thən] のむ、眠[myen] ねむる、
○同源語:
野(の)、嶋(しま・洲)、妹(い
も)、紐(ひも・絆・繙)、返(かへす・還)、御(み)、獦(かり)、立(たつ)、未通女(をとめ・女)、清(きよい)、
【はら(原)】
朝
茅原(あさぢはら)小野(をの)に印(しめゆふ)空事(むなごとを)何(いか)在(なりと)云(いひて)公(きみをし)待(またむ)(万2466)
秋
(あき)去(さら)ば今(いま)も見(みる)如(ごと)妻(つま)戀(こひ)に鹿(か)将レ鳴
(なかむ)山(やま)そ高野原(たかのはら)の宇倍(うへ)(万84)
語頭の[ng-] がハ行であらわれる例:牙[ngea] は、芽子[ngea] はぎ、臥[nguai] ふす、
語頭の[ng-] がカ行であらわれる例:雁[ngean] かり、刈[ngiat] かる、言[ngian] こと、
韻尾の[-n] がラ行であらわれる例:漢[xan]・韓[han] から、雁[ngean] かり、塵[dien] ちり、
群[giuən] むれ、潤[njiuən] ぬらす、練[lian] ねる、薫[xiuən] かをる、
○同源語:
小(を)、野(の)、印(しめ・標)ゆふ、公(き
み)、今(いま)、見(みる)、妻(つま・妻女)、鹿(か)、鳴(なく)、山(やま)、
【はら(腹)】
皇
(おほきみ)は神(かみ)にし座(ませ)ば赤駒(あかごま)の腹(はら)ばふ田(た)ゐを京師(みやこ)となしつ(万4260)
韻尾の[-k]がラ行であらわれる例:織[tjiek] おる、射[djyak] いる、色[shiək] いろ、悪[ak] わるい、
涸[hak] かれる、櫟[lek] なら、など
また、日本語の「へそ」は中国語の腹臍[piuək-dzei] から派生したことばであろう。
○同源語:
皇(おほきみ・君)、神(かみ)、駒(こま)、田
(た)、京師(みやこ)、
【はらふ(掃・拂・祓)】
國
(くに)看(み)之(し・為)せして 安母里(あもり・天降)麻之(まし・坐) 掃(はらひ)平(たひらげ) 千代(ちよ)累(かさね)、、(万4254)
奈
加等美(なかとみ・中臣)の敷刀能里等(ふとのりと・祝詞)其等(ごと・言)伊比(いひ)波良倍(はらへ)安賀布(あかふ・贖)伊能知(いのち)も多
(た)が多米(ため)に奈礼(なれ
(万4031)
韻尾の[-t]がラ行に転移した例:没[muət] うもる、渇[khat] かれる、刈[ngiat] かる、徹[diat] とほる、
垂[zjiuat]* たれる、など
朝鮮漢字音では中国語の韻尾[-t]は規則的に[-l]に転移する。「拂」「祓」の朝鮮漢字音は拂(pul)、祓(pul) である。
○同源語:
由美(ゆみ・弓)、夜麻(やま・山)、邊(へ)、
伊毛(いも・妹)、多弖(たて・立)、祢(ね・寐)、國(くに)、看(みる・見)、安母里(あもり・天降)、千代(ちよ・世)、奈加等美(なかとみ・中
臣)、
【はり(針・鍼)】
針
(はり)は有(あれ)ど妹(いも)し無(なけれ)ば将レ著
(つけめ)やと吾(われ)を令レ煩
(なやまし)絶(たゆる)紐(ひも)の緒(を)(万2982)
吾
(わが)背子(せこ)が盖(け)せる衣(ころも)の針目(はりめ)不レ落
(おちず)入(いり)にけらしも我(わが)情(こころ)さへ(万514)
古代中国語の「針」は針[tjiəm] である。「はり」は箴・鍼[tjiəm] とも書く。「箴」「鍼」と同じ声符をもつ漢字に
「感」があり、古代中国語音は感[həm] である。「箴」「鍼」の祖語(上古音)は箴・鍼[həm*] に近い音であったと考えられる。それが[-i-] 介音の発達により箴・鍼[hiəm*] になり、それが更に口蓋化して箴・鍼[tjiəm] になったものであろう。針[tjiəm] の祖語(上古音)も針[hiəm*]に近いかたちになったものと考えるころができる。
日本語の「はり」は中国語の「箴」「鍼」あるい
は「針」と同源である。韻尾の[-m] がラ行であらわれる例としては、降[hoam] おる・ふる、嫌[hyam] きらふ、沾[tham] ぬれる、などがある。
○同源語:
妹(いも)、無(な)し、著(つけ)る、吾(わ
れ)、煩(なやます・悩)、絶(たゆる・断)、紐(ひも・絆・繙)、吾・我(わが)、背子(せこ)、目(め)、落(おちる・堕)、入(いる)、情(ここ
ろ・心)、
【はり(榛)】
和
我(わが)勢故(せこ)が 垣都(かきつ)の谿(たに)に あけけされば 榛(はり)の狭枝(さえだ)に 暮(ゆふ)されば 藤(ふじ)の繁美(しげみ)
に はろはろに 鳴(なく)霍公鳥(ほととぎす)、、(万4207)
引
馬野(ひくまの)ににほふ榛原(はりはら)入乱(いりみだり)衣(ころも)にほはせ多鼻(たび・旅)のしるしに(万57)
榛[tzhen] の祖語(上古音)は榛[hen*] に近い形であった可能性がある。榛[hen*] が摩擦音化して唐代には榛[tzhen] になったものと思われる。
一般に中国語音韻史では口蓋化は前口蓋音[t-][d-] 系から起こったことになっている。前口蓋音が口蓋
化して摩擦音になる[t-][d-]→[tj-][dj-]→[ts-][tz-] という変化は中国語音韻史でもよく知られている。
中国の韻書である『韻鏡』をみても韻図に後口蓋
系、喉音系の舌頭音や舌上音の欄はみられない。後口蓋音[k-][g-] 系や喉音[h-][x-]系からは起こらなかったのだろうか。音韻変化の一
般原則によれば、前口蓋音[t-][d-]が介音などの影響で摩擦音化した場合、[tz-][dz-] の位置にあった音は、さらに押されて後口蓋音[k-][g-] などに転移していくということが知られているしか
し、前口蓋音[t-][d-]と後口蓋音[k-][g-] が同時に摩擦音化するということは普通考えられな
い。
後口蓋音[k-][g-] や喉音[h-][x-] がサ行であらわれる例:榛(シン・はり)、 秦(シン・はた)、箴・鍼(シン・はり)、神(シン・かみ)、辛(シン・からい)、嗅(シュウ・かぐ)、切(セツ・きる)、小(ショウ・こ)、子(シ・こ)、消(ショウ・きえ る)、削(サク・けずる)、など
漢字には、同じ声符の漢字にカ行とサ行に読み
分けられるものが多い。
例:技(ギ)・枝(シ)、期(キ)・斯(シ)、耆
(キ)・旨(シ)、祇(ギ)・氏(シ)、訓(ク
ン)・川(セン)、堅(ケン)・腎(ジン)、坤
(コン)・神(シン)、宦(カン)・臣(シ
ン)、絢(ケン)・旬(ジュン)、赫(カク)・赤
(セキ)、言(ゲン)・信(シン)、活(カ
ツ)・舌(ゼツ)、逆(ギャク)・朔(サク)、嗅
(キュウ)・臭(シュウ)、勘(カン)・
甚(ジン)、庫(コ)・車(シャ)、馨(ケイ)・
声(セイ)、
これれの事実を総合的に考えると、後口蓋音[k-][g-]にも口蓋化が起こり、摩擦音化したとする仮説は蓋
然性があるように思われる。榛(はり)は上代中国語音の痕跡をとどめた音であり、日本語の「はり」と中国語の「榛」は同源であろう。
○同源語:
和我(わが)、勢故(せこ・背子)、狭枝(さえ
だ)、暮(ゆふ・夜)、鳴く(なく)、霍公鳥(ほととぎす・隹)、馬(うま)、野(の)、原(はら)、入(いる)、乱(みだる)、
【はる(春)】
石
(いは)激(ばしる)垂見(たるみ)の上(うへ)の左和良妣(わわらび)の毛要(もえ)出(いづる)春(はる)に成(なりに)けるかも(万1418)
春
楊(はるやなぎ)葛山(かづらきやま)に發(たつ)雲(くもの)立(たちても)座(ゐても)妹(いもをしそ)念(おもふ)(万2453)
例:禿[thuk](トク・はげ)、紐[thio](チュウ・ひも)、恥[thiə](チ・はぢ)、
春[thjiuən] は口蓋化音であり、春[hiuən*] に近い音価をもっていた可能性がある。[t-][d-] 系のことばでも介音[-i-] を伴うものには日本語の訓がハ行であらわれるもの
がいくつか見られる。
例:張[tiang](チョウ・はる)、彫[tyu](チョウ・ほる)、昼[tiu](チュウ・ひる)、箸[dia](チョ・
はし)、柱[dio](チュウ・はしら)、
これを偶然の一致とみるか、音韻転移の法則に
あったものとみるかは、判断の別れるところであろう。ちなみに、「春」にあたる朝鮮語は春(pom)であり、日本語の春(はる)に近い。
○同源語:
垂(たれる)、見(みる)、毛要(もえ・萌)る、
出(いづる)、楊(やなぎ)、葛(かづら)、山(やま)、發・立(たつ)、雲(くも)、妹(いも)、念(おもふ)、
【はる(墾・治)】
住
吉(すみのえ)の岸(きし)を田(た)に墾(はり)蒔(まきし)稲のさて及レ苅
(かるまでに)不レ相
(あはぬ)公(きみ)かも(万
2244)
新
治(にひばりの)今(いま)作(つくる)路(みち)清(さやかにも)聞(ききてける)かも妹(いもが)於(うへの)事(こと)を(万2855)
語頭の[kh-] や[k-] がハ行であらわれる例:寛[khuan] ひろい、誇[khoa] ほこる、開[khei] ひらく、
頬[kyap] ほほ、骨[kuət] ほね、蓋[kat] ふた、経[kyeng] へる、干[kan] ほす・ひる、
広[kuang] ひろい、
韻尾の[-n] がラ行であらわれる例:原[ngiuan] はら、榛[tzhen] はり、馴[ziuən] ならす、
潤[njiuən]ぬらす、練[lian]ねる、邊[pyen]へり、漢[xan]・韓[han]から、雁[ngean]かり、
○同源語:
田(た)、蒔(まく・播)、稲(いね・秈)、苅
(かる)、相(あふ)、公(きみ)、今(いま)、作(つく)る、清(さやか)、妹(いも)、
【ひ・ほ(火)】
能
登海(のとのうみ)に釣(つり)為(する)海部(あま)の射去火(いさりび)の光(ひかり)にい徃(ゆけ)月(つき)待(まち)がてり(万3169)
可
麻度(かまど)には 火気(ほけ)布伎(ふき)多弖受(たてず) 許之伎(こしき)には 久毛(くも)の須(す)可伎弖(かきて)、、(万892)
螢
(ほたる)成(なす) 髣髴(ほのかに)聞(きき)て 大土(おほつち)を 火穂(ほのほ)と跡(ふみ)て 立(たちて)居(ゐ)て 去方(ゆくへ)も不レ知
(しらず)、、(万
3344)
火(カ)は日本語が本格的な文字時代に入った
8世紀以降、中国では唐の時代の中国語音を取り入れたものであり、火(ひ)は日本が中国文明の影響を受けはじめた弥生時代の初期から古墳時代をとおして約
1000年にわたって中国と接触するなかで、多分江南地方に依拠した発音である。
現代の中国語でも、日本漢字音でカ行であらわれ
るものが、広東音ではfであらわれるものがみられる。
例:火(fo)、花(fa)、灰(fui)、惚(fat)、幌(fong)、寛(fun)、
8世紀の人お視点でみれば、火(ひ)は以前から
日本で行われていた発音であり、火(カ)は新しく唐から入ってきた発音であったに違いない。中国語の喉音[x-]は訓ではハ行であらわれることが多い。中国語の喉
音[h-]が訓ではハ行であらわれ、音ではカ行であらわれる
ものにはつぎのような例がある。
例:灰[huəi](カイ・はひ)、戸[ha](コ・へ)、匣[heap](コウ・はこ)、華[hoa](はな)、
檜[huai](カイ・ひのき)、挟[hyap](キョウ・はさむ)、荷[hai-]子(カ・はす)、含
[həm](ガン・ふふむ)、降[hoəm](コウ・ふる)、
○同源語:
海(うみ)、釣(つり)、海部(あま)、射(い
る)、往(ゆく・行)、多弖・立(たて)、須(す・巣)、可伎(かき・懸)、螢(ほたる・火垂)、土(つち・地)、穂(ほ)、居(ゐ)る、去方(ゆくへ・
行方)、知(しる)、
【ひ(氷)】
吾
(わが)衣袖(ころもで)に 置(おく)霜(しも)も 氷(ひ)に左叡(さえ)渡(わたり) 落(ふる)雪(ゆき)も 凍(こほり)渡(わたり)ぬ、、、(万3281)
𣑥
(たへ)の穂(ほ)に 夜(よる)の霜(しも)落(ふり) 磐床(いはとこ)と 川(かは)の氷(ひ)凝(こごり) 冷(さむき)夜(よ)を、、、(万79)
○同源語:
吾(わが)、置(おく)、霜(しも)、渡(わた
る)、落(ふる・降)、穂(ほ)、夜(よる)、床(とこ)、川(かは・河)、凝(こごる)、
【ひ(檜)】
衣
手(ころもで)の 田上山(たなかみやま)の 真木(まき)さく 檜(ひ)の嬬手(つまで)を、、(万50)
例:匣[hea](コウ・はこ)、挟[hyap](キョウ・はさむ)、荷子[hai-](カ・はす)、花[xoa]・
華[hoa](カ・はな)、灰[huəi](カイ・はひ)、火[xuəu](カ・ひ)、など。
○同源語:
手(て)、田(た)、山(やま)、真(ま)、木
(き・枝)、嬬(つま・妻嬬)、
【ひえ(稗)】
打
田(うつたには)稗(ひえは)數多(あまたに)雖レ有
(ありといへど)擇(えらえ)為(し)我(われぞ)夜(よを)一人(ひとり)宿(ねる)(万2476)
水
(みづ)を多(おほみ)上(あげ)に種(たね)蒔(まき)比要(ひえ・稗)を多(おほみ)擇擢(えらえ)し業(なり)ぞ吾(わが)獨(ひとり)宿(ねる)(万2999)
『古事記』を誦述したのは稗田阿礼とされてい
る。稗(ひえ)も田(た)も中国語と同源である。弥生時代の初期には稗は米、麦、などとともに重要な作物であった。稗[pie] も米[hmei*] も麥[muək] も中国語と同源である。
日本語のハ行は中国語の頭音[p-]に対応するものと、中国語の喉音[h-][x-]に対応するものとがある。[p-] は必ずハ行であらわれる。喉音[h-][x-]はカ行であらわれるものと、ハ行であらわれるもの
がある。中国語の喉音[h-][x-] は日本語にはない音であり、調音の位置が近いこと
からカ行であらわれる。また、中国語の喉音[h-][x-] は現在は摩擦音化しているが古代中国語音は破裂音
であったものと考えられる。そのため日本語のハ行と音価が近かったのであろう。
○同源語:
打(うつ)、田(た)、我・吾(われ)、夜(よ
る)、宿(ねる・寐)、種(たね)、蒔(まく・播)、
【ひかり(光)】
天
皇(すめろぎ)の 神(かみ)の御子(みこ)の 御駕(いでまし)の 手火(たび)の光(ひかり)ぞ ここだ照(てり)たる(万230)
光
(ひかる)神(かみ) 鳴波多(なりはた)[女
感]*嬬
(をとめ) 携レ手
(たづさへて) 共(ともに)将レ有
(あらむ)と 念(おもひ)しに、、(万4236)
「光」の古代中国語音は光[kuang]である。「光」は「ひかる」「ひかり」である。中
国語の「光」は日本語の「ひかり」にも「かげ」にも使われる。「影」も上古音は影[kyang*]であり、「かげ」にも「ひかり」にも用いられる。
中国語では売買、授受など、同音(あるいは近い音)のことばを反対に意味に使うことがある。
落
(おち)多藝知(たぎち)流(ながるるる)水(みづ)の磐(いはに)觸(ふれ)賣類(よどめる)与杼(よど)に月影(つきのかげ)所レ見
(みゆ)(万
1714)
「光」も「影」も日本語の「ひかり」にあたるこ
とばに用いられることがある。「ひかり」も「かげ」も光[kuang] から派生したことばであろう。中国語の[k-] は日本漢字音ではカ行であらわれるが、訓ではハ行
であらわれることがある。
例:姫(キ・ひめ)、機(キ・はた)、古(コ・ふ
るい)、蓋(ガイ・ふた)、干(カン・
ひる)、果(カ・はて)、広(コウ・ひろい)、經(ケイ・へる)、頬(キョウ・ほお)、
○同源語:
神(かみ)、御(み)、子(こ)、駕(いで・
出)、手(て)、火(ひ)、照(てる)、鳴(なる)、[女感]*嬬(をとめ・嬬)、念(おもふ)、天(あめ)、原(はら)、見(み
る)、度(わたる・渡)、陰(かげ・影)、照(てる)、落(おちる・堕)、流(ながる)、与杼(よど・澱)、影(かげ)
【ひめ(姫・媛)】
夏
野(なつのの)の繁(しげ)みに開(さけ)る姫(ひめ)百合(ゆり)の不レ所レ知
(し
らえぬ)戀(こひ)は苦(くるしき)物(もの)ぞ(万1500)
夜
麻(やま・山)の奈(な・名)と伊賓(いひ)都夏(つげ・續)とかも佐用比賣(さよひめ)がこの野麻(やま・山)の閉(へ・上)に比例(ひれ)を布利(ふ
り)けむ(万
872)
姫の声符は臣[sjien] であり、妃の声符は己[kiei] である。「臣」には宦[huan]、臥[ngua] などの音をもった漢字もある。「姫」の祖語(上古
音)は姫[hiən*] であり、「妃」の祖語(上古音)は妃[hiuəi*] に近い音だったのではあるまいか。もし、この仮説
が正しいとすれば、日本語の「ひめ」は姫[hiən*]、妃[hiuəi*] は同系のことばということになる。
日本書紀には「媛(ひめ)蹈鞴(たたら)五十鈴
(いすず)媛(ひめ)命(みこと)」(神武前紀)の名がみえ、「媛」が使われている。愛媛県の「媛」である。「媛」の古代中国語音は媛[hiuan]であり、日本語の「ひめ」に音義ともに近い。
○同源語:
夏(なつ・熱)、野(の)、姫・比賣(ひめ)、知
(しる)、苦(くる)し、夜麻(やま・山)、奈(な・名)、都夏(つげ・續)、
【ひも(紐・繙・絆)】
吾
妹兒(わぎもこ)が結(ゆひ)てし紐(ひも)を将レ解
(とかめ)やも絶(たえ)ば絶(たゆ)とも直(ただ)に相(あふ)までに(万1789)
粟
路(あはぢ)の野嶋(のじま)の前(さき)の濱風(はまかぜ)に妹(いも)が結(むすび)し紐(ひも)吹(ふき)返(かへす)(万251)
現代の日本語では「繙」は「ひもとく」と動詞に
使われ、「絆」は絆(きずな)として定着している。
○同源語:
吾妹兒(わぎもこ)、紐(ひも・絆・繙)、絶(た
え)る、直(ただ)、相(あふ・合)、野(の)、嶋(しま・洲)、濱(はま)、妹(いも)、返(かへす・還)、
【ひら(平)】
樂
浪(ささなみ)の平(ひら)山風(やまかぜ)の海(うみ)吹(ふけ)ば釣(つり)為(する)海人(あま)の袂(そで)變(かへる)見ゆ(万1715)
韻尾の[-ng]がラ行に転移した例としては、乗[djəng] のる、狂[giuang] くるふ、香[xiang] かをり、凝[ngiəng] こる、通[thong] とほる、などをあげることができる。
○同源語:
浪(なみ)、山(やま)、海(うみ)、吹(ふ
く)、釣(つり)、海人(あま)、袂(そで・袖)、變(かへる・還)、見(みる)、
【ひる・ふる・ほす(干・乾)】
妹
(いも)が見(み)し屋前(やど)に花(はな)咲(さき)時(とき)は経(へ)ぬ吾(わが)泣(なく)涙(なみだ)未レ干
(いまだひなく)に(万
469)
三 川(みつかは)の淵(ふち)瀬(せ)も不レ落 (おちず)左提(さで・小網)刺(さす)に衣手(ころもで)潮(ぬれぬ・濡)干(ほす)兒(こ)は無(なし)に(万1717)
荒妙(あらたへ)の 衣(ころも)の袖(そで)は 乾(ふ
る)時(とき)も無(なし)
(万159)
春
(はる)過(すぎ)て夏(なつ)來(きたる)らし白妙(しろたへ)の衣(ころも)乾有(ほしたり)天(あま)の香來山(かぐやま)(万28)
例:干[kan](カン・ひる・ほす)、戸(コ・へ)、家[kea](カ・ケ・へ)、蓋[kat](ガイ・ふた)、 經[kyeng](ケイ・ふる)、古[ka](コ・ふるい)、減[kəm](ゲン・へす・へる)、骨[kuət](コ ツ・ほね)、頬[kyap](キョウ・ほほ)、など、
日本語の「ひる」「ほす」は中国語の「乾」
「干」と同源であろう。「干」は干(かる)にも用いられることもある。
妹(いも)、見(みる)、花(はな)、咲(さ
く)、時(とき)、経(へる)、吾(われ)、泣(なく)、未(いまだ)、川(かは・河)、淵(ふち)、落(おちる・堕)、刺(さす)、手(て)、潮(ぬれ
る・濡)、兒(こ)、無(な)し、春(はる)、過(すぎ)る、夏(なつ・熱)、來(く)る)、天(あめ)、香(か)、山(やま)、霍公鳥(ほととぎす・
隹)、今(いま)、音(こゑ・声)、
[k-] の例:廣[kuang] ひろい、古[ka] ふるい、經[kyeng] ふる、蓋[kat] ふた、骨[kuət] ほね、
[h-] の例:羽[hiua] は、灰[huəi] はひ、匣[heap] はこ、華[hoa] はな、挟[hyap] はさむ、
[p-] の例:濱[pien] はま、腹[piuək] はら、拂[piuət] はらふ、剥[peok] はぐ、稗[pie] ひえ、
【ひろい(廣)】
靫
(ゆき)懸(かく)る伴(ともの)雄(を)廣(ひろ)き大伴(おほとも)に國(くに)将レ榮
(さかえむ)と月(つき)は照(てる)らし(万1086)
大
野路(おほのぢ)は繁道(しげぢ)森徑(もりみち)しげくとも君(きみ)し通(かよは)ば徑(みち)は廣(ひろ)けむ(万3881)
例:姫[kiə] ひめ、機[kiəi]はた、古[ka] ふるい、蓋[kat] ふた、骨[kuət] ほね、光[kuang] ひかり、
経[kyeng] へる、頬[kyap] ほほ、
また、韻尾の[-ng]はラ行に転移することがある。日本語の「ひろし」
は中国語の「廣」と同源のことばである。
○同源語:
懸(かける)、雄(を)、國(くに)、榮(さか
え)る、照(てる)、野(の)、君(きみ)、
【ひろふ(拾)】
机
(つくゑ)の嶋の 小螺(しただみ)を い拾(ひろひ)持(もち)來(き)て 石(いし)以(もち) 都追伎(つつき)破夫利(やぶり)、、(万3880)
暇
(いとま)有(あら)ば拾(ひりひ)に将レ徃
(ゆかむ)住吉(すみのえ)の岸(きしに)因(よると)云(いふ)戀(こひ)忘(わすれ)貝(かひ)(万1147)
東京の下町方言などではヒとシの区別がつかない
といわれるが、中国語音韻史のなかでも「ヒ」は口蓋化によって「シ」に変化したことが分かる。古代日本語のなかでも中国語の[p-]はサ行に転移してあらわれることがある。
例:品[phiəm](ヒン・しな)、標[biao](ヒョウ・しめ)、
○同源語:
机(つくゑ・卓)、嶋(しま・洲)、來(くる)、
都追伎(つつく・突)、徃(ゆく・行)、住(すむ)、因(よる)、忘(わすれ)る、貝(かひ・蛤)、
【ふ・ふる(経・歴)】
海
(わた)の底(そこ)奥(おき)は恐(かしこし)礒廻(いそみ)従(より)水手(こぎ)運(たみ)徃(ゆか)為(せ)月(つき)は雖二経過一(へ
ぬとも)(万
3199)
妹
(いも)が見(み)し屋前(やど)に花(はな)咲(さき)時(とき)は経(へ)ぬ吾(わが)泣(なく)涙(なみだ)未レ干
(いまだひなく)に(万
469)
年
(とし)も不レ歴
(へず)反(かへり)來(こ)なむと朝(あさ)影(かげ)に将レ待
(まつらむ)妹(いも)し面影(おもかげ)に所レ見
(みゆ)(万
3138)
[k-][g-] 系の例:蓋[kat](ガイ・ふた)、骨[kuət](コツ・ほね)、光[kuang](コウ・ひかり)、
頬[kyap](キョウ・ほほ)、鋏[kyap](キョウ・はさみ)、篋[keap](キョウ・はこ)、干
[kan](カン・ひる)、掘[giuət](クツ・ほる)、原[ngiuan](ゲン・はら)、など
[h-][x-] 系の例:灰[huəi](カイ・はひ)、匣[heap](コウ・はこ)、降[hoəm](コウ・ふる)、
挟[hyap](キョウ・はさむ)、火[xuəi](カ・ひ)、花[xoa](カ・はな)、惚[xuət](コツ・
ほれる)、など。
韻尾の[-ng] がラ行に転移した例:平[bieng] ひら、倉[tsang] くら、蔵[dzang] くら、
乗[djəng] のる、狂 [giuang] くるふ、香[xiang] かをり、通[thong] とほる、軽[kyeng] かるい、
廣[kuang] ひろい、
○同源語:
奥(おき・澳)、徃(ゆく・往)、妹(いも)、見
(みる)、花(はな)、咲(さく)、時(とき)、吾(わが)、泣(なく)、未(いまだ)、反(かえる・還)、來(く)る、影(かげ)、面(おも)、見(み
る)、
【ふける(深・更深)】
吾
(わが)勢祜(せこ)を倭(やまと)へ遣(やる)と佐夜(さよ)深(ふけ)て鶏鳴(あかとき)露(つゆ)に吾(わが)立(たち)所レ霑
(ぬれ)し(万
105)
吾
(わが)背子(せこ)を且今(いまか)且今(いまか)と待(まち)居(をる)に夜(よの)更深(ふけ)去(ぬれ)ば嘆(なげき)つるかも(万2864)
○同源語:
吾(わが)、勢祜・背子(せこ)、夜(よる)、鶏
鳴(あかとき・暁時)、立(たつ)、霑(ぬれ・濡)る、今(いま)、居(を)る、嘆(なげ)く、
【ふす(伏・臥)】
神
風(かむかぜ)の伊勢(いせ)の濱荻(はまをぎ)折(をり)伏(ふせて)客宿(たびね)や将レ為
(すらむ)荒(あらき)濱邊(はまべ)に(万500)
蒸
(むし)被(ぶすま)なごやが下(した)に雖レ臥
(ふせれども)与レ妹
(いもとし)不レ宿
(ねね)ば肌(はだ)し寒(さむ)しも(万524)
「臥」の古代中国語音は臥[ngua] である。疑母[ng-]は後口蓋音音であり、喉音[h-] に調音の位置が近く、転移することがある。
[ng-]がハ行であらわれる例:牙[ngea] は、涯[ngai] はて、外[nguat] ほか、
○同源語:
神(かみ・かむ)、濱(はま)、荻(をぎ)、折
(をる)、宿(ねる・寐)、荒(あら)き、邊(べ)、妹(いも)、
【ふた(蓋)】
[女
感]*嬬
(をとめ)らが 手(て)に取(とり)持(もて)る 真鏡(まそかがみ) 蓋上山(ふたがみやま)に 許(こ・木)の久礼(くれ・昏)の 繁(しげ)き谿
邊(たにべ)を 呼びとよめ、、(万4192)
語頭の[k-]が日本語でハ行であらわれる例:干[kan]ひる、廣[kuang] ひろし、古[ka] ふるい、經[kyeng]
へる、骨[kuət] ほね、など
○同源語:
[女感]*嬬(をとめ・嬬)、手(て)、取(とる)、真
(ま)、鏡(かがみ)、山(やま)、許(こ・木)、久礼(くれ・昏)、邊(へ)、
【ふち(淵)】
吾
(わが)行(ゆき)は久(ひさに)は不レ有
(あらじ)夢(いめ)の和太(わだ)湍(せに)は不レ成
(ならず)て淵(ふちに)有毛(あらぬかも)(万335)
三
川(みつかは)の淵(ふち)瀬(せ)も不レ落
(おちず)左提(さで・小網)刺(さす)に衣手(ころもで)潮(ぬれぬ)干(ほす)兒(こ)は無(なし)に(万1717)
古代中国語の頭音の[h-] は日本漢字音では脱落するものが多い。
例:圓[hiuən] エン、垣[hiuan] エン、媛[hiuan] エン、園[hiuan] エン、猿[hiuan] エン、遠[hiuan] エン、
員[hiuən] イン、院[hiuan] イン、運[hiuən] ウン、雲[hiuən](ウン・くも)、
古代中国語の喉音[h-] は日本語の訓ではハ行であらわれることがある。
例:羽[hiuə] は、戸[ha] へ、華[hoa] はな、閑[hean] ひま、降[hoəm]] ふる、宏[hoəng] ひろい、
含[həm] ふふむ、
○同源語:
吾(わが)、行(ゆく)、夢(いめ)、三(み)、川(かは・河)、落(おち・堕)る、刺(さ)す、手(て)、潮(ぬれる・濡)、干(ほす)、兒(こ)、無
(な)し、
【ふで・ふみて(筆)】
吾
(わが)爪(つめ)は 御弓(みゆみ)の弓波受(ゆはず) 吾(わが)毛(け)らは 御筆(みふで)はやし 吾(わが)皮(かは)は 御(み)箱(はこ)
の皮(かは)に、、(万
3885)
中国語の韻尾[-t]を日本語でタ行であらわすものとしては、次のよう
な例をあげることができる。
例:舌[djiat] した、鉢[puat] はち、蓋[kat] ふた、佛piuət] ほとけ、葛[kat] かづら、絶[dziuat] たつ、
熱[njiat] あつい、拙[tjiuat] つたない、
○同源語:
吾(わが)、爪(つめ)、御(み)、弓(ゆみ)、
毛(け)、箱(はこ・筐)、
【ふな(鮒)】
香
(こり)塗(ぬれ)る塔(たふ)に莫(な)依(よりそ)川隅(かはくま)の屎鮒(くそふな)喫(はめ)る痛(いたき)女奴(めやつこ)(万3828)
中国語の疑母[ng-] はいわゆる鼻濁音である。古代日本語では鼻母音[ng-] が語頭に来ることがなかったので転移した。疑母[ng-] はマ行であらわれることが多いが、ナ行であらわれ
ることもある。
[ng-] がマ行であれわれる例:眼[ngean] め、御[ngia] み、元[ngiuan] もと、迎[ngyang] むかへる、
詣[ngyei] まうづ、
[ng-] がナ行であらわれる例:額[ngeak] ぬか、訛[nguai] なまり、業[ngyap] なり、偽[ngiuai] にせ、
睨[ngei] にらむ、願[ngiuan] ねがう、
○同源語:
香(こり)、塗(ぬる)、塔(たふ)、莫(な)、
依(よる)、川(かは・河)、痛(いた)き、女(め)、
【ふね(船・舟・舶・盤)】
何
所(いづく)にか船泊(ふなはて)為(す)らむ安礼(あれ)の埼(さき)榜(こぎ)たみ行(ゆき)し棚(たな)無(なし)小舟(をぶね)(万58)
海
若(わだつみ)の何(いづれの)神(かみ)を齊祈(いのら)ばか徃方(ゆくさ)も來方(くるさ)も舶(ふね)の早(はや)けむ(万1784)
スウェーデンの言語学者ベルンハルト・カールグ
レン(1889-1978)は、その著書『言語学と古代中国』(1920年、オスロ)のなかで、「現代の日本語では「ふ
ね」は「舟」しか意味しないが、古事記では「盆」の意味にも使われている。英語でもvesselは船を意味するばかりでなく、窪んだ容器を意味す
る。」としている。
江南地方は早くから水運がひらけ、船に関する文
字も多い。舫[piuang]、舨[piuan]、艀[biu]、艦[heam]、帆[biuəm]、などいずれも船に関係のある文字である。「舫」
は「もやいぶね」であり「舟を並べてもやる」ことをいう。「帆」は「ほ」あるいは「ほかけぶね」である。「舨」は「舢舨」などとして使われ「小舟」であ
る。「艀」は小舟であり、わが国では「はしけ」を言う。「艦」は「戦い船」である。舫[piuang]、舨[piuan]、艀[biu]、艦[heam]、帆[biuəm]、も「ふね」と同系のことばである。
○同源語:
泊(はつ)、埼(さき)、行・徃(ゆく)、棚(たな・壇・段)、無(な)し、小(を)、海(うみ)、神(かみ)、来(くる)、
【ふふむ・ふくむ(含)】
春
雨(はるさめ)を待(まつ)とにし有(あら)し吾(わが)屋戸(やど)の若木(わかき)の梅(うめ)も未(いまだ)含有(ふふめり)(万792)
例: 限[heam] かぎり、河[hai] かは、牙[ngea] きば、瓦[ngoai] かはら、願[ngiuan] ねがふ、直[diək] ただ、畳[dyap] たたみ、渟[dyeng] とどまる、續[ziok] つづく、集[dziəp] つどふ、雀[tziôk] すずめ、進[tzien] すすむ、
もうひとつの解釈は日本語の「ふくむ」と中国語
の包含[peu-həm]とするものである。いずれにしても、日本語の「ふ
ふむ」「ふくむ」は中国語から派生したものである。
○同源語:
春(はる)、吾(わが)、若(わかい)、木(き・
枝)、梅(うめ)、未(いまだ)、
【ふみ(圖・書・文)】
我
國(わがくに)は 常世(とこよ)に成(なら)む 圖(ふみ)負(おへ)る 神(くすしき)龜(かめ)も 新代(あらたよ)と 泉(いづみ)の河(かは)
に、、(万
50)
書
殿(ふみどの)にて餞酒(うまのはなむけ)せし日の倭歌(万876題詞)
韻尾の[-n] がマ行であらわれる例:濱[pien] はま、絆[puan] ひも、眠[myen] ねむる、呑[thən] のむ、
絹[kyuan] きぬ、肝[kan] きも、蝉[zjian] せみ、進[tzien] すすむ、
韻尾の[-n] がナ行であらわれる例:難波[nan-] なには、壇[dan]・段[duan] たな、殿[dyən] との、
○同源語:
我(わが)、國(くに)、常(とこ)、世・代
(よ)、負(おふ)、亀(かめ)、泉(いづみ)、河(かは)、殿(との)、
【ふる(零・落・降)】
田
兒(たご)の浦(うら)ゆ打(うち)出(いで)て見(みれ)ば真白(ましろに)ぞ不盡(ふじ)の高嶺(たかね)に雪(ゆき)は零(ふり)ける(万318)
三
吉野(みよしの)の 耳我(みみがの)嶺(みね)に 時無(ときじく)ぞ 雪(ゆき)は落(ふり)ける 間(ま)無(なく)ぞ 雨(あめ)は零(ふり)け
る、、(万
25)
同じ声符をもった漢字がラ行とカ行に読み分けら
れるものがいくつかある。カ行音は入りわたり音[h-]が発達したものであり、ラ行音は入りわたり音[h-]が脱落したものである。
例:果(カ)・裸(ラ)、各(カク)・洛(ラ
ク)、監(カン)・藍(ラン)、兼(ケン)・簾(レ
ン)、京(キョウ)・涼(リョウ)、験(ケ
ン)・斂(レン)、楽(ガク・ラク)など
○同源語:
田(た)、兒(こ)、打(うつ)、出(いづ)、見
(みる)、真(ま)、嶺(みね)、三(み)、野(の)、耳(みみ)、時(とき)、間(ま)、無(な)く、
【ふるし(古・故)】
立
(たち)易(かはり)古(ふるき)京(みやこ)と成(なりぬれ)ば道(みち)のしば草(くさ)長(なが)く生(おひ)にけり(万1048)
古
(いにしへ)の人(ひと)に和礼(われ)有(あれ)や樂浪(ささなみ)の故(ふるき)京(みやこ)を見(みれ)ば悲(かなし)き(万32)
「古」と同じ声符をもった漢字の古代音は[k-][kh-][h-]などであらわれる。後口蓋音[k-] は喉音[h-] と調音の位置が近く、転移しやすい。「古」と同じ
声符をもつ漢字でも古代中国語音は[k-][kh-][h-] などに分かれるものがある。[k-]は後口蓋(軟口蓋)音であり、喉音[h-] と調音の位置が近く、転移しやすい。同じ声符をもった漢字でも、[ka][kha][ha] に読み分けるものもみられる。
例:古[ka]、故[ka]、固[ka]、箇[kai]、枯[kha]、胡[ha]、湖[ha]、涸[hak]、
○同源語:
立(たつ)、京(みやこ)、草(くさ)、長(なが
い)、和礼(われ・我)、浪(なみ)、見(みる)、
【へ(邊・方)】
奥
(おきつ)波(なみ)邊波(へなみ)の來(き)縁(よる)左太(さだ)の浦(うら)の此(この)佐太(さた)過(すぎ)て後(のち)将レ戀
(こひむ)かも(万
2732)
春
草(はるくさ)の繁(しげき)吾(わが)戀(こひ)大海(おほうみの)方(へに)徃(ゆく)浪(なみ)の千重(ちへに)積(つもりぬ)(万1920)
○同源語:
奥(おき・澳)、波・浪(なみ)、来(くる)、縁
(よる)、此(こ)れ、過(すぎ)る、春(はる)、草(くさ)、吾(わが)、海(うみ)、徃(ゆく・行)、千(ち)、
【へ(家・陛)】
吾
(わが)背子(せこ)が古家(ふるへ)の里(さと)の明日香(あすか)には乳鳥(ちどり)鳴(なく)成(なり)嬬(つま)待(まち)かねて(万268)
伊
母(いも・妹)が陛(へ・家)に由伎(ゆき・雪)かも不流(ふる・降)と弥流(みる・見)までにここだも麻我不(まがふ)烏梅(うめ)の波奈(はな・花)
かも(万
844)
万葉集第一番目の歌「この岳(をか)に 菜
(な)採(つ)ます児(こ) 家(いへ)聞かな 告(の)らさね」の「家」は「いへ」である。日本語の家(いへ)は家(へ)が語幹で、家(いへ)は「へ」
に母音を添加したものである可能性がある。記紀万葉の時代の日本語では、中国語の[k-]も[h-]もハ行であらわれることが多い。
[k-] がハ行であらわれる例:蓋[kat] ふた、干[kan] ひる、廣[kuang] ひろい、古[ka] ふるい、
經[kyeng] へる、骨[kuət] ほね、光[kuang] ひかり、頬[kyap] ほほ、
[h-] がハ行であらわれる例:例:羽[hiuə] は、戸[ha] へ、華[hoa] はな、閑[hean] ひま、脛[hyeng]
はぎ、降[hoəm] ふる、宏[hoəng] ひろい、弘[huang] ひろい、含[həm] ふくむ
○同源語:
吾(わが)、背子(せこ)、古(ふるい)、家・陛
(いえ・へ)、香(か)、乳鳥(ちどり・千鳥)、鳴(なく)、嬬(つま・嬬)、伊母(いも・妹)、不流(ふる・降)、弥流(みる・見)、烏梅(うめ)、波
奈(はな・花)、
【ほ(穂)】
秋
田(あきのた)の穂上(ほのへ)に霧相(きらふ)朝(あさ)霞(かすみ)何時(いつ)邊(へ)の方(かた)に我(わが)戀(こひ)将レ息
(やまむ)(万
88)
秋
田(あきのた)の穂向(ほむき)の所レ依
(よれる)片縁(かたよりに)吾(われ)は物(もの)念(おもふ)つれ無(なき)物(もの)を(万2247)
しかし、「穂」の声符は恵[hyuet] である。「穂」の祖(上古音)に穂[hyuet*] に近い音があったと考えることができる。穂[ziuat] は唐代の音であり、上古音の穂[hyuet*] が摩擦音化したものである可能性がある。日本語の
「ほ」は上古中国語の穂[hyuet*] と同系のことばであろう。
漢字には音ではサ行であらわれ、訓ではカ行また
はハ行であらわれるものがある。サ行音はカ行音やハ行音が摩擦音化したものである。訓のほうが古く、音は新しい。
例;歯[thjiə](シ・は)、鍼[tjiəm](シン・はり)、春[thjiuən](シュン・はる)、秦[dzyen]
(シン・はた)、
榛[tzhen](シン・はり)、辛[sien](シン・からい)、神[djien](シン・
かみ)、切[tsyet](セツ・きる)、斬[tzheam](ザン・きる)、
また、同じ声符の漢字をサ行(摩擦音)とカ行
(後口蓋音)に読み分ける漢字がいくつかみられる。
例:感[həm](カン)・鍼[tjiəm](シン)、赫[xeak](カク)・赤[thjiyak](シャク)、技[gie](ギ)
・枝[tjie](シ)、祇[gie](ギ)・氏[zie](シ)、庫[kho](コ)・車[kia](シャ)、坤[khuan]
(コン)・神[djien](シン)、
埼玉県行田市の稲荷山で発見された鉄剣には「獲
加多支鹵」という銘文があり「ワカタケル」と読む。「ワカタケル」は古事記には「大長谷若建命」とあり、日本書紀には「大泊瀬幼武天皇」とあって、雄略天
皇のことである。「支」は支(キ)が古く、支(シ)が古い。
○同源語:
田(た)、相(あふ)、霞(かすみ・霞
霧)、邊(へ)、我(わが)、向(むき)、依・縁(よる)、吾(われ)、物(もの)、念(おもふ)、無(な)き、
中国語の音韻研究は詩の韻の研究からはじまって
いるので、韻尾については詳しいが、頭音についてはまだ解決されていない問題があるように思われる。中国語の音韻学では「穂」は「去声・至」とあって韻尾
が「至」と同じであることはわかる。去声とは四声(平声・上声・去声・入声音)のう
ち三番目の声調である。平声は平調形、上声は降昇形、去声は降調形であり、入声音は韻尾に[-p][-t][-k]を伴う声調である。
中国には古くから反切といういう表音法があって
頭音と韻尾を分けて表示する方法もある。「穂」は「敍位切音遂寘韻去声」とあって、頭音が「敍」と同じであり、韻は「寘」で、四声は「去声」であることを
示しているが、これも「敍」という漢字の音価をあらかじめ知らなければ音価をしることはできない。循環論になっているうえ、唐代の規範音を示してはいるも
のの、日本が中国大陸と接触を持ちはじめた弥生時代の中国語音のことはわからない。韻尾の「寘」は「至」に相当する音であるが、声符が「眞」なので「シ
ン」と読むのか「シ」と読むのかわからない。
その点、漢字の70%は声符をもっていて、漢字
ができた時代の音を仕えているので、上古音の復元の手がかりを与えてくれる。「穂」は漢字ができた時代には恵[hyuet]と同じ音価をもっていたと推論することができる。
【ほ(帆)】
海
人(あま)小船(をぶね)帆(ほ)かも張(はれ)ると見(みる)までに鞆(とも)の浦廻(うらみ)に浪(なみ)立有(たてり)所レ見
(みゆ)(万
1182)
○同源語:
海人(あま)、小(を)、船(ふね・盤)、見(み
る)、廻(み・まわる)、浪(なみ)、立(たつ)、
【ほえる・ほゆ(吼・吠)】
十
六(しし)待(まつが)如(ごと) 床(とこ)敷(しき)て 吾(わが)待(まつ)公(きみを) 犬(いぬ)莫(な)吠(ほえ)そね(万3278)
雷
(いかづち)の 聲(おと)と聞(きく)まで 吹(ふき)響(なせ)る 小角(くだ)の音(おと)も 敵(あだ)見有(みたる) 虎(とら)か叫吼(ほゆ
る)と 諸人(もろびと)の 恊(おびゆ)るまでに、、(万199)
例:火[xuəi] ひ、灰[huəi] はい、花[xoa はな、揮[xiuəi]ふるう、化[xuai] ばける、響[xiang]ひびく、
華[hoa] はな、戸[ha] へ、荷[hai]子・はす、脛[hyeng] はぎ、弘[huəng] ひろい、
宏[hoəng] ひろい、含[həm] ふふむ、降[hoəm] ふる、
古代日本語のハ行には中国語の唇音([p-][b-][m-])系のことばと喉音([h-][x-])系のことばの二つの系統のことばが弁別されずに
使われている。
○同源語:
床(とこ)、吾(わが)、公(きみ)、犬(い
ぬ)、莫(な)、聲・音(おと)、見(みる)、
【ほこ(桙)】
池
神(いけがみ)の力士儛(りきしまひ)かも白鷺(しらさぎ)の桙(ほこ)啄(くひ)持(もち)て飛(とび)渡(わたる)らむ(万3831)
董同龢は「矛」「牟」の上古音を矛・牟[miog] と再構している。「ほこ」は上古中国語音の痕跡を
とどめているものであろう。古代日本語では濁音が語頭にくることがなかったので日本語では語頭の鼻濁音[m-] はハ行に転移したと考えられる。
○同源語:
神(かみ)、力士(リキシ)、儛(まひ)、鷺(さ
ぎ・鵲)、飛(とぶ)、渡(わたる)、
【ほたる(螢)】
黄
葉(もみちば)の 過(すぎて)行(いにき)と 玉梓(たまづさ)の 使(つかひ)の云(いへ)ば 螢(ほたる)成(なす) 髣髴(ほのかに)聞(きき)
て、、(万
3344)
日本語の「ほたる」は中国語の「螢」と関係のあ
ることばである可能性は否定できない。しかし、「ほ+たる」の「たる」はどこからきたのだろうか。日本語の「ほたる」は「火垂」という説もある。
野坂昭如の『火垂るの墓』は知られているが、記紀万葉にはその用例はない。「はたる」「火垂」という連想はまことに文学的である。しかし、これを言語学的
に検証することはむずかしい。
○同源語:
葉(は)、過(すぎる)、行(いぬ)、
【ほとけ(佛)】
佛
(ほとけ)造(つくる)真朱(まそほ)不レ足
(たらす)は水(みづ)渟(たまる)池田(いけだ)の阿曾(あそ・朝臣)が鼻上(はなのうへ)を穿(ほ)れ(万3841)
古代中国語の「佛」は佛[biuət] である。日本語の「ほとけ」は「佛」から派生した
ことばであろう。「ほと+け」の「け」は不明だが、仏教伝来以前に「ほとけ」ということばが「やまとことば」にあったとは考えられない。
○同源語:
造(つくる)、真(ま)、渟(たま)る、田
(た)、阿曾(あそ・朝臣)、穿(ほる・掘)、
【ほむ(誉・褒)】
黒
樹(くろき)取(とり)草(くさ)も苅(かり)つつ仕(つかへ)めど勤(いそしき)和氣(わけ)と将レ誉
(ほめむ)とも不レ有
(あらず)(万
780)
古代日本語では濁音が語頭に立つことがなかった
ので、語頭の[b-]に清音「ほ」を添加して「ほ+む」になったもので
あろう。
「勤(いそしき)和氣(わけ)」の「わけ」は
「王」であろう。「王」の現代北京語音は王(wang) である。
○同源語:
黒(くろ)い、樹(き)、取(とる)、草(く
さ)、苅(かる)、和氣(わけ・王)、
【ほる(穿・掘)】
安
志妣(あしび・馬酔木)成(なす)榮(さかえ)し君(きみ)が穿(ほり)し井(ゐ)の石井(いしゐ)の水(みづ)は雖レ飲
(のめど)不レ飽
(あかぬ)かも(万
1128)
佛
(ほとけ)造(つくる)真朱(まそほ)不レ足(たらす)は水(みづ)渟(たまる)池田(いけだ)の阿曾(あそ・朝臣)が鼻上(はなのうへ)を穿(ほ)れ(万3841)
[k-][g-] 系の例:蓋[kat](ガイ・ふた)、骨[kuət](コツ・ほね)、頬[kyap](キョウ・ほほ)、
閑[kean](カン・ひま)、家[kea](カ・ケ・へ)、古[ka](コ・ふるい)、広[kuang](コウ・
ひろい)、干[kan](カン・ひる・ほす)、経[kyeng](ケイ・へる)、など、
[x-][h-]系 の例:灰[huəi](カイ・はひ)、火[xuəi](カ・ひ)、羽[hiuə](ウ・)は、戸[ha](コ・へ)、
匣[heap](コウ・はこ)、華[hoa](カ・はな)、檜[huai](カイ・ひのき)、挟[hyap](キョウ・
はさむ)、荷[hai-]子(カシ・はす)、弘[huəng](コウ・ひろい)、含[həm](ガン・ふふむ)、
降[hoəm](コウ・ふる)、惚[xuət](コツ・ほれる)、など
○同源語:
榮(さかえ)、君(きみ)、飲(のむ・呑)、佛
(ほとけ)、造(つくる)、真(ま)、渟(たまる)、田(た)、
【ほろぼす(滅・亡)】
君
(きみ)が由久(ゆく)道(みち)の奈我弖
(ながて)を
久里(くり)多々祢(たたね)也伎(やき)保呂煩散牟(ほろぼささむ)安米(あめ)の火(ひ)もがも(万3724)
古代中国語の「滅」「亡」は滅[miat]、亡[miuang] である。王力は『同源字典』のなかで「亡」と
「滅」は同源であるとしている。語頭の[m-] は鼻濁音であり、日本語ではハ行に転移した。韻尾
の[-t]は[-l]に転移した。亡[miuang] の韻尾[-ng]は日本語ではカ行であらわれることがもあるが、こ
の場合はラ行に転移している。
日本語の「ほろぶ」「ほろぼす」は中国語の
「滅」「亡」に音義ともに近く、同源である。
○同源語:
君(きみ)、由久(ゆく・行)、奈我弖(ながて・
長手)、多々祢(たたね・畳)、也伎(やき・焼)、安米(あめ・天)、火(ひ)、
【は行のまとめ】
日本語のハ行音の起源は大きくわけて脣音[p-][ph-][m-]系のことばと喉音系[x-][h-]系・後口蓋音[k-][g-][ng-]系のことばの二つにわけられる。
1.唇音系[p-][ph-][m-]系のことば
○剥[peok]はぐ、幡[phiuan]はた、濱[pien]はま、腹[piuək]はら、拂[piuət]・祓[biiuat]はらふ、
氷[pieng]ひ、稗[pie]ひえ、絆[puan]ひも、筆[piet]ふで、鮒[pio]魚[ngia]ふな、邊[pyen]へ、
方[piuang]へ、
○佩[buə]はく、泊[beak]はつ、匍匐[bua-biuk]はふ、繙[biuan]ひも、平[being]ひら、伏[biuək]
ふす、盤[buan]ふね<舟・船>、帆[biuəm]ほ、吠[biuat]ほえる、佛[biuət]ほとけ、褒[biu]ほむ、
○墓[mak]はか、文[miuən]ふみ、桙・矛[miu]ほこ、滅[miat]・亡[miuang]ほろぶ、
韻尾の[-p]が独立して音節をなす例としては、葉[jiap]は、がある。
2.喉音系[x-][h-]系のことば
○花[xoa](カ・はな)、火[xuəi](カ・ひ・ほ)、吼[xo](ク・コウ・ほゆ)、
○羽[hiua](ウ・は)、匣[heap](コウ・はこ)、挟[hyap](キョウ・はさむ)、荷[hai]子(カ・
はちす・はす)、華[hoa](カ・はな)、灰[huəi](カイ・はひ)、檜[huai](ケ・カイ・ひ)、
媛[hiuan](エン・ひめ)、淵[(h)jyuən*](エン・ふち)、含[həm](ガン・ふふむ・ふくむ)、
降[hoəm](コウ・ふる)、螢[hyueng](ケイ・ほたる<火垂>)、
3.後口蓋音[k-][g-][ng-]の転移したことば
○篋[kyəp](キョウ・はこ)、墾[khən](コン・はり)、光[kuang](コウ・ひかり)、姫[kia]
(キ・ひめ)、干・乾[kan](カン・ひる・ほす)、廣[kuang](コウ・ひろい)、更[keang]
(コウ・ふける)、蓋[kat](ガイ・ふた)、経[kyeng](ケイ・ふ・ふる)、古・故[ka](コ・
ふるい)、家[kea](カ・へ・いへ)、
○牙[ngea](ガ・は)、芽子[ngea-](ガ・はぎ)、原[ngiuan](ゲン・はら)、臥[ngua](ガ・
ふす)、掘[giuət](クツ・ほる)、
4. 祖語(上古音)の入りわたり音[h-*]の痕跡と思われることば
○陵[liəng/(h)liəng*](リョウ・はか)、蓮[(h)lian*](レン・はす)、落[lak/(h)lak*](ラク・
ふる)、零[lyəng/(h)lyəng*](レイ・ふる)、
○拾[zjiəp/həp*](シュウ・ひろふ・ひりふ)、穂[ziuat/hyuet*](スイ・ほ)、榛[tshen/hən*]
(シン・はり)、
針[tshiəm/həm*](シン・はり)、
○春[thjiuən](シュン・はる)、歯[thiə](シ・は)、紐[thiô](チュウ・ひも)、穿[thjiuən](セン・ ほる)、
◎ま行
【ま・め(目・眼)】
人
目(ひとめ)多(おほみ)眼(め)にこそ忍(しのぶ)れ小(すくなく)も心(こころの)中(うち)に吾(わが)念(おもは)莫(な)くに(万2911)
天
雲(あまぐも)を 日(ひ)の目(め)も不レ令レ見
(みせず) 常闇(とこやみ)に 覆(おほひ)賜(たまひ)て、、(万199)
また、日本語の「め」は眼[ngean] の頭音がマ行に転移し、韻尾の[-n] が脱落したものだとみることもできる。眼[ngean]の頭音[ng-] と[m-] はともに鼻音であり、転移しやすい。
例:芽[ngea] め、御[ngia] み、、元[ngiuan] もと、迎[ngyang] むかへる
王力は『同源字典』のなかで目[miuk] と眸[miu] は同源であるとしている。いずれにしても日本語の
「め」は中国語の「目」「眼」「眸」などと同系のことばであろう。
○同源語:
目・眼(め)、小(すくな)い、心(こころ)、吾
(わが)、念(おもふ)、莫(なく)、天(あめ)、雲(くも)、見(みる)、常(とこ)、闇(やみ)、
日本語の身体をあらわすことばには中国語と同源と
思われることばが多い。日本語と中国語とは文法の構造、音韻構造などは異なるものの、基本語彙に共通なものが多いということは、日本語の形成にあたって中
国語の影響がかなり早い時期から、長期間にわたってあったことを示している。
例:腕[uan] うで、肩[kyan] かた、肝[kan] きも、口[kho] くち、舌[djiat] した、手[tjiu*] て、
歯[thjiə]・牙[ngea] は、脛[ngyang] はぎ、腹[piuək] はら、腹臍[piuək tzyei] へそ、
頬[kyap] ほほ、目[miuk]・眼[ngean] め、眉[miei] まゆ、耳[njiə] みみ、
【ま(真)】
水
薦(みこも)苅(かる)信濃(しなの)の真弓(まゆみ)吾(わが)引(ひか)ば宇真人(うまひと)さびて不欲(いな)と将レ言
(いはむ)かも(万
96)
田
兒(たご)の浦(うら)従(ゆ)打(うち)出(いで)て見(みれ)ば真白(ましろ)にぞ不盡(ふじ)の高嶺(たかね)に雪は零(ふり)ける(万318)
例:身[sjien] み、山[shean] やま、臣[sjien] おみ、世[sjiat] よ、色[shiək] いろ、折[tjiat] をる、
織[tjiək] おる、
漢字の「真」は「まこと」と読まれることもあ
る。日本語の「まこと」は真言(まこと)と同源であろう。
薦(こも)、苅(かる)、弓(ゆみ)、吾(わ
が)、田(た)、兒(こ)、打(うつ)、見(みる)、出(いづ)る、嶺(みね)、零(ふる・降)、奇(くす)し、神(かみ)、居(を)る、嶋(しま・
洲)、
【ま(間・際)】
う
つ蝉(せみ)の人目(ひとめ)を繁(しげ)み石走(いははしの)間(ま)近(ちかき)君(きみ)に戀(こひ)度(わたる)かも(万597)
隠
口(こもりく)の泊瀬山(はつせのやま)の山際(やまのま)にいさよふ雲(くも)は妹(いも)にかも有(あら)む(万428)
○同源語:
蝉(せみ)、目(め)、間(ま)、君(きみ)、度
(わたる・渡)、隠(こもる)、口(くち)、山(やま)、雲(くも)、妹(いも)、
【まかね(真金)】
麻
可祢(まかね)布久(ふく)尓布(にふ)の麻保曾(まそほ)の伊呂(いろ)に[亻
弖]*弖(で
て)伊波(いは)奈久(なく)のみぞ安我(あが)古布(こふ)らくは(万3560)
○同源語:
麻可禰(まかね・真金)、尓布(にふ・丹生)、麻
保曾(まほそ・真)、伊呂(いろ・色)、
[亻弖]*(で・出)る、安我(あが)、
【まがり(勾)】
嶋
宮(しまのみや)勾(まがり)の池(いけ)の放鳥(はなちどり)人目(ひとめ)に戀(こひ)て池(いけ)に不レ潜
(かづかず)(万
170)
青
柳(あをやぎ)の 細(ほそき)眉根(まよね)を 咲(ゑみ)麻我理(まがり) 朝(あさ)影(かげ)見(み)つつ、、(万4192)
「勾」の祖語(上古音)には入りわたり音があっ
て、勾[h(m)əu*] あるいは[h(m)iok*] のような音であったと思われる。勾(まがり)は[m] の痕跡を留めたものであり、勾(コウ)は入りわた
り音が発達して[m]が脱落したものである。
曲[h(m)iok*] についてもおなじことがいえる。曲(まがる)は音[m] の痕跡を留めたものであり、曲(キョク)は[m] が脱落したものである。
海(カイ・うみ)の場合も同じことがいえる。
「海」の上古音は海[h(m)uə*] であり、入りわたり音[h-]が発達したものが海(カイ)であり、[m] の痕跡を留めたものが毎(マイ)である。日本語の
海(うみ)は[m-] の前に母音が添加されたもので、梅(うめ)、馬
(うま)などの例がある。
宮田一郎編『上海語常用同音字典』(光生館)に
よると、上海方言ではmの前に声門閉鎖音?あるいは入りわたり音hが聞こえるという。
例:馬(hma)、梅(hme)、母(?mu)、米(hmi)、暮(hmu)、毛(hmɔ)、墨(hmə?)、物(hmək)、
これを見ると同じ声符の漢字がカ行とマ行(また
はバ行)に読み分けられる理由が解明できる。米(こめ)は入りわたり音hが発達したものであり、米(マイ・ベイ)は入りわ
たり音が脱落したものである。
例:梅(バイ)・海(カイ)、墨(ボク)・黒(コ
ク)、物(ブツ)・忽(コツ)
中国語音で[k-] ではじまる漢字の多くが訓ではマ行であらわれる。
これらの漢字の祖語(上古音)には[(h)m-*] のような入りわたり音があったと想定すると整合的
に説明ができる。
例:求[k(m)iu](キュウ・もとむ)、球[k(m)iu](キュウ・まり)、禍[kh(m)uai](カ・まが)、
曲[kh(m)iok](キョク・まがる)、宮[k(m)iuəm](キュウ・みや)、京[k(m)yang](キョウ・みや こ)、
○同源語:
嶋(しま・洲)、宮(みや)、鳥(とり)、目
(め)、柳(やなぎ)、眉(まゆ)、根(ね)、影(かげ)、見(みる)、
日本語のなかに音はカ行で訓はマ行の単語が多い
ことは、こうした音韻構造をもった民族との関係を示唆しているのかもしれない。
また、日本語とはまったく違う言語であるが、英
語にも入りわたり音の痕跡が残されている。knife,
knock, know, knit, knee, knightなどのkは現在の英語では発音されないが、入りわたり音kの痕跡を綴り字のなかに残している。
蜻
野(あきつの)を人(ひと)の懸(かくれ)ば朝(あさ)蒔(まきし)君(きみ)が所レ思
(おもほえ)て嗟(なげき)は不レ病
(やまず・不止)(万
1405)
玉
梓(たまづさ)の妹(いも)は珠(たま)かもあしひきの清(きよき)山邊(やまへ)に蒔(まけば)散(ちり)ぬる(万1415)
○同源語:
野(の)、懸(かけ)る、君(きみ)、思(おも
ふ・念)、嗟(なげく・嘆)、妹(いも)、清(きよき)、山(やま)、邊(へ)、散(ちる)、
山
河(やまかは)を 伊波祢(いはね)さくみて 布美(ふみ・踏)等保利(とほり・通) 久尓(くに・國)麻藝(まぎ・覓)しつつ、、(万4465)
「麻藝(まぎ)」は覓[mek] である。日本書紀に「自二頓丘一覓レ国」(神代紀下)とあり、訓注に「矩弐磨儀」とあ
ることから「クニマギ」と読むことが分かる。「国を求めて」の意味である。
古代中国語の「覓」は覓[mek] である。日本漢字音は覓(ベキ・もとむ)である。
古代日本語では語頭に濁音がくることがなかったから「覓」は日本語では覓「まぐ」となった。
○同源語:
山(やま)、河(かは)、祢(ね・根)、等保利
(とほり・通)、久尓(くに・国)、麻藝(まぎ・覓)、
【まぬかる(免)】
生
(いける)者(もの) 死(しぬと)云(いふ)事(こと)に 不レ免
(まぬかれぬ) 物(もの)にし有(あれ)ば、、(万460)
○同源語:
生(いける)、死(しぬ)、物(もの)、
【まひ・まふ(儛)】
池
神(いけがみの)力士(りきし)儛(まひ)かも白鷺(しらさぎ)の桙(ほこ)啄(くひ)持(もち)て飛(とび)渡(わたる)らむ(万3831)
王力の『同源字典』によれば巫[miua]は舞[miua] と同源であるという。巫女(みこ)は舞子なのであ
る。
○同源語:
神(かみ)、力士(リキシ)、鷺(さぎ・鵲)、桙
(ほこ)、飛(とぶ)、渡(わたる)、
【まもる(守・護)】
淡
路(あふみ)の海(み)浪(なみ)恐(かしこみ)と風(かぜ)守(まもり)年(とし)はや将ニ経去一(へ
なむ)なむ榜(こぐと)は無(なし)に(万1390)
神
名火(かむなび)にひもろき立(たて)て雖レ忌
(いはへども)人(ひと)の心(こころ)は間守(まもり)不レ敢
(あへぬ)物(もの)(万
2657)
「護」の祖語(上古音)は護[h(m)o*] に近い音であったと考えられる。日本語の「まも
る」は 護[(h)mo*] の入りわたり音[h-] が脱落したものであろう。「ま+もる」の「ま」は
梅(むめ・うめ)、馬(むま・うま)のように二つの音節を重ねたものである。
○同源語:
海(うみ)、浪(なみ)、守(まもる・護)、経
(へる)、無(なし)、神(かみ)、名(な)、火(ひ)、立(たつ)、心(こころ)、物(もの)、
【まよ(眉)】
如レ眉
(まよのごと)雲居(くもゐ)に所レ見
(みゆる)阿波(あは)の山(やま)懸(かけ)て榜(こぐ)舟(ふね)泊(とまり)不レ知
(しらず)も(万
998)
月
(つき)立(たち)て直(ただ)三日月(みかづき)の眉根(まよね)搔(かき)氣(け)長(ながく)戀(こひ)し君(きみ)に相(あへ)るかも(万993)
清音
鼻濁音
濁音
(ハ行)
(マ行)
(バ行)
日本語の「まゆ」は中国語の「眉」と同源であ
る。日本語の「まよ」は蚕の繭にも用いられる。万葉集には繭(まゆ)に「眉」の字をあてたものがいくつかある。
雲(くも)、居(ゐ)、見(みる)、山(やま)、
懸(かける)、舟(ふね・盤)、知(しる)、立(たつ)、直(ただ)、根(ね)、長(なが)き、君(きみ)、相(あふ・合)、母(はは)、養蠶(かふこ・
蛺蠱)、隠(こもる)、異母(いも・妹)、
【まろ(丸)】
旅
(たび)に尚(すら)襟(ひも)解(とく)物(もの)を事(こと)繁(しげ)み丸宿(まろね)吾(わが)為(する)長(ながき)此(この)夜(よを)(万2305)
○同源語:
襟(ひも・絆・繙)、物(もの)、事(こと・
言)、宿(ね・寐)る、吾(わが)、長(なが)き、此(こ)の、夜(よる)、
【み(御)】
吾
(わが)御門(みかど)千代(ちよ)常登婆(とことば)に将レ榮
(さかえむ)と念(おもひ)て有(あり)し吾(われ)し悲(かなし)も(万183)
春
日野(かすがの)の藤(ふじ)は散(ちり)去(に)て何(なにを)かも御狩(みかり)の人(ひと)の折(をり)て将来レ挿
頭(かざさむ)(万
1974)
例:芽[ngea] め、眼[ngean] め、元[ngiuan] もと、雅美[ngea] みやび、、迎[ngyang] むかへる、
詣[ngyei] もうでる、
御(お)は御[ngia] の語頭音が脱落したものである。朝鮮漢字音は御(eo) であり日本漢字音の御(お)に近い。朝鮮漢字音で
は中国語の疑母[ng-] は規則的に脱落する。古代日本語の音韻構造は朝鮮
漢字音に近かったといえる。
御(ゴ・ギョ)は日本が本格的な文字時代になっ
て、中国語の影響で語頭に濁音が立つようになってから受け入れられた発音である。
○同源語:
吾(わが)、門(かど)、千(ち)、代(よ・
世)、常(とこ)、榮(さかえ)、念(おもふ)、野(の)、散(ちる)、狩(かり・獦)、折(をる)、挿頭(かざす・冠挿)、
【み(神)】
山
神(やまつみ)の奉(まつ)る御調(みつき)と春部(はるべ)は花挿頭(かざし)持ち、、、山川も依(よ)りて奉(つか)ふる神(かみ)の御代(みよ)か
も(万
38)
「神」と同じ声符をもった漢字に天地乾坤の
「坤」があり、古代中国語音は坤[khuan] である。声符「申」には[kh-] の音もあったものと考えられる。日本語の「かみ」
は「神」の上古音、神[khuan] を継承したものであり、「み」は神[djien] あるいは神[khuan] の頭音が失われたものである。韻尾の[-n] はマ行に転移している。
○同源語:
山(やま)、御(み)、春(はる)、花(はな)、
挿頭(かざし・冠挿)、川(かは・河)、依(より)、代(よ・世)、
【み(身)】
戀
(こひ)為(するに)死(しに)為(する)物(ものに)有(あらませ)ば我(わが)身(みは)千遍(ちたび)死(しに)反(かへらまし)(万2390)
露
(つゆ)霜(しも)の消(け)安(やすき)我(わが)身(み)雖レ老
(おいぬとも)又(また)若(をち)反(かへり)君(きみ)をし将レ待
(またむ)(万
3043)
古代中国語の「身」は身[sjien]である。日本語の身(み)は「身」の頭音が口蓋化
の影響で脱落したものである。日本語では口蓋化の影響などで注置く語の頭音が脱落することがしばしばある。
例:眞[sjien] ま、臣[sjien] おみ、息[siək] いき、色[shiək] いろ、秈[shean] しね、織[tjiək] おる、
神[djien] み、射[djyak] いる、天[thyen] あめ、赤[thjyak] あか、
○同源語:
死(しに)す、物(もの)、我(わが)、千
(ち)、反(かへる・還)、霜(しも)、消(きえる・ける)、君(きみ)、
【み(三)】
月
(つき)立(たち)て直(ただ)三日月(みかづき)の眉根(まよね)掻(かき)氣(け)長(ながく)戀(こひ)し君(きみ)に相有(あへる)かも(万993)
白
細(しろたへ)の 紐(ひも)緒(を)も不レ解
(とかず) 一重(ひとへ)結(ゆふ) 帯(おび)を三重(みへ)結(ゆひ)、、(万1800)
例:身[sjien] み、真[tjien] ま、臣[sjien] おみ、山[shean] やま、
○同源語:
立(たつ)、直(ただ)、眉(まゆ)、根(ね)、
長(なが)き、君(きみ)、相(あふ・合)、紐(ひも・絆・繙)、
【みこと(御命・御言・命)】
天
皇(おほきみ)の 御命(みこと)恐(かしこみ) 百礒城(ももしき)の 大宮(おほみや)人(ひと)の 玉桙(たまほこ)の 道(みちに)も不レ出
(いでず)戀(こふる)此(この)日(ころ)(万948)
三
吉野(みよしの)の玉松(たままつ)が枝(え)は波思吉(はしき)かも君(きみ)が御言(みこと)を持(もち)て加欲波久(かよはく)(万113)
天
(あま)照(てらす)日女(ひるめ)の命(みこと)(万167)
古代中国語の「命」は命[mieng] である。白川静の『字通』によると、「命[mieng] と令[lieng] は古くは令の一字で示されており、初期の金文では
令をその二義に用いる。」とある。「令」は「命」や「領土」を含んだ広い概念であった。日本語の「みこと」は「命言(みことば)」あるいは「命人(みこひ
と)」であろう。古代中国語の命[mieng] の祖語(上古音)は命[miek*] に近かったと考えられている。韻尾[-ng] は調音の位置が[-k] と同じであり、転移しやすい。
「言」の古代中国語音は言[ngian] である。唐代の韻尾[-n]の上古音は[-t]に近かったと考えられている。日本語の「こと」は
上古音言[ngiat*] を継承したものである。
○同源語:
三(み)、野(の)、枝(え)、君(きみ)、言
(こと)、天皇(おほきみ・君)、宮(みや)、出(いで)、此(この)、天(あめ)、照(てる)、女(め)、
【みだる(乱)】
我
(わが)刺(させる)柳(やなぎの)絲(いと)を吹(ふき)乱(みだる)風(かぜ)にか妹(いも)が梅(うめ)の散(ちる)らむ(万1856)
三
吉野(みよしの)の水具麻(みぐま)が菅(すげ)を不レ編
(あまなく)に苅(かり)耳(のみ)苅(かり)て将レ乱
(みだりてむ)とや(万
2837)
例:令[lyeng]・命[mieng]、來[lə]・麥[muək]、陸[liuk]・睦[miuk]、勵[liat]・萬[muan]、
古代日本語にはラ行ではじまることばはなかった
のでマ行に転移した。中国語の[l-]は[m-]と相通じるところがある。[l-]は調音の位置が前口蓋(歯茎の裏)であり、[m-]は脣音であり調音の位置が近い。調音の位置が近い
音は音価も近く、転移しやすい。漢字のなかには音がラ行で、訓はマ行であらわれるものがいくつか見られる。古代日本語にはラ行ではじまることばはなかった
から、マ行に転移して受け入れられたものと思われる。
例:濫[lam](ラン・みだら)、緑[liok](リョク・みどり)、戻[lyei](レイ・もどる)、漏[lo]
(ロウ・も
る)、覧[lam](ラン・みる)、嶺[lieng](レイ・みね)、
○同源語:
我(わが)、刺(さす・挿)す、柳(やなぎ)、妹
(いも)、梅(うめ)、散(ちる)、三(み)、野(の)、菅(すげ)、苅(かる)、
【みつ(満・盈)】
世
間(よのなか)は空(むなしき)物(もの)と将レ有
(あらむ)とそ此(この)照(てる)月(つき)は満(みち)闕(かけ)為(し)ける(万442)
隠
口(こもりく)の泊瀬(はつせ)の山(やま)に照(てる)月(つき)の盈(みち)県(かけ)為(し)けり人(ひと)の常(つね)無(なき)(万1270)
例:腕[uan] うで、肩[kyan] かた、言[ngian] こと、断[duan] たつ、楯[djiuən] たて、など
盈[jieng] の意味はやはり「みちる」であり、盈満ということ
ばもある。
○同源語:
世間(よのなか・中)、物(もの)、此(こ)の、
照(てる)、闕(かけ)る、隠(こもる・籠)、口(くち・口嘴)、山(やま)、常(つね)、無(な)き、
【みどり(緑)】
春
(はる)は毛要(もえ)夏(なつ)は緑(みどり)に紅(くれなゐ)の綵色(まだら)に所レ見
(みゆる)秋(あき)の山(やま)かも(万2177)
淺
緑(あさみどり)染(そめ)懸有(かけたり)と見(みる)までに春(はるの)楊(やなぎ)は目生(もえに)けるかも(万1847)
例:亂[luan](みだる)、濫[lam](みだら)、戻[lyei](もどる)、漏[lo](もる)、
○同源語:
春(はる)、毛要・目生(もえる・萌)、夏(な
つ)、見(みる)、山(やま)、染(そめる)、懸(かける)、楊(やなぎ)、
【みなみ(南)】
南
(みなみ)吹(ふき) 雪(ゆき)消(げ)益(まさり)て射水河(いみづがは)流(ながる)水沫(みなわ)の余留弊(よるべ)奈美(なみ)、、、(万4106)
御
食(みけ)向(むかふ)南淵(みなふち)山(やま)の巖(いはほに)は落(ふりし)は太列(だれ)か削(きえ)遺有(のこりたる)(万1709)
例:馬[mea](むま・うま)、梅[muə](むめ・うめ)、眠[myen](ねむる)、牧[miuək](むまき)、
鰻[miuan](むなぎ)、汝[njia](なむぢ)、稔[njiəm]みのる、任[njiəm]になふ、
日本語の「みなみ」は中国語の南[nəm] の頭音を重複して「み+なみ」としたものであろ
う。
○同源語:
消・削(きえる)、射(いる)、河(かは)、流(ながる)、余留弊(よるべ・寄邊)、奈美(なみ・無)、御(み)、淵(ふち)、山(やま)、落(ふる・
降)、
英語などではもっと音節構造が複雑なため英語で
一音節のspring、street、strikeなどがそれぞれ「スプリング」「ストリート」「ス
トライク」日本語では五音節になっている例さえある。外来語はそのことばが入ってきた時期の発音を留めているのではなかろうか。駅の「ホーム(platform)」は今でも「ホーム」であり、「ユニフォーム(uniform)」が「フォーム」になったからといって「駅の
フォーム」になるわけではない。「コーヒー」は英語ではcoffeeだと知っていても、「コフィー飲みましょう」とは
云わない。
【みぬめ(敏馬)】
嶋
(しま)傳(づたひ)敏馬(みぬめ)の埼(さき)をこぎ廻(みれ)ば日本(やまと)戀(こほし)く鶴(たづ)さはに鳴(なく)(万389)
○同源語:
嶋(しま・洲)、傳(つた)ふ、埼(さき)、廻
(みる)、鳴(なく)、
【みね(峰・嶺)】
平
山(ならやま)の峰(みね)の黄葉(もみちば)取(とれ)ば落(ちる)鍾礼(しぐれ)の雨し無レ間
(まなく)零(ふる)らし(万
1585)
此
(この)山(やま)の嶺(みね)に近(ちかし)と吾(わが)見(み)つる月(つき)の空有(そらなる)戀(こひも)為(する)かも(万2672)
日本語の「みね」には「嶺」という字もあてられ
ている。「嶺」の古代中国語音は嶺[lieng]である。峰[phiong] と嶺[lieng] はかなり違った音のようにみえるが、[l-] と[ph-][m-] は調音の位置も近く、音価も近い。嶺[lieng] の頭音[l-] は日本語では語頭に立つことのない音であり、日本
語ではマ行に転移したものと考えることができる。日本語の「みね」は中国語の峰[phiong] や嶺[lieng] と同系のことばであろう。
同じ声符をもった漢字をラ行とマ行に読み分ける
ものもある。
例:陸[liuk]・睦[miuk]、令[lieng]・命[mieng]、來[lə]・麥[muək]、勵[liat]・萬[[muan]、里[liə]・埋[məi]、
また、日本漢字音ではラ行であらわれるが、訓で
はマ行であらわれるものもある。古代日本語にはラ行ではじまることばはなかったので、マ行に転移したものと思われる。
例:漏[lo](ロウ・もる)両[liang](リョウ・もろ)、戻[lyet](レイ・もどる)、李[liə](リ・もも)、
○同源語:
山(やま)、葉(は)、取(とる)、落(ちる・
散)、間(ま)、無(な)き、零(ふる・降)、此(こ)の、吾(わが)、見(みる)、
【みみ・のみ(耳)】
喧
(なく)鳥(とり)の 音(こゑ)も更(かはら)ふ 耳(みみ)に聞(きき) 眼(め)に視(みる)ごとに うち嘆(なげき)、、(万4166)
日母[nj-]がマ行であらわれる例:女[njia] め、燃[njian] もえる、稔[njiəm] みのる、壬[njiam]生・みぶ、
「耳」は「のみ」に使われることもある。古代日
本語では語尾の[-n][-m]ばかりでなく、語頭でも弁別されないことがある。
喧(なく・鳴)、鳥(とり)、音(こゑ・聲)、眼
(め)、視(みる・見)、嘆(なげ)く、吾(われ)、君(きみ)、背子(せこ)、言(こと)、
【みや(宮)】
樂
浪(ささなみ)の思賀(しが)の辛碕(からさき)雖二幸
有一(さ
きくあれど)大
宮人(おほみやびと)の船(ふね)麻知(まち)兼(かね)つ(万30)
内
(うち)日(ひ)刺(さす)宮(みや)にはあれど鴨頭草(つきくさ)の移(うつろふ)情(こころ)吾(わが)思(おもは)なくに(万3058)
例:覧[lam](ラン・みる)、漏[lo](ロウ・もる)、嶺[lieng](レイ・みね)、両[liang](リョウ・
もろ)、椋[liang](リョウ・むく)、燎[lyô](リョウ・もゆ)、乱[luan](ラン・みだる)、
緑[liok](リョク・みどり)、戻[lyet](レイ・もどる)、李[liə](リ・もも)、
日本語の「みや」は廟[miô]とも音義ともに近い。
○同源語:
辛(から)い、碕(さき)、船(ふね・盤)、兼
(かねる)、刺(さ)す、草(くさ)、情(こころ・心)、吾(わが)、思(おもふ・念)、
【みやこ(京)】
樂
浪(ささなみ)の國(くに)つ美神(みかみ)の浦(うら)さびて荒有(あれたる)京(みやこ)見(みれ)ば悲(かなし)も(万33)
然
(しか)と不レ有
(あらぬ)五百代(いほしろ)小田(をだ)を苅(かり)乱(みだり)田廬(たぶせ)に居(をれ)ば京師(みやこ)し所レ念
(おもほゆ)(万
1592)
○同源語:
浪(なみ)、國(くに)、美(み・御)、神(か
み)、荒(あれ)る、見(みる)、小(を)、田(た)、苅(かる)、乱(みだれ)、居(を)る、念(おもふ)、
【みる(見・視)】
淑
(よき)人(ひと)の良(よし)と吉(よく)見(み)て好(よし)と言(いひ)し芳野(よしの)吉(よく)見(み)よ良(よき)人(ひと)よくみ(万27)
喧
(なく)鳥(とり)の 音(こゑ)も更(かはら)ふ 耳(みみ)に聞(きき) 眼(め)に視(みる)ごとに うち嘆(なげき)、、(万4166)
二番目の歌(万4166)の視(みる)は偏の
「示」の部分が声符になっているが、意味は「見」と同じである。
中国語の後口蓋音[k-][-kh-][ng-] あるいは喉音[h-] が音ではカ行であらわれ、訓ではマ行であらわれる
ものが多い。これらの漢字の祖語(上古音)は[hm-] という語頭音をもっていたと考えられる。
例:観[kuan](カン・みる)、看[khan](カン・みる)、監[keam](カン・みる)、巻[kiuan](カン・
まき)、還[hoan](カン・めぐる)、丸[huan](ガン・まる)、眼[ngean](ガン・め)、
覧[lam](ラン・みる)も祖語(上古音)は覧[hlam*] であったと考えられ、見[hmyan*] と同系のことばである。
○同源語:
淑・良(よき)、野(の)、喧(なく・鳴)、鳥
(とり)、音(こゑ・声)、耳(みみ)、眼(め)、嘆(なげ)く、
【みる・めぐる(廻)】
縄
浦(なはのうら)従(ゆ)背向(そがひ)に所レ見
(みゆる)奥嶋(おきつしま)榜(こぎ)廻(みる)舟(ふね)は釣(つり)為(しす)らしも(万357)
海
人(あま)小船(をぶね)帆(ほ)かも張(はれ)ると見(みる)までに鞆(とも)の浦廻(うらみ)に浪(なみ)立有(たてり)所レ見
(みゆ)(万
1182)
海
若(わたつみ)は 霊(くすし)き物(もの)か 淡路嶋(あはぢしま) 中(なか)に立(たて)置(おき)て 白浪(しらなみ)を 伊与(いよ)に廻(め
ぐら)し、、(万
388)
○同源語:
背(せ・脊)、向(むかひ)、見(みる)、奥(お
き・澳)、嶋(しま・洲)、舟・船(ふね・盤)、釣(つり)、海人(あま)、小(を)、帆(ほ)、浪(なみ)、立(たつ)、海(うみ)、物(もの)、中
(なか)、立(たて)る、置(おく)、
【むかふ(向)】
た
まきはる命(いのちに)向(むかひ)戀従(こひむゆ)は公(きみ)が三舶(みふね)の梶柄(かぢから)にもが(万1455)
日雙
斯(ひなみしの)皇
子(みこの)命(みこと)の馬(うま)副(なめ)て御獦(みかり)立(たた)しし時(とき)は來(き)向(むかふ)(万49)
○同源語:
公(きみ)、三(み・御)、舶(ふね・盤)、皇子
(みこ・御子)、馬(うま)、御(み)、獦(かり)、立(たつ)、時(とき)、來(くる)、
【むかふ(迎)】
去
年(こぞ)の春(はる)相有(あへり)し君(きみ)に戀(こひ)にてし櫻(さくらの)花(はな)は迎(むかへ)來(け)らしも(万1430)
例:相模(さがみ)、相楽(さがらか・さがら)、
香美(かがみ)、伊香(いかご)、香山(かぐ
やま)、當麻(たぎま)、望多(うまぐ
た)、愛宕(おたぎ)、余綾(よろぎ)、
○同源語:
春(はる)、相(あふ・合)、君(きみ)、花(は
な)、來(くる)、
【むぎ(麥)】
柜
楉(うませ)越(ごし)に麦(むぎ)咋(は
む)駒(こま)の雖レ詈
(のらゆれど)猶(なほし)戀(こひし)く思(おもひ)不レ勝
(かねつ)も(万
3096)
麥[muək] と同じ声符をもった漢字に來[lə] がある。[m-](唇音)と[l-](歯茎の裏)は調音の位置が近く、中国語でも転移
することがある。
○同源語:
越(ごし)、駒(こま)、思(おもふ・念)、
【むなぎ(武奈伎・鰻)】
石
麻呂(いしまろ)に吾(われ)物(もの)申(まをす)夏(なつ)痩(やせ)に吉(よし)と云(いふ)物(もの)そ武奈伎(むなぎ)取(とり)喫(めせ)(万3853)
「武奈伎」は「鰻」である。「鰻」の古代中国語
音は鰻[muan]である。中国語の[m-] の前には馬[mea](うま・むま)、梅[muə](うめ・むめ)のように語頭に母音が添加されるこ
とがある。日本語の「うなぎ」は鰻[muan]+魚[ngia] であろう。
○同源語:
吾(われ)、物(もの)、夏(なつ・熱)、痩(や
せ)る、取(とる)、
【むね(胸)】
今
更(いまさらに)妹(いも)に将レ相
(あはめ)やと念(おもへ)かも幾許(ここだく)吾(あが)胸(むね)欝悒(いぶせく)将レ有
(あるらむ)(万
611)
夜
(よ)のほどろ出(いで)つつ来(く)らく遍(たび)多數(まねく)成(なれ)ば吾(あが)胸(むね)截(たち)焼(やく)如(ごとし)(万755)
例:芽(ガ・め)、廻(カイ・まはる)、丸(ガ
ン・まる)、観(カン・みる)、看(カン・
みる)、眼(ガン・め)、還(カン・めぐ
る)、京(キョウ・みやこ)、宮(キュウ・ み
や)、求(キュウ・もとむ)、球(キュウ・ま
り)、曲(キョク・まがる)、恵(ケイ・
めぐみ)、迎(ゲイ・むかへる)、見(ケン・
みる)、元(ゲン・もと)、御(ゴ・ギョ・ み)、向(コウ・むかふ)、
○同源語:
今(いま)、更(さら)に、妹(いも)、相(あ
ふ・合)、念(おもふ)、吾(あが)、夜(よる)、出(いづ)、來(くる)、截(たつ)、焼(やく)、
【むま(牟麻・馬)】
牟
麻(むま)の都米(つめ)都久志(つくし)の佐伎(さき)に知麻利(ちまり・留)為(ゐ・居)て阿例(あれ・吾)は伊波々牟(いははむ・齊)、、、(万4372)
宮田一郎編『上海語常用同音字典』によると
「馬」は現代の上海語では馬(hmo) である。日本語の駒(こま)は中国語の入りわたり
音(h-)を継承している可能性がある。また、「うま」「む
ま」も中国語の唇音[m-] が日本語のマ行音より合音性が強いことを示してい
るものと思われる。
○同源語:
都米(つめ・爪)、佐伎(さき・崎)、為(居・
ゐ)、阿礼(あれ・吾)、
【むれ・むらがる(群)】
夕
(ゆふべに)は 召(めし)て使(つかひ) 遣(つかはし)し 舎人(とねり)の子(こ)等(ら)は 行(ゆく)鳥(とり)の 群(むらがり)て待(ま
ち)有(あり)雖レ待
(まてど) 不レ召
賜(めしたまはね)ば、、(万
3326)
朝
(あさ)鳥(とり)の 朝(あさ)立(たち)為(し)つつ 群鳥(むらとり)の 群(むら)立(たち)行(いな)ば 留(とまり)居(ゐ)て 吾(あれ)
は将レ戀
(こひむ)な 不レ見
(みず)久(ひさ)有(なら)ば(万1785)
○同源語:
夕(ゆふ・夜)、子(こ)、行(ゆく)、鳥(と
り)、立(たつ)、留(とま)る、居(ゐ)る、吾(あれ)、見(みる)、
【め・をみな(女・妻・娘)】
石
戸(いはと)破(わる)手力(たぢから)もがも手弱(たよは)き女(をみなにし)有(あれ)ば為便(すべ)の不レ知
(しらな)く(万
419)
父 母(ちちはは)は 飢(うゑ)寒(こゆ)らむ 妻子(めこ)等(ども)は 乞(こひ)て泣(なく)らむ(万892)
娘 部思(をみなへし)秋(あき)芽子(はぎ)交(まじる)蘆城野(あしきの)今日(けふ)を始(はじめ)めて萬代(よろずよ)に将レ見 (みむ)(万 1530)
日本語の女(め)は上古中国語音の痕跡を留めて
いる。「をみな」の「を(wo)」は女[mia*] と調音の位置が同じ(脣音)であり、「な(na)」は女[mia*]と調音の方法が同じ(鼻音)である。「をみな」は
女[mia*]から派生したものであろう。妻(め)、娘(をみ
な)は女(め)の訓借である。
古事記歌謡では「女」には音で売[me] と表記されている。
吾
(あ)はもよ売(め)にしあれば、、(記歌謡)
○同源語:
手(て)、弱(よわき)、女(をみな)、知(し)
る、母(はは)、妻子(めこ・女子)、等(ども)、泣(なく)、娘部思(をみなへし・女)、芽子(はぎ)、野(の)、今日(けふ)、代(よ・
世)、見(みる)、
【め(芽)】
秋
柏(あきかしは)潤和(うるわ)川邊(かはべの)細竹(しのの)目(めの)人(ひとには不顔面(しのび)公(きみに)無レ勝
(あへなく)(万
2478)
現代の日本語では語頭では濁音「ガ」、語中・語
尾では鼻濁音「カ゜」が正しいとされているが、東京方言では鼻濁音「カ゜」が失われ、語頭でも語尾でも「ガ」が使われるようになてきている。
○同源語:
潤(うる)おふ、川(かは・河)、邊(べ)、公
(きみ)、無(な)く、
【も(方)】
天
下(あめのした) 四方(よも)の人(ひと)の 大船(おほふね)の 思(おもひ)憑(たのみ)て 天水(あまつみづ) 仰(あふぎ)て待(まつ)
に、、、(万
167)
紫
草(むらさき)のにほへる妹(いも)を尓苦久(にくく)有(あら)ば人嬬(ひとづま)故(ゆゑ)に吾(あれ)戀(こひ)め八方(やも)(万21)
○同源語:
天(あめ)、船(ふね・盤)、思(おもふ・念)、
仰(あふぐ)、妹(いも)、嬬(つま・妻嬬)、吾(あれ)、
【もえる・(毛要・毛延・萌)】
石
(いは)激(ばしる)垂見(たるみ)の上(うへ)の左和良妣(わわらび)の毛要(もえ)出(いづる)春(はる)に成(なり)にけるかも(万1418)
春
雨(はるさめ)に毛延(もえ)し楊奈木(やなぎ)か烏梅(うめ)の花(はな)ともにおくれぬ常(つね)の物能(もの)かも(万3903)
○同源語:
垂(たれ)る、見(みる)、出(いづ)、春(は
る)、楊奈木(やなぎ)、烏梅(うめ)、花(はな)、常(つね)、物能(もの)、
【もだす(黙)】
辱
(はぢ)を忍(しのび)辱(はぢ)を黙(もだして)無レ事
(こともなく)物(もの)不レ言
(いはぬ)先(さき)に我(われ)は将レ依
(よりなむ)(万
3795)
黙
然(もだ)居(をり)て賢(さかし)ら為(する)は飲レ酒
(さけのみ)て酔(ゑひ)泣(なき)為(する)に尚(なほ)不レ如
(しかず)けり(万
350)
○同源語:
辱(はぢ・恥)、事(こと・言)、無(な)き、物
(もの)、我(われ)、依(よ)る、居(を)る、賢(さか)し、酒(さけ)、飲(のむ・呑)、泣(なく)、
【もち(望)】
望
月(もちづき)の 満有(たれる)面(おも)輪(わ)に 如レ花
(はなのごと) 咲(ゑみ)て立有(たてれ)ば 夏蟲(なつむし)の 入火(ひにいる)が如(ごと)、、(万1807)
望
(もち)降(くたち)清(きよき)月夜(つくよ)に吾妹兒(わぎもこ)に令レ視
(みせむ)と念(おもひ)し屋前(やど)の橘(たちばな)(万1508)
望[miuang](もち)は満[muan](みつ)とも音義ともに近い。
○同源語:
面(おも)、花(はな)、立(たつ)、夏(なつ・
熱)、火(ひ)、入(いる)、清(きよき)、夜(よる)、吾妹兒(わぎもこ)、視(みる・見)、念(おもふ)、
【もと(本)】
春
霞(はるかすみ)立(たち)にし日(ひ)従(より)至二今
日一(け
ふまでに)吾(わが)戀(こひ)不レ止
(やまず)本(もと)の繁(しげ)けば(万1910)
此
(この)筥(はこ)を 開(ひらき)て見(み)てば 如レ本
(もとのごと) 家(いへ)は将レ有
(あらむ)と 玉篋(たまくしげ) 小(すこし)披(ひらく)に 白雲(しらくも)の 自レ箱
(はこより)出(いで)て、、(万1740)
また、韻尾の[-n] の上古音は一般に[-t] であったと考えられている。日本語の「もと」は中
国語の本[puən]と同源である。
○同源語:
春(はる)、霞(かすみ・霞霧)、立(たつ)、今
日(けふ)、吾(わが)、筥・篋・箱(はこ・筺)、此(こ)の、見(みる)、家(いへ)、小(すこし)、雲(くも)、出(いづ)、
【もとほる(廻)】
大
殿(おほとの)の 此(この)廻(もとほり)の 雪(ゆき)莫(な)踏(ふみそ)ね 數(しばしば)も 不レ零
(ふらざる)雪(ゆき)ぞ 山(やま)耳(のみ)に 零(ふり)し雪(ゆき)そ ゆめ縁(よる)な人(ひと)や 莫(な)履(ふみそ)ね雪(ゆき)は(万4227)
鶉
(うづら)こそ 伊波比(いはひ)廻(もとほ)れ 四時自物(ししじもの) 伊波比(いはひ)拜(をろがみ) 鶉(うづら)成(なす) 伊伊波比(いは
ひ)毛等保理(もとほり)、、
(万239)
古代中国語の「廻」は廻[huəi] である。「廻」の祖語(上古音)は廻[h(m)uəi*] に近い音であったと思われる。日本語の「もとほ
る」の「も」は廻[h(m)uəi*] の入りわたり音[h-]が脱落したものであり、日本漢字音の廻(カイ)
は、入りわたり音[h-] が発達したものである。
董同龢は『上古音韻表稿』のなかで「回」の上古
音を回[hiwəd*] と再構している。「廻」の上古音も[hmuəd*] に近い音であり、韻尾の[-d] の痕跡が日本語の「もとほる」の「と」となって
残っているものとと考えることができる。「廻」は万葉集では廻(みる)、廻(めぐる)にも使われている。
○同源語:
殿(との)、此(こ)の、莫(な)、踏・履(ふ
む)、零(ふる・降)、山(やま)、縁(よる)、波比(はふ・匍匐)、
【もの(物)】
生
(いける)者(もの)遂(つひに)も死(しぬる)物(もの)に有(あれ)ば今生(このよ)在(なる)間(ま)は樂(たのしく)を有(あら)な(万349)
橘
(たちばな)の蔭(かげ)履(ふむ)路(みち)の八衢(やちまた)に物(もの)をぞ念(おもふ)妹(いも)に不レ相
(あはず)して(万
125)
[p][m][b]も調音の位置が同じ(唇音)であり、転移しやす
い。「物」の日本漢字音は物(ブツ・もの)である。古代日本語では濁音は語頭にくることがなかったので訓では物(もの)となり、日本が本格的な文字時代に
入って濁音が語頭に立つようになってからは物(ブツ)となった。
タ行の濁音はダ行だと考えられているが、タ行の
半濁音(鼻濁音)はナ行であり、ダ行はタ行の濁音でもあるがナ行の濁音でもある、つまりタ行、ナ行、ダ行という関係にある。また、ハ行、マ行、バ行の関係
も同様である。
(タ行)清音[t]
(ナ行)鼻濁音[n]
(ダ行)濁音[d]
(ハ行)清音[p]
(マ行)鼻濁音[m]
(バ行)濁音[b]
○同源語:
遂(つひ)、死(しぬる)、今生(このよ・今
世)、間(ま)、蔭(かげ・影)、履(ふむ)、念(おもふ)、妹(いも)、相(あふ・合)、
【もゆ(燃・燎・焼)】
燃
(もゆる)火(ひ)も取(とり)て褁(つつみ)て福路(ふくろ)には入(いる)と不レ言
(いはず)や面(おも)知(しら)なくも(万160)
不レ念
(おもはぬ)に妹(いも)が咲(ゑ)まひを夢(いめに)見(みて)心(こころ)の中(うち)に燎(もえ)つつぞをる(万718)
吾
妹子(わぎもこ)に相(あふ)縁(よし)を無(なみ)駿河(するが)有(なる)不盡(ふじ)の高嶺(たかね)の焼(もえ)つつか将レ有
(あらむ)(万
2695)
例:女[njia](ニョ・ジョ・め)、汝[njia](ニョ・ジョ・な・みまし)、稔[njiəm](ネン・みのる)、
耳[njiə](ニ・ジ・みみ)、認[njiəm](ニン・みとめる)、壬生[njiəm](ジン・みぶ)、
燎[liô]の頭音[l-]は[m-]は調音の位置が近く、音価も近い。同じ声符がラ行
とマ行に読み分けられることもある。
例:陸[liuk]・睦[miuk]、命[mieng]・令[lieng]、麥[muək]・來[lə]、
日本漢字音でラ行であらわれ、訓ではマ行であ
らわれる例もある。
例:漏(ロウ・もる)、覧(ラン・みる)、両
(リョウ・もろ)、緑(リョク・みどり)、
乱(ラン・みだる)、
焼[ngyô]は一般に「やく」にあてられているが、焼[ngyô]の頭音[ng-]は鼻濁音であり、[m-]と調音の方法が同じであり、音価も近い。日本語の「もゆ」は中国語の「燃」「燎」「焼」
と同系のことばであろう。
○同源語:
火(ひ)、取(とる)、入(いる)、面(おも)、
知(しる)、念(おもふ)、妹(いも)、夢(いめ)、見(みる)、心(こころ)、吾妹子(わぎもこ)、相(あふ・合)、無(な)き、嶺(みね)、
【もる(漏)】
天
(あま)飛(とぶ)や鴈(かり)の翹(つばさ)の覆(おほひ)羽(ば)の何處(いづく)漏(もりて)か霜(しも)の零(ふり)けむ(万2238)
古代中国語の「漏」は漏[lo]である。日本漢字音は漏(ロウ・もる)である。中
国語の[l-] と[m-] は調音の位置が近く、音価も近い。古代日本語には
ラ行ではじまる音節はなかったのでマ行に転移した。日本語の「もる」は中国語の「漏」と同源であろう。音の漏(ロウ)という発音ができるようになったのは
長年にわたる中国語との接触の結果であり、万葉集でラ行ではじまる単語が出てくるのは四千首を超える歌のなかで「力士儛」という単語ひとつのみである。
○同源語:
天(あめ)、飛(とぶ)、鴈(かり)、羽(は)、
霜(しも)、零(ふる・降)、
【ま行のまとめ】
日本語のマ行音の起源は唇音[m]系と喉音[h-]系の二つに大きく分けることができる。
1.唇音[m-][p-][b-]系のことば。
○目[miuk]ま・め、覓[mek]まぐ、免[mian]まぬかる、儛[miua]まひ・まふ、眉[miei]まゆ・まよ、
命[mieng]みこと(命人・命言)、満[muan]みつ、敏[mien]馬(みぬめ)、麥[muək]むぎ、鰻
(むなぎ・鰻魚)、馬[mea]むま・うま、黙[mək]もだす、望[miuang]もち、物[miuət]もの、
萌[məng]もゆ、
○播[puai]まく、方[piuang]も、本[puən]もと、峰[phiong]みね、
南(みなみ)も南[nəm]の頭音を重ねたものであろう。
2.疑母[ng-] あるいは日母[nj-] がマ行に転移したことば
○眼[ngean](ガン・ま・め)、御[ngia](ゴ・み)、迎[ngyang](ゲイ・むかふ)、芽[ngea]
(ガ・め)、
焼[ngyô](ショウ・もゆ)、
○耳[njiə](ジ・みみ)、女[njia](ジョ・め)、燃[njian](ネン・もゆ)、
疑母[ng-] は調音の方法が[m-] と同じ(鼻音)であり、音価も近く、転移しやす
い。唐代の日母
[nj-] の祖語(上代音)は[m-] であったと推定できる。日母[nj-] は[m-] の口蓋化したものであろ う。日母[nj-]はさらに[dj-]→[zj-]と変化した。
3.來母[l-] がマ行に転移したことば
乱[luan](ラン・みだる)、緑[liok](リョク・みどり)、嶺[lieng](レイ・みね)、燎[liô]
(リョウ・もゆ)、漏[lo](ロウ・もる)、
[l-] と[m-] は調音の位置が近く、音価も近い。古代日本語では
ラ行音が語頭にくることばはなかっ
たので、マ行に転移した。
4.[hm-*] あるいは[hl-*] の入りわたり音[h-]が失われ、マ行になったたことば
○勾[h(m)əu*]・曲[h(m)iok*](ク・キョク・まがる)、護[h(m)o*](ゴ・まもる)、丸[h(m)uan*]
(ガン・まろ・まる)、見[h(m)yan*](ケン・みる)、廻[h(m)uəi*](カイ・みる・めぐる・
もとほる)、向[h(m)iang*](コウ・むかふ)、胸[h(m)iong*](キョウ・むね)、群[h(m)iuən*]
(グン・むれ)、
○宮[h(l)iuəm*](キュウ・みや)、京[h(l)yang*](キョウ・みやこ)、
漢字には同じ声符をカ行とラ行に読み分けるものが
いくつかあり、上古音は[hm*]であったと考えられている。
例:海(カイ)・毎(マイ)、黒(コク)・黙(モ
ク)、間(カン)・門(モン)、
また、同じ声符をカ行とラ行に読み分ける漢字もあ
り、上古音は[hl*]であったと考えられる。
例;果(カ)・裸(ラ)、格(カク)・洛(ラ
ク)、監(カン)・藍(ラン)、など
同じ声符をマ行とラ行に読み分けるものもあり、[m]と[l]は音価が近い。
例:埋(マイ)・里(リ)、萬(マン)・勵(レ
イ)、命(メイ)・令(レイ)、
「宮」は「呂」と声符が同じであり、「京」は 「涼」と声符が同じであることから、上古音は宮[h(l)iuəm*]、京[h(l)yang*] であったと推定することができる。[l]は[m]と調音の位置が近く転移しやすい。
5.口蓋化によって頭音が脱落したことば。
真[sjien] ま、間[kean] ま、神[djien] み、身[sjien] み、三[səm] み、
古代中国語の[m-]に入りわたり音[h-]があったであろうことは現代の江南音(上海音)に その痕跡が残されているほか、同じ声符の漢字がカ行とマ行に読みわけられるなどの事実からしてかなりの蓋然性をもって推定できる。
古い漢和辞典には切韻が示されていて、唐代の漢 字音の規範をしることができる。例えば諸橋徹次の『大漢和辞典』では海(許亥切)・毎(母罪切・莫佩切・謨杯切)、物(文拂切)・忽(呼骨切)、黒(迄得 切)・黙(密北切)・墨(密北切・莫佩切・旻悲切)、米(母禮切)・迷(帛系*批切・民卑切)、などとある。
最初の漢字が頭音(声母)をあらわし、二番目の 漢字が韻部(韻尾)をあらわしている。しかし、反切は隋唐の時代の規範的な音を示しているものの、これらの漢字がなぜ同じ声符をもっているかについては何 も語っていない。
切韻は600年頃成立しているが、それ以前の上 古音については『詩経』の韻をしらべたり、中国語の方言音をしらべたりして、音韻学の方法論を駆使して再構する。また、同じ声符をもった漢字は、その文字 が成立した時代には同じ音価をもっていたはずなので、声符を頼りに上古音を復元することも可能である。
◎や行
【や(矢・箭)】
大
夫(ますらを)の弓上(ゆずゑ)振(ふり)起(おこし)射(い)つる矢(や)を後(のち)将レ見
(みむ)人(ひと)は語(かたり)繼(つぐ)がね(万364)
三
雪(みゆき)落(ふる) 冬(ふゆ)の林(はやし)に 飃(つむじ)かも い巻(まき)渡(わたる)と 念(おもふ)まで 聞(きき)し恐(かしこ)く
引(ひき)放(はなつ) 箭(や)の繁(しげ)けく、、(万199)
例:舎[sjia](シャ・や)、世[sjiai](セ・よ)、夕[zyak](セキ・ゆふ)、山[shean](サン・やま)、
二番目の歌(万199)では「箭」を「や」にあてている。
「箭」は長さや太さをそろえて作った矢のことである。「箭」の古代中国語音は箭[tzian] である。「箭」は意味は日本語の「や」に近いが、
音が対応していない。日本語の「や」は矢[sjiei] と同源であろう。
○同源語:
弓(ゆみ)、起(おこす)、射(いる)、見(み
る)、語(かたる)、繼(つぐ・続)、三(御・み)、落(ふる・降)、渡(わたる)、念(おもふ)、放(はなつ)、
【やく(焼・熾)】
冬
(ふゆ)隱(こもり)春(はる)の大野(おほの)を焼(やく)人(ひと)は焼(やき)不レ足
(たらぬ)かも吾(わが)情(こころ)熾(やく)(万1336)
網
(あみ)の浦(うら)の 海處女(あまをとめ)等(ら)が 焼(やく)塩(しほ)の念(おもひ)ぞ所レ焼
(やくる)吾(わが)下情(したこころ)(万5)
韻尾の[-ô] の上古音は[-ôk]*に近く、王力の『同源字典』によると超[thô]・卓[teôk]、照[tjiô]・燿[jiôk]、燋[tziô]・爝[tziôk] などは同源であるという。
日本語の「やく」には「熾」も用いられている。
「熾」の原義は「盛ん」ということだが、「火の燃える」ことも「熾」という。「熾」の古代中国語音は熾[thjiə]あるいは[thjiək] であり、頭音[thj-]が脱落したと考えれば日本語の「やく」とも通じ
る。
○同源語:
隠(こもる・籠)、春(はる)、野(の)、吾(わ
が)、情(こころ・心)、網(あみ)、海(あま)、處女(をとめ・女)、等(ら)、塩(しほ・潮)、念(おもひ)、
【やど・やどり(屋戸・宿)】
戀
(こひ)しけば形見(かたみ)に将レ為
(せむと)吾(わが)屋戸(やど)に殖(うゑ)し藤浪(ふじなみ)今(いま)開(さき)にけり(万1471)
客
人(たびびと)の宿(やどり)将レ為
(せむ)野(の)に霜(しも)降(ふら)ば吾(わが)子(こ)羽褁(はぐくめ)天(あめ)の鶴(たづ)群(むら)(万1791)
宿(やどる)は宿[siuk]の頭音[s-] が介音[-i-] の影響で脱落したものであろう。韻尾の[-k] は江南音では[-t]に近く、転移した可能性がある。
頭音脱落の例:勺・約、除・余、序・予、秀・誘、
詳・洋、場・陽、誦・甬、袖・由、
○同源語:
見(みる)、吾(わが)、浪(なみ)、今(い
ま)、開(さく・咲)、野(の)、霜(しも)、降(ふる)、子(こ)、羽(は)、天(あめ)、群(むら・むれ)、
【やな(梁)】
古
(いにしへ)に樑(やな)打(うつ)人(ひと)の無有(なかり)せば此間(ここに)も有(あら)まし柘(つみ)の枝(えだ)はも(万387)、
例:柳[liu] やなぎ、良[liang] よき、陸[liuk] をか、陵[liəng]] をか、
現代朝鮮語音では[l-] は[-i-] 介音の前では規則的に脱落する。「梁」の朝鮮漢字
音は梁(yang)である。
例:李(i)、利(i)、里(i)、離(i)、理(i)、履(i)、罹(i)、臨(im)、立(ip)、
韻尾の[-ng] はナ行に転移している。
例:常[zjiang] つね、嶺[lieng] みね、種[diong] たね、胸[xiong] むね、
同源語:
打(うつ)、無(な)き、此(こ)こ、枝(え
だ)、
【やぎ・やなぎ(楊奈疑・柳)】
春
雨(はるさめ)に毛延(もえ)し楊奈疑(やなぎ)か烏梅(うめ)の花(はな)ともにおくれぬ常(つね)の物能(もの)かも(万3903)
梅
花(うめのはな)取(とり)持(もち)見(みれ)ば吾(わが)屋前(やど)の柳(やなぎ)の眉(まよ)し所レ念(おもほゆる)かも(万1853)
「柳」の古代中国語音は柳[liu] である。柳(やなぎ)は中国語の頭音[l-] が介音[-i-]の影響で脱落したものである。古代日本語にはラ行
ではじまることばなかったので、頭音[l-]は脱落した。柳(やなぎ)も「柳[jiu]+の+木」の連想である。
「楊」は川柳であり、「柳」は柳一般をさすとい
うが、楊[jiang] と柳[liu] とは、かなり音義ともに近い。 現代朝鮮語音には(l-)ではじまる音節はない。そのため[-i-]介音を伴うものは頭音が脱落する。
例:柳(yu)、流(yu)、留(yu)、陸(yuk)、李(i)、利(i)、理(i)、隣(in)、日本(il-bon)、など。
○同源語:
春(はる)、毛延(もえ・萌)る、烏梅・梅(う
め)、花(はな)、常(つね)、物能(もの)、取(とる)、見(みる)、吾(わが)、屋前(やど)、眉(まよ)、念(おもふ)、
【やま(山)】
あ
しひきの山(やま)のしづくに妹(いも)待(まつ)と吾(わが)立(たち)所レ沾
(ぬれぬ)山(やま)のしづくに(万107)
○同源語:
妹(いも)、吾(わが)、立(たち)、沾(ぬれ・
濡)る、
【やみ(闇)】
照
(てる)月(つき)を闇(やみ)に見成(みなし)て哭(なく)涙(なみだ)衣(ころも)沾(ぬらし)つ干(ほす)人(ひと)無(なし)に(万690)
闇
夜(やみ)有(なら)ばうべも不二來
座一(き
まさじ)梅(うめ)の花(はな)開(さけ)る月夜(つくよ)に伊而(いで)まさじとや(万1452)
○同源語:
照(てる)、見(みる)、哭(なく・泣)、沾(ぬ
ら・濡)す、干(ほ)す、無(な)し、夜(よる)、來(く)る、梅(うめ)、花(はな)、開(さく・咲)、伊而(いづ・出)、
【ゆ(湯)】
湯
原(ゆのはら)に鳴(なく)蘆(あし)多頭(たづ)は如レ吾(わがごとく)妹(いも)に戀(こふ)れや時(とき)不レ定
(わかず)鳴(なく)(万
961)
○同源語:
原(はら)、鳴(なく)、吾(わが)、妹(い
も)、時(とき)、鳴(なく)、
【ゆく(行・去)】
奥
山(おくやま)の木葉(このは)隱(かくり)て行(ゆく)水(みづ)の音(おと)聞(ききし)従(より)常(つね)不レ所レ忘
(わすらえず)(万
2711)
物
乃部(もののふ)の八十氏(やそうぢ)河(がは)の阿白木(あじろき)にいさよふ浪(なみ)の去邊(ゆくへ)白不(しらず)も(万264)
「行」の古代中国語音は行[heang] であり、日本漢字音は音が行(コウ)、訓が行(ゆ
く)である。漢字のなかには、同じ声符をもった漢字をカ行とア行に読み分けるものがある。ア行音は頭音[h-][k-]が介音[-i-] の発達によって脱落したものである。
例:軍[kiuən]グン・運[hiuən]ウン、完[huan]カン・院[hiuan]イン、黄[huang]オウ・コウ・き、
また、日本漢字音のなかには音訓ともに古代中国
語の頭音[h-] を喪失したものもある。
例:往[hiuang]オウ・ゆく、詠[hyuang]エイ・よむ、雄[hiuəng]ユウ・を、泳[hyuang]エイ・およぐ、
中国語音韻史によると、韻尾の[-ng] の上古音は[-k]に近い音であったという。日本の古地名などでは中
国語の韻尾[-ng]がカ行であらわれることが多い。
例:相[sinag]模(さがみ)、香[xiang]山(かぐやま)、愛宕[dang](あたご)、餘稜[ləng](よろぎ)、 美嚢[nang](みなぎ)、望[miuang]多(まぐた)、勇[jiong]礼(いくれ)、英[yang]太(あがた)、 双[seong]六(すごろく)、
日本語の「ゆく」は行[heang]あるいは往[hiuang]の頭音が脱落したものである。「ゆく」には去[khia]も用いられている。「去」は「行」と義(意味)が
近く、訓借である。
○同源語:
奥(おく)、山(やま)、木(き・枝)、葉
(は)、隠(かく)れる、音(おと)、常(つね)、忘(わす)る、物(もの)、氏(うぢ)、河(かは)、浪(なみ)、邊(へ)、白
不(しらず・不知)
例:雲[hiuən]ウン・くも、熊[hiuəm]ユウ・くま、越[hiuat]エツ・こえる、
音韻の変化は一般に同じ方向に進むものであり、
一方に行(ゆく)→(コウ)のような変化があり、他方に雲(くも)→(ウン)のような変化が同じ時代に同じ地方で起こることは考えにくい。
現代の北京語では行(hang/xing)、熊(xiong)は頭音に喉音[h-][x-]を留めているが、雲(yun)、越(yue)は頭音を失っている。喉音喪失の過程はかなりゆっ
くりとしたもので、まだ続いているように思われる。
【ゆみ(弓)】
梓
弓(あづさゆみ) 弓腹(ゆはら)振(ふり)起(おこし) 志乃伎羽(しのきは)を 二(ふたつ)手挟(たばさみ) 離(はなち)けむ 人(ひと)し悔
(くやしも) 戀(こふ)らく思(おもへ)ば(万3302)
大
夫(ますらを)の弓上(ゆずゑ)振(ふり)起(おこし)獦高(かりたか)の野邊(のへ)副(さへ)清(きよく)照(てる)月夜(つくよ)かも(万1070)
例:今[kiəm] いま、犬[khyuan] いぬ、寄[kiai] よる、居[kia] ゐる、拠[kia] よる、禁[kiəm] いむ、
及[kiuəng] およぶ、吉[kiet] よし、乞[khiət]・乙[eat]、渇[khat]・謁[iat]、
○同源語:
腹(はら)、起(おこ)す、羽(は)、手(て)、
挟(はさむ)、悔(くや)し、思(おもふ・念)、獦(かり)、野(の)、邊(べ)、清(きよき)、照(てる)、夜(よる)、
【よ(世・代)】
う
つせみの世(よ)の事(こと)なれば外(よそ)に見(み)し山(やま)をや今(いま)は因鹿(よすか)と思(おもは)む(万482)
遠
(とほき)代(よ)に 有(あり)ける事(こと)を 昨日(きのふ)しも 将レ見
(みけむ)がごとも 所レ念
(おもほゆる)かも(万
1807)
○同源語:
見(みる)、山(やま)、今(いま)、思・念(おも
ふ)、
【よ・よる(夜)】
夜
(よる)光(ひかる)玉(たま)と言(いふ)十方(とも)酒(さけ)飲(のみ)て情(こころ)を遣(やる)に豈(あに)しかめやも(万346)
水
底(みなそこ)の玉(たま)さへ清(きよく)可レ見
(みつべく)も照(てる)月夜(つくよ)かも夜(よ)の深(ふけ)去(ゆけ)ば(万1082)
「夜」の古代中国語音は夜[jyak] だと考えられている。同じ声符をもった漢字に液[jyak] があり、液(えき)は現在でも韻尾[-k] を残している。日本語の「よる」は夜[jyak] の韻尾が転移したものであろう。夜(よ・ヤ)の古
代中国語の夜[jyak] の韻尾が脱落したものである。夜(よる)が古く、
夜(ヨ・ヤ)が新しい。
日本語では夜(よる)は訓で「やまとことば」
(日本古来のことば)であり、夜(ヤ)は音で中国語音であるとされているが、夜(ヤ・よ・よる)は同系のことばであろう。 八世紀の日本漢字音では韻尾の[-k]はすでに失われていたことは「やまと」を「夜麻
登」あるいは「夜麻等」と表記していたことからも知られる。
○同源語:
光(ひかる)、酒(さけ)、飲(のむ・呑)、情
(こころ・心)、清(きよい)、見(みる)、照(てる)、去(ゆく・行)、
【よ・よひ・ゆふ・ゆふべ(夕)】
将レ相
(あはむ)夜(よ)は何時(いつ)も将レ有
(あらむ)を何如(なに)為(す)とかその夕(よひ)相(あひ)て事(こと)の繁(しげき)も(万730)
今
日(けふ)もかも明日香(あすかの)河(かは)の夕(ゆふ)不レ離
(さらず)川津(かはづ)鳴(なく)瀬(せ)の清(さやけく)有(ある)らむ(万356)
た
まかぎる昨(きのふの)夕(ゆふべ)見(みし)物(ものを)今(けふの)朝(あしたに)可レ戀
(こふべき)物(ものか)(万
2391)
自二高
山一(た
かやまゆ)出(いで)來(くる)る水(みづ)の石(いはに)觸(ふれ)破(われて)ぞ念(おもふ)妹(いも)に不レ相
(あはぬ)夕(よ)は(万
2716)
万葉集では「夜」は夜(よ)、夜(よる)にあて
られ、「夕」は夕(ゆふ)、夕(よひ)、夕(よ)などにあてられているが、夜[jyak] と夕[zyak] は音義ともに近く、夜[jyak] は夕[zyak] の頭音が脱落したものでる。「ゆ+ふ」の「ふ」は
夕[zyak]の韻尾が転移したものであろう。実際に、四番目の
歌(万2716)では「夕」も夕(よ)と読まれている。
○同源語:
今日・今(けふ)、河(かは)、川津(かはづ・
蝦)、鳴(なく)、瀬(せ・湍)、清(さやか)、見(みる)、物(もの)、相(あふ)、出(いづ)、來(くる)、念(おもふ)、妹(いも)、
【よこ(横)】
青
山(あをやま)を横(よこ)ぎる雲(くも)のいちしろく吾(われ)と咲(ゑま)して人(ひと)に所レ知
(しらゆ)な(万
688)
垣
保(かきほ)なす人(ひと)の横辭(よこごと)繁(しげみ)かも不レ遭
(あはぬ)日(ひ)數多(まねく)月(つき)の経(へぬ)らむ(万1793)
○同源語:
山(やま)、雲(くも)、吾(われ)、知(し
る)、辭(こと・言)、遭(あふ・合)、経(へる)、
【よし(因・縁)】
妹
(いもが)門(かど)去(ゆき)過(すぎ)不レ勝
(かね)つひさかたの雨(あめ)も零(ふら)ぬか其(そ)を因(よしに)将レ為
(せむ)(万
2685)
永
代(ながきよ)に 標(しるしに)将レ為
(せむ)と 遐代(とほきよ)に 語(かたり)将レ繼
(つがむ)と 處女(をとめ)墓(はか) 中(なか)に造(つくり)置(おき) 壮士(をとこ)墓(はか) 此方(こなた)彼方(かなた)に 造(つく
り)置有(おける) 故(ゆえ)縁(よし)聞(きき)て、、(万1809)
古事記には「よし」に「由」と使った用例があ
る。古代中国語の「由」は由[jiu] である。日本語の「よし」は由[jiu]から派生したものであろう。
例:石[zjyak] いし、吉[kiet] よし、樫[kyen] かし、串[hoan] くし、伏[biuək] ふす、
妹(いも)、門(かど)、去(ゆく・行)、過(す
ぎ)る、零(ふる・降)、其(そ)の、永(なが・長)き、代・世(よ)、語(かたる)、繼(つぐ・續)、處女(をとめ・女)、墓(はか)、此(これ)、中
(なか)、造(つく)る、置(おく)、
【よし(淑・良・吉・好・芳)】
淑
(よき)人の良(よし)と吉(よく)見(み)て好(よし)と言(いひ)し芳野(よしの)吉(よく)見(み)よ良(よき)人(ひと)四來(よく)三(み)(万27)
月
夜(つくよ)吉(よし)河音(かはと)清(さやけ)し率(いざ)此間(ここに)行(ゆく)も不レ去
(ゆかぬ)も遊(あそび)て将レ歸
(ゆかむ)(万
571)
例:淑[zjiuk]・良[liang] よき、吉[kiet] よく、好[xu] よし、芳[phiuang] よし、
淑[zjiuk]・良[liang](よき)はいずれも介音[-i-]の発達により頭音が脱落したものである。良(よ
し)は良[liang]の韻尾が転移したものである。吉[kiet](よし)も韻尾の[-t]が転移したものであろう。中国語には[-s]という韻尾はない。
好[xu]・芳[phiuang](よし)は義(意味)が「良」に近いが、音が対応
していない。訓借である。
○同源語:
見・三(みる)、野(の)、來(くる)、夜(よ
る)、河(かは)、音(おと)、清(さやか)、此(こ)こ、行・去・歸(行・ゆく)、
【よど(與騰・与等)む・澱】
麻
都良(まつら・松浦)我波(がは)奈々勢(ななせ)の與騰(よど)は与等武(よどむ)とも和礼(われ)は与騰麻受(よどまず)吉美(きみ)をし麻多(ま
た)む(万
860)
○同源語:
我波(かは・河)、勢(せ・湍)、和礼(われ・
我)、吉美(きみ・君)、
【よる(寄・縁・依・因)】
大
伴(おほとも)の名(な)に負(おふ)靫(ゆき)帯(おび)て萬代(よろづよ)に慿(たのみ)し心(こころ)何所(いづく)か将レ寄
(よせむ)(万
480)
浪
(なみ)こそ來(き)縁(よれ) 浪(なみ)のむた 彼(か)縁(より)此(かく)依(よる) 玉藻(たまも)成(なす) 依(より)宿(ね)し妹(い
も)を、、(万131)
秋
田(あきのた)の穂(ほ)向(むき)の所レ縁
(よれる)異所(かた)縁(よりに)君(きみ)に因(より)なな事痛(こちたく)有(あり)とも(万114)
「縁」の唐代の中国語音は頭音が脱落して縁[jiuan] になっていたものと思われる。日本語の「よる」は
寄[(k)iai]、縁[jiuan]、依[iəi]、因[ien] と同系のことばであろう。日本語のア・ヤ・ワ行は
転移しやすい。ヤ行は直音の拗音化したものである。
例:闇(アン・やみ)、役(エキ・やく)、往(オ
ウ・ゆく)、横(オウ・よこ)、益(エキ・
ヤク)、など
「因」「縁」は「よし」にも用いられている。
○同源語:
名(な)、負(おふ)、代(よ・世)、心(ここ
ろ)、浪(なみ)、來(くる)、此(か)く、宿(ね・寐)る、妹(いも)、田(た)、穂(ほ)、向(むき)、君(きみ)、事(こと・言)、痛(いた)き、
【よわし(弱)】
玉
緒(たまのを)を片緒(かたを)に搓(より)て緒(を)を弱(よわ)み乱(みだるる)時(とき)に不レ戀
有(こひざら)めやも(万
3081)
石
戸(いはと)破(わる)手力(たぢから)もがも手弱(たよわ)き女(をみなにし)有(あれ)ば為便(すべ)の不レ知
(しらな)く(万
419)
弱[njiôk]は柔[njiu ] と音義ともに近い。日本語では弱(よわし)・柔
(やはら)である。王力は『同源字典』のなかで、「柔」と「弱」は同源であるとしている。日本語の「よわし」「やわら」も「柔」「弱」と同系のことばであ
る。
乱(みだる)、時(とき)、手(て)、女(をみ
な)、知(し)る、宇奈波良(うなばら・海原)、根(ね)、古須氣(こすげ・小菅)、伎美(きみ・君)、和須良酒(わすら・忘)す、和礼(われ・我)、
【や行のまとめ】
日本語のヤ行は中国語の[-i-]介音の発達にによって頭音が脱落したものが多い。
1.中国語の古代音が母音または拗音である例:
闇[əm] やみ、因[ien] より、依[iəi] よる、屋[ok]<至[tjiet/jiet*]>やど、楊[jiang] やなぎ、
湯[thang]<陽[jiang*]>ゆ、夜[jyak] よる、
2.口蓋化によって頭音が脱落した例:
○矢[(s)jiei](シ・や)、宿[(s)iuk](シュク・やど)、山[(sh)ean](サン・やま)、世[(s)jiai]
(セ・よ)、淑[(z)jiuk](シュク・よし)、夕[(z)yak](セキ・よひ・ゆふ・ゆふべ)、
熾[(th)jiək](シ・やく)、
○縁[(d)jiuan](エン・よし・よる)、澱[(d)yen](デン・よど)、
○梁[(l)iang](リョウ・やな)、柳[(l)iu](リュウ・やなぎ)、良[(l)iang](リョウ・よし)、
○弱[(n)jiôk](ジャク・よわし)、焼[(ng)yô](ショウ・やく)、
○吉[(k)iet](キチ・よし)、寄[(k)iai](キ・よる)、弓[(k)iuəm](キュウ・ゆみ)、行[(h)eang]
(コウ・ゆく)、横[(h)oang](オウ・よこ)、
頭音の脱落には介音[-i-]の発達が関与しているものと思われる。
◎ら行
【ら(等)】
未 通女(をとめ)等(ら)が放(はなりの)髪(かみ)を木綿(ゆふの)山(やま)雲(くも)莫(な)蒙(たなびき)家(いへの)當(あたり)将レ見(みむ)(万1244)
古代日本語ではラ行音が語頭に立つことはない が、等(ら)は接尾辞として用いられる。「等」の古代中国語音は等[təng] であり、万葉集では等(ども)、等(ら)などと読 む。等(ら)は等[təng] の頭音[t-]がラ行に転移し、韻尾[-ng]が脱落したものである。等(ども)は韻尾[-ng]がマ行に転移したものであり、いずれも意味は同じ である。
○同源語:
女(め)、山(やま)雲(くも)、莫(な)、當 (あたり)、見(みる)
【りきし(力士)】
池
神(いけがみ)の力士(りきし)儛(まひ)かも白鷺(しらさぎ)の桙(ほこ)啄(くひ)持(もち)て飛(とび)渡(わたる)らむ(万3831)
「力士」もまた外来語であった。「相撲」は古語
では「すまひ」などと「やまとことば」めかして書いているが、相撲[siang-phuk] が転移したもので、「あひ+撲する」が原義であろ
る。「撲」は打つ、倒すの意味であり、相撲の原義は四つに組む相撲では突き相撲であったものと思われる。
○同源語:
神(かみ)、儛(まひ)、鷺(さぎ・鵲)、飛(と
ぶ)、渡(わたる)、
例:ラジオ、ラシャ、ラムネ(レモネードの転)、
ランプ、リボン、レコード、レストラン、レモン、ロザリオ、など
◎わ行
【わが・われ(我・吾・吾等)】
吾
(わが)舟(ふね)は明石(あかし)の湖(みと)に榜(こぎ)泊(はて)む奥(おき)へ莫(な)放(さかり)そ狭夜(さよ)深(ふけ)にけり(万1229)
石
見乃(いはみの)や高角山(たかつのやま)の 木際(このま)従(より)我(わが)振(ふる)袖(そで)を妹(いも)見(み)つらむか(万132)
處
女(をとめ)等(ら)を袖振山(そでふりやまの)瑞垣(みづかき)の久(ひさしき)時(とき)ゆ念(おもひ)けり吾等(われ)は(万2415)
中国語の疑母[ng-]が日本語でワ行であらわれる例としては鵞[ngai] わし、鰐[ngak] わに、岳[ngak] をか、などをあげることができる。
三番目の歌(万2415)では吾等(われ)と表
記されることがある。「われ」の「れ」は等[təng] である可能性がある。[t-] と[l-] は調音の位置が同じ(歯茎の裏)であり、「等」は
「ら」あるいは「れ」に転移することがある。
我[ngai]、吾[nga] は頭音が脱落して「あ」であらわれることもある。
○同源語:
舟(ふね・盤)、泊(はて)、奥(おき・澳)、莫
(な)、夜(よる)、深(ふけ・更)る、
見(みる)、乃(の・野)、山(やま)、木(き・枝)、袖(そで)、妹(いも)、處女(をとめ・女)、等(ら)、時(とき)、念(おもふ)、
【わかし(若)】
白
髪(しらかみ)し子(こ)等(ら)も生(おひ)なば如レ是
(かくのごと)将二若
異一(わ
かけむ)子(こ)等(ら)に所レ罵
(のらえ)かねめや(万
3793)
春
雨(はるさめ)を待(まつ)とにし有(あら)し吾(わが)屋戸(やど)の若木(わかき)の梅(うめ)も未(いまだ)含有(ふふめり)(万792)
日本語の柔(やはら)、譲
(ゆずる)、潤(うる)おふ、熱(あつい)、入(いる)などは朝鮮語音の影響があると思われる。
例:柔(yu)、譲(yang)、潤(yul)、熱(yeol)、入(ip)、
日本語では中国語の日母[nj-] がワ行・ヤ行であらわれることがある。ワ行は合音
であり、ヤ行は拗音であり、ア行・ヤ行・ワ行は互いに親和性がある。
ヤ行であらわれる例:弱[njiôk] よわし、柔[njiu] やわらか、譲[njiang] ゆづる、
ワ行であらわれる例:若[njiak] わかい、餌[njiə] ゑ、女[njia] をみな、
○同源語:
子(こ)、等(ら)、是(かく)、春(はる)、吾
(わが)、屋戸(屋・やど)、木(き・枝)、梅(うめ)、未(いまだ)、含(ふふむ)、
【わき(腋)】
小
兒(わらは)等(ども)草(くさ)は勿(な)苅(かりそ)八穂(やほ)蓼(たで)を穂積(ほづみ)の阿曾(あそ)が腋(わき)草(くさ)を可礼(かれ)(万3842)
ア行
ヤ行
ワ行
湧[jiong]
ユウ
わく
涌[jiong]
ヨウ
わく
訳[jyak]
ヤク
わけ
我[ngai]・吾[nga]
あ
わ
顎・鰐[ngak]
あご
わに
委・倭[iuai]
イ
ワ
域[hiuak]・惑[hiuək]
イキ
ワク
液・夜・腋[jyak]・ エキ
よ・よる
わき
○同源語:
等(ども)、草(くさ)、勿(な)、苅(かる)、
穂(ほ)、蓼(たで)、穂(ほ)、
【わくご・若子・王子】
開
木代(やましろの)來背(くせの)若子(わくごが)欲(ほしと)云(いふ)余(われ)相(あふ)さわに吾(われ)を欲(ほしと)云(いふ)開木代(やまし
ろの)來背(くせ)(万
2362)
伊
祢(いね・稲)都氣(つけ・舂)ばかかる安我(あが)手(て)を許余比(こよひ・今夜)かも等能(との・殿)の和久胡(わくご)が等里(とり・取)て奈氣
(なげ・歎)かむ(万
3459)
天皇のおくり名:
漢風諡号 和風諡号
日本書紀の表記
開化 ワカヤ
マトネコヒコオホヒヒ 稚日本根子彦大日日
景行 オホタラシヒコオシロワ
ケ 大足彦忍代別
成務 ワカタ
ラシヒコ 稚足彦
応神 ホムタワケ
誉田別
履中 イザホワケ
去来穂別
反正 ミツハワケ
瑞歯別
允恭 ヲアサヅマワクゴ
ノスクネ 雄朝津間稚子宿禰
雄略 オホハツセノワカタ
ケ 大泊瀬幼武
清寧 シラカノタケヒロクニオシワ
ケヤマトネコ 白髪武広国押稚日本根子
武烈 ヲハツセノワカサ
ザキ 小泊瀬稚鷦鷯
天智 アメミコトヒラカスワ
ケ
天命開別
日本書紀では「わか」「わけ」に「稚」、 「別」、「幼」などの漢字があてられている。しかし、これだけ多くの天皇のおくり名に「わか」「わけ」が使われていることから、「わか」「わけ」は王[hiuang]と関係のあることばであろう。万葉集でも「和氣 (わけ)」ということばが使われた歌がある。
古代日本語の「わか」「わけ」は中国語の王(wang) と同源であろう。万葉集の時代にはすでに語源が分
からなくなってしまっていたたため、「わくご」を「若子」あるいは「稚子」と解釈した。
○同源語:
山(やま)、余・吾(われ)、相(あふ・合)、伊
祢(いね・秈)、都氣波(つく・舂)、安我(あが)、手(て)、許余比(こよひ・今夜)、等能(との・殿)、等里(とり・取)、奈氣可武(なげく・嘆)、
黒(く
ろ)、樹(き)、取(とる)、草(くさ)、苅(かる)、
【わし(鷲・鵞鷲)】
澁
谿(しぶたに)の二上山(ふたがみやま)に鷲(わし)ぞ子(こ)産(む)と云(いふ)指羽(さしは)にも君(きみ)が御為(みため)に鷲(わし)そ子生
(こむ)と云(いふ)(万
3882)
日本語の「わし」の漢字には鷲[dziuk] があてられているが、日本語の「わし」は中国語の
「鵞[ngai]+鷲[dzyu]」から派生したものであろう。
○同源語:
澁(しぶ)、山(やま)、子(こ)、指(さ)す、
羽(は)、君(きみ)、御(み)、
【わする(忘)】
明
日香川(あすかがは)明日(あす)だに将レ見
(みむ)と念(おもへ)やも吾(わが)王(おほきみ)の御名(みな)忘(わすれ)せぬ(万198)
あ
らたまの年(としの)緒(を)長(なが)く相(あひ)見(み)てしその心(こころ)引(ひき)将レ忘
(わすらえめ)やも(万
4248)
[m-] がワ行であらわれる例:尾[miuəi] を、綿[mian] わた、罠[mien] わな、
○同源語:
見(みる)、念(おもふ)、吾(わが)、王(おほ
きみ・君)、御(み)、名(な)、長(なが)く、相(あふ・合)、心(こころ)、
【わた(綿)】
し
らぬひ筑紫(つくし)の綿(わた)は身(みに)著(つけ)て未(いまだ)は伎祢(きね・著)ど暖(あたたけく)将レ見
(みゆ)(万
336)
○同源語:
身(み)、著(つけ)る、未(いまだ)、伎祢(き
ね・著)ど、見(みる)、
【わたくし(私)】
住
吉(すみのえ)の小田(をだを)苅(から)為(す)子(こ)賤(やつこ)かも無(なき)奴(やつこ)雖レ在
(あれど)妹(いも)が御爲(みため)と私(わたくし)田(だ)苅(かる)
(万1275)
例:飢餓、柔弱、存在、窮極、強健、弁別、跳躍、
命令、改革、報復、冷涼、など
○同源語:
小(を)、田(た)、苅(かる)、子(こ)、無
(な)き、妹(いも)、御(み)、
【わな(和奈・罠)】
安
思我良(あしがら)の乎弖
毛(を
ても・面)許乃母(このも・面)に佐須(さす・刺)和奈(わな・罠)のかなる麻(ま・間)之豆美(しづみ)許呂(ころ・兒等)安礼(あれ・吾)比毛(ひ
も・繙)等久(とく・解)(万
3361)
例:尾[miuəi](を・ビ)、綿(わた・メン)、忘[miuang](わすれる・ボウ)、分[piuən](わける・
ブン)、沸[piuət](わく・フツ)、破[phuai](わる・ハ)、別[biat](わかれる・ベツ)、
煩[biuan](わづらふ・ボン)、蟠[buan](わだかまる・バン)、
○同源語:
佐須(さす・刺)、安礼(あれ・吾)、比毛(ひ
も・繙)、
【ゐる・をる(居)】
雲
(くも)隱(がくり)鳴(なく)なる鴈(かり)の去(ゆき)て将レ居
(ゐむ)秋田(あきた)の穂立(ほたち)繁(しげく))し所レ念
(おもほゆ)(万
1567)
難
波(なには)邊(べ)に人(ひと)の行(ゆけ)れば後(おくれ)居(ゐ)て春菜(はるな)採(つむ)兒(こ)を見(みる)が悲(かなし)さ(万1442)
古代中国語の「居」は居[kia]である。日本語の「ゐる」は居[kia] の語頭音[k-] が脱落したものである。「居」は古代日本語では居
(ゐる)・居(をり)としてワ行であらわれる。
念
(おもひ)出(いで)て為便(すべ)無(なき)時(とき)は天雲(あまぐも)の奥(おく)香(か・處)も不レ知
(しらず)戀(こひ)つつぞ居(を)る(万3030)
雲(くも)、隠(かくる)、鳴(なく)、鴈(か
り)、去・行(ゆく)、田(た)、穂(ほ)、立(たつ)、念(おもふ)、邊(べ)、春(はる)、兒(こ)、見(みる)、國(くに)、吾(われ)、出(い
づ)、無(な)き、時(とき)、天(あ
め)、奥(おく)、知(し)る、
【ゑ(畫・絵)】
和
我(わが)都麻(つま・妻)を畫(ゑ)に可伎(かき・描)等良無(とらむ・取)伊豆麻(いづま・暇)もが田妣
(たび)由久(ゆく)阿礼(あ
れ)は美都々(みつつ)志努波牟(しのはむ)
(万
4327)
日本語では繪(ヱ)は呉音とされ、繪(カイ)は
漢音とされている。現在でも呉音は盂蘭盆会(うらぼんえ)など仏教用語などに使われている。呉音は5~6世紀に南宋からもたらされた江南音に準拠したもの
である。漢音は音博士などによってもたらされた唐代の正音だとされている。
○同源語:
和我(わが)、都麻(つま・妻女)、畫(ゑ・
絵)、可伎(かき・畫)、等良武(とら・取)む、由久(ゆく・行)、阿礼(あれ・吾)、美都々(見・み)つつ、
【を(尾)】
念
(おもへ)ども念(おもひ)もかねつあしひきの山鳥(やまどり)の尾(を)の永(ながき)此(この)夜(よ)を(万2802)
例:沸[piuət] わく、忘[miuang] わする、綿[mian] わた、罠[mien] わな、海(pa da) わた、
○同源語:
念(おもふ)、山(やま)、鳥(とり)、永(な が・長)き、此(こ)の、夜(よ)、
【を・をとこ(雄)】
か
きつばた衣(きぬ)に須里(すり)都氣(つけ)ますら雄(を)のきそひ獦(かり)する月(つき)は伎(き)にけり(万3921)
吾 妹子(わぎもこ)が 形見(かたみ)に置有(おける) 緑兒(みどりご)の 乞(こひ)哭(なく)別(ごとに) 取(とり)委(まかす) 物(もの)し無 (なけれ)ば 男自物(をとこじもの) 腋(わき)挟(はさみ)持(もち) 吾妹子(わぎもこ)と 二人(ふたり)吾(わが)宿(ね)し(万213)
音訓の例:雲[hiuən](ウン・くも)、熊[hiuəm](ユウ・くま)、越[hiuat](エツ・こえる)、
煙[(h*)yen](エン・けむ)、隠[(h*)iən](イン・かくる)、
同じ声符の例:院[hiuan] イン・完[huan] カン、運[hiuən] ウン・軍[hiuən] グン、
域[hiuək] イキ・國[kuək] コク、話[huat] ワ・活[huat] カツ、横[hoang] オウ・
黄[huang] コウ、和[huai] ワ・禾[hua] カ、絵[huat] ヱ・カイ、
○同源語:
衣(きぬ・巾)、須里(すり・摺)、獦(かり)、
伎(き・來)、吾妹子(わぎもこ)、形見(かたみ)、置(おく)、緑(もどり)、兒・子(こ)、哭(なく・泣)、取(とる)、物(もの)、無
(な)き、腋(わき)、挟(はさむ)、吾(われ)、宿(ね・寐)る、
【を(小)】
武
庫浦(むこのうら)を榜(こぎ)轉(みる)小舟(をぶね)粟嶋(あはしま)を背(そがひ)に見つつ乏(ともしき)小舟(をぶね)(万358)
事 (こと)出(で)しは誰言(たがこと)なるか小山田(をやまだ)の苗代(なはしろ)水(みづ)の中(なか)与杼(よ ど)にして(万 776)
現代の北京音、小(xiao) は摩擦音であるが、上古音の咽音は閉鎖音系列のも
のであったに違いない。上古音の小[xiô*] が摩擦音化して現代北京音の小(xiao) になったと考えれば、「小」が日本語の「こ」ある
いは「を」であらわることも整合的に説明できる。日本語の小(こ)は上古音の小[xio*] を継承したものであり、小(を)は中国語の上古音[xio*] の頭音[x-] が介音[-i-] の影響で脱落したものである。
万葉集の時代にもすでに「小」には小(を)と小
(こ)の二つの読み方があった。万葉集には「古須氣(小菅)」(万3369)「乎夫彌(小舟)」(万4006)などの例がある。
○同源語:
轉(みる・廻)、舟(ふね・盤)、嶋(しま・
洲)、背(そがひ・脊向)、見(みる)、事・言(こと)、出(でる)、山(やま)、田(た)、苗(なへ)、中(なか)、与杼(よど・澱)
【をか(岳)】
此
(この)岳(をか)に菜(な)採(つま)す兒(こ)家(いへ)吉閑(きかな)告(のら)さね、、、(万1)
霍 公鳥(ほととぎす)鳴(なく)音(こゑ)聞(きく)や宇(う)の花(はな)の開(さき)落(ちる)岳(をか)に田葛(くず)引(ひく)[女 感]*嬬 (をとめ)(万 1942)
例:我[ngai]・吾[nga] あ・わ・われ、顎[ngak] あご、仰[ngiang] あふぐ、魚[ngia] うを、
焼[ngyô] やく、鵞[ngai] わし、
日本語の「をか」には「陸」が用いられることも
ある。「陸」の古代中国語音は陸[liuk]であり、頭音[l-]が介音[-i-]の影響で脱落して陸(をか)になる。 日本語の
「をか」は中国語の「岳」「陸」と同系である。
朝鮮漢字音では語頭の[ng-]や[l-]は介音[-i-]が続くとき規則的に脱落する。「岳」の朝鮮漢字音 は岳(ak) であり、「陸」の朝鮮漢字音は陸(yuk)である。日本語の岳(をか)、陸(をか)は朝鮮漢 字音と同じように介音[-i-] の影響で頭音が脱落している。古代日本語は古代朝 鮮語に近い音韻構造をもっていたものと考えられる。
○同源語:
此(こ)の、兒(こ)、家(いへ)、
霍公鳥(ほととぎす・隹)、鳴(なく)、音(こゑ・聲)、花(はな)、開(さく・咲)、落(ちる・散)、田葛(くづ・葛)、[女感]*嬬(をとめ・女)
【をぎ(荻)】
葦
邊(あしべ)在(なる)荻(をぎ)の葉(は)左夜藝(さやぎ)秋風(あきかぜ)の吹(ふき)来(くる)なへに鴈(かり)鳴(なき)渡(わたる)(万2134)
神 風(かむかぜ)の伊勢(いせ)の濱(はま)荻(をぎ)折(をり)伏(ふせて)客(たび)宿(ね)や将レ為 (すらむ)荒(あらき)濱邊(はまべ)に(万500)
例:途・余、多・移、誕・延、談・炎、暖・援、
湯・陽、蝶・葉、脱・悦、的・約 澤・譯、
擢・躍、剔・易、笛・由、
古代日本語では濁音が語頭に立つことがなかった
ので荻[dyek]の頭音は失われたものと考えられる。
例:萩[dyek](テキ・をぎ)、桶[dong](トウ・をけ)、踊[djiong*](ヨウ・をとる)、涌[djiong*]
(ユウ・わく)、
○同源語:
邊(へ)、葉(は)、左夜藝(さやぎ・障)、來
(くる)、鴈(かり)、鳴(なく)、渡(わたる)、神(かみ)、濱(はま)、折(をる)、伏(ふす)、宿(ね・寐)る、荒(あらき)、
【をけ(遠家・麻笥・桶)】
安
左乎(あさを・麻苧)らを遠家(をけ・麻笥)に布須左(ふすさ)に宇麻受(うまず・績)とも安須(あす・明日)伎西(きせ・着)さめや伊射(いざ)西
(せ・為)乎騰許(をどこ・小床)に
(万3484)
處 女(をとめ)等(ら)が 麻笥(をけ・麻笥)に垂有(たれたる) 紡麻(うみを)成(なす) 長門(ながと)の浦(うら)に、、(万3243)
日本語の「をけ」は古代中国語の桶[dong] と関係のあることばではなかろうか。「桶」と同じ
声
符をもった漢字に甬[jiong] がある。日本語の「をけ」は桶[dong] の頭音[d-] が介音[-i-] の発達によって脱落したものであろう。韻尾の[-ng] はカ行に転移している。
日本語の桶(をけ)は中国語の頭音[d-] を失っているが韻尾[-ng]が上古音[-k*] の痕跡を留めていることから、頭音[d-]の脱落は唐代よりかなり早い時期に起こり、上古音
の韻尾[-k*] は唐代まで残っていたと推定できる。
○同源語:
布須(ふす・伏)、乎騰許(をどこ・小床)、處女
(をとめ・女)、等(ら)、垂(たれ)る、
【をとめ(未通女・[女感]*嬬)】
未
通女(をとめ)等(ら)が放(はなりの)髪(かみ)を木綿(ゆふの)山(やま)雲(くも)莫(な)蒙(たなびき)家(いへの)當(あたり)将レ見
(みむ)(万
1244)
[女 感*]嬬 (をとめ)等(ら)に行(ゆき)相(あひ)の速稲(わせ)を苅(かる)時(ときに)成(なりに)来(けら)しも芽子(はぎの)花(はな)咲(さく)(万2117)
未通女(をとめ)は音表記であはあるまいか。未[miuət] は未[uət] に通じ、通[thong] は通(とほる)、女[njia] の祖語(上古音)は女[mia*] である。
「をとめ」の「め」は「嬬」とも表記されている
が、「嬬」は嬬[njio] であり、女[njia] に音義ともに近い。「未通女」意味のうえでも處女
を意味している可能性がある。
○同源語:
女(め)、等(ら)、山(やま)、雲(くも)、莫
(な)、家(いへ)、當(あたり)、見(みる)、行(ゆく)、相(あふ・合)、苅(かる)、時(とき)、來(くる)、芽子(はぎ)、花(はな)、咲(さ
く)、
【をどる(踊)】
椙
野(すぎのの)にさ乎騰流(をどる)[矢
鳥]*(き
ぎし・雉)いちしろく啼(ね)にしも将レ哭
(なかむ)己母利(こもり・籠)豆麻(づま・妻)かも(万4148)
○同源語:
椙(すぎ)、野(の)、啼(ね・音)、哭(なく・
鳴)、己母利(こもり・籠)、豆麻(づま・妻女)、
【をみな(女)】
石
戸(いはと)破(わる)手力(たぢから)もがも手弱(たよわ)き女(をみな)にしあればすべの知らなくに(万419)
古代中国語の「女」は女[njia] である。「女」の祖語(上古音)は女[mia*] であり、それが唐代には口蓋化して女[njia] になったものと考えられる。日本語の「を+み+
な」は中国語の上古音女[mia*] から派生したものであろう。
「を+み+な」の「を」は女[mia*] がワ行に転移したものである。マ行とワ行はともに
合口音であり転移しやす。「み」は上古中国語音の女[mia*] を継承している。「な」もまた、女[mia*]の転移したものであろう。「を」「み」「な」は、
いずれも上代中国語の女[mia*] から派生していることになる。
万葉集の時代の日本語ではマ行音は馬(むま)、 梅(むめ)のように重ねられることが多かった。日本語の女(め・をみな・むすめ)などは上古中国語の女[mia*] から派生したことばであろう。
○同源語:
手(て・た)、弱(よわき)、知(し
る)、
【をる(折)】
毎レ時
(ときごと)に彌(いや)めづらしく咲(さく)花(はな)を折(をり)も不レ折
(をらず)も見(み)らくし余志(よし)も(万4167)
暇 (いとま)有(あら)ばなづさひ渡(わたり)向峯(むかつを)の櫻(さくらの)花(はな)も折(をら)まし物(もの)を(万1750)
例:折(jeol)、節(jeol)、切(jeol)、雪(seol)、舌(seol)、一(il)、越(wol)、乙(ul)、活(hwal)、掘
(kul)、
骨(kol)、札(chal)、室(sil)、鉄(cheol)、日(il)、八(phal)、仏(pul)、物(mul)、
古代日本語の音韻構造は朝鮮語に近かったといえ る。それは、古代の史(ふひと)たちが朝鮮半島出身者だったからというだけでなく、日本語そのものが朝鮮語と近い言語だったからではなかろうか。
○同源語:
時(とき)、彌(いや)、咲(さく)、花(は
な)、見(みる)、渡(わたる)、向(むか)つ、物(もの)、
【わ行のまとめ】
日本語のワ行は中国語の頭音が介音[-i-][-iu-]などの影響で脱落したものが多い。
1.中国語の原音が母音または半母音である例:
腋[jyak](エキ・ヤク・わき)、訳[jyak](ヤク・わけ)、湧[jiong](ユウ・わく)、涌[jiong](ヨウ・わく)、踊[jiong](ヨウ・をどる)、
日本漢字音でヤ行であわれる音は訓ではワ行であら われる場合が多い。
2.中国語の疑母[ng-]、日母[nj-]の頭音が脱落してワ行であらわれる例:
○我[ngai]・吾[nga](ガ・われ)、鷲[ngai](わし<鵞[ngai]・鷲[dzyu]>)、岳[ngak](ガク・
をか)、
○若[njiak/miak*](ジャク・わかし)、女[njia/mia*](ジョ・をみな)、
疑母[ng-]と日母[nj-]は音価が近い。
例:兒[njie]・睨[ngyie]、熱[njiat]・藝[ngiei]、偽[ngiue]にせ、
3.中国語の唇音[m-][ph-]がワ行(合音)であらわれる例:
忘[(m)iuang](ボウ・わすれる)、綿[mian](メン・わた)、罠[mien](ビン・わな)、尾[(m)iuəi](ビ・を)、未(m)iuət]通[thong]女[njia/mia*](をとめ)、
4.中国語の喉音[h-][x-]が脱落して、介音[-u-][-iu-]などがワ行であらわれる例:
王[(h)iuang]子(わくご)、畫[(h)oek](ガ・カク・ゑ<絵([h]uai]カイ・ゑ>)、雄[(h)iuəng](ユウ・を・をとこ)、小[siô/(x)iô*](ショウ・を)、
5.中国語の頭音が脱落してワ行であらわれる例:
居[(k)ia](キョ・ゐる・をる)、荻[(d)yek](テキ・をぎ)、桶[(d)ong](トウ・をけ)、折[(ts)yet](セツ・をる)、