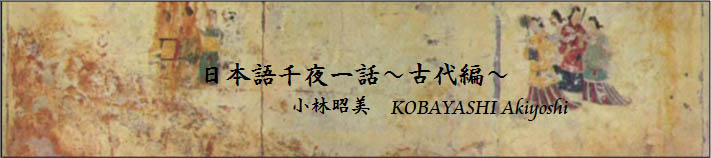
第152話 ことばにとって意味とは何か
ことばは意味を伝えることにその存在意義があ
る。ことばの意味とは何であろうか。近代言語語学の父といわれる、言語学者のフェルディナン・ド・ソシュール(1857~1913)は「記号なしで明確な思考はありえない」と述べて
いる。実世界は存在するが、記号を媒介することなく対照を人間が認識できない、ということである。ソシュールは、「記号は、対象に貼り付けられたラベルで
はなく、名前こそが意味を分節する」と述べたのである。ソシュールは、ことばや文字を「シニフィアン」と命名し、ことばや文字によって指し示されるものを
「シニフィエ」と名づけた。そして、ことばや文字が物に後付けされたのではなく、ことばや文字によって物が規定されるのだと主張した。
日本語には出世魚というものがある。ブリは15cmくらいまではワカシと呼ばれ、40cmくらいになるとイナダ、60cmくらいになるとワラサ、90cm以上になるとブリと呼ばれるようになる。生物学的 にはいづれも「ブリ」である。しかし、同じ魚でも成長の早い魚は当年の魚、2年目の魚、3年目の魚では大きさも味もちがい商品 価値も違うので別の名前をつけておいたほうが便利である。
魚の名前は地方によっても違う。
関西:ツバス→ハマチ→メジロ→ブリ
人間は誰でもことばを話す。ことばは人間ととも にあるともいえる。しかし、生れたばかりの赤ん坊はことばを話すわけではない。ことばは人間に生まれながらにして備わった特質であるが、赤ん坊に歯が生え てくるように、成長とともにことばを話し、ことばを理解するようになる。生後6~9カ月は喃語期とよばれる準備期間である。生後9カ月から14カ月になると一語文を話すようになる。そして生後 17カ月から26カ月になると二語文が話せるようになる。
ことばの能力は成長とともに伸びていく。目の能 力は日本人でもアメリカ人でも大体同じであると考えられる。しかし、ことばの認知能力は環境によって異なった発達の仕方をする。赤ん坊は世界中の言語がつ かる様々音声を区別する潜在能力をもって生れる、と考えられる。しかし、その感応力は年齢とともに劇的に失われる、と考えられる。日本語環境のなかで育つ 子どもはvとb、tとthを区別する必要がないから、それを区別する能力は 顕在化することなく失われる。中国語環境に育つ子どもは四声を区別する能力を顕在化させることができる。
日本語環境のなかで育つ赤ん坊は「犬」という動 物が「ワンワン」「いぬ」あるいは「シロ」などを呼ばれるのを何回か経験するはずである。犬を飼っていない家庭でも「ママ」とか「パパ」ということばを聞 くはずである。子どもは辞書をもって生れてきているわけではないから、「パパ」「ママ」「ワンワン」もその意味を理解することはむずかしいはずである。 「パパ」「ママ」「ワンワン」は赤ん坊のなかでは、確定しない何かでしかない。仮にそれをx、y、zとする。何回か繰り返しそれを聞いているうちに「パ パ」はx、「ママ」はy、「ワンワン」はzへと結びついていく。ことばの使用が意味へと凝固していくのである。内容は使用によって決定される。
記号は同じものに繰り返し使われなければならな い。交通信号の赤はどこでも「止まれ」であり、青は世界中どこでも「行け」であることによって記号の意味を伝えている。自然言語でも記号は使用されるたび にその意味が規定されていく。「パパ」は「パパ」に繰り返し使われることによって「パパ」を意味することになる。そして、「パパ」は「ママ」と差別化され ていく。しかし、「パパ」「ママ」「ワンワン」とx、y、zとの結びつきはあくまでも恣意的であり、「パパ」はxであってもyまたはzであっても何の不思 議もない。「パパ」ということば自体は「パパ」という人の実像とは何の類似性も認められない。
二語文期になると「白い犬」とか、「パパ好き」
とかいえるようになる。人間は言語は話す潜在能力をもって生れてくるからといって、はじめから関係代名詞が使えたり、日本国憲法が読めるわけではない。文
章が理解できるようになるまでには数千時間あるいは数万時間の学習が必要であることも確かである。
This
is a dog.
2.これは犬ですか。
Is
this a dog.
3.これは犬ではありません。
This
is not a dog.
に不定冠詞(a)がついている。
2では、日本語では疑問の副助詞(か)を文末に
つけることによって疑問文を表してい
る。英語では語順を換えることによって疑問文を
表している。
3では、日本語では文末に否定の助動詞をおくこ
とによって否定を表している。英語で
はbe動詞のあとに否定のnotをつけている。
しかし、はじめてことばに接する赤ん坊にとって はどんな言語も想定内のことであり、言語習得の障害になることはない。人はことばの順序を組み換えるだけで異なる意味を作り出すこともできる。また、こと ばの意味は名詞や動詞の意味に注目するだけでなく、助詞や活用語尾などにもしっかり注意しなければ正しく理解できない。しかし、言語間の違いは一定のパ ターンの範囲に納まるので、子どもはいくつかのパラメータ(可変部)の組み合わせとして学ぶことができるというのだ。
