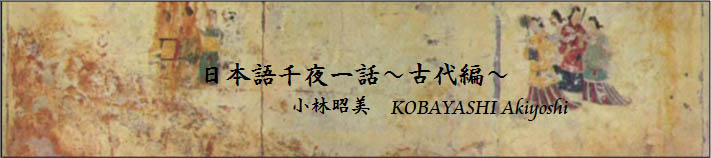
第139話
古代日本語には母音が八つあった
本居宣長に『漢字三音考』という著書がある。三
音とは呉音、漢音それに唐音のことである。そのなかで本居宣長は次のように述べている。
「皇國の古音は五十の音を出ず。是天地の純粋正
雅の音のみを用ひて、溷雜不正の音を厠(まじ)へざるが故に。さて如此く用る音は甚少(すくな)けれども。彼此相連ねて活用する故故に。幾千萬の言語成す
といへども。足(たら)ざることなく盡ることなし。」
本居之宣長は『古事記傳』を書いた江戸時代の大
国学者である。ところが明治時代になると古代の日本語の母音は五つではなく八つあったことが橋本進吉などによっ
て明らかになってくる。古代の日本語の音図を書いてみると次のようになる。
ア行 あ い
う
え お
カ行 か き(甲)・
き(乙)
く け(甲)・
け(乙)
こ(甲)・
こ(乙)
サ行 さ し
す
せ
そ(甲)・
そ(乙)
タ行 た ち
つ
て
と(甲)・
と(乙)
ナ行 な に
ぬ
ね
の(甲)・
の(乙)
ハ行 は ひ(甲)・
ひ(乙) ふ
へ(甲)・
へ(乙)
ほ
マ行 ま み(甲)・
み(乙)
む め(甲)・
め(乙) も(甲)・
も(乙)
ヤ行 や ―
ゆ
イ
エ よ(甲)・
よ(乙)
ラ行 ら り
る
れ ろ(甲)・
ろ(乙)
ワ行 わ ゐ
―
ゑ
を
これは上代特殊假遣の発見とされ、後に日本語が ウラル・アルタイ系統の言語であるとする系統論に有力な示唆を与えることになる。古代日本語ではイ談、エ段、オ段はそれぞれ2種類の漢字が使い分けられて いる。
例えば古事記歌謡では「き」の音に六種類の漢字
が使われている。( )内は回数
岐(150)、
紀(24)、
伎(5)、
棄(1)、
貴(1)、
疑(1)
このうち岐、伎、棄は甲類の単語のみに使われ、
紀、貴、疑は乙類の単語のみに使われている。
甲類:由岐(雪)、淤岐(沖)、登岐(時)、加岐(垣)、美岐
(御酒)、岐美(君)、
岐奴(絹)、都婆岐
(椿)、須岐(鋤)、由岐(行き)、那伎(鳴き)、
乙類:都紀(月)、紀(木)、
多加紀(高城)、疑理(霧)、阿治志貴(あぢしき)、
雪、沖、時な
どには甲類の漢字のみが用いられ、乙類の漢字が用いられることはない。また、月、木、霧などには乙類の漢字のみが用いられて、甲類の漢字が用いられること
はない。橋本進吉はこのように漢字が使い分けられているのは記紀万葉の時代の日本語に何らかの発音上の違いがあったからに違いないと考えた。甲類、乙類と
いうのはいかにも古めかしい命名だが、甲類と乙類のあいだにどのような違いがあったかは分からなかったのでいたしかたない。
五十音図は平安時代に作られたものであり、古事
記や日本書紀の時代の音を全部あらわすことができない。例えば、古事記歌謡につぎのような歌がある。これを古事記の時代の日本語音に復元すれば次のように
なる。
多迦比迦流 比
能美古
夜
須美斯志
たかひ(甲)か
る ひ(甲)の(乙)み(甲)こ(甲)
やすみ(甲)し
し
和賀意富岐美 阿良多麻能
登斯賀岐布禮婆
わがおほき(甲)み(甲) あらたまの(乙) と(乙)しがき(甲)ふれば
阿良多麻能 都紀波岐閉由久 宇倍那宇倍那
あらたまの(乙) つき(乙)はき(甲)へ(乙)ゆく うべ(乙)なうべ(乙)な
岐美麻知賀多爾
和賀祁勢流 意須比能須蘇爾
き(甲)み(甲)まちがたに わがけ(甲)せる おすひ(甲)の(乙)すそ(甲)に
都紀多多那牟余
つき(乙)たたなむよ(乙)
この歌は現代の五母音で読むと次のようになる。
高光る 日の御子 やすみしし
我が大君 あらたまの 年が来
経(ふ)れば
あらたまの 月が来経(へ)ゆ
く うべなうべな
君待ちがたに 我が着(け)せ
る 襲(おすひ)の裾に
月立たなむよ
古代日本語の 母音の甲乙はどのような違いがあったのだろうか。橋本進吉も、その二種類の別は何等かの発音上の差異にもとづくことが推定される、としているだけでその違 いを解明するには至っていない。大野晋は岩波古語辞典で記紀万葉における甲乙の音を弁別しているが、その音価については、き(甲)ki、き(乙)kï、け(甲)ke、け(乙)kë、こ(甲)ko、こ(乙)köと示すだけで、その音価については明言をしていな い。
古事記歌謡におけるイ段の甲乙に使われている漢
字はつぎのとおりである。( )内は濁音
き(甲):岐、伎、棄、(藝、岐)
き(乙):紀、貴、疑、(疑)
ひ(甲):比、(毘)
ひ(乙):斐、肥、(備)
み(甲):美、弥、
み(乙):微、味、
甲類の漢字音も乙類の漢字音も現代の日本漢字音
では同じである。甲乙の違いは中国語音の違いに依拠しているものと考えてみる。まず、き(甲)とき(乙)について中国語の四声を調べてみると、次のように
なる。
き(甲): 岐(上)、伎(上)、棄(去)、藝(去)、
き(乙): 紀(上)、貴
(去)、疑(平)、
次にこれらの漢字の古代中国語音は白川静の『字
通』、藤堂明保の『学研漢和大辞典』などによって推定すると次のようになる。
き(甲):岐[gie]、
伎[gie]、
棄[khiei]、
藝[ngiai]、
き(乙):紀[kiǝ]、
貴[kiuǝi]、
疑[ngiǝ]、
ひ(甲):比[piei]、毘[phiei]、
ひ(乙):斐[phiuǝi]、肥[biuǝi]、備[buǝi]
み(甲):美[miei]、弥[miai]、
み(乙):微[miuǝi]、味[miuǝi]、
乙類の漢字には、あいまい母音の[ǝ]が含まれていることがわかる。もうひとつの特徴として乙類 の漢字音は[-u-]介音を含んだものが多いということで ある。ひ(乙)、み(乙)は明らかに合音である。き(乙)についても「貴」は合音であり、「疑」も鼻音であり、唇は閉じられている。
き(甲)とき(乙)の違いについてさらにその特 徴を現代の北京語音、広東語音、朝鮮語音で調べてみると次のようになる。
甲類 乙 類
|
|
北京音 |
広東音 |
朝鮮音 |
|
北京音 |
広東音 |
朝鮮音 |
|
岐(152) |
qi |
keih |
ki |
紀(24) |
ji |
gei |
ki |
|
伎(5) |
ji |
geih |
ki |
貴-(1) |
gui |
gwai |
kwi |
|
棄(1) |
qi |
keih |
ki |
疑(5)- |
yi |
yih |
ui |
|
藝(18) |
yi |
ngaih |
ui |
|
|
|
|
( )内の数字は使用頻度をあらわす。
日本語、朝鮮語ではき(甲)・き(乙)の区別はほとんどつかないが、北京音では甲類のほ とんどが(qi)であり、乙類では(ji)が 多い。現代の漢字音は古代の漢字音の変化してきたものであり、古代の発音の違いの痕跡を留めているものと思われる。現代の漢字音では音符の「支」はカ行 (技、岐、伎など)で読むものとサ行(枝、支)で読むものがあるがカ行音のほうが古い。日本で出土した稲荷山鉄剣の銘にある「獲加多支鹵」は「わかたけ る」と「支」を支(け)とカ行で読む。
岐の類と紀の類の差異については『韻鏡』などの
韻書をみても必ずしも明らかでないが、現代の北京語音では差異が明らかである。現代語音の差異は唐の時代の差異を何らかの形で反映しているはずである。森
博達は『古代の音韻と日本書紀の成立』のなかでき(甲)・き(乙)の違いを重紐、つまり中舌的拗音(ï)と前舌的拗音(i)の差異に求めている。いずれにしてもき(甲)・き(乙)の違いは主母音の違いによるものではなく、介音の
違いであり、介音の違いが後に北京語音では頭子音に影響を与えたものと考えられる。
これらのこと
を綜合すると古代日本語における岐の類と紀の類の違いは母音の側よりもむしろ頭子音またはわたり音(介音)にあるのではないかと思われる。従来橋本進吉、
有り坂秀世、大野晋などの国語学者は古代の日本語には母音が八つあったとしているが、古代の日本語も主母音は五つであり、介音の影響で拗音(i)あるいは合音(u)になり、やがてそれが頭音に影響を及ぼして摩擦音
あるいは破擦音になったのではあるまいか。「支」の古代音がカ行からサ行に転移していった事実はそのことを裏づけているように思われる。
古代日本語には二重母音はなかった。古代日本語 には二重母音を避ける工夫がみられる。我家(わぎへ)、我妹(わぎも)、などは我(waga)の最後の音節の母音と家(ihe)、妹(imo)の語頭の母音が二重母音になることを避けている。 吾が思ふ妻(あがもふつま)なども吾が(waga)の最後の母音と思う(omoufu)の語頭の母音とが二重母音になることを避けてい る。
しかし、ヤ行はi介音を含む音節であり、ワ行はu介 音を含む音節であった。青(あを)、岡(をか)、乙女(をとめ)、尾(を)、猪(ゐ)、居(ゐ)る、枝(イエだ)、末(すゑ)、植(うゑる)などは現在で はア行に統合われているが、ヤ行、ワ行のことばであった。また、「我」は古代日本語では我(われ)でもあり我(あれ)でもあった。現代の日本語ではi介音あるいはu介音が失われている。
これと同じことが古代日本語の甲乙についても起 こったに違いない。古代日本語には母音が八つあったのではくて、ア行以外の行にも拗音や合音があったと考えるべきであろう。古代日本語でも母音は五つで あったと考えれば、現代の日本語ではわたり音(i介音、u介音)が失われたということになる。
