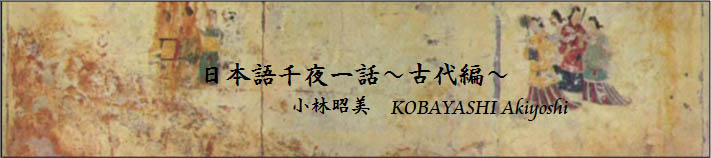
第118話 神とは何か
〇 神(かみ)。『古事記』のなかで「神」は「天」、「地」とともに宇宙を構成する重要な概念になっている。本居宣長は『古事記伝三之巻』神代の一で、「神」について次のように述べている。
迦微(かみ)と申す名の義(こころ)は未だ思ひ得ず。さて凡て迦微とは古(いにしへ)の御典(みふみ)どもに見えたる天地の諸々(もろもろ)の神たちを始め て、そを祀(まつ)れる社に坐ス御霊(みたま)をも申し、又人はさらにも云ず、鳥獣木草のたぐひ海山など、そのほか何にまれ、尋常(よのつね)ならずすぐ れたる徳(こと)ありて、かしこき物を迦微とは云なり。
また、本居宣長は『鈴屋答問録』では次のように述べている。
かみの名義、年来相考へ候らへども、未思得候。旧説は皆非なり。さてかみと唐の神とは、大抵は同じき故に此字をあつ。然れども、神と唐に云ふ神とは、七八分 は同じくて、二三分は異なることあり。
「神」の古代中国語音は白川静の『字通』によれば神[djien]である。「神」の声符は申[sjien]である。もし、照系の音は端系の音から生じたという中国音韻学の一般法則が正しいとすれば、神[djien]は古代中国語では神[den]に近い音で発音されていたはずである。これを裏づける形声文字が確かにある。「電」の声符は「申」であるが、発音は電[dyen]である。ところが、「申」を声符とする漢字には坤[khuən]という文字もある。もし、神が坤[khuən] に近い音をもっていたとすれば、日本語の「カミ」は中国語の神[khuən]と関係のあることばである可能性がある。
五世紀の考古学遺物である稲荷山鉄剣には「獲加多支鹵」とあり、「支」は「シ」ではなく「ケ」をあらわしている。董同龢は『上古音韻表稿』でいくつかの例をあげて、「旨-・耆-、樞’-・區k’-、示-・祁’-などは、上古に於てはk-、k’-、g’-であったのではないか。」(一六頁)としている。たしかに旨(シ)と耆(キ)は声符が同じであり、樞(スウ)と區(ク)、示(ジ)と祁(ギ)も、古代中国語音が舌根音であったと仮定すれば説明がつく。日本漢字音を調べてみても支(シ)・枝(シ)はサ行で発音されるが、同じ声符をもつ技(ギ)、岐(ギ)はいずれもガ行で発音される。漢字には同 じ声符がカ行とサ行に読み分けられるものがいくつかある。
例:公(コウ)・頌(ショウ)、 感(カン)・鍼(シン)、 勘(カン)・甚(ジン)、
嗅(キュウ)・臭(シュウ)、喧(ケン)・宣(セン)、 堅(ケン)・腎(ジン)、
嚇(カク)・赤(シャク)、 絢(ケン)・旬(ジュン)、耆(キ)・嗜(シ)、
峡(キョウ)・陝(セン)、 祇(ギ)・
氏(シ)、
活(カツ)・舌(ゼツ)、
「神」は隋唐の時代には申[sjien]あるいは神[djien]に近く発音されていたが、さらに時代を遡ると乾坤の坤[khuən]に近い発音であったと考えることができる。
軟口蓋音のgやkの調音点が前よりに移って摩擦音化することは中国語に限らず、ヨーロッパの言語でもみられる。インド・ヨーロッパ語族は「百」ということばをkで発音するか、sで発音するかによってcentum言語とsatem言語にわかれる。Centum 言語はラテン語、ギリシャ語、ケルト語、ゲルマン語などであり、satem言語はロシア語、インド・イラン語、アルメニア語、アルバニア語などである。東のグループに属する言語は歯擦音[s] または[ʃ]で、西のグループに属する言語は[k] まはた[h] で特徴づけられる。Caesar (カエサル・シーザー)は古代ローマでは「カエサル」であったが、現代のイタリア語、フランス語などロマンス語では「シーザー」と発音されるようになった。
結論として、日本語の神(かみ)は古代中国語音の神[khuən]を継承したものであり、日本漢字音の神(シン)は隋・唐の時代の中国語音に依拠したものである。訓の神(かみ)も、音の神(シン)もともに中国語からの借用語である。
神代とはいつの時代か
古事記の時代認識はまず神代からはじまり、人代に至る。現代人の歴史認識ではまず旧石器時代があり、縄文時代、弥生時代、古墳時代を経て記紀万葉の世界へと進む。古事記にいう神代とは現代人の歴史認識 ではどの時代にあたるのだろうか。
古事記の天の石屋戸の場面では「天照大御神は機屋で神に奉る神衣を機織女に織らせていた。するとスサノヲノ命はまだら毛の馬の皮を剥ぎ取って投げ入れてき た。天照大御神はこれを見て天の石屋戸にたてこもってしまった。八百万の神が集まって相談し、常世の長鳴き鳥を集めて鳴かせることにした。次に天の金山の 鉄を採って鏡を作らせた」とある。
神の世界にはすでに機織が行われていた。つまり、蚕を飼っていたのである。馬も飼育されているし、鶏もいる。そればかりか、鉄が用いられている。縄文時代の家畜は犬くらいで、馬や鶏はいない。『魏志倭人伝』には「その地には牛、馬、虎、 豹、羊、鵲(さぎ)なし」とある。また、『古事記』応神天皇の条に「百済の王が牡馬一匹、牝馬一匹を貢上した」とある。『古事記』の天の石屋戸の段の馬に 関する記述は応神天皇の条の記述と明らかに矛盾している。
また、『日本書紀』によると、雄略天皇は皇后に蚕を飼うことを奨励したとある。日本で養蚕が本格的に行なわれるようになったのは5世紀のことである。また、『古事記』五穀の起源の条には「オホゲツヒメノ神の頭からは蚕が生まれ、目からは稲の 種が生まれ、耳からは粟が生まれ、鼻からは小豆が生まれた。陰部に麦が生まれ、尻に大豆が生まれた。これが五穀の種となった」とある。これはまさに農耕時 代のはじまりの物語である。
『古事記』の神代の記述には弥生時代の文物がいくつも登場する。八俣のおろち退治の段では酒船に酒を満たして大蛇に飲ませ、酔いつぶさせてしまう。酒を醸すことも穀物の栽培があってはじめてできる。『古事記』では一方、応神天皇の時に「酒 を醸むことを知れる人、名は仁番(にほ)またの名は須須許理(すすこり)が渡来した」とある。日本で酒を醸すようになったのも4~5世紀以降であろう。
これらを総合すると、『古事記』にいう神代とは、現代の歴史認識に置き換えれば、石器時代のことでも、縄文時代のことでもなく、弥生時代のことであるということになる。
